1990年代のポップ・ミュージックの傑作──古内東子のニューヨーク録音『Strength』
 Album : 古内東子 / Strength (1995)
Album : 古内東子 / Strength (1995)
Today’s Tune : 朝
気のおけない友人との再会──あのころ聴いていたシティ・ポップ
いささか私的な雑談になってしまうので、気楽に読み流していただければ嬉しい。昨年の12月のこと、何年もご無沙汰していた親友のNくんから突然の電話をもらい、ぼくたちは再会を果たした。いつもそうなのだけれど、ふたりは特にその機会を待ちわびているわけでもない。ひとから見たら薄情と思われるかもしれないが、たぶん普段は、お互いに相手のことなどすっかり忘れているのだろう。それがある日あるとき、まるで天啓を得たかのように、旧交を温める気になる。神さまからの託宣がいつ下されるのかは、だれにもわからない。ただ云えることはひとつ、Nくんが連絡してくるのは十中八九、彼がある音楽からインスピレーションを得たときなのである。その点、ぼくも同様だ。
というわけで、ぼくたちは昨年の年末にささやかな忘年会を開いたのだが、ひとから見ればとりとめのないはなしは、いつまでも果てしなくつづいた。長いあいだ連絡をとっていなくても、まるで昨日まで一緒に過ごしてきたかのごとく、会話は淀みなくすすむ。親友という間柄では、そういうのはごく当たりまえのことなのかもしれない。いずれにしても、ぼくは久々に美味しいビールを家庭外で、しかも様々なスタイルのものを選びながら楽しんだ。もともとビール党のぼくは、のどごしの良さと爽快感から、いつもより心地よく、それでいていつもどおりの自分でいられるような、そんな素敵な時間を過ごすことができたのである。Nくんと再会を期すといつもこうだから、実にありがたい。
そんな気のおけない友人と、ぼくは現在も過去とまったく変わることなく、よもやまばなしに花を咲かせたのだが、その話題といえばやはり音楽が中心。ぼくたちはともに高校時代に吹奏楽部に在籍し、大学時代にはバンド活動に明け暮れていた。青春時代は、まさに音楽三昧の日々だったわけだ。ちなみにNくんは、もともとビル・ワトラスを敬愛するトロンボーン吹きだったのだけれど、バンドではキーボードを弾いてもらった。ぼくは、自分がピアノとフェンダー・ローズに集中するため、シンセサイザーのパートを彼に無理やり押しつけてしまった。でも彼は然るべき音楽教育機関で楽理を学んでいたので、ぼくが小難しいコードやスケールをもち出しても即座に理解してくれたもの。
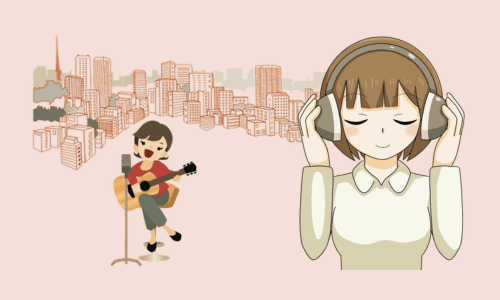
もちろん見解が相違することもままあるのだけれど、そういうときは一緒に問題をとことん推し究めたりする。ふたりとも音楽については、固定的な観念にとらわれることがなく柔軟思考なので、問題解決は思いのほか早い。そんなぼくたちがもっとも意気投合するのは、音楽をひとつのジャンルにこだわらずに聴くという姿勢において。これは自分の昔からの信条みたいなものなのだが、音楽は心地よさが第一、そして聴いていて気持ちよくならなければ意味がない──と、ぼくは思うのである。裏を返せばそれは、快然たる響きをもつ音楽であれば、どんなジャンルの作品でも積極的に手にするということだ。その点、Nくんも実に幅広く音楽を聴いていて、ぼくのあずかり知らなぬところで面白いネタを仕入れ披露してくれる。
思えば、ともにバンド活動に勤しんでいるときは、もっとも多岐にわたるジャンルの音楽を聴いていたもの。ぼくは高校時代からジャズ・ピアノを弾いていたし、Nくんもクラシックとジャズを並行して演奏していた。しかしながらバンドでは、インストゥルメンタルも演っていたけれど、ヴォーカル曲のほうがレパートリーの主体となっていた。その内訳といえば、インストはフュージョン風、カヴァーはソウル・ミュージックのあまり知られていないナンバー、そしてオリジナルは女性シンガー用の日本語の歌詞の曲──ということになる。そのせいでぼくとNくんの間では、それまであまり手をつけていなかったシティ・ポップを話題にすることが多くなった。作編曲を務めていたぼくは、当時のアイドル・ソングでさえ真剣に研究したもの。
当時のシティ・ポップというと、どんなものを聴いていたのだろう──。バンドのシンガーが女性だったので、フィメール・シンガーのアルバムばかり。1980年代の作品ですぐに思い浮かぶのは、矢野顕子の『ただいま。』(1981年)、松任谷由実の『昨晩お会いしましょう』(1981年)、大貫妙子の『クリシェ』(1982年)、吉田美奈子の『ライトゥン・アップ』(1982年)、EPOの『VITAMIN E・P・O』(1983年)、上田知華の『クラシェスト』(1984年)など(以上リリース順)。あと特に印象に残っているのが、飯島真理の3枚のアルバム『ロゼ』(1983年)『ブランシュ』(1984年)『ミドリ』(1985年)。各々のプロデュースとアレンジが、坂本龍一、吉田美奈子、清水信之と異なるのだが、まったくテイストの違う作品に仕上がっていて興味深い。
そういえば、バンドでマネジメントと作詞をしてくれていたSくんが飯島真理の大ファンで、彼から『飯島真理SONGメモリー〜ミンメイ SINGS FOR YOU〜』(1986年)というレコードを聴かせてもらった。これは、飯島さんがテレビアニメ『超時空要塞マクロス』(1982年10月3日 – 1983年6月26日)に登場するアイドル歌手、リン・ミンメイ役の声優をやっていたことにちなんだ作品。劇伴を担当した羽田健太郎の作曲とアレンジが聴ける。羽田さんの音楽はぼくも好きなのだけれど、これに関しては単なるソース・ミュージックにしか聴こえなかった(ごめんなさい)。それはそれとして、Sくんはアイドル・ソングに造詣が深く、彼の教えからNくんもぼくもアイドルの作品を聴くようになった。
アイドル・ソングと1990年代のポップ・ミュージックのフレッシュな感覚
これはまったくの私感だが、1980年代のアイドル・ソングといえば、大まかには2種類のタイプに分けられる。主役がシンガーとしてのスキルに恵まれていて、制作サイドも本格的な音楽作品を作ろうとしているもの。逆にメインに高い歌唱力が要求されていないせいか、歌はぜんぜん(こころに)入ってこないのだけれど、そのぶんオケだけがやたらと耳につくもの──である。もちろん、歌が上手いほうが聴きやすい。でも実は、ぼくはそれを取り立てて云うほどのことではないとも思っているのだ。アイドルの第一の重点は、大衆の偶像であること。シンギング・アビリティは、二の次。これはまったくの自論だが、アイドル・ソングにおいて大切なのは、そのキャラクターが理解されイメージに沿った音楽が作られているかどうかではないだろうか。
これ以上アイドルについてあげつらうのも、いまさらここにアイドル・ソングの名曲の数々をずらりと並べるのも控えるが、このひとについてだけは触れておきたい。それは、もと東北新幹線というユニットのヴォーカリスト兼キーボーディストだった山川恵津子である。彼女は、1980年代から1990年代にかけてコンポーザー、アレンジャー、そしてプレイヤーとして、シティ・ポップからアイドル・ソングまで数多くの作品を手がけた。その個性的なソングライティングとアレンジメントは、ハイクォリティでスタイリッシュ。最近その功績が再評価され、2種類のコンピレーションCD『編曲の美学 山川恵津子の仕事 Victor Entertainment編』(2024年)と『編曲の美学 山川恵津子の仕事 PONYCANYON編』(2024年)が発売された。
たぶん、あのころのNくんもぼくも、山川さんのクリエイトするサウンドにはずいぶん刺激を受けたと思う。参考までに、ぼくのおすすめを3曲挙げておこう。まず歌唱がご愛嬌程度のもの(失礼!)では新田恵利の「星を探して」(1986年)、つぎにシティ・ポップでは姉妹ユニットMILKのひとり、M-Rie(宮島理恵)の「SEEDS of HAPPINESS -しあわせのたね-」(1993年)、そして最後にインストゥルメンタルではエレクトーン・プレイヤーの柏木玲子の「ジェントル・ブリーズ」(1984年)となる。特に最後の曲は柏木さんの『ドリーム・オブ・ドリーム』(1984年)というアルバムに収録されており、山川さんはここで作編曲をするとともにシンセサイザーも弾いている。知るひとぞ知る名曲だ。

ここではなしをシティ・ポップに戻すが、さきに挙げたアーティストはみな、1970年代からすでに都会的で洗練されたポップ・ミュージックを世に送り出していたひとばかりだ。1980年代の彼女たちの音楽からは、登場時の世界観が保持されながら、サウンドがより洋楽寄りにシフトアップされたという印象を受ける。それは同時に地に足がついた音楽でもあって、深い味わいがあるいっぽうで新味に欠けるというのもまた事実。それに反して1990年代のシティ・ポップには、若干の危うさをはらみながらも、フレッシュな感覚で楽しませてくれるものが多かった。1970年代から1980年代へと受け継がれたシティ・ポップの影響を受けた、よりアーバンライフを演出するような新世代のアーティストが多く登場したのである。
そんな1990年代のポップ・ミュージックのなかで、ぼくが熱心に聴いていたアーティストを挙げると、やはり女性のシンガーソングライターばかりになるが、野田幹子、今井優子、久野かおり、平松愛理(デビュー順)ということになる。実は彼女たちはみな、1980年代の後半にデビューを果たしている。しかしながら、そのユニークな音世界は、明らかに1990年代のものだ。バブル経済が崩壊して、だれもが社会の停滞を感じていたあのころ、ぼくには彼女たちが作り出し歌い上げた楽曲が、実にリアルなものとして受け取られた。それまでのシティ・ポップといえば、夢や理想を語るような内容のものが多かったように思う。それとは対照的に、日常の些末なことに幸せを発見するという、等身大のライフスタイルを綴った彼女たちの曲は、ぼくにも共感を与えた。
さて、ぼくは最初に、長い間連絡をとっていなかったNくんが突然電話をしてきたのは、彼がある音楽からインスピレーションを得たからと述べた。実際そのときのNくんの弁では、ひとりでボブ・ジェームスの『オブセッション』(1986年)というアルバムを聴いているうちに、にわかに学生時代にぼくと過ごしたことが思い出され、居ても立ってもいられなくなったとのこと。まったく嬉しいことを云ってくれる。ぼくもやにわに、彼とふたりでこのアルバムを聴きながら深夜のドライヴを楽しんだことを思い出した。そして『オブセッション』は、ぼくも好きな作品。(親愛の情を込めてファーストネームで呼ぶが)ボブは従来とは異なる感覚で、シンセサイザーを駆使したオーケストレーションに取り組んでおり、そのサウンドはひときわ異彩を放っている。
アブストラクトでもありポップでもあるこの『オブセッション』は、いま聴いても新鮮な気持ちにさせられる名作だ。ボブは1985年にCBSとの8年間にわたる契約を終了させ、自己のレーベル、タッパン・ジー・レコードを閉鎖した。その翌年、彼はワーナー・ブラザース・レコードに移籍し、アルト奏者のデヴィッド・サンボーンとの共作『ダブル・ヴィジョン』(1986年)を経て、まもなくリーダー作を発表。それが『オブセッション』だった。それまでキーボーディストであると同時にプロデューサーでもあったボブが、このアルバムではコンポーザーでシンセサイザー・プログラマーのマイケル・コリーナと、レコーディング・エンジニアのレイ・バルダニにプロデュース業務のほとんどを委託している。これは、新機軸だ。
マイケル・コリーナがプロデュースを手がけた日本産シティ・ポップ作品
コリーナもバルダニも、サクソフォニスト、カーク・ウェイラムのデビュー作であると同時に、タッパン・ジー・レコードの最後の作品でもある『フロッピー・ディスク』(1985年)から、すでにボブと関わっていた。このコンビは1980年代から1990年代にかけてワーナー・ブラザースにおいて、目覚ましい活躍を見せた。デヴィッド・サンボーンをはじめ、ベーシストのマーカス・ミラー、ヴォーカリストだとマイケル・フランクスやマリリン・スコットのアルバムがすぐに思い浮かぶ。特にコリーナは、その後もしばしばボブを、プロデューサーのみならずソングライター、アレンジャーとしてサポートした。だが彼の2000年代以降の音楽活動は、原点であるクラシック作品の創作にウェイトが置かれた。
そうはいってもコリーナは、ジャズ、ラテン、ソウル、ゴスペルなどからも影響を受けていて、幅広い音楽性を身につけたアーティストと云える。その証拠に彼は、ドイツの電子音楽グループ、タンジェリン・ドリームのもとキーボーディスト、ピーター・バウマンが設立したレーベル、プライヴェート・ミュージックから2枚のリーダー作をリリースしている。実際に聴いていただければお分かりいただけると思うが、コリーナは『シャドウ・アルバーノ』(1988年)と『リチュアルズ』(1990年)のレコーディングおいて、自らのキーボード演奏とプログラミング以外に、フュージョン系のミュージシャンをフィーチュアしている。しかしそこで展開されている音楽は、コンテンポラリー・ジャズに収まり切らない独創的なインストゥルメンタル・ミュージックだった。
そんな一風変わった音楽家、マイケル・コリーナが全面的にプロデュースを手がけた、貴重な日本産のシティ・ポップ作品がある。現在もシンガーソングライターとして活躍する、古内東子の4枚目のアルバム『ストレングス』(1995年)である。1996年に発表したシングル「誰より好きなのに」が、テレビドラマやヴァラエティで使用されたこともありヒットし、あまねく知られるようになった。特に恋愛をテーマにした楽曲が多いことから、いまも同世代の女性たちから圧倒的な支持を集めている。その点で彼女を、当時から松任谷由実や竹内まりやの次代を担う逸材と評価する向きも多かった。と、利いた風な口をきいているが、1993年に上智大学比較文化学部に籍を置いたままテビューした古内さんについて、当時のぼくはまったくノーマークだった。

早くから古内さんの才能に注目していたのが、実はNくんだった。古内さんにとって初の海外(ニューヨーク)のレコーディング作品である『ストレングス』も、ぼくはNくんの自宅のハイエンド・オーディオではじめて聴いた。レイ・バルダニによるレコーディングは、相変わらずいい音を創造している。ところがそのときのぼくは、迂闊にもこのアルバムを聴き流してしまった。なぜかといえば、日本人アーティストの海外レコーディングは特別に珍しくもなかったし、おそらくこのアルバムと同時にもっとぼくの食指が動くような作品を聴かされたからだろう。現に古内さんは次作の『アワーグラス』においても、“キング・オブ・グルーヴ”の異名をとるR&B系ドラマー、ジェームス・ギャドソンをプロデューサーに迎え、ロサンゼルスでレコーディングを行なっている。
これは余談だが、古内さんと同様に、当時ソニー・ミュージックエンタテインメントに所属していたシンガーソングライター、五島良子がジャン・ジャック・サージュとドン・グルーシンの協力を得てロサンゼルスで吹き込んだ『フロッギー』(1995年)は、奇しくも『ストレングス』と同じ年にリリースされている。これも忘れ難い作品だ。ときに、今回のNくんとの再会がきっかけで、ぼくは『ストレングス』がたまらなく聴きたくなった。ということで、慌ててすでに廃盤となっていたCD(ストリーミングサービスあり)を入手。こちらは、29年ぶりの再会となる。自分の粗忽を恥じながら云うが、これは名盤だ。全曲古内さんによるソングライティング、ヴォーカル・アレンジ、全曲コリーナによるアレンジ。古内さんの軽くソウルフルでリズミカル、そして感情表現がナチュラルなヴォーカルと、コリーナのシンプルなサウンドメイキングが見事に融け合っている。
まず冒頭の「朝」にやられた。肩の力が抜けた潤いのあるヴォーカルが素敵。ボブ・ジェームスの作品ではおなじみのマックス・リーゼンフーヴァーによるすわりのいいドラム・プログラミングが絶品。マイケル・ブレッカーによるテナーもいつになく軽やか。つづく「Strength」はアルバム中もっともアクティヴなナンバー。スティーヴ・ジョーダンの軽快なドラミング、飾らないホーン・セクションが都会的な活気を演出する。ちょっとメランコリックな「あえない夜」には、ボブがMIDIピアノで参加。ソロはもう少し聴きたかった。バウンスするリズムがポップな「今の二人が好き」では、デヴィッド・スピノザのギターによるブルージーなオブリガートが効果的。リーゼンフーヴァーのプログラムしたベース・ラインがクールな「Promise」では、ギル・パリスのギターによるロッキッシュなプレイが随一。
アコースティックな「できるだけ」では、やはりボブがピアノを弾いている。バッキングのみとは、もったいない。むしろニック・モロックによるアコギのほうが印象に残る。リズミカルな「秘密」では、ジョーダンとベースのジェームス・ジナスとによるリズム、エッジの効いたホーン・セクションがキャッチー。ランディ・ブレッカーによるトランペット・ソロも美味しい。意外なことに、シングル・ヴァージョンも発売されたハートウォーミングな「歩き続けよう」とグルーヴィーな「幸せの形」は、アルバム中比較的地味に響く。だが、アルバムのラストを飾るバラード「雨の水曜日」では、柔らかなストリングスとデヴィッド・サンボーンによるビターな味わいのアルトとのコントラストが華美。古内さんのヴォーカルも、いくばくかエモーショナルに聴こえる。これほど卒がなく充実したシティ・ポップは、なかなかない。いまさらだが、ここのところ毎日聴いている。29年のブランクを埋めるように──。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。








コメント