デイヴ・ブルーベック・クァルテットによる人気のディズニー・ソング集『デイヴ・ディグズ・ディズニー』
 Album : The Dave Brubeck Quartet / Dave Digs Disney (1957)
Album : The Dave Brubeck Quartet / Dave Digs Disney (1957)
Today’s Tune : Alice In Wonderland
ディズニー・ソングはスクリーンから離れてもマスターピース
月並みな云いかたになるが、ここ何日かは穏やかな日差しが心地よく、鈍感なぼくでも春を感じる今日このごろである。私的なことで恐縮だが、わが家のふたりの娘たちは今年ともに進学受験に臨んだ。いまでは長くて厳しかったであろう受験勉強からも解放されて、束の間の自由を謳歌している。というか、毎日遊び放題である。まあ、それもよかろう。そもそもまともに学業に励んだことのないぼくに、彼女たちに教えさとす資格はないのだ。だから当節、たまにはハメを外しても構わないだろうと、寛大なこころのもち主のフリをして、妻に睨まれたりすることがしばしばある。なにか云われたら、知らぬ顔の半兵衛を決め込んで、さっさと自室に戻り、ジャズのレコードでも聴けばいい。
ところで面白いのは、受験を終えたふたりの娘たちが時を移さず、まるで示し合わせたかのごとく、一様にそれぞれの友だちと連れ立って東京ディズニーランドに遊びに行ったことである。しかも彼女たちは、住まいが3大副都心と称される地域に位置するのにもかかわらず、朝の4時に起きて始発列車に乗るためにいそいそと出かけていったのだ。ふだんは思い切り寝坊助なのに、そういうときは、少しも抜かりがない。ぼくにはまったく理解できないのだけれど、これって常識のことなのだろうか?自慢するわけではないけれど、実を云うとぼくは生まれてこのかた東京ディズニーランドを体験したのは1回のみ。娘たちがまだ小さいころ家族全員で行ったのが、いまのところ最初で最後だ。
正直に告白すると、ぼくは恥ずかしながら東京ディズニーランドと東京ディズニーシーとの違いもよくわかってはいない。べつに東京ディズニーランドにもウォルト・ディズニーが生み出したアニメーションのキャラクターたちにも、疎ましさを感じるようなことはないのだけれど、かといって率直に云うと特別な思い入れもないのである。幼いころにずいぶんとディズニーのアニメ映画を観たけれど、万感胸に迫るようなことはほとんどなかった。唯一『ファンタジア』(1940年)には、ぼくもこころを躍らせた。まあそれは、映像にというよりはどちらかというと、レオポルド・ストコフスキー指揮フィラデルフィア管弦楽団によって演奏されるクラシック音楽の名曲の数々に、胸を高鳴らせたと云ったほうが正しい。
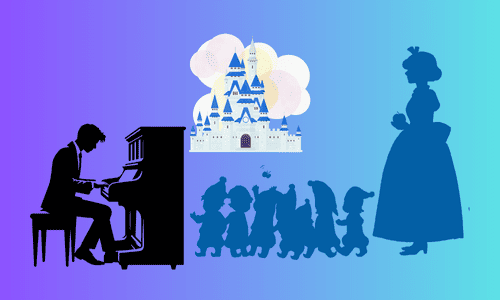
いずれにしても、多くのひとに感動を与える“夢と魔法の王国”とぼくとの関係は、いたって希薄なのである。敢えてぼくのディズニーへの関心を挙げると、それは音楽にとどめを刺す。ただしウォルト・ディズニー・アニメーション・スタジオ長編作品のなかでも、1937年に公開された『白雪姫』から1960年代くらいまでの作品に限定される。ちょうどウォルト・ディズニーがまだ現役のころの映画に当たる。ディズニー・アニメの主題歌、挿入歌、あるいは劇伴は、もちろん銀幕で奏でられるとき鮮明な印象を与えるのだけれど、スクリーンから離れても独立した楽曲としてリスナーのこころを揺さぶることがままある。そんなマスターピースがモダン・ジャズにおいて採り上げられ、さらにジャズ・スタンダーズへと進化するケースも少なくない。
ではここで、ジャズ・プレイヤーが過去に演奏したディズニー・アニメの楽曲のなかから、ベスト3(順不同)をぼくの独断と偏見で挙げさせていただく。古いほうから述べると、まずはウォルト・ディズニー・アニメーション・スタジオ製作による長編映画第1作で、世界初の長編アニメーション映画でもある『白雪姫』(1937年)の挿入歌「いつか王子様が(Someday My Prince Will Come)」が、なんといっても素晴らしい。白雪姫が7人のこびとに向かって歌うあの曲だ。歌っているのは、白雪姫役の声優でもあるアドリアナ・カセロッティ。作詞はラリー・モーリー、作曲はフランク・チャーチルによる。なおチャーチルはもともとピアニストだったが、ディズニー・スタジオに入社し同社のアニメ作品を多く手がけた。
このワルツ・タイムで歌われる可憐でピュアなイメージを与える名曲は、多くのジャズ・ミュージシャンによってレコーディングされている。モダン・ジャズの帝王ことマイルス・デイヴィスなどは、曲名をそのままアルバム・タイトルに冠した『サムデイ・マイ・プリンス・ウィル・カム』(1961年)というリーダー作をリリースしている。このヴァージョンでは、イントロに観られるペダルポイントの技法が特徴的。コードの変化にかかわらずボトムを司るベースはおなじ音(持続低音)を弾きつづけるという手法だ。このメソッドは後続のジャズ・プレイヤーたちによって、よく真似されたものである。マイルスのキレのあるミュート・ソロも然ることながら、構成の妙が際立つ名演だ。
とにかく星の数ほどのレコーディングが存在するこの曲、圧倒的にピアニストの作品が多い。オスカー・ピーターソン、ハービー・ハンコック、キース・ジャレット・スタンダーズ・トリオ、チック・コリア・アコースティック・バンドなど、名演も多い。もっとも古い吹き込みは、スタン・ゲッツのグループに在籍したことで知られる幻のピアニスト、ジョン・ウィリアムスがエマーシー・レコードに吹き込んだ『ジョン・ウィリアムス・トリオ』(1956年)のヴァージョンあたりだろう。パウエル派とも云われる彼の唯一のリーダー作は、その軽快なスウィング感から日本ではたいへん人気があって、ことあるごとにリイシューされる。一応お断りしておくが、ジョージ・ルーカスやスティーヴン・スピルバーグの映画のスコアを手がけたひととは、同姓同名の別人だ。
そんななかでもっとも有名な「いつか王子様が」といえば、やはりビル・エヴァンス・トリオの『ポートレイト・イン・ジャズ』(1960年)に収録されている演奏だろう。このアルバムは云うまでもなく、ベースにスコット・ラファロ、ドラムスにポール・モチアンを迎えて吹き込まれた、エヴァンス・トリオのいわゆる4部作のうちの最初の作品だ。1959年12月28日のセッションにおいて、この曲をエヴァンスはまず自身のソロ・ピアノでリリカルにスタートさせる。ルバートからインテンポになるとトリオはよく引き締まったインタープレイを展開。エヴァンスが多彩なフレーズを綴っていくなか、ラファロの力強くも繊細さが光るベース・ソロも繰り出される。その1年半余りあと、ラファロは交通事故に遭い帰らぬひととなった。
ディズニー・ソングのジャズ・ヴァージョンに関するあれこれ
ぼくもエヴァンス・トリオのヴァージョンは文句なしの名演と思うけれど、個人的に好きなのはウィントン・ケリーの『サムデイ・マイ・プリンス・ウィル・カム』(1977年)のなかの演奏。ケリーがヴィージェイ・レコードに残した名盤『枯葉』(1961年)と同日のセッションで、1961年7月20日にベースにサム・ジョーンズ、ドラムスにジミー・コブといったトリオで吹き込まれた。当初は1961年に発売される予定だったがお蔵入りとなり、ケリーがすでに他界したあとの1977年にようやく日の目を見た。ぼくはジャズ・ピアノを独学する際、ケリーのピアノ・プレイをよく聴きいていたのだけれど、そのレイドバックが少なめの独特のスウィング感に魅力を感じたもの。ここでも彼は明朗快活にスウィングしているのだけれど、しごく垢抜けて聴こえる。そこがいい。
さて、つづいて2曲目だが、こちらはだれもが掛け値なしにディズニー・ソングの名曲と評価するであろう。1940年公開の『ピノキオ』の主題歌「星に願いを(When You Wish Upon A Star)」だ。おそらく「小さな世界(It’s A Small World)」や「ミッキーマウス・マーチ(Mickey Mouse Club March)」と並んで、多くのひとがディズニー、あるいは東京ディズニーランドといえば、この曲のメロディを思い浮かべるのではないだろうか。ぼくはこの曲を聴くと、ついスティーヴン・スピルバーグ監督による映画『未知との遭遇』(1977年)のエンディングを思い出してしまう。リチャード・ドレイファス演じる主人公のロイが、家族と観に行きたかった映画が『ピノキオ』だったことから使用された。
ただしこの曲が流れるのは、1980年に発表された『特別編』のみでのこと。スピルバーグは当初から「星に願いを」を使うつもりだったのだが、試写の批評が芳しくなかったことから使用を断念。リニューアル版によって、ようやく彼の願いは成就した。それは、まるで異星人の存在に思いを馳せ星空を見上げる──そんな人類の見果てぬ宇宙への憧れが象徴されているかのようだった──。オーケストラによってあの有名なコダーイ・ゾルターンのペンタトニック・スケールなどが奏でられたあと、銀幕から(サビの旋律からはじまる)「星に願いを」が聴こえてきたとき、ぼくはなんともロマンティックな気分にさせられた。星に願いをかければ夢が叶うという内容の歌詞もイメージに合っているが、生憎ここで歌は入ってこない。
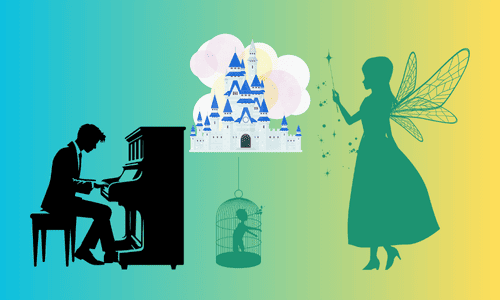
原曲は『ピノキオ』でコオロギのジミニー・クリケットを演じた、ヴォードヴィリアンのウクレレ・クリフことクリフ・エドワーズが歌った。彼の歌は、映画のオープニングクレジットとラスト・シーンで流れる。作詞はネッド・ワシントン、作曲はリー・ハーラインによる。ワシントンは「オン・グリーン・ドルフィン・ストリート」や「星影のステラ」の歌詞を書いたひと。ハーラインは1932年から1941年までウォルト・ディズニー・プロダクションに所属しており、前述の『白雪姫』の劇伴や短編アニメ映画シリーズ『シリー・シンフォニー』(1929年〜1939年)の音楽を手がけた。この「星に願いを」は、アカデミー賞において作曲賞、歌曲賞を受賞したが、オスカーを獲得した最初のディズニー・ソングとなる。
ジャズ・ヴァージョンではやはりピアニストのアルバムで採り上げられることが多いが、すぐに思い出されるのはケニー・ドリューの初期の傑作、リヴァーサイド盤『ケニー・ドリュー・トリオ』(1956年)での演奏。ルバートでの美しいソロ・ピアノのエクスプレッションと、インテンポでのポール・チェンバースのベースとフィリー・ジョー・ジョーンズのブラシとが打ち出す軽妙なリズムをともなって展開されるリリカルなバラード・プレイは絶品。ホントこのころのドリューのパフォーマンスには、深い情感が込められていて素晴らしい。なおドリューはこの曲をずっとあとに『ファンタジア』(1984年)というアルバムでも演奏しているが、こちらからはいささか奇を衒ったような印象を受ける。最初のプレイのほうが、断然いい。
個人的にどうしてもお薦めしたいのは、ビル・エヴァンスの『インタープレイ』(1962年)に収録されているヴァージョン。本作は、フレディ・ハバード(tp)、ジム・ホール(g)、パーシー・ヒース(b)、フィリー・ジョー・ジョーンズ(ds)、そしてビル・エヴァンス(p)といった敏腕家たちが繰り広げる、知的で洗練された印象を与えるポスト・バップ作品。彼らは「星に願いを」においても、唯一無二の艶やかさと軽やかさをもつ演奏を展開。繊細なフィーリングをもつイントロから、ちょっとグレイッシュなホールのギターによるテーマへ移行。それに絡むハバードのトランペットによるオブリガートが、ことのほか美しい。寛いだ雰囲気のなか、エヴァンスは都会的であり官能的でもあるフレーズを淡々と綴っていく。まさに快演だ。
では、最後に3曲目だが、この曲は前述の2曲と比べるとやや慎ましやかな存在感を放つ。しかしその野に咲くいち輪の花のごとき淑やかな美しさに、ぼくはこころ惹かれるのである。曲は1951年公開のミュージカル・ファンタジー・コメディ『ふしぎの国のアリス』の主題歌「不思議の国のアリス(Alice In Wonderland)」で、おなじディズニー作品『ピーター・パン』(1953年)でも知られるザ・ジャド・コンロン・コーラスが歌っている。リーダーのジャド・コンロンはシンガーであり、コーラスのアレンジャー兼コンダクターでもある。彼はザ・リズメアーズという男性3人女性2人のコーラス・グループを結成し、ビング・クロスビーなどのバックグラウンド・ヴォーカリストとして活躍した。
この飾り気はないけれどメロディック・ラインがどことなく愛らしい曲、作詞はボブ・ヒリアード、作曲はサミー・フェインによる。ヒリアードはマンハッタンの音楽出版社、ティン・パン・アレーで作詞家として活躍したひと。個人的には、フランク・シナトラが歌った「夜は更けて(In The Wee Small Hours Of The Morning)」という曲が好き。デヴィッド・マンが作曲した美しいバラードだが、カーリー・サイモンのカヴァーも有名だ。かたやフェインといえば、その代表曲はなんといっても映画『慕情』(1955年)の同名主題歌だろう。アカデミー賞において歌曲賞も獲得している。作詞はポール・フランシス・ウェブスターが手がけた。ヒリアードは前述の『ピーター・パン』をはじめ『眠れる森の美女』(1959年)『ビアンカの大冒険』(1977年)といったディズニー作品に、楽曲を提供している。
ときに『不思議の国のアリス』のジャズ・ヴァージョンだが、さきに挙げた2曲と比較するとぼくの記憶に残っているものはごく限られる。俗に名演と云われるのは、オスカー・ピーターソンがサム・ジョーンズ(b)、ボビー・ダーハム(ds)といったトリオでドイツのMPSレコードに吹き込んだ『オスカー・ピーターソンの世界』(1968年)のなかのワンテイク。ほっこりするような楽しい演奏ではあるが、例によってハッピー過ぎるというかデリカシーに乏しい。意外なところでは、われらが佐藤允彦のエディ・ゴメス(b)、スティーヴ・ガッド(ds)をサイドに迎えた六本木ピットインでの実況録音『ダブル・エクスポージャー』(1988年)のなかの1曲。ピアノ・トリオのスリリングなインタープレイは秀逸だが、これもまた(ぼくのイメージする)可憐というコトバからはほど遠い。
ディズニー・ソング集をコマーシャル・ベースに乗せるひと
ということで、ビル・エヴァンスに三たびご登場いただく。前述の4部作のうち3作目に当たる『サンデイ・アット・ザ・ヴィレッジ・ヴァンガード』(1961年)に収録された、エヴァンス、ラファロ、モチアンといった俗にいうファースト・トリオの演奏。云うまでもなく1961年6月25日にニューヨーク市マンハッタン区グリニッジ・ヴィレッジに所在するジャズ・クラブ、ヴィレッジ・ヴァンガードで録音された素材である。さきにも触れたが、ラファロはこの収録からわずか11日後に不慮の死を遂げる。急遽発売されたアルバムは、“フィーチュアリング・スコット・ラファロ”というサブタイトルが付されたように、彼を追悼するものであり、全編にわたってそのベース・プレイのもち味が出たトラックでまとめられている。
本作における3人のプレイはパーフェクト過ぎて逆に容易ならざる雰囲気を放つのだが、くだんの「不思議の国のアリス」では こころなしか緊張が解ける。それはこの曲がもつ、さながらいじらしい乙女ごころのごときピュアでセンシティヴな味わいが影響しているからだろう。リリカルなピアノのルバートによるテーマのあと、コーラスでインテンポとなりアンサンブルが色彩豊かな風景を織りなす。エヴァンスが繊細なタッチで楚々とした小気味いいフレーズを紡ぎ出しはじめるやいなや、ラファロが重厚かつ軽快に独自の旋律を奏でる。モチアンのブラシもまた、別の色の絵の具で曲を染め上げていく。途中のラファロのポエティックな即興演奏といい、そのあとのエヴァンスのエモーショナルな表現といい、インタープレイの真骨頂がここにある。
往々にしてディズニー・ソングを採り上げている(しかも名演を残している)エヴァンスだから、さぞやディズニー作品に思い入れがあるのだろうと思われるかもしれないが、それはないとぼくは思う。おそらくエヴァンスは自己の音楽表現において、良質と思われるマテリアルを選んでいるだけなのだろう。なにせ彼は楽曲がもつ本質や可能性を見抜く、優れた眼力の持ち主なのだから──。だからエヴァンスのアルバムに、たとえば“トリビュート・トゥ・ウォルト・ディズニー”みたいな作品はない。彼はあの「サンタが街にやってくる」をソロ、トリオ、オーヴァーダブによるひとりデュオ、そして弾き語り(!)と、何度も演っているけれど、かといって猫も杓子もといった具合にクリスマス・アルバムを制作したりはしないのである。
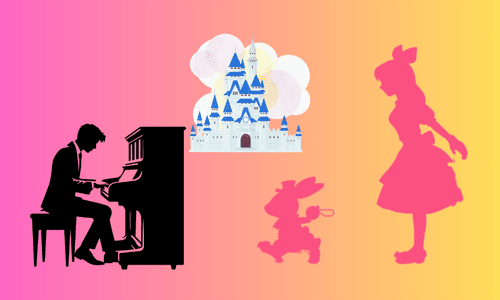
その点、最後になったがデイヴ・ブルーベックは、ディズニー・ソングを採り上げた作品を、まさにコマーシャル・ベースに乗せるようなタイプの音楽家だ。ブルーベックは1920年12月6日カリフォルニア州コンコード市生まれの、ウェストコースト・ジャズの代表的なピアニスト。ザ・デイヴ・ブルーベック・クァルテットのアルバム『タイム・アウト』(1959年)に収録されている、5拍子の曲「テイク・ファイヴ」はあまりにも有名だ。作曲したのはバンド・メンバーのアルト奏者、ポール・デスモンドだけれど、ブルーベックが起案するところもあったと思われる。個人的には、ブルーベックが書いた8分の9拍子の曲「トルコ風ブルー・ロンド」のほうが好き。伝統的なトルコ民謡のリズムが、西洋音楽的な解釈で打ち出されている。
こういうマナーは、もはやジャズではなくクラシックのもの。それもそのはず、ブルーベックは幼少期にピアノ教師を副業としていた母親から、クラシック・ピアノの手ほどきを受けている。10代にディキシーランド・ジャズのバンドで演奏したこともあるが、当初獣医学を学んでいたパシフィック大学でも途中から専攻をクラシック音楽に変えている。初見演奏ができないことから危うく退学になりかけたが、対位法と和声法における優れた才能が認められて無事卒業となった。その点は、いかにも彼らしい。またブルーベックは従軍後ミルズ大学に通い、フランスの近現代音楽の大家、ダリウス・ミヨーにフーガやオーケストレーションを学んでいる。そういう経歴ゆえ、彼が奏でるジャズはクラシック音楽からアプローチしたものと受けとられる。
したがってブルーベックの音楽家としての魅力といえば、卓越したコンポジションとアレンジメントに尽きる。ピアノ・プレイは控えめで、いかにもアレンジャーが弾いているといった印象を与える。彼は1940年代の終わりごろから2012年12月5日、コネチカット州ノーウォークの病院において91歳でこの世を去るまで、膨大な数のリーダー・アルバムを残している。しかしピアノ・トリオ作品ともなると、ごく僅かしかない。しかもトリオといっても、ドラムスよりもパーカッションやヴィブラフォンが入ることが多い。ということでピアニストとしてまえに出ようとはしないブルーベックではあるが、彼がクリエイトするトータル・サウンドはフルコースでもアラカルトでも絶品。特にデスモンドとのクァルテットは極上だ。
ザ・デイヴ・ブルーベック・クァルテットの『デイヴ・ディグズ・ディズニー』(1957年)は、ぼくにとって『タイム・アウト』と並んで長きにわたり愛聴盤となっている。本盤が商業的な成果を上げながらも単なる企画モノに終わらない充実した内容となっているのは、かねてよりブルーベックがディズニー・ソングを自己のコンボのレパートリーとして何度も採り上げていたからだろう。ここではさきに挙げたぼくのベスト3も、すべて収録されている。パーソネルは、デイヴ・ブルーベック(p)、ノーマン・ベイツ(b)、ジョー・モレロ(ds)、そしてポール・デスモンド(as)となっている。ベイツは兄のボブのあとを引継ぎ1955年から1958年までコンボのボトムを支えた。モレロはのちの変拍子ジャズを成功に導いたリズム面でのキーパーソン。
オープニングの「不思議の国のアリス」では、なんといってもテーマがオリジナルの展開を見せるピアノのルバート演奏がスウィート。実はぼくもかつてこの曲を弾いたとき、このアレンジをそっくりマネしたもの。煌びやかなコーラスで転調したあと、デスモンドがまろやかな音色で甘クチのソロを聴かせる。ブルーベックもやや訥々とした感じも受けるが優雅さを放つ。後半の4人のソロ交換も軽快だ。つづく『ピノキオ』からの「口笛吹いて」では、デスモンドとモレロの絡み合いが甘美な気分を醸し出す。 ブルーベックの気取った感じのフレージングもオツだ。A面ラストの『白雪姫』からの「ハイ・ホー」では、クァルテットがアップテンポでストレートにスウィングする。コンボの躍動感も然ることながら、ここでは断然モレロによるソロの切れ味のよさが光る。
B面最初の「星に願いを」では、ゆったりとしたテンポに乗ってデスモンドが流麗なフレーズを紡ぎ出しつづける。その乾いた感じとリラックスしたムードは絶品。エンディングのブルーベックによるエモーショナルなルバート演奏もいい。つづく「いつか王子様が」では、これぞブルーベック・サウンドといった感じのアレンジが施されていて、変拍子ジャズへの先駆的なプレイが聴ける。特にワルツのリズムでの、ブルーベックのアドリブにおけるポリメトリックなアプローチがキャッチーだ。ラストを飾る『白雪姫』からの「ワン・ソング」では、クァルテットによる快速調の力強い演奏が、得もいわれぬ爽快感を生む。エンディングのバロック風の表現もまた軽妙だ。以上、ぼくにとって本盤は、気軽にディズニーの世界に触れることができる、良質のBGMとなっている。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。








コメント