「口紅にミステリー」──田辺信一が音楽を手がけた東宝映画「金田一耕助シリーズ」第4弾『女王蜂』のオリジナル・サウンドトラック・アルバム
 Album : 田辺信一 / 女王蜂 オリジナル・サウンドトラック (1978)
Album : 田辺信一 / 女王蜂 オリジナル・サウンドトラック (1978)
Today’s Tune : 女王蜂のテーマ
秋の気配が漂う天城の山道──仲代達矢が与える強烈なインパクト
久々に東宝映画「金田一耕助シリーズ」のサウンドトラック・アルバムを採り上げる。石坂浩二主演、市川崑監督によるシリーズ第4弾『女王蜂』(1978年)である。この映画は、1978年2月11日に公開されたのだけれど、当時まだ小学校高学年生だったぼくはクラスメイトとともに劇場に足を運んだ。そんなこともあって、個人的にはちょっとした思い出の1本となっている。この映画を観たのは春の気配をほのかに感じるころだったが、ぼくがこの作品からいの一番に連想するのは、秋という季節である。スクリーンに映し出される伊豆の天城山や京都市の風景では、木々の葉があたかも錦のごとく美しい秋色を帯びている。原作では春から初夏に移り変わる時季のハナシだったが、映画版の改変をぼくは天晴れと云いたい。
たとえば映画の冒頭のシーンなどは強く脳裏に焼きつけられていて、却って軽い心理的苦痛を感じるほどだ。昭和7年、秋の気配が漂う天城の山道を、ふたりの学ラン姿の男と着物姿の見目麗しい女性が歩いてくる場面だ。色鮮やかな山景に、ピアノのスタッカートとストリングスのクレッシェンドとが呼応するような音楽(サントラ盤では「一枚の写真」というタイトルの曲)が挿入され、爽やかな空気を作り出している。物語の発端となる過去のシーンなのだが、注意して観ていると登場人物の性格や身の上などが抜け目なくほのめかされていることがわかる。まあ、映画だけでなく小説もそうだけれど、作品のイントロダクションでは定めし重要なこと柄が語られているのである。
具体的には、ふたりの学生が握りこぶしを振りながら歌っているのは「逍遥の歌」という曲なのだけれど、これは京都大学の前身のひとつである旧制第三高等学校の寮歌。彼らが京都帝国大学の学生で京都からやってきたことがわかる。しかもその学生服に注目すると、ひとりは下ろしたてと思われる服を折り目正しく着こなしている。それに反してもうひとりは、弊衣破帽のバンカラ学生風。その着古した服、ことに擦り切れた帽子は胡散くさいほどボロボロだ。これはふたりの身分の違いをハッキリ示すものであって、その後の不幸な出来事を暗示するものでもある。延いてはそのことが、実は物語の中心となる連続殺人事件の犯行の動機について、それとなく観客に手がかりを与えているとも云えるのだ。
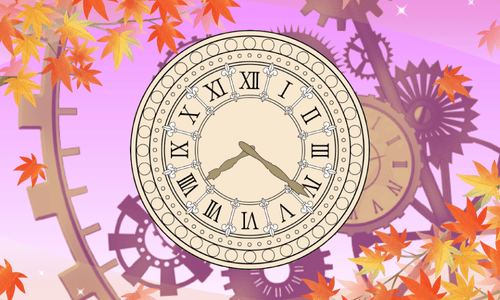
さながら本編の理解を助ける序説のようなシーンだが、すでに述べたように小学生のぼくにとっては、軽い心理的苦痛をともなうものでもあった。その原因はふたりの学生のうちのひとり、当時は「速水」姓だった大道寺銀造(原作では大道寺欣造)を演じた仲代達矢の圧倒的な存在感だ。市川作品では『炎上』(1958年)の戸刈(三島由紀夫の原作小説『金閣寺』では柏木)、さらに『鍵』(1959年)の木村といった難しい役どころを革新的な芝居で見事に演じた。そんな個性的な演技とそのガッシリした体躯やカッと見開いた双眸とが相まって、仲代さんは強烈なインパクトを与える。さらに仲代さんは『女王蜂』が封切られてからちょうど半年後、異例の早さで公開された市川作品『火の鳥』(1978年)にも出演している。
この市川監督自らが失敗作と云い放った『火の鳥』において仲代さんが演じたのは、大陸から来た馬賊、高天原一族の冷酷な族長、ジンギ(手塚治虫の原作漫画ではニニギ)。弥生時代末期の日本が舞台となるこの物語では、現在の学説では完全に否定されているが、当時の歴史学では議論の対象として波紋を呼んでいた「騎馬民族征服王朝説」が採り入れられている。火の鳥がもつ永遠の生命にはまったく興味を示さず、ひたすら国々を粉砕、侵略し、逆らうものはみな虐殺するという、非情な現実主義者とも云うべきジンギは、まさに仲代さんのハマり役だった。そして『女王蜂』『火の鳥』といった両作品において邂逅した仲代さんは、ぼくにとって、その年のもっとも印象に残るアクターのひとりとなったのである。
ところで『女王蜂』の仲代さんだが、撮影は1977年の11月から開始されたということだから、スクリーンに登場する氏の実年齢は45歳か46歳(1932年12月13日生まれ)。にもかかわらず、仲代さんは冒頭のシーンで大学生を演じているのだ。山道を一緒に歩いているのは、佐々木勝彦演じる日下部仁志(銀造の学友で原作では日下部達哉となっている)と、萩尾みどり演じる大道寺琴絵(銀造と仁志が伊豆旅行で訪れた名家の娘)。その後、昭和11年の夏に銀造は琴絵に求婚するのだが、その場面で彼は春に大学を卒業し京都の材木会社に就職したと述べているので、最初に天城を訪れたときはおそらく20歳くらいと思われる。いくらなんでも、それにはちょっと辛いものがあるだろう。
ちなみに仁志役の佐々木さんは当時33歳、琴絵役の萩尾さんは23歳だった。まあ昔のひとは現代のひとと比較すると同年齢でも老けて見えたようだから、おふたりの場合はギリギリセーフと云えるのかもしれない。しかしながら仲代さんの場合は、どんなにひいき目に見ても20歳には見えない。失礼ながら、なにも知らずにいきなり写真だけ見せられたら、きっとぼくも氏のことをバンカラ学生のコスプレをした酔狂なオッサンと思ってしまっただろう。現にはじめてこの映画を観にいった帰り路、ぼくはクラスメイトと一緒になって「銀造は若いころから老けていたんだな。そりゃ琴絵も仁志のほうを好きになるよな」(琴絵と仁志は相思相愛)などと、冗談めかして大いに笑ったのだった(ゴメンなさい)。
そんなわけで、映画『女王蜂』の冒頭のシーンは、ぼくの脳裏に強く焼きつけられたのだった。いまでも秋になると、ふとしたときにこの映画のことが思い出され、それと同時に学ラン姿の仲代さんがアタマをよぎるのだ。これはもはや、トラウマ体験からくるフラッシュバックのようなものだ。いやまてよ、もしやこの演出は、日本映画の巨匠でありながら作品の随所に前衛的な技巧を凝らすという、市川崑が仕掛けた思いもよらない落とし穴なのではなかろうか。そういえば「金田一耕助シリーズ」では決まって、ストーリーが通常時間軸に沿って進行するなかで、にわかに過去の場面が割り込んでくると、たとえ中高年の俳優であっても本人がそのまま若いころを演じていたりする。
推理小説としてはイマイチ、映像化という点では非常に人気が高い
このパターンに当てはまるのは、主演女優の場合が多い。たとえばシリーズ第1作『犬神家の一族』(1976年)の高峰三枝子、三条美紀、草笛光子らが演じる犬神三姉妹(なぜか白塗りメイク)が、父親の愛人宅に三種の家宝をとり返しにいく場面、第2作『悪魔の手毬唄』(1977年)の岸恵子が演じる亀の湯の女将の女芸人時代、第3作『獄門島』(1977年)の司葉子が演じる本鬼頭家の下働きのお遍路さん時代(おさげ髪が可愛い)、第5作『病院坂の首縊りの家』(1979年)の佐久間良子が演じる法眼病院の女理事長の恋人との逢瀬のシーン(衣装が大正ロマン風)などがそれに該当する。さらに同作で女理事長の母親役を務める入江たか子に至っては、なんと当時68歳という年齢で40歳代を演じている。その突拍子もない絵面は、倒錯の世界と云いたくなるほどだ。
まあこの市川流の作法は、たいてい事件の顛末が説明されるときフラッシュバックとして施される。そしてよくよく考えてみると、事件に深く関わった人物の過去の出来事が語られるとき、それを若くてよく似た代理の役者が演じるよりも、たとえ道理に反しているとはいえ本人が演じたほうが、たとえば運命から背負ってしまった宿業のようなもの、それから生まれる哀感のようなものがストレートに伝わってくるようにも思われる。ただ『女王蜂』の場合、オープニングの昭和7年から物語の通常時間軸である昭和27年に移行するまでは、それなりの長さがある。前述の『獄門島』では、司さん扮するおさげ髪のお遍路少女も、さらなる若き日では、荻野目慶子、荻野目洋子が代役を務めたのだから、仲代さんの場合もそのような便宜がはかられるべきだったのでは──。
なぜそうされなかったのかは、いまとなっては知る由もないけれど、大学生の銀造を人生半ばの過渡期にあたる仲代さん本人が演じるという、無理のある趣向は敢行された。そこで観客に違和感を覚える隙を与えないようにするためか、禍根となる過去のシーンは盛り沢山のわりには7分強と、並外れたテンポのよさを見せる。こういうスピーディな展開は『八つ墓村』(1996年)の序盤と同様に、いかにも市川作品らしい。それに反して後半の事件解決のくだりでは進行が緩慢になり、そこに漂うお涙ちょうだいのムードにはいささか嫌気が差す。大道寺家が所在する伊豆の天城山中や、野点の会場となった京都市右京区の仁和寺など、とにかく紅葉の美しさに思わずため息が出るシーンが多い『女王蜂』だが、ハッキリ云って全体的にはキレがわるい。
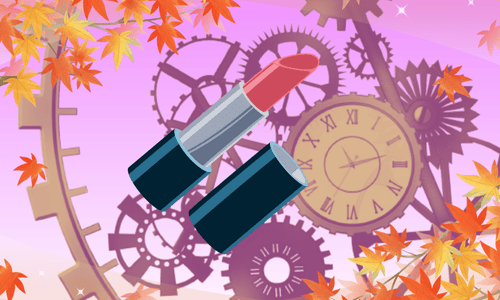
そもそも原作小説の『女王蜂』が、横溝正史が著した数々の本格派推理小説のなかにおいて、探偵小説の愛読者を自認する市川監督が『犬神家の一族』『悪魔の手毬唄』『獄門島』につづき映画化を希望するほどの名編かというと、いささか疑問である。ミステリー小説としては『女王蜂』よりも『本陣殺人事件』『八つ墓村』『悪魔が来りて笛を吹く』といった作品のほうがはるかに傑作であると、ぼくは思う。しかしながらそれらの作品は、当時空前の横溝ブームだったこともあり、ATG、松竹、東映によってすでに映画化されていたか、あるいは映画化権が取得されていた。そんなわけで、市川監督にとって『女王蜂』の映画化は、苦渋の選択だったのかもしれない。
横溝作品には、ほかにも『仮面舞踏会』『三つ首塔』『夜歩く』『不死蝶』といった、金田一耕助が登場する面白い作品はあるにはあるのだけれど、当然のことながら映像作品として引き立つかどうかはハナシが別だ。なお、個人的には1970年代に執筆された『病院坂の首縊りの家』と『悪霊島』とが金田一モノのベスト10に入るのだけれど、東宝が「金田一耕助シリーズ」の4作目を企画したとき、前者はまだ連載が終わっていなかったと思われるし、後者に至っては執筆すらされていなかった。ということで結局『女王蜂』の映画化と相なったわけだが、横溝さん自身も「(自選の)ベスト10に入れるとなると躊躇せざるをえない」と述べているとおり、この作品には推理小説における謎や論理の整合性という点でいささか不満が残る。
しかしながら『女王蜂』は映像化という点では、非常に人気の高い作品となっている。推理小説においてとりわけ重要な意味をもつ要素といえばトリックだが、この小説ではトリックらしいトリックを見受けることができない。横溝ミステリーならではの絢爛たる装飾が施された見立て殺人も出てこない。法律事務所からの依頼を受けて探偵の金田一耕助が行動を起こすという筋立て、彼が依頼案件に介入した途端、次々に殺人事件が起こるという展開は『犬神家の一族』とおなじだが、事件に絡む問題が相続争いならぬ婿争いと、いささかスケールがダウンする。それでも源頼朝の末裔と称する大道寺家の娘であり、しかも気高い絶世の美女であるヒロインが、凄惨な事件に巻き込まれるというプロットは、映像作品にうってつけなのだろう。
現に『女王蜂』は、市川作品を含めて7回も映像化されているのだ。せっかくなので具体的に挙げてみよう。なおカッコ内は、映画公開年ないしテレビ放映年、配給会社ないし放送局、そして金田一役の俳優となっている。①『毒蛇島綺談 女王蜂』(1952年/大映/岡譲二)、②『女王蜂』(1978年/東宝/石坂浩二)と、ここまでは劇場映画で以下はテレビドラマとなる。③『横溝正史シリーズII 女王蜂』(1978年/TBS/古谷一行)、④『横溝正史傑作サスペンス 女王蜂』(1990年/テレビ朝日/役所広司)、⑤『名探偵 金田一耕助シリーズ 女王蜂』(1994年/TBS/古谷一行)、⑥『横溝正史シリーズ 女王蜂』(1998年/フジテレビ/片岡鶴太郎)、⑦『金田一耕助シリーズ 女王蜂』(2006年/フジテレビ/稲垣吾郎)、以上計7作品である。
ぼくははからずも、この7作品をすべて鑑賞するに至った。①ではマムシがウジャウジャいる毒蛇島で、不死身かつ変装名人の金田一が背広姿で活躍する。③ではヒロインの影の守護者的存在、多門連太郎が悲惨なことに──(いくらなんでも、それはないだろう!)。④ではストーリーラインがほぼ原作どおりに進行するが、ホラー色の強いシークエンスがつづくなか、気のいい金田一がダイナミックに奔走する。⑤では原作とはまるで別モノのストーリーが展開され、特にヒロインが酷い扱いを受ける(もはや『女王蜂』ではない)。⑥ではストーリーが大幅に変更されているが整合性がとれていない。ハッキリ云って、理性を失うほど情に脆い金田一が疎ましい。⑦では横溝作品へのリスペクトは感じられるものの、バラエティ番組風の過剰な演出に嫌気が差す。
ポップなコンポジションとモダンなアレンジが冴えている
結局のところ、市川監督がメガホンをとった東宝映画「金田一耕助シリーズ」5作品のなかでは、もっとも詰めの甘い『女王蜂』ではあるが、原作を同じくするほかの6作品と比較してみると、そのどれよりも映像芸術としての完成度が高く、こころ置きなく横溝ワールドを満喫することができる映画であると、あらためて感じられる。惟みれば市川監督のアイディアによる、かつてシリーズに出演した高峰三枝子、岸惠子、司葉子といったヴェテラン女優の競演、早世の二枚目俳優、佐田啓二の忘れ形見で、当時は早稲田大学第一文学部に在籍していた中井貴惠のヒロイン抜擢といった粋な計らいもまた、すこぶる楽しい。そして、協力監督として松林宗恵が手がけたロケシーン、ことに紅葉の艶やかな色彩が実に素晴らしい。
1960年代後半に東宝のエース監督として活躍した松林さんは、市川監督とは気ごころの知れた仲。その職人気質も手伝って、氏の撮った映像は市川ワールドに違和感なく溶け込んでいる。市川監督が援軍を要請するのはごく稀なケースだが、これはすでに『火の鳥』の制作に取りかかっていた氏による、タイトなスケジュールに対する窮余の一策である。原作では物語の舞台が、伊豆の下田港からおよそ28キロの海上に浮かぶ月琴島と東京とを往来するが、映画ではそれぞれ天城山中の月琴の里、そして京都に設定変更された。その結果、繰り返しになるが、フィルムに各々の地の錦秋が見事に収められた。それは『女王蜂』を原作とした7本の映像作品のなかで、市川版が圧倒的な艶やかさを誇る要因のひとつでもあろう。
ちなみに、市川監督が手がけた「金田一耕助シリーズ」5作品に、東京は出てこない。東京が京都に変更された『女王蜂』と同様に、シリーズの最終作にあたる『病院坂の首縊りの家』(1979年)においても、物語の舞台が原作の東京都港区高輪から吉野市という架空の土地(奈良県の吉野町がモデル?)に変更されている。以下はぼくの推測になるので、あらかじめご了承いただきたい。市川監督は折に触れて、金田一耕助は神様や天使のような存在である──というようなことを述べている。石坂浩二が演じる金田一は、狂言回しとして人間の運命を悄然と俯瞰する。そういう風格は、まさに天使。そんな市川版金田一は原作どおり東京から来た探偵という設定だが、天使である彼が住むところは天界。地上の遥か上にある東京は、決して描かれることはないのである。
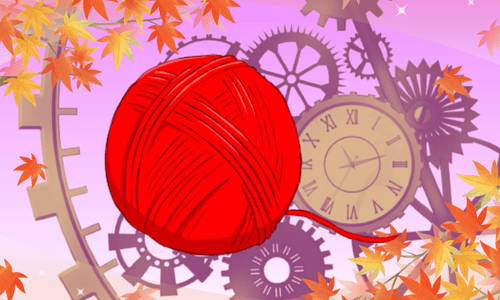
それはさておき映画『女王蜂』では、その風光明媚なロケシーンも然ることながら、ヒロイン大道寺智子を演じた中井さんのフレッシュで溌剌とした魅力も作品に華やかさを添えるものとなった。この映画はもともとカネボウ化粧品とのタイアップ作品だったが、中井さんはカネボウの当時の新商品でリップとグロウがひとつになったリップスティック「ツイニー」のコマーシャルモデルも務めた。商品のキャッチフレーズはズバリ「女王蜂のくちびる」で、テレビCMでは加藤武演じる等々力警部が「ツイニー」を手にしながら「口紅にミステリー」と呟く。しかもこの映像、映画本編のカットとは別に用意されたCMオリジナルのものだったりする。そうとは知らず撮影に臨んだ加藤さんは、あとで事情を知らされて大いに照れたという。
この口紅は映画では智子の母、琴絵の形見として登場し、大道寺家の開かずの間をひらく鍵の在り処を知らせる重要なアイテムとなっている。そんな気の利いた映画と化粧品との連携は見事に成功を収め、作品の出来は一歩も二歩も譲るものの『女王蜂』は、前作『獄門島』を上回るヒットを記録した。そして「女王蜂のくちびる」キャンペーンのイメージソングとして制作されたのが「愛の女王蜂」である。作詞を松本隆、作曲を三木たかし、編曲を若草恵が手がけた。シングル・レコードは映画公開の3週間ほどまえに発売され、メディアミックス戦略としては絶大な効果を上げた。この曲を歌ったのは、1977年に開催された第6回東京音楽祭国内新人大会において最優秀歌唱賞を獲得した塚田三喜夫だった。
塚田さんが歌う「愛の女王蜂」は、情熱的な歌唱、メジャーキーに転調するサビ、はたまた煌びやかなアレンジと、いかにも1970年代のビート歌謡といった感じだ。むろん映画本編では使用されていないが、そこはタイアップということで、劇伴ではサワリだけだがインストゥルメンタル・ヴァージョンが何度か流れる。フィルム・スコアは、昭和歌謡をはじめ映画やテレビドラマの劇伴など、数多くの作編曲を手がけた田辺信一によるもの。田辺さんは『悪魔の手毬唄』でアレンジとコンダクティングを担当、前作『獄門島』からはシリーズすべての音楽を手がけている。サウンドトラック・アルバムは映画の公開の直前に発売されたが、演奏は毎度のごとく東宝スタジオ・オーケストラとなっている。
このアルバムでは珍しくインサートにリズム・セクションのみだがメンバーの記載があるので、以下に列記しておく。井上鑑(key)、津村泰彦(g)、金田一昌吾(b)、宗台春男(ds)、川原直美(perc)、前田照光(Bandoneon)となるが、特に前田さんによるバンドネオンの演奏は、この映画に横溢する秋のイメージに見事にフィットしている。曲目はホンキートンク・ピアノとバンドネオンがリードをとる躍動的な「女王蜂のテーマ」ストリングスのトレモロやギターのスライドが不穏な空気を作る「月琴の里」木管と弦、それにハープが艶やかな秋の彩りを描き出す「智子のテーマ〜愛の女王蜂」ヴァイブ、ピアノ、バンドネオン、そして弦が燃える秋を演出する、転調を効果的に使ったシンプルな「アカイケイトノタマ」とつづく。
さらにバンドネオンがストレートに哀感を伝える「父の墓」弦の刻みとハーモニクス、金管のアクセント、そしてギター・ソロが印象的に反復する「京都へ」本編では未使用のやはりバンドネオンがフィーチュアされたフランスの映画音楽を彷彿させるメランコリック・ナンバー「銀造のテーマ〜灰色の海」と、レコードではここまでがA面。B面は「父の墓」と同曲でウェットなアコースティック・ギターが哀憐を誘う「秀子のテーマ〜閉ざされた思い」からスタート。その後「愛の女王蜂」のメロディに不安感を煽るアンサンブルが重なる「開かずの間」秋の気配を感じさせる軽やかなリフレインから重厚な「女王蜂のテーマ」へと繋がる「一枚の写真」ストリングスのトレモロやスラップ・ベースの弾音が凄惨な場面に直結する「血ぬられた茶会」とつづく。
さらにゴスペル・タッチのピアノとワウ・ペダルを使ったギターがいい塩梅のコミカル・ナンバー「ある日の金田一耕助」不気味で重苦しいムードのシークエンスとショッキングなコーダで結ばれる「時計台」そして、ゆったりとしたテンポで「女王蜂のテーマ」がリプライズされる「遺書」でアルバムは締め括られる。厳かな陰影を湛えながらも爽やかな余韻を残すところには、田辺さんの作編曲のセンスのよさが感じられる。ただし、CD化の際に追加された「愛と憎しみ」は「女王蜂のテーマ」のプロトタイプのような印象を与えるが、いささかピントの外れた8ビートや頓狂なオブリガートが、映画の雰囲気にそぐわないように思われる。まあそれを除けば『女王蜂』の音楽では、田辺さんのポップなコンポジションとモダンなアレンジが冴えている。そしてそれは間違いなく、映画をより秋色に染めるものだった。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。








コメント