アジムスのキーボーディスト、ジョゼ・ホベルト・ベルトラミがキャリア初期に率いたジャズボサ・トリオ、プロジェート・トレシュによる作品『オ・トリオ』
 Album : Projeto III / O Trio (1968)
Album : Projeto III / O Trio (1968)
Today’s Tune : Can’t Take My Eyes Off You
ジャズボサいろいろ①──タンバ・トリオとサンバランソ・トリオ
今回もピアノ・トリオの作品をご紹介する。とはいっても、いつもとは趣向の異なる1枚である。プロジェート・トレシュなんて聞いたことないな──という、ジャズの愛好家のかたはけっこう多いと思う。それもそのはず。このアルバムで演奏されている音楽は、ビバップでもなく、ハード・バップでもない。1960年代の後半の作品だが、そのスタイルはモード・ジャズでもなく、はたまたソウル・ジャズでもない。では、なんなんだ!?──と、小首をかしげる向きもあるだろう。怒らないで聞いていただきたいのだけれど本作は、要はモダン・ジャズではなく、いわゆるジャズボサにカテゴライズされるものなのだ。それは反則だろ!──という声が聞こえてきそうだ。でもぼくの場合、こう暑いとジャズボサような清涼感のある音楽を欲するのは、ごく自然なこと。
いちいち説明する必要もないと思うけれど、ジャズボサとはジャズとボサノヴァを掛け合わせたコトバ。そもそもボサノヴァ自体が、ジャズの影響を受けた音楽である。ブラジルのサンバやショーロといったトラディショナルな音楽に、ソフィスティケーテッドなテイストを加味しようと、クラシックの印象主義音楽やクール・ジャズなどのアメリカ西海岸の音楽を採り入れたのが、そのはじまりだ。さらにギタリストのバーデン・パウエルやピアニストのアントニオ・カルロス・ジョビンといった、ブラジルのミュージシャンによるインストゥルメンタル・ミュージックがより即興性をもち、ジャズボサへ進化したのだろう。ピアノ・トリオやコンボ・スタイルで演奏されることが多く、ときには即興演奏がヒートアップすることもある。
ぼくは小学校高学年のころからジャズを聴きはじめたのだけれど、それとほぼ同時期からボサノヴァのほうにも関心を寄せていた。それからいまに至るまで、長いあいだ分け隔てなく両者につきあってきた。ジャズ・ファンのなかには、案外ぼくとおなじような楽しみかたをしているひとも、それなりにいるのではないだろうか。たとえば、テナー奏者のスタン・ゲッツのアルバムに『ゲッツ/ジルベルト』(1964年)という、グラミー賞4部門を獲得した大ヒット作がある。“ボサノヴァの神様”と呼ばれるギタリスト兼シンガー、ジョアン・ジルベルトとのコラボレーション作品だ。これはジャズの名門ヴァーヴ・レコードからリリースされたものの、内容的にはジャズ色がかなり薄い。
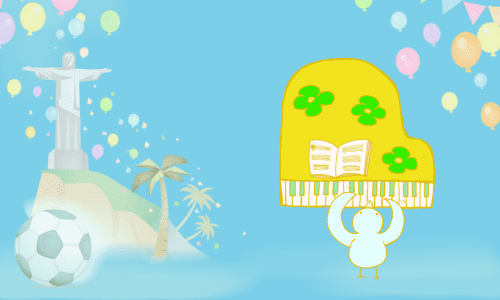
というか、すべてがブラジル産の曲というトラックリストや、アントニオ・カルロス・ジョビン(p)、セバスチャン・ネト(b)、ミルトン・バナナ(ds)、アストラッド・ジルベルト(vo)といったレコーディング・メンバーからもわかるように、もはやこのアルバムのことをボサノヴァ作品と云い切ってしまっても間違いではない。プロデュースを担当したのは、あのクリード・テイラーだけれど、ヴァーヴではほかにもアストラッド・ジルベルトやブラジルのオルガニスト、ワルター・ワンダレイのヒット作を手がけている。彼の意図するところはジャズのポピュラライズで、その一環としてボサノヴァはあつらえむきの音楽だったのだろう。結果的に多くのジャズ・ファンが、ボサノヴァに親しむ契機を得たわけである。
テイラーはCTIレコードを立ち上げてからも積極的に、そのカタログにブラジルの音楽を導入していた。なかでもジョビンやミルトン・ナシメントの作品とともにリリースされた、タンバ・クアトロの2枚のアルバム『二人と海』(1967年)『サンバ・ブリン』(1968年)は強く印象に残った。4人編成のコンボが織りなすサウンドは、濃厚なボサノヴァのテイストが反映されていながら、ピアノとフルートのインプロヴィゼーションや、ベースとドラムスとによるサンバの複合リズムが際立っている。そのアパッショナートな演奏とモダンな響きには、即興演奏に焦点があてられた当時の斬新なジャズのそれと比較しても、まったく引けを取らない躍動感と鮮烈さがあった。
このタンバ・クアトロはもともと、1962年にリオデジャネイロにおいて、ルイス・エサ(p, vo)、ベベート・カスチーリョ(b, fl, sax, vo)、エウシオ・ミリート(ds, perc, vo)によって結成された、タンバ・トリオがもととなっている。なお1971からはふたたびトリオに戻り、カスチーリョ以外は何度かメンバーチェンジが繰り返されるが、バンドは1992年までつづいた。この独特の響きをもつバンド名に冠せられたタンバとは、西アフリカ発祥の樽型の太鼓タンボールと、ブラジル音楽のサンバとが組み合わされた造語である。そのソフィスティケートされたスタイルとスリリングな演奏から、数あるジャズボサ系バンドのなかでも圧倒的な存在感を放っていたのは、このタンバ・トリオだったとぼくは思う。
いまではブラジル音楽産業の中心となっている南半球最大のメガシティ、サンパウロでは1960年代のなかごろ、数多のピアノ・トリオが鎬を削っていた。名実ともにトップを走っていたのは、やはりタンバ・トリオだろう。ぼくは彼らのアルバムをずいぶんと聴いたけれど、同時期にそれとおなじくらい愛聴していたグループがある。それは1964年にサンパウロにおいて、セザル・カマルゴ・マリアーノ(p)、ウンベルト・クライベール(b)、アイルト・モレイラ(ds)によって結成された、サンバランソ・トリオである。まずバンド名が、やはりユニークだ。サンバランソはサンバとバランソを連結したコトバ。バランソは遊具 のブランコの語源となったポルトガル語で、英語のスウィングに直結する。つまり、サンバでスウィングするという意味だ。
ジャズボサいろいろ②──天才肌のピアニスト、ジョアン・ドナート
名は体を表すというけれど、サンバランソ・トリオはジャズボサのグループとしてはかなりジャジーだ。スウィングというよりはバランス感覚というべきなのだろうが、きわめてグルーヴィーだ。ブルージーなフレージングといいアドリブの応酬といい、ジャズ以上にジャズっぽいシーンもある。3人ともパフォーマンス能力が卓越していて、アップテンポでの力強いプレイは迫力満点だ。ただ残念なことに彼らの活動期間は、たったの2年。純然たるトリオ名義のアルバムは、3枚しかない。そんなわけで彼らには、まるで疾風のごとく鮮烈な印象を与えながらジャズボサ・シーンを駆け抜けた──というイメージがある。そのサウンドは、ブラジルのミュージシャンだけでなくジャズ・プレイヤーにも多大な影響を与えた。
ぼくはその昔、上記のふたつのグループを夢中で聴いていたのだが、ルイス・エサとセザル・カマルゴ・マリアーノに関しては、ソロになってからもコンポーザー、アレンジャー、そしてキーボーディストとして敬愛しつづけた。実はおなじような感じで、個人的にリスペクトするブラジルの音楽家がもうひとりいる。アマゾン奥地、アクレ州リオブランコ生まれのピアニスト、ジョアン・ドナートだ。このひとは、天才肌のひと。10代でアコーディオンを弾くようになり15歳にしてレコーディングを経験。ピアノを弾きはじめたのは20歳になってからだが、21歳のときにはすでにドナート・エ・セウ・コンジュント(ドナートとその楽団)名義で、初リーダー作『シャ・ダンサンチ』(1956年)を吹き込んでいる。まあ、まだピアノ演奏はぜんぜん目立っていないけれど──。
ぼくが最初に手にしたドナートのアルバムは、パシフィック・ジャズからリリースされた『サンボウ・サンボウ』(1965年)。いまから考えると、ぼくにとって本作こそが、はじめて聴いたジャズボサのレコードだったように思われる。中学生のころに国内盤を手に入れたのだけれど、レコード店ではジャズのコーナーに陳列されていた。だからきっとこのアルバムは、ジャズの愛好家にもよく知られているのではないだろうか。パーソネルには、ジョアン・ドナート(p)、セバスチャン・ネト(b)、ミルトン・バナナ(ds)、アマウリ・ホドリゲス(perc)と、前述の『ゲッツ/ジルベルト』と重なるところもあるしね。とはいっても本盤は、ブラジルのポリドール・レコードで制作された『ムイト・ア・ヴォンタージ』(1963年)のリイシュー盤なのだけれど──。
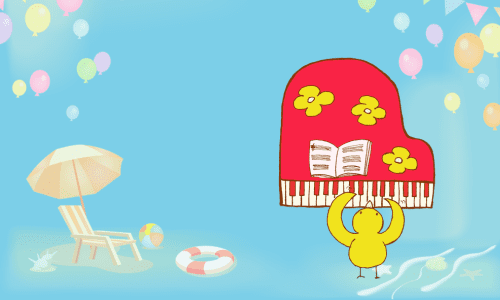
ドナートといえば、ボサノヴァのことをゴキブリを殺虫剤で駆除したサンバと表現したことがある。奇人変人というか、ちょっと気難しいひとというイメージがつきまとう。それに反して、作曲もピアノ演奏も軽妙洒脱。清々しいくらい小気味いい。なちなみにパシフィック盤のタイトルにもなっているサンボウ・サンボウとは、サンバを踊った、サンバを踊った──という意味で、つまりサンバを躍りまくったということ。なんとも、気持ちが華やぐではないか。ドナートはおなじメンバーでもう1枚吹き込んでいて、そちらはパシフィック・ジャズでリイシューされなかった。ブラジルのポリドールから『ア・ボッサ・ムイト・モデルナ』(1963年)としてリリースされているが、日本でもCD化されているので気軽に聴いていただきたい。
それから間もなくドナートはアメリカでも人気を博し、ニューヨークでもレコーディングを行った。RCAビクターが発売した『ザ・ニュー・サウンド・オブ・ブラジル』(1965年)というアルバムなのだが、ジョビンの作品が意識されたのか、クラウス・オガーマンのオーケストラとの共演作となっている。これがよくない。オガーマンのアレンジは相変わらず素晴らしいのだけれど、ドナートの個性的なプレイが抑制されてしまっている。ジャズボサがすべてではないが、こういうボサノヴァ作品はどうしてもジョビンの二番煎じに聴こえてしまう。まあ、ビル・エヴァンスもオガーマンと一緒に『プレイズ・V.I.P.s・アンド・グレイト・ソングス』(1963年)という、とんでもないアルバムを録音しているけれど、それよりはかなりマシかな──。
このあとドナートは『ヒキガエル(ア・バッド・ドナート)』(1970年)『デオダートの新しい空間(ドナート/デオダート)』(1973年)『ケン・エ・ケン(紳士録)』(1973年)『ルガール・コムン』(1975年)といった傑作を次々にリリースしていくのだけれど、それらはドナートがピアノ以外にハモンド・オルガンやフェンダー・ローズを弾きまくる、ブラジリアン・フュージョン作品。どのアルバムもDJやクラブ世代からは圧倒的な支持を得ているが、モダン・ジャズの信奉者にはちょっと耐えがたいかもしれない。そんなかたには、ジョビンの作品集『ソ・ダンソ・サンバ』(1999年)あたりがオススメ。ピアノ・トリオ+パーカッションに4管編成のホーン・セクションが加わった、リラックスして聴ける佳作だ。
それにしても、このジョアン・ドナートにしても、さきにご紹介したルイス・エサとセザル・カマルゴ・マリアーノにしても、1970年代以降、申し合わせたようにクロスオーヴァー/フュージョンを志向するようになるから面白い。ほかにジャズボサを演っていたピアニストでは、マンフレッド・フェストも然り。強いて云うなら、ワルター・ワンダレイやセルジオ・メンデスにもその傾向が見られた。それは、彼らにとってジャズは異国の音楽であり、云ってみればマテリアルのようなもので、曲作りにしても演奏にしても俯瞰的に取り組まれているからだろう。1960年代の後半、モダン・ジャズの帝王ことマイルス・デイヴィスがエレクトリック・ジャズの旗を振れば、それに応じて自己のスタイルを素早く変化させることもできるのだ。
そんな状況を鑑みると、ボサノヴァやジャズボサを演っていたブラジルのミュージシャンたちが、ジャズ・スピリッツを燃やすアメリカのプレイヤーたちよりも、大きなキャパシティと柔軟性に富んだ音楽性をもっているようにも思えてくる。もちろん、ひとところに留まり自己のアイデンティティを掘り下げるようなジャズメンたちも素晴らしいと思うけれど、鷹揚に構えて様々なカテゴリーの音楽を採り入れていくブラジルのアーティストたちに、ぼくはポジティヴな印象を受けるのだ。長々と語ってきたけれどジャズボサは、ジャズという音楽に対してふところが深く寛容なこころで接するかたであれば、大いに楽しむことができる音楽。そしてリスナーに、モダン・ジャズとはひと味もふた味も違う心地よさを与えるものである。
ジャズボサいろいろ③──アジムスのジョゼ・ホベルト・ベルトラミ
ということで、いよいよプロジェート・トレシュについてお伝えしていこうと思う。さきにメンバーを挙げておくと、ジョゼ・ホベルト・ベルトラミ(p, org)、クラウディオ・エンリケ・ベルトラミ(b)、ホベルチーニョ・シウヴァ(ds)といったトリオである。このバンドのピアニストの名前を見てピンとくるひとは、ことのほか多いと思う。しかし、それはコアなジャズ・ファンではなく、ブラジル音楽に親しんでいるひと、クロスオーヴァー/フュージョンをリアルタイムで聴いていた世代、そしてレア・グルーヴの音盤を探し求めるクレート・ディガーなどだろう。なぜなら、この(便宜上そう呼ぶが)ジョゼ・ホベルトは、ブラジルのフュージョン・バンド、アジムス(現地では“アジムチ”と発音される)のキーボーディストだったからだ。
アジムスは、ここで詳しくはお伝えしないけれど、ブラジリアン・グルーヴに特化した唯一無二のフュージョン・グループだ。わたくしごとで恐縮だが、音楽にあまり関心のないぼくの妻も、なぜかアジムスやそのメンバーが関わった作品は好きらしい。もしかすると彼女のようなひとは、存外いるのかもしれない。というのも、たとえばアジムスの3rdアルバム『ライト・アズ・ア・フェザー』(1979年)に収録されている「フライ・オーヴァー・ザ・ホライズン」と、4thアルバム『オウトゥブロ』(1980年)に収録されている「オクトーバー」は、1981年からNHK-FM放送の『クロスオーバーイレブン』という番組で、それぞれオープニング曲、エンディング曲として、多くのひとたちに親しまれたからだ。
つまりアジムスが奏でるサウンドには、特に音楽の愛好者でなくても気軽に聴けるような、清涼感に溢れた心地よさがあるのだ。アジムスが1973年にリオデジャネイロで結成されてから、ジョゼ・ホベルトはこのバンドにおいて30年近くも、ブラジルの音楽とジャズを融合させると同時に各々の形態を解放し新しい音楽を模索しつづけた。彼は1989年からの5年間、いったんバンドを離脱していたが、はっきり云ってそのころのアジムス・サウンドは精彩を欠いていた。ジョゼ・ホベルトは2012年7月8日、リオにおいて66歳という若さでこの世を去ったが、その直前まで彼の創作意欲は衰えることを知らなかった。僚友のギタリスト、アルトゥール・ヴェロカイとともに『ザ・ファー・アウト・モンスター・ディスコ・オーケストラ』(2014年)というキャッチーな作品をリリースしたほどである。

これまたわたくしごとではあるが、ぼくの妻いわく「アジムスの作品は未来の音楽」とのこと。なるほど、ロンドンのレーベル、ファー・アウト・レコーディングスに移籍した1996年以降も、アジムスはあまりイノヴェーションに左右されることなく、フェンダー・ローズ、ハモンド・オルガン、ミニモーグ、アープ・オデッセイなどによって、スペイシーでコズミックなサウンドを創出していた。それには確かに、レトロフューチャーをイメージさせるものがある。そういえば、UKに拠点を構えながらブラジル音楽に特化したレーベル、ファー・アウトの、サンバ、MPB、ジャズなどを、ハウス、ブロークンビーツ、エレクトロニカなどと同等に扱うというスタンスにも、懐古趣味に富んだ音楽の未来像が感じられる。
いずれにしても、アジムスの音楽は1990年代からクラブ・シーンにおいて重宝されているが、いまになってみるとプロジェート・トレシュの『オ・トリオ』(1968年)という作品は、ジョゼ・ホベルトによる未来予想図の序章だったようにも思われる。彼は本作のまえに、クインテットによる『オス・タトゥイス』(1965年)と、トリオによる『ジョゼ・ホベルト・トリオ』(1966年)を吹き込んでいるが、それらはピュアなジャズボサ作品だった。しかしその後の作品といえば『オルガン・サウンド』(1970年)ではジャズ・ロックが導入され、プロジェクト・スリーの『エンコントロ』(1970年)、ソン・アンビエンチの『ソン・アンビエンチ』(1972年)、ブラジル・バイ・ミュージックの『フライ・クルゼイロ』(1972年)などでは、いわゆるプリ・アジムス・サウンドへと進化していく。
つまりジョゼ・ホベルトのディスコグラフィにおいて、プロジェート・トレシュの『オ・トリオ』は、ジャズボサからジャズ・ロックやフュージョンへの架橋的な作品と云える。なおベースのクラウディオ・エンリケは、ジョゼ・ホベルトの弟で前2作にも参加していた。ドラムスのシウヴァは、その後ソン・イマジナリオのメンバーとなる名手。オープニングはフォー・シーズンズのフランキー・ヴァリの1967年のソロ・シングルとしてヒットした「君の瞳に恋してる」で、ポップなリズム、洒脱なオルガン、歯切れのいいピアノが鮮やかだ。つづくブラジルのピアニスト兼シンガー、ジョニー・アルフの「私とそよ風」は、エレガントなピアノが静謐を湛える。3曲目は本作のリリースもとであるエピキのオーナー、オズワルド・カダクソの自作「ナウン・ソモス(アイ・ラヴ・ユー)」で、オルガンとピアノのチルアウトな感覚がいい。
4曲目のアントニオ・カルロス・ジョビンとヴィニシウス・ジ・モライスの「ナウン・ポッソ・イスケセール(モーホの嘆き)」は、アップテンポでジャズボサが全開する。つづく映画『ピンクの豹』(1963年)のためにヘンリー・マンシーニが作曲した「サムシング・フォー・セラーズ」では、弾けるようなリズムをラウンジ感覚で楽しめる。ここからレコードではSide-Bで、最初のマルコス・ヴァーリの「ヴィオラ・インルアラーダ」と、ホベルト・カルロス・ブラガの「コモ・イ・グランジ・オ・メウ・アモール・ポル・ヴォセ」は、アルバム中もっともサウダージ感覚が横溢するボサノヴァ。タートルズの1967年のヒット曲「ハッピー・トゥゲザー」は、タンゴ、ボサノヴァそれにロックがクロスする楽しい演奏となっている。
女優でもあったカリオカ・シンガー、ドリス・モンテイロが1957年にヒットさせた、ビリー・ブランコの曲「モシーニョ・ボニート(美少年)」は、エスプリの効いた小気味いいジャズボサ。ピアノのアドリブもちょっとだけアウトしたりする。ラストのジョゼ・ホベルトのオリジナル「ヴァニア」は、もっともジャジーなナンバー。かの有名な「ラウンド・アバウト・ミッドナイト」を爽やかな感じにしたような曲。途中ベースのソロもある。この曲を聴くと、ジャズとブラジルの音楽が溶け合い、ブルージーな雰囲気のなかに明るさや広がりが生まれるているのがよくわかる。本作はジャズボサがよりポップになったところがリフレッシングだけれど、特に音楽の愛好者でなくても楽しめるし、モダン・ジャズしか聴かないひとにも一服の清涼剤となるだろう。ぜひ、お試しあれ。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。








コメント