クラブ・シーンを席巻したロニー・リストン・スミスがスピリチュアルな音作りよりもメロウ・グルーヴとディスコ・テイストを強調した『ラヴ・イズ・ジ・アンサー』
 Album : Lonnie Liston Smith / Love Is The Answer (1980)
Album : Lonnie Liston Smith / Love Is The Answer (1980)
Today’s Tune : On The Real Side
スピリチュアル・ジャズの流れを汲むキーボーディスト
ロニー・リストン・スミスというと、レア・グルーヴ・シーンを語るとき絶対外せないアーティストのひとり。1975年に発表した『越境(Expansions)』の表題曲「エクスパンションズ」などは、1990年代のクラブ・シーンにおいてヘヴィー・ローテーションとして重宝され、リヴァイヴァル・ヒットとなった。このアルバムも含めて、フライング・ダッチマン・レコードとRCAレコードからリリースされた、ロニー・リストン・スミス&ザ・コズミック・エコーズ名義の諸作は、新時代の価値観で捉え直されたときもっとも高く評価された。どのへんに価値があるのかといえば、そのサウンドがファンキーでグルーヴィーでダンサブルなところだろう。その点については、ぼくも太鼓判を捺す。
でもぼくがスミスのレコードを聴いていたころは、彼の音楽は一般的にはそれとちょっと違う捉えられかたをしていたように思う。スミスの作品は音楽ジャンルとしてはフュージョンにカテゴライズされていたけれど、彼自身は1960年代に生まれたスピリチュアル・ジャズの流れを汲むキーボーディストと観られていた。スピリチュアル・ジャズは、音楽的に特徴づけたり満たすべき一定の要件を挙げたりするのはなかなか難しいけれど、モーダル、フリー、アヴァンギャルドといったジャズから派生したことは間違いない。テーマ的にはほとんどの場合、超越性と精神性に焦点が置かれているようだ。そのはじまりは、ジョン・コルトレーンの名作『至上の愛』(1965年)あたりかもしれない。
たとえば、ロニー・リストン・スミス&ザ・コズミック・エコーズ名義の諸作のアルバム・タイトルを観ていただきたい。原題にしても当時の邦題にしても、すこぶるスピリチュアリズムが意識されているように思われる。その6作品を列記すると『星体遊泳(Astral Traveling)』(1973年)『宇宙渦動(Cosmic Funk)』(1974年)『越境(Expansions)』(1975年)『曙光(Visions Of A New World)』(1975年)『夢幻(Reflections 0f A Golden Dream)』(1976年)『復興(Renaissance)』(1977年)となる。いかがだろう、ちょっと不安を煽られるくらいアルバム・タイトルに霊的なものを感じるのは、果たしてぼくだけだろうか。まあ当時は、こういうのが流行ったのだろうね。

ぼくがスミスの音楽にはじめて触れたのは、1970年代の後半のこと。当時中学生だったぼくは、ジャズとフュージョンを並行して聴いていた。コルトレーンの『至上の愛』はすでに体験していたけれど、スピリチュアリズムを意識するようなことはなかった。まあぼくは、少年時代にテレビ放送で死後の世界との交信や超能力のパフォーマンスを、嫌というほど見せられた世代だけれど、基本的にそういうものは眉唾と思っていた。スピリチュアルというコトバ自体、知らなかったと思う。おそらくスピリチュアル・ブームみたいなものは、ミレニアム・イヤー以降の出来事だったのではないだろうか。いずれにしても、ぼくの『至上の愛』に対する興味は、純粋に音楽的なことだけだった。
当時のぼくは確かに『至上の愛』から大きな衝撃を受けたけれど、コルトレーンをはじめ、マッコイ・タイナー(p)、ジミー・ギャリソン(b)、エルヴィン・ジョーンズ(ds)らをひたすら追いかけるいっぽうで、モーダルなインプロヴィゼーションやポリメトリックなリズムにただひたむきに取り組むばかりだった。邪念のない音楽好きの少年には、精神世界や心霊主義はどうでもよかったのである。だからスミスの音楽に対しても、端からスピリチュアルであるかないかを気にかけるようなことは、まったくなかった。スピリチュアル・ジャズという分類があることも知らなかったしね。ただ当時、日本でもスミスはすでにフュージョン系のキーボーディストとして注目されていたけれど、ぼくは彼の作品になかなか手を出すことができなかったのである。
まったくお恥ずかしいかぎりだが、その理由とは青くさくて愚にもつかないことだった。ひとを外見で判断するのはよくないことだけれど、堂々たる鬚髯を蓄え、ほとんど目の表情を読み解くことができないサングラスをかけ、芸術的とも云うべきメロンスキンハットをかぶるという風貌から、ぼくはスミスに近寄り難いものを感じていた。だからいざレコード店で今日こそ彼の作品を手にとろうと思っても、いつも二の足を踏んでいたのである。なんともバカらしいハナシではあるが、第一印象とはロジックで決まるものではない。そして最初に与えられた情報は、案外いつまでも強く印象に残るものなのである。それでも一念発起して、ぼくはスミスのレコードをついに手に入れた。
そのキッカケとなったのは、とある音楽雑誌の記事だった。ページをなんとなく繰っていたぼくは、スミスのアルバムが1枚、フュージョンの名盤として採り上げられているのを発見した。それはさきに挙げた、ロニー・リストン・スミス&ザ・コズミック・エコーズ名義の4作目『曙光』だった。名盤と云われればいっぺんは聴いてみたくなるのが人情で、ぼくは慌ててこのレコードを購入した。国内盤のタスキには「アメリカ・ジャズ界で今話題騒然、クロスオーヴァー・ジャズの新しきヒーロー誕生!!」と記されているが、この『曙光』こそ日本のRCAからリリースされた最初のスミス作品だったわけだ。リヴァイヴァル・ヒットとなった3作目の『越境』のほうが、実は日本ではあとに発売されたのだった。
まったくの私事で恐縮だが、ぼくは中学校の卒業文集に寄せた文章のなかで、もっとも好きなキーボーディストはボブ・ジェームス、デイヴ・グルーシン、リチャード・ティーの3人であると断言している。当時はまだそれほど多くのアーティストの音楽作品に触れていたわけではないけれど、ぼくのなかにはそのころから確信めいた思いがあったし、それはいまに至ってもそれほど変わってはいない。だからはじめて『曙光』を聴いたとき、ぼくは当たりまえのようにスミスと上記の3人とを比較してしまったのである。そしてスミスのほうが、音楽の芸術性、汎用性、そして大衆性において若干引けをとるように感じられたし、演奏家としても数段劣るように思われた。ところがスミスの音楽には、ぼくのこころになにか引っかかるものがあったのである。
アルバムを重ねるごとに音楽的エヴォリューションを遂げる
この『曙光』のトップに「平和のねがい(A Chance For Peace)」という曲が収録されているけれど、この曲のイントロを聴いたときぼくはすぐにハービー・ハンコックの「カメレオン」を思い浮かべた。あの名曲を彷彿させるベース・ラインを軸として、リズム・セクションはちょっと重たくうねるような感じの律動を打ち出していく。そのあたりには、いま聴いてもゾクゾクさせられる。ひとことで云えば、これはジャズ・ファンクだ。ジャズ・ファンクといえば、マイルス・デイヴィスの『オン・ザ・コーナー』(1972年)が有名だけれど、実はこのアルバムにスミスが関わっている。このときのセッションに、スミスはキーボーディストのひとりとして参加していたのだ。もちろん当時のぼくは、そんなことを知る由もない。
なにせ『オン・ザ・コーナー』がオフィシャル・リリースされたときは、スミスの演奏はオミットされてしまったからね、ぼくが彼の参加を知ったのはずっとあとのことだった。なおこのときのスミスのプレイはその後、6枚組ボックス『ザ・コンプリート・オン・ザ・コーナー・セッションズ』(2007年)で聴くことができるようになった。まあスミスが参加したテイクのうち「イーフェ」1曲だけなら、1969年から1972年までの音源が寄せ集めされたマイルスの『ビッグ・ファン』(1974年)で聴くことは可能だったのだけれど、当時のぼくはそのアルバムについてはまだ未聴だった。いずれにしても、スミスもまたハービー・ハンコック、チック・コリア、ジョー・ザヴィヌルらと同様に、エレクトリック・マイルスの洗礼を受けていたのである。
だいぶわき道に逸れてしまったが、ハナシをもとに戻すとしよう。マイルスからの影響を受けたこともありロニー・リストン・スミス&ザ・コズミック・エコーズの演奏には、確かにジャズ・ファンクの要素が多く含まれている。しかしながら『曙光』は、ジャズ・ファンクの傑作であるハービー・ハンコックの『ヘッド・ハンターズ』(1973年)のような即興演奏に主眼が置かれた作品ではない。たとえば前述の「平和のねがい」という曲を観ても、スミスの実弟であるドナルド・スミスのソウルフルなヴォーカルがフィーチュアされていたり、バックにスケールは大きくないけれどファンキーなブラスが入っていたりして、かなりポップな仕様と感じられる。それよりも当時のぼくは、楽曲のコード進行が非常にシンプルなのは受け入れられたのだが、肝心のスミスのキーボード・プレイが至って質素なのには正直、戸惑いを禁じ得なかった。
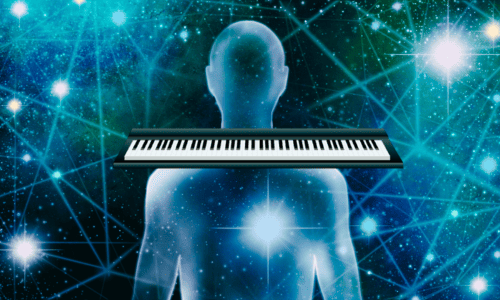
スミスによるフェンダー・ローズのソロは、ハンコックのようにターゲット・ノートを目指して半音階でアプローチしたり激しくアウトしたりするようなことはない。つまりスミスの楽曲では、彼のキーボード・ワークが巧みにエスカレートするような場面はまったくない。スミスはフェイズシフターを深くかけたローズでひたすらトレモロをつづけたり、一定のフレーズを何度も反復させたりするばかりなのだ。ただの中学生の分際でおこがましいのだけれど、これくらいだったら自分のほうが上手く弾けるなどと思ったほどだ。サウンドのスケールやポピュラリティにおいても、ボブ・ジェームスやデイヴ・グルーシンのほうがずっと優れているように思われたのだった。
では、ぼくがスミスの音楽にすっかり鼻白んでしまったのかというと、実はそうではない。むしろその逆である。何度も『曙光』を聴いているうちに、そのサウンドのカッコよさと気持ちよさが次第にぼくのなかに浸透してきた。しかもロニー・リストン・スミスという音楽家が、ぼくには思いのほか屈託のないひとのようにも思えてきたのだ。たぶんそのサウンドに、コマーシャリズムがまったく感じられないからだろう。彼は端からボブ・ジェームスやデイヴ・グルーシンの作品のような、クリエイティヴな音楽を演ろうとはしていない。そのいっぽうで『ヘッド・ハンターズ』のような超絶技巧が凝らされた作品、あるいは『オン・ザ・コーナー』のようなシリアスなジャズ作品を創出しようともしていない。スミスが目指すのは、いわば音の楽園なのである。
たとえば『曙光』には「平和のねがい」のようなグルーヴィーなナンバーがあるかと思えば、ブライトトーンの「愛の光(Love Beams)」や、それとは対照的にメランコリックな「サマー・ナイツ」といったラテン・タッチのリラクゼーションに富んだ曲もある。一聴このふたつのスタイルは対極をなすように思えるかもしれないが、実は共通するところがある。それは心地よさだ。スミスはおそらく瞬間的にアタマに浮かんだインスピレーションを、アクティヴかつポジティヴに音で表現しているのだと、ぼくは思う。しかも彼のプレイは、サウンドに彩りを添えることに徹しているようにも感じられる。彼のキーボード・マナーにおいて、コード・ワークにしてもインプロヴィゼーションにしてもシンプリシティを極めるのは、そういう理由からではないだろうか。
そういうことに気がつくと、最初スミスのことを見くびっていた自分が恥ずかしくなる。結局ぼくは気を取り直して、彼の作品を手当たり次第、手にとるようになった。まずはロニー・リストン・スミス&ザ・コズミック・エコーズ名義のアルバムをコンプリートした。幸いなことに『越境』『夢幻』『復興』の3枚は、すでに国内でもRCAから順次リリースされていたし、その後『星体遊泳』と『宇宙渦動』といった過去の作品も廉価盤として発売された(『星体遊泳』は過去にキングレコードが発売していた)。それらを聴いてわかったのは、スミスの音楽がアルバムを重ねるごとに音楽的エヴォリューションを遂げているということ。1作目の『星体遊泳』と6作目の『復興』とを比較すると、かなり作風が変わっているのがわかる。
まず『星体遊泳』では、ドリアン・モードやクォータル・ハーモニーなどが駆使されて、瞑想的なサウンドが創出されていた。つづく『宇宙渦動』では、一気にジャズ・ファンク色が強くなる。そして3作目の『越境』では、ジャズ・ファンクとポップ・フィーリングとが上手く調和し、スミス・サウンドはファースト・デスティネーションに到達する。さらに『曙光』でもスミスはその路線を辿り、トータル・サウンドの完成度を上げる。5作目の『夢幻』では、前作で完成されたスペイシーなジャズ・ファンクがよりメロウ志向になるいっぽうで、曲によってはディスコ・サウンドも採り入れられている。6作目の『復興』に至っては、はじめてストリングス・セクションが加えられ、劇的なソウル・フュージョンといった趣きを感じさせる。
都会的なサウンドスケープが描き出されたコロムビア時代の諸作
このようにロニー・リストン・スミス&ザ・コズミック・エコーズ名義の作品をすべて体験することによって、ぼくはスミスの音楽が明らかに進化していると認識した。そしてその時点で、仮に『復興』で展開されたサウンドを成体とするならば、その胚子にあたる初期段階の音楽様式はどのようなものだったのか、ぼくはさらに知りたくなったのである。結果、フリー・ジャズ系のテナー奏者、ファラオ・サンダースのアルバム『カーマ』(1969年)『テンビ』(1971年)『イジフォ・ザム』(1973年)、そしてアルゼンチン出身のテナー奏者、ガトー・バルビエリの『第三世界』(1970年)『フェニックス』(1971年)『エル・パンペロ』(1972年)『アンダー・ファイア』(1973年)『ボリビア』(1973年)といった作品に、手を出すハメになった。
スミスは1940年12月28日アメリカ、ヴァージニア州リッチモンド市に生まれた。幼少期には父親の影響で地元のゴスペル・クワイアに参加したり、トランペットを吹いたりしていた。ハイスクール時代には、ピアノとチューバも演奏するようになる。その後メリーランド州ボルチモア市のモーガン州立大学において、ピアノ演奏と音楽教育学を専攻した。大学ではヨハン・ゼバスティアン・バッハ、クロード・ドビュッシー、モーリス・ラヴェルらの芸術音楽を研究したというから、ちょっと驚きだ。卒業後はボルチモアで2年ほどプロ活動をしたあとニューヨーク市に移る。マックス・ローチ、アート・ブレイキーといったドラマー、マルチ・リード奏者のローランド・カークなどのグループで、ピアニストとして活躍した。
そんなスミスに強い影響を与えたのは、やはりその後に出会ったファラオ・サンダースとガトー・バルビエリだとぼくは思う。スミスはサンダースとともに、ゴスペル、ファンク、アフロビートのエッセンスを吸収したフリー・ジャズをプレイしながらインナー・トリップの壮途に就いた。おなじくフリー・ジャズ・ムーヴメントに乗じていたバルビエリは、ちょうど自己のスタイルに閉塞感を感じたことから中南米の音楽に活路を見出していた。その後のスミス・サウンドに含まれるラテン・フレーヴァーは、バルビエリの音楽から受けた薫陶のたまものと思われる。いずれにしても、スミスがスピリチュアル・ジャズの系譜に属するミュージシャンと観られるのは、サンダース、バルビエリとの関わりからだろう。

もっと云えば当初スミスは、サンダースやバルビエリのスピリチュアルな作品をインパルス!、フライング・ダッチマンといったレーベルから世に送り出した音楽プロデューサー、ボブ・シールのイデオロギーを正統的に受け継いだのだろう。というのも当時のシールが手がけた多くの作品が、超越性と精神性とを核として展開されたものだからだ。スミスも『星体遊泳』や『宇宙渦動』あたりでは、まだそういうスピリチュアリズムを重視した音楽を展開していた。ただ彼は徐々に自己の音楽において、そういったある種の観念形態よりもグルーヴやクールネスを追求するようになっていく。レゾンデートルと向き合うよりも、建設的に心地よさとカッコよさを掘り下げたところに、スミスのひと柄が窺える。ぼくの彼に対する畏怖の念も、いつの間にか雲散霧消していた。
スミスはニューヨーク、ブルックリンのスマッカーズ・キャバレーでの実況録音盤『入魂』(1977年)を最後に、シールと袂を分かつ。ヒット曲「エクスパンションズ」のエキサイティングなライヴ・ヴァージョンも聴けるこのアルバムには、もはや“ザ・コズミック・エコーズ”の名はない。スミスは翌年、ソロ・アーティストとしてコロムビア・レコードに移籍する。彼はこの新天地において、1960年代から1970年代にかけてのソウル・ミュージックの立役者で、プロデューサー兼アレンジャーのバート・ドゥ・コトー、そして当時GRPレコードで頭角を現す直前だった新進気鋭のベーシスト、マーカス・ミラーの協力を得て、これまでのリーダー作では観られなかった都会的なサウンドスケープを描き出すようになる。
当時、このスミスの転身を「腑抜けた」とか「魂を売った」とか辛辣に批判する向きもあったが、ぼくはその意見にまったく賛同することができなかった。むしろこれまでになくオープンマインドに心地いい音楽を繰り広げるコロムビア時代のスミスに、ぼくは好感をもつ。それは、鬼才シールのケレン味のあるプロデュースによる呪縛を解かれた彼が、スピリチュアリズムとは無関係のスペーシャスでアーバンなフュージョン・ミュージックを気持ちよさそうにプレイしているからだ。実際『ラヴランド』(1978年)『エキゾティック・ミステリーズ』(1978年)『ア・ソング・フォー・ザ・チルドレン』(1979年)『ラヴ・イズ・ジ・アンサー』(1980年)といった4枚のアルバムは、秀作の揃い踏みとなっている。
なかでもぼくは、唯一セルフ・プロデュースで制作された最終作『ラヴ・イズ・ジ・アンサー』を推す。メンバー的にはもっとも地味だけれど、開放感溢れる音景という点では随一だ。ブライトトーンのラテン・ナンバー「イン・ザ・パーク」では、しなやかなリズムとパーカッシヴなピアノが爽快。ジェームス・ロビンソンのヴォーカルがフィーチュアされた「ラヴ・イズ・ジ・アンサー」では、瞑想的リラクゼーションが横溢。ブラスのアンサンブルが際立つ「スピーク・アバウト・イット」では、ソウルフルなディスコ・ファンクが展開される。フィンガースナップ入りのメロウ・グルーヴ「ブリッジ・スルー・タイム」では、ゆったりしたテンポのなかアブドゥル・ワリのギターがジャジーに歌う。
クルマー・オルガンがメインに据えられた「オン・ザ・リアル・サイド」では、ピー・ウィー・フォードのベースとリノ・レイエスのドラムスとによるビートの弾けかたが圧巻。悠久のクワイエット・ストーム「ジ・エンチャントレス」では、デイヴ・ハバードのアルト・フルートが清澄な空気を作る。前述の「平和のねがい」の再演「ギヴ・ピース・ア・チャンス(メイク・ラヴ・ノット・ウォー)」では、疾走感のあるディスコ・サウンドが全開される。ラストの「フリー・アンド・イージー」では、軽妙なピアノがチルアウトな雰囲気を作る。以上、いい意味でリスニングに最適なフュージョン作と云えよう。その後スミスは、ふたたびシールのレーベル、ドクター・ジャズでリーダー作を4枚制作するが乱脈を極める。その反動からか次のイチバン・レコードの3作ではR&B色がかなり強くなる。その点からも、コロムビア時代のスミスの充実ぶりを見直すべきではないだろうか。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。








コメント