映画音楽のマエストロ、ジョン・ウィリアムズのいつになく情緒的で甘美なオーケストラル・アルバム『サブリナ』
 Album : John Williams / Sabrina (1995)
Album : John Williams / Sabrina (1995)
Today’s Tune : Theme From Sabrina
映画監督シドニー・ポラックと彼が自作で起用した音楽家たち
アメリカ映画でぼくがもっとも好きな監督は、シドニー・ポラック(1934年7月1日 – 2008年5月26日)だ。彼はアメリカ映画界において長きにわたり監督としてはもちろんのこと、プロデューサーとしても大いに腕を振るった。これはほんの豆知識ではあるけれど、彼の前身は俳優だった。ニューヨークの俳優養成学校、ネイバーフッド・プレイハウスの出身なのである。1950年代の半ばにしっかりブロードウェイ・デビューを果たしており、テレビのドラマ・シリーズにもしばしば出演していた。監督時代にコンビを組むことが多かったハリウッド屈指の二枚目俳優、ロバート・レッドフォードともアクターとして共演している。レッドフォードの映画デビュー作でもあるデニス・サンダースの監督作品『戦場の追跡』(1961年)に、ポラックもまた出演している。
ついでに云っておくと、ポラックは自分が監督を務めた映画にもちょくちょく出演している。みなさんは、お気づきだろうか?よく知られているのは、主演のダスティン・ホフマンの女装が大きな話題となった『トッツィー』(1982年)だろう。ホフマン演じる売れない俳優に向かっていつもガミガミ云っているタレント・エージェントのおじさんが、ポラックだ。ほかにも『コンドル』(1975年)のタクシー運転手『ランダム・ハーツ』(1990年)の下院議員のメディア対応担当者『ザ・インタープリター』(2005年)のシークレットサービス長官などを、ポラックは堂々と演じている。なかには『出逢い』(1979年)の場合のように、クレジットなしのカメオ出演もあるので要注意である。
ときに『戦場の追跡』に出演したあと、テレビ・シリーズのエピソード監督を務めたりしていたポラックは、まもなく映画『いのちの紐』(1965年)でメガホンをとり表舞台に出る。これは、なかなかの名作。主演のシドニー・ポワチエが、電話の音声通話でひとりの自殺志願者の女性を救おうとする、社会派のヒューマンドラマだ。個人的にはクインシー・ジョーンズが手がけたスコアのサウンドトラック・アルバムが、欠かすことのできないアイテムとなっている。実はこれに限らずポラックの作品では、概して音楽がこころに残るのだ。本人も陳述しているけれど、ポラックは自己の映像作品をクリエイトするときの表現手段として、音楽を極めて重要なファクターと観ているのである。
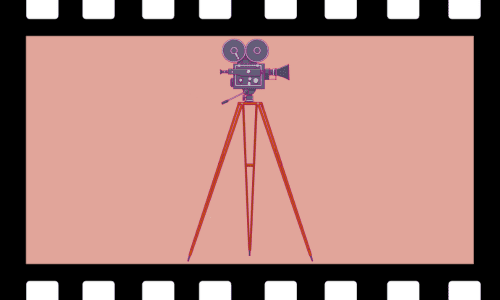
現にポラックは監督2作目の『雨のニューオリンズ』(1966年)で、ジャジーなスコアが得意な作曲家、ケニヨン・ホプキンスを、つづく『ひとりぼっちの青春』(1969年)では、ブロードウェイの作曲家でピアニストのジョニー・グリーンを、それぞれ起用している。ホプキンスは、シドニー・ルメットの監督作品『十二人の怒れる男』(1957)の劇伴を手がけたひと。グリーンのほうは、ジャズ・スタンダーズ「身も心も」の作曲者として知られる。いずれにしても、ポラックは伝統的な芸術音楽にはあまり関心がないようで、どちらかといえばヒネリの利いたスコアを好むようだ。その点では、名作『大いなる勇者』(1972年)での、カントリー・ミュージックのヴォーカリスト、ティム・マッキンタイアとミュージカルが得意なジョン・ルービンスタインとの組み合わせも然りだ。
なんといっても忘れられないのは『追憶』(1973年)の音楽だ。映画は反戦主義で政治活動に熱心な女性と特に政治傾向をもたないブルジョア気質の男性との、1937年の出会いから激動の時代を生きたおよそ20年間が描かれた、ポリティカルでもありロマンティックでもあるヒューマンドラマ。スコアを手がけたのは、舞台や映画で数々の賞に輝くマーヴィン・ハムリッシュ。そのスコアは『スティング』(1973年)『007/私を愛したスパイ』(1977年)『普通の人々』(1980年)『ソフィーの選択』(1982年)といった具合に実に守備範囲が広い。ハムリッシュは『追憶』でアカデミー作曲賞を獲得。主演を務めたバーブラ・ストライサンドが歌った主題歌「追憶(The Way We Were)」は、アカデミー歌曲賞を授与された。
そんななかポラックの寵愛をもっとも受けた音楽家といえば、やはりジャズ/フュージョン・シーンの雄、デイヴ・グルーシンだろう。グルーシンとポラックとは同い年ということもあり、意思疎通が上手くいき互いの芸術的感覚をよく理解し合えたのだろう。ふたりは絶妙なコンビネーションを発揮し、銀幕に実に個性的な名作を何本か残している。グルーシンは1967年から2013年まで、60本以上の映画作品に印象的なスコアを残した。ロバート・レッドフォードの監督作品『ミラグロ/奇跡の地』(1988年)では、アカデミー作曲賞も受賞している。それ以外にもノミネートは6回を数え、彼は本業であるジャズ・ピアニストとしての活動をしっかり継続させながら、映画音楽作家としても確固たる地位を築いたと云える。
ところで、ポラックの映画といえば、社会的にはリベラル、政治的にはモデレート、そしてストーリーラインはとてもリアル。ラヴ・ストーリーを描いても甘口にはならないし、サスペンス・スリラーを取り扱っても過剰な演出はしない。そして多くの作品において、彼が創造する物語は決してハッピーエンドを迎えることがない。その結末での描写は毎度のごとく、観客に登場人物たちの行く末を案じさせるような余韻を残すのだ。そんなハリウッドのコマーシャリズムとは一線を画すようなポラックの作風が、ぼくは大好きなのだが、グルーシンもまたハリウッドの伝統を汲みながら、ちょっとそこから逸脱するような多様性と革新性をもった音楽家。そういう点で、ポラックとグルーシンとの相性は抜群と、ぼくは思うのである。
ポラックとグルーシンとのコラボレーションは、ロバート・ミッチャムと高倉健とが共演したクライムアクション『ザ・ヤクザ』(1974年)にはじまる。東京、鎌倉、京都と日本が物語の舞台となっていることから、グルーシンはコンテンポラリー・ジャズにエキゾティックな独特のサウンドを加味した。不穏なムードを醸し出す日本の伝統的なエアリード楽器、尺八のブロウも然ることながら、ガムランで使用されるダーマをはじめ銅鑼、ミキシングボウル、ベルツリー、ブーバムといったユニークなパーカッション類や、ホラー映画でおなじみの不調和な共鳴音を奏でるウォーターフォンなどを、グルーシンは効果的に使用している。そういった映像にマッチした楽句や色彩を容易にイメージするところも、ポラックが彼に厚い信頼を寄せる要因のひとつだろう。
お約束とも云えるそのユニークなマナーの埒外にあるような作品
ポラックとグルーシンとの名コンビによる作品は、この『ザ・ヤクザ』を含めて『コンドル』(1975年)『ボビー・デアフィールド』(1977年)『出逢い』(1979年)『スクープ 悪意の不在』(1981年)『トッツィー』(1982年)『ハバナ』(1990年)『ザ・ファーム 法律事務所』(1993年)『ランダム・ハーツ』(1999年)と、9本を数える。なおポラックがメガホンをとらず製作総指揮を手がけた『恋のゆくえ/ファビュラス・ベイカー・ボーイズ』(1989年)でも、グルーシンが音楽を担当した。これらの作品はすべてサウンドトラック・アルバムが発売されているが、残念ながら2025年現在『ボビー・デアフィールド』(原盤=カサブランカ・ミュージック)のみが未CD化のままである。
ポラックとグルーシンとの絶妙なコンビネーションはおよそ25年ほどつづいたが、ときとしてインターバルを置くこともあった。アカデミー賞において作品賞、監督賞ほか7部問を同時受賞したポラック作品『愛と哀しみの果て』(1985年)においては、グルーシンは音楽を手がけていない。デンマークを代表するゴシック小説家、イサク・ディーネセンによる自伝文学のベストセラー『アフリカの日々』を原作とした本作は、20世紀初頭のアフリカを舞台に愛と冒険に生きたひとりの女性(ディーネセン本人)の半生が描かれた一大ロマンス。アフリカの美しい雄大な風景も然ることながら、ロバート・レッドフォード演じる自由と孤独を愛する男性と、メリル・ストリープ演じる男性の生きかたに強く惹かれる孤独な女性との、熱く切ない大人の恋愛劇が感動を呼ぶ。
ポラックの映画としてはいささか異色作とも思えるのだが、とにもかくにもこの愛と感動の大河ロマンにスコアを提供したのはグルーシンではなく、イングランドのノース・ヨークシャー出身の作曲家、ジョン・バリーである。バリーといえばすぐに思い出されるのは「007/ジェームズ・ボンド」シリーズにおける、豪勢で雄渾なオーケストレーションだろう。しかしながら、彼は膨大な映画作品にスコアを提供しているけれど、実はストレートに美しいメロディック・ラインをもつ楽曲を書くのが得意なひと。グルーシンと比較すると、バリーのほうが圧倒的に正統派の作曲家なのである。平明にしてこころに響くサウンドを創出するというそのマナーには、もはや巨匠というよりも天才の域に達するものがある。
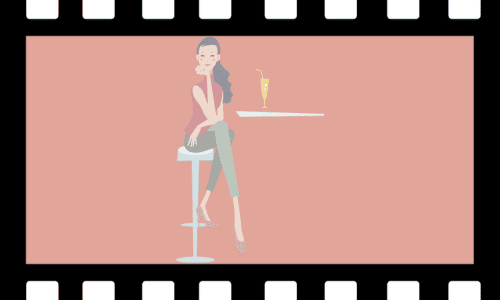
いずれにしてもバリーの直線的なスコアは、茫洋たる大自然と高度な文化や社会制度に影響されない人生観を、ナチュラルに表現していたようにぼくは思う。ポラックはこの作品を企画した当初、もしかするとグルーシンの音楽を一度は想定したかもしれないが、結果的にはバリーの起用が正しかったことは火を見るよりも明らかだ。この映画の趣旨を鑑みるに、グルーシン・サウンドがもつエスプリやアクティヴィティは、本作では出番がなかったと云えよう。ひょっとするとポラックはアフリカをイメージしたとき、バリーが書いたジェームズ・ヒルの監督作品『野生のエルザ』(1966年)の音楽を想起したのかもしれない。この作品でバリーはアカデミー作曲賞を受賞しているが、奇しくも『愛と哀しみの果て』でも同賞を獲得した。
さて、ポラックの数あるマスターワークスのなかには、もはやお約束とも云えるそのユニークなマナーの埒外にあるような作品がもう1作ある。それは時間的には、独特の世界観をもつポラック映画の最大の理解者でもあるグルーシンが音楽を手がけた『ザ・ファーム 法律事務所』と『ランダム・ハーツ』とのちょうど間に位置する作品で、ジャンル的にはハリウッド映画の流れを汲むいわゆるロマンティック・コメディに属するものとなる。この1995年に公開された『サブリナ』は、云うまでもなく軽妙洒脱なストーリーラインの作品を得意とする名匠、ビリー・ワイルダーが監督した1954年の映画『麗しのサブリナ』のリメイク作。サミュエル・テイラーの戯曲を原作とするこの作品は、パラマウント・ピクチャーズにとっても41年ぶりの再映画化である。
もとの『麗しのサブリナ』の主演は、ハンフリー・ボガート、オードリー・ヘプバーン、そしてウィリアム・ホールデンの3人。ヘプバーンにとっては、ウィリアム・ワイラー監督、グレゴリー・ペック共演による『ローマの休日』(1953年)につづく、大ヒット作となった。ちなみにこの映画が、サブリナパンツというファッション文化を生み出したことは、あまりにも有名。この細身の微妙に丈が短いボトムスは、もともと1948年にドイツのファッション・デザイナー、ソニア・デ・レナートによって編み出された、カプリパンツ(イタリアのカプリ島に由来)というものだった。映画で大富豪のお抱え運転手の娘、サブリナを演じたヘプバーンがこのパンツを履いていたことから、その呼び名がサブリナパンツに転じた。
もちろんポラックには端から過去のヒット作を単純に焼き直すつもりはなかったのだろうが、そうかといって名プロデューサーでもある彼はこのリメイク版においてコマーシャリズムを極限まで排除するようなこともしていない。正直なところそういうところが、作品の完成度において本作がオリジナル版に一歩譲ることになるいち因だったと、ぼくは思うのである。そうはいっても化粧直しされた『サブリナ』は、名作『麗しのサブリナ』の優れた点を凌駕するには至らなかったものの、ポラックの確かな演出とベテラン俳優陣の演技によって十分に楽しめる娯楽作品に仕上がっている。パリのシーンなどは、サウンド・ステージでの撮影だったオリジナル版とは対照的に、リメイク版ではしっかり屋外ロケが敢行されており、映像に立体感が増した。
特に映画のラストシーンとなる、セーヌ川両岸に架かるポンデザール橋から望むかわたれどきのパリの景色が、やたらと美しい。そのグレイッシュな色合いが、いかにもポラックらしい。ただ橋の上でひたすら抱擁と接吻とを繰り返すライナスとサブリナは、ハーレクイン・ロマンス顔負けの熱々ムードで、観てるほうが気恥ずかしくなる。スタッフロールがはじまっても、ふたりはまだまだとろけるような甘美さを放ちつづけるのである。こういう演出はまったくポラックらしくないのだけれど、ある意味でこういう愛情表現は現代的でもあり、逆にリアルなものとさえ捉えることができる。恋人たちの橋として知られるポンデザールにひっかけたのか、それとも実はあるがままを映し出しただけなのか、ポラック本人に訊いてみたいところだが、いまとなってはそれも叶わぬこと。
あのワンパターンとひと味違うサウンドトラック・アルバム
ポラック作品では稀有なケースであるハッピーエンド、しかもあの“ロンバケ”の眩い波光に包まれながらキムタクと唐沢夫人とがイチャイチャする迷シーンのように、個人的にはなんともいたたまれない気持ちになるような局面──。この大団円で堂々とその役回りを務めたのは、ハリソン・フォード(ライナス)とジュリア・オーモンド(サブリナ)。ハッキリ云ってフォードのキャラクターには、いささか似つかわしくない。フォードのパッショネートなシーンだったら、たとえばピーター・ウィアーの監督作品『刑事ジョン・ブック 目撃者』(1985年)でのケリー・マクギリスとの抱擁のほうが断然彼らしい。実際フォードはのちに、ポラックの演出には信頼を置いていたが、ライナス役は自分には合っていないと感じたと述懐している。
以下は余談だが、このリメイク版ではオリジナル版でウィリアム・ホールデンが演じていたデイヴィッド(ライナスの弟)に、もともとヴァラエティ・ショーで人気を博していたグレッグ・キニアがキャスティングされた。これも微妙な配役と思われるのだけれど、実は企画段階でこの役の候補にすでにトップスターの座に就いていたトム・クルーズの名も挙がっていた。しかもクルーズは当時フォードとの共演を切望していたこともあり、デイヴィッド役に強い関心を示したという。しかしながらクルーズのギャランティの問題から、この夢の顔合わせが果たされることはなかった。もしこれが現実のものとなっていたら、映画『サブリナ』もまた永遠に語り継がれるような作品になっていたかもしれない。
そんなわけで、ポラック作品としてはどこまでもイレギュラーな印象を与える『サブリナ』ではあるが、音楽もまた然り。キャスティングと同様に企画段階ではグルーシンが音楽を担当することになっていたが、結局その構想は暗礁に乗り上げた。こういうことはハリウッドでは、日常茶飯事。本作のフィルム・スコアを手がけたのは、ジョン・ウィリアムズである。ウィリアムズこそ説明不要の、映画音楽はもちろんのこと独立した芸術音楽においてもマエストロと呼ぶに相応しい音楽家だ。1932年2月8日ニューヨーク生まれの彼は、現在93歳。盟友のスティーヴン・スピルバーグが製作した『インディ・ジョーンズと運命のダイヤル』(2023年)の音楽担当を機に、作曲家を引退すると宣言するもすぐに撤回。その真意やいかに──。
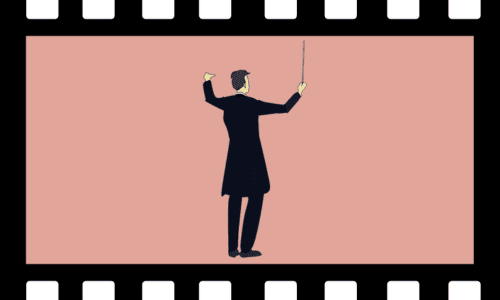
ところで『サブリナ』におけるウィリアムズの抜擢には、製作会社や配給会社のしたたかな思惑が感じられる。映画史に残る名作のリメイクだけに、音楽にも贅を尽くしたかったのだろう。なにせウィリアムズはアカデミー賞において、受賞が5回(作曲賞4回、編曲賞1回)、ノミネートならなんと54回と存命の映画人ではもっとも多い。飽くまで受賞歴においてだが、グルーシンはその足元にも及ばないのである。ポスト・ロマン主義風のフルオーケストラで、キャラクターの性格やストーリー展開を表現した印象的なライトモティーフを響かせる、ウィリアムズのある種のオペラ的手法は、音楽に特別な関心をもたない向きも含めて観客の大多数に感動を与える。まさに優雅な気分と贅沢な味わいを演出するものと云える。
さらにウィリアムズのスコアの素晴らしさといえば、スクリーンから離れても鑑賞用音楽としてしっかり機能を果たすという点。名門ジュリアード音楽院に通うかたわらジャズ・ピアニストとして働いたり、ボストン・ポップス・オーケストラのコンダクターを務めたり、ウィリアムズはクラシック音楽のフィールドに身を置きながらも、ポピュラー・ミュージックに深い理解を示す音楽家。それ故か彼の映画音楽は、本格的にシンフォニックであると同時にポップ・クラシカルでもあるから、自宅のオーディオでも気軽に楽しむことができるのである。ウィリアムズといえば『スター・ウォーズ』(1977年)『スーパーマン』(1978年)『インディ・ジョーンズ』(1981年)などのテーマ曲が有名だけれど、あのワンパターンとひと味違うのが『サブリナ』のサウンドトラック・アルバムだ。
このアルバムをひとことで云うと、全編にわたってロマンティシズムが横溢する作品。ピアノをソロ楽器とする協奏的ラプソディ風の「サブリナのテーマ」は、ちょっとセルゲイ・ラフマニノフの曲を彷彿させる甘美な曲。このスウィートなメロディック・ラインは、すぐに脳内にインプットされる。つづく「ムーンライト」では、もとポリスのスティングのヴォーカルがフィーチュアされる。ボサノヴァの寛いだムードと清涼感のある歌声が見事にマッチする。その曲とテーマ曲をミックスして変奏した「ライナスの新生活」は、ウィリアムズお得意のドラマティックな展開を見せる。もの憂げな「パリ育ち」は、ヒロインの心理描写が鮮やかだ。躍動感のある「ムーンライト(インスゥルメンタル)」では、いかにもウィリアムズらしい色彩豊かな管弦楽法が披露される。
アコーディオンとストリングスが絡む「サブリナの回想/バラ色の人生」では、オリジナル版でヘップバーンが何度か口ずさむエディット・ピアフの曲が挿入される。静閑な「サブリナの帰郷」では、木管と弦の按配が絶妙だ。チェンバロが入る「ナンタゲット・ヴィジット」では、アンサンブルのエスプリの効いた表現が楽しい。ソース・ミュージックの「ザ・パーティー・シークエンス」は、エレガントなウィリアムズ版イージーリスニングとして楽しめる。メドレーの内訳はロバート・ウェルズの「ジョアンナが恋した時」ジョニー・マンデルの「いそしぎ」ジミー・ヴァン・ヒューゼンの「私は無責任」そしてヴィクター・ヤングの「星影のステラ」となる。ことに伝説的トロンボニスト、ディック・ナッシュの甘い音色が極上だ。
アルバムはさらに、アコースティック・ギターが静かにメロディを綴る「サブリナとライナスのデート」テキサス出身のシンガー、マイケル・ディースの繊細な歌唱が光る「ハウ・キャン・アイ・リメンバー」叙情性に不穏な空気が入り交じる「サブリナ、パリへ戻る」とつづき、ラストではふたたびリリカルなピアノから壮麗なオーケストラへと移行する「サブリナのテーマ(リプライズ)」が演奏される。やはりこの曲、ぼくはどうしてもラフマニノフの『パガニーニの主題による狂詩曲』の第18変奏をイメージしてしまう。まあ、それもまたご愛嬌。本作は、ウィリアムズのいつになく情緒的で甘美なオーケストラル・アルバムとして、申し分なく楽しめる仕様なのだから──。さすがにグルーシンでは、こうはいかなかっただろう。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。








コメント