非の打ちどころのない、巧みなしかも華麗なレトリックでリスナーを楽しませてくれるヘンリー・マンシーニの『シャレード』
 Album : Henry Mancini / Charade (1963)
Album : Henry Mancini / Charade (1963)
Today’s Tune : Charade (Main Title)
映画への興味は「サウンド・オブ・ミュージック」を弾いたことから
映画音楽はすばらしい!──というのは、俳優の安田顕がMCを務めるNHKのテレビ番組のタイトル。フレッシュな日本のアーティストの歌唱とゴージャスなオーケストラの演奏によるスタジオ・コンサート、さらに安田さんと出演アーティストのみなさんとのトークがなかなか楽しい。そして、懐かしい。ぼくの場合も、映画音楽が素晴らしいという思いは、いまも昔もまったく変わらない。ただ、ぼくが大好きな映画音楽といえば、1960年代から1980年代までの作品に集中する。それは、ぼくがピアノを継続して弾いていた時期にあたる。クラシック音楽の愛好家だった父の影響から、ぼくは生まれたときから音楽に親しんでいた。ピアノの個人レッスンを受けるようになるのも、ごく自然なことだったと云えよう。
ぼくは幼少のころからいろいろな習い事をさせられたが、そのほとんどがイヤイヤやらされていたものだった。体操教室、絵画、スイミングスクール、ボーイスカウト、すべて中途半端に終わった。親のこころ子知らずとはよく云ったもので、しょっちゅうサボっては本屋さんで立ち読みをしていたし、どの習い事においてもやめるときは本当に清々したものだった。ところがピアノだけは、大学生までつづいた。理由は説明できないが、音楽だけはぼくの感性に合ったのだろう。バイエル、ハノン、ブルグミュラー、ツェルニー、ソナチネと、お定まりの単調なピアノの練習体系も経験したが、苦痛に感じられるようなことはなかった。きっと大人になっていたら、ストレスを感じてやめていただろう。
ぼくが長年師事したピアノの先生は若い女性のかただったけれど、とても鷹揚なひとで採り上げる曲もぼくに好きなものを選ばせてくれた。ぼくが背伸びしてドビュッシーやラヴェルの曲を弾きたいと云っても、決してはねつけるようなことはなく、ちゃんと比較的優しい曲を選んで弾かせてくれたもの。だからぼくは、ずっと楽しくレッスンを受けることができたのだ。先生は顔立ちがちょっと若いころの女優アヌーク・エーメに似ていて、いまでも『モンパルナスの灯』(1958年)などの彼女の出演作品を観ると、ぼくのこころは、すっかり子どものころに戻ってしまい、落ち着きを失う。先生はぼくが大学生のころ、結婚を機に教鞭を置いた。そしてぼくもまた、次の先生とはそりが合わなくて、レッスンに通うのをやめてしまった。

新しい先生はまえの先生と考えかたや気質がまるで異なるかただった。たとえば、ぼくがピアノを弾いているとき少しでも間違うと、すぐに演奏を中断させ、はじめから弾き直しするよう指示した。まえの先生からは、小さな間違いにはこだわらず、間違いに気づいても絶対に演奏を止めてはいけないと教わっていたから、ぼくは戸惑うばかりだった。結局、ぼくはこれを機にピアノをひとから教わることをやめてしまったけれど、最初に師事した先生の教えはいまだにこころに留めている。なにがあっても演奏を止めてはいけない。ぼくはいまでも、そう信じている。そして、そんなピアノのレッスンに明け暮れていた時期に観た映画作品、そして聴いた映画音楽に、ぼくの愛着はいつの間にか深まっていたのである。
それはなぜかといえば、ぼくが最初に教わったピアノの先生が、ゆったりとした、こせこせしない音楽教育を与えるひとだったからだろう。先生は「弾きたい曲があれば、クラシックでなくても構わないから、楽譜をもってらっしゃい」そんな云いかたをするひとだった。ぼくが子どものころからポピュラー・ピアノにも馴染むことができたのは、先生のおかげだ。さらに楽譜に記載されたコードネームの意味を早い時期から理解するという、恩恵にも浴することができたのだから、ほんとうに幸運だった。最初はトライアドやセヴンスくらいのものだったろうが、そのとき覚えたことは、その後ぼくがジャズ・ピアノを独学するのに大いに役立った。最初に弾いたポピュラー・ソングは「サウンド・オブ・ミュージック」──1965年の映画音楽だ。
いまから思うと、ぼくがリチャード・ロジャースという作曲家の名前を知ったのは、ジャズを聴いたり演ったりするまえのことだったわけだ。それはともかく、この曲を弾いたことからぼくは、映画作品のほうにも興味をそそられた。とすると、ぼくが映画少年になったキッカケはこの曲ということになる。ぼくは小学校高学年のころから、隔週土曜日、4時限授業を終えて下校すると、池袋の文芸坐(現在の新文芸坐)に通うようになったのである。この映画館はいわゆる名画座で、新旧の名作映画を2本ないし3本立てで上映していた。音楽から映画にも関心を寄せ、逆に映画からその音楽を好きになる──そんな日々をぼくは過ごすようになったのである。あげくの果てには、分をわきまえず将来は映画音楽の作曲家になると決心した(ならなかったけれど)。
オードリー・ヘプバーンの主演映画からヘンリー・マンシーニへ
ぼくが当時よく聴いていた映画音楽の作曲家といえば、フランシス・レイ、ミシェル・ルグラン、ジョルジュ・ドルリュー、エンニオ・モリコーネ、アルマンド・トロヴァヨーリなど。ヨーロッパの作曲家ばかりだ。特にレイとルグランは1960年代から1970年代にかけて、日本でもすっかり人気者だった。たとえば、このころポピュラー音楽のジャンルとして耳目を集めていたイージーリスニング(当時はムード音楽とも呼ばれていた)において、彼らの曲は積極的に採り上げられていた。ポール・モーリア・グランド・オーケストラやレイモン・ルフェーヴル・グランド・オーケストラのレコードが、どこの家庭でも必ずといっていいほど所持されているような時代のことだ。楽譜においてもポピュラー・ピアノの曲集には、彼らの曲がたいてい収録されていた。
では、アメリカの映画音楽の作曲家では誰が好きかといえば、ぼくはデイヴ・グルーシンを真っ先に挙げる。ただ、もともとジャズ・ピアニストだった彼が、映画音楽の作曲家として脚光を浴びるのはもう少しあとのこと。グルーシンは1960年代の後半からフィルムスコアを手がけていたけれど、ぼくも彼の映画音楽に注目するようになったのは『コンドル』(1975年)以降だった。ということで、ぼくがポピュラー・ピアノを弾きはじめたころもっとも多く聴いていたアメリカの映画音楽は、ヘンリー・マンシーニ(1924年4月16日 – 1994年6月14日)の作品ということになる。なおマンシーニはグルーシンがリスペクトする作曲家でもあり、グルーシンは、名匠トミー・リピューマのプロデュースのもと『酒とバラの日々~ヘンリー・マンシーニに捧ぐ』(1997年)という素晴らしいアルバムを吹き込んでいる。
ヘンリー・マンシーニは、ある意味で映画少年だったころのぼくにとって、もっとも影響力のあった作曲家と云える。というのも、彼が1960年代にオードリー・ヘプバーン主演の映画作品を多く手がけたからだ。前述のように、ぼくは池袋の文芸坐に頻繁に足を運んでいたが、すぐに映画館のスクリーンに映るヘプバーンのチャーミングな魅力にこころを奪われた。この文芸坐ではヘプバーンの特集が組まれたこともあり、そのとき劇場ではオリジナルのパンフレットまで販売されていて、ぼくも映画を鑑賞したあとに購入したもの。たぶん、ぼくはヘプバーンの出演作品をほとんど観ていると思うけれど、アカデミー主演女優賞を獲得した名作『ローマの休日』(1953年)のときよりも、どちらかといえば30代のころの彼女が好きだった。
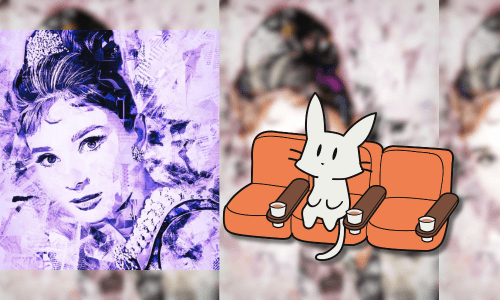
ぼくなりにヘプバーンの主演映画ベスト5を挙げると『ティファニーで朝食を』(1961年)『シャレード』(1963年)『おしゃれ泥棒』(1966年)『いつも2人で』(1967年)『暗くなるまで待って』(1967年)となる。これには異論のあるひとも多いだろう。言い訳になるかもしれないが、ぼくはヘプバーンに対して性的魅力を感じていないし求めてもいない。ぼくが彼女に惹かれるのは、どこかとぼけたところ、でもその立ち居振舞いがやたら洗練されていて可愛らしいところ、華奢な身体つきに反して結構じゃじゃ馬なところ、大ピンチに陥ってもそれに対して機転を利かせて勇敢に立ち向かうところ──と、彼女がクラスにひとりくらいは居そうでなかなか居ないような女の子みたいな、ちょっとした憧れの存在だからだ。結果、そういう選択になる。
上記の作品では、そんなぼくの好きなヘプバーンが大活躍する。どんなに深刻な状況であっても、どんなに粛然とした場面であっても、彼女の存在はまるでコメディリリーフのように観るものを楽しませてくれる。それを少年のぼくは、とてもスタイリッシュでロマンティックに感じたもの。特に驚いたときに滑稽なまでにキョトンと見開かれる彼女の双眸は、あまりにも魅力的だ。いま風に云えば、ハートがズギャン!となるのである。そして偶然にも、これらの5作品のうち4作の音楽をヘンリー・マンシーニが担当している。唯一『おしゃれ泥棒』のスコアは、ジョン・ウィリアムズによるものだ。マンシーニが多忙を極めたていたが故に、彼に師事したウィリアムズが起用された。そこでは、あの『スター・ウォーズ』(1977年)とはまったく違った、軽妙洒脱なサウンドが披露されている。
ところで、マンシーニの音楽を端的に云い表すと、それこそ『おしゃれ泥棒』ではないが、お洒落のひとことに尽きる。ぼくの敬愛するグルーシンと比較しても、格段にお洒落だ。お洒落であるが故に、彼の音楽はエレベーター・ミュージックと呼ばれることもある。欧米ではエレベーターのなかで音楽が流されるのは、一般的なこと。そこでかかるような音楽だから、エレベーター・ミュージック。つまり、ショップ、レストラン、ホテル、あるいは病院などで流されるBGMの呼称、ミューザックとおなじようなニュアンスで使われるコトバ。そしてその云いかたは、BGMにしかなり得ない平凡で無個性な音楽というスラングでもある。だが、ぼくはその観かたには、まったく賛同しかねる。一聴でそれとわかるような彼の音楽を、むしろ個性的とさえ云いたいくらいだ。
マンシーニ楽団によるラテン・フレイヴァーのラウンジ・アルバム
オハイオ州クリーブランド生まれ、ペンシルベニア州育ちのヘンリー・マンシーニは、フルート奏者だった父親の影響で8歳のときからフルートとピッコロを吹いていた。12歳になるとピアノとオーケストレーションを学びはじめる。ハイスクールを卒業後には、一度はピッツバーグのカーネギー工科大学(現在のカーネギー・メロン大学)に入学したが、間もなく名門ジュリアード音楽院のオーディションに合格し転校している。その際、尊敬するベニー・グッドマンの勧めでニューヨークへ移住、音楽院で本格的に音楽理論を究めた。彼は第二次世界大戦中、アメリカ陸軍航空隊に入隊し空軍音楽隊での演奏経験をもつ。それが縁でグレン・ミラー楽団にピアニスト兼アレンジャーとして採用された。ミラーもまた、陸軍航空隊のひとだった。
マンシーニがミラーの楽団に在籍したことは、のちの彼のサウンドに大きく影響を与えたと思われる。親しみやすいエレガントでロマンティックなメロディック・ラインと、ダンス・ミュージックとしても重宝されるような、即興演奏よりもアンサンブルが主軸に据えられたスウィンギーなサウンドは、ミラーの楽曲と共通する。ただこれはぼくの個人的な感想だけれど、マンシーニの音楽にはジャズのエッセンスが溢れているが、情熱的なジャズ・スピリッツのようなものは感じられない。アクの強さなど毛ほどもないのだ。それは彼がイタリア系アメリカ人であることが関係しているのかもしれない。つまりそのサウンドは、ジャズを異国の音楽として俯瞰しているようにも聴こえるのである。
マンシーニの音楽には、ジャズのほかにもラテン・ミュージック、特にカリビアンの要素が盛り込まれることが多い。云ってしまえば、いろいろな国の音楽の美味しいところを採り入れるのが、とても上手いのだ。マンシーニ・サウンドとは、カンツォーネの血筋を継ぐ、ときに甘美でありときに悲壮美に富んだ旋律と、アメリカのジャズやロック、ラテンのルンバやマンボ、さらにチャチャチャなどの軽快な律動とが、ミックスされて生まれたカクテル効果のようなものなのだ。その塩梅のよさと人情味溢れる演出からは、ダンディズムのようなものさえ感じられる。その洗練された格調の高いサウンドは、確かに気持ちがよく快適ではあるけれど、決してありふれたものではない。マンシーニ節は唯一無二である。

そんなマンシーニ・サウンドは、いつでも非の打ちどころのない、巧みなしかも華麗なレトリックでリスナーを楽しませてくれる。常にパーフェクト。ベストワンを選ぶことなど、ぼくにはできない。だから最初に観たヘプバーン映画、最初に手に入れたマンシーニのレコード『シャレード』をここに挙げる。ジャケットに“music from the motion picture score”と表記されているとおり、本盤は厳密にはサウンドトラック・アルバムではない。マンシーニは必ずと云っていいほど、フィルム・マスターとは別に商品化のためのフルレングス・ヴァージョンをレコーディングする。映像から離れても鑑賞するに足る音楽をリスナーに届けるという、彼のこだわりだ。そんなところも、実にダンディだ。なおオリジナルのスコアリング・セッションに興味のあるかたは、2012年に発売されたイントラーダ盤をどうぞ──。
ということで本作は、ヘンリー・マンシーニ楽団によるラテン・フレイヴァーのラウンジ・アルバムとして楽しむべき一枚。なんといっても一曲目の「シャレード(メイン・タイトル)」が素晴らしい。ウッドブロックとフット・ハイハット&タム、そしてコンガによるイントロの軽快なラテン・グルーヴ、4ビートになってからのエレクトリック・ギターによるミステリアスでメランコリックなテーマ、ときおり聴こえてくる箒で掃くようなサスペンスフルな効果音(ギロ?)、そしてストリングスによる広がりのあるサビ──と、このエキゾティックでジャジーなナンバーを名曲と云わずしてなんと云おう。ちなみに、大野雄二が作曲した映画『犬神家の一族』(1976年)のテーマ曲「愛のバラード」は、おなじ3拍子で曲の構成も酷似している。影響大である。
このテーマ曲はほかに、ジョニー・マーサーが歌詞をつけたコーラス・ヴァージョン、公園の回転木馬のBGMとして使用されたカルーセル・ヴァージョンが収録されている。公園のBGMといえば、ドリーミーなマーチング「幸運の回転木馬」も印象的。そのほかマンシーニが得意なラテン・タッチのナンバーには、南国情緒溢れるサンバ「陽気な酒場」ヴァイオリンとアコーディオンが哀愁を漂わせるルンバ「夜のセーヌめぐり」テナーやミュート・トランペットのソロも飛び出す「マンボ・パリジェンヌ」などがある。クラシカルな曲には、弦楽四重奏によるもの悲しいチェンバー・ミュージック「チャーリーの葬送」ユーモラスで可愛らしい3拍子「シャワーのワルツ」ミュージック・ホールのレヴュー風「あやつり人形の夫婦」などがある。そんな収録曲のほとんどがソース・ミュージックというのも、実に興味深い。
個人的には、洗練されたホーンズのアンサンブルと小粋なピアノ・ソロが光るボサノヴァ「雪のメジェーブ」トロンボーンとストリングスがやたらスウィートなムード満点のボッサ「淋しく降る雪」などが好み。マンシーニのハイセンスでスタイリッシュなサウンドの典型である。当時、作曲編曲についてはまったくの独学だったぼくは、かなり影響を受けた。とにもかくにも、説得力と鮮明さに富んだメロディック・ラインを推進させるコンポジション、ジャズやラテンをふんだんに盛り込んだアレンジメント、そして、なんといってもユーモアとペーソスが交じり合うような温もり感のあるエクスプレッション──と、マンシーニの音楽はファンタスティック。彼の作品に触れると、あらためて映画音楽は素晴らしいという思いが、ふつふつと湧いてくる。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。








コメント