映画音楽の神さま、エンニオ・モリコーネによる独立した音盤としても楽しむことができるサウンドトラック・アルバム『アンタッチャブル』
 Album : Ennio Morricone / The Untouchables (1987)
Album : Ennio Morricone / The Untouchables (1987)
Today’s Tune : The Strength Of The Righteous (Main Title)
イタリア出身の映画音楽の作曲家に関するあれこれ
そういえばこのブログでは、エンニオ・モリコーネ(1928年11月10日 – 2020年7月6日)の作品をまだ一度も採り上げていなかったな──。なんて、実は何度もそう思いながら、ぼくはその度に先送りにしてしまっていた。なぜなら、モリコーネ先生くらいの巨匠ともなると、多くのひとに語られているだろうから、いまさらぼくが拙い文章でなにを語るのか?──という思いがあったからだ。そのいっぽうで、実を云うとぼくにはそれと相反する考えもあった。それはモリコーネの音楽については、いつでも語ることができるという心境である。ちょっと大げさな云いかたになるけれど、それはぼくがモリコーネの音楽と向き合うときの姿勢を示唆するものでもあるのだ。
たったいま、ぼくはモリコーネのことを先生とか巨匠などと云い表したばかりだが、それは飽くまで一般的な彼に対する評価に準じたまでで、正直に云うとぼくは、彼に威厳や風格のようなものをまったく感じていないのだ。モリコーネの音楽は、ぼくにとってカジュアルというかフランクな感覚で接するものなのである。誤解しないでいただきたいのだけれど、なにもぼくは彼が創造する音楽を軽視しているわけではない。むしろその逆で、映画音楽の作曲家としてずっと敬愛の念を抱いてきた。小学校高学年のころから名画座通いをしていたぼくにとって、間違いなくモリコーネは映画音楽の神さまのようなひとなのだけれど、その音楽に気安さのようなものが感じられるのもまた事実だ。
エンニオ・モリコーネは、いまも歴史と文化が息づくローマの生まれ。ローマでもっとも有名な音楽学校、サンタ・チェチーリア音楽院で作曲を学んだ。映画音楽の作曲家では、ニーノ・ロータもこの学校の出身だ。モリコーネは、あのイタリア現代音楽の代表的な作曲家、ゴッフレード・ペトラッシに師事したということだから、無調性の作曲法や12音技法などについてもみっちり腕を磨いたのだろう。とはいっても彼の場合、自分は純音楽の作曲家で映画音楽の作曲は趣味などと吐かしたロータ先生とは異なり、純器楽作品を手がけることはごく稀で、ひたすらラジオ、テレビ、そして映画音楽の作曲に徹した。いずれにしてもモリコーネは、生粋のコンポジトーレ・イタリアーノである。
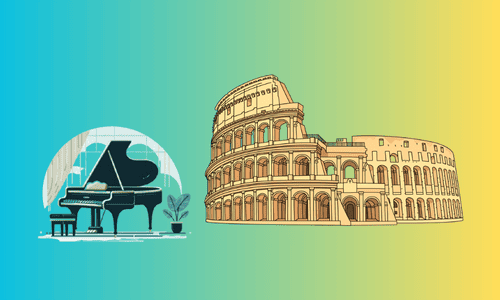
イタリアの映画音楽の作曲家といえば、やはりまずはロータの名前を挙げざるを得ない。ルネ・クレマン監督の『太陽がいっぱい』(1960年)や、フランコ・ゼフィレッリ監督の『ロミオとジュリエット』(1968年)、あるいはフランシス・フォード・コッポラ監督の『ゴッドファーザー』(1972年)などのテーマ曲は、多くのひとが口ずさむことができるだろう。それらの楽曲にはみな甘く切ない旋律が内包されているけれど、それと同時にどこか厳粛な雰囲気が漂うという特色がある。子どものころからオラトリオやオペラを作曲し、音楽大学を卒業すると間もなくシンフォニーの作曲に取りかかったというロータは、やはりバリバリの芸術音楽の作曲家なのだ(本人もそう云っているしね)。
ぼくは名画座通いをしていたころ、フェデリコ・フェリーニ監督やルキノ・ヴィスコンティ監督の映画をずいぶん観たけれど、それらの作品ではロータが音楽を手がけていることが多かった。特にフェリーニは、確かロータが健在だったころは、すべて彼に音楽を任せていたのではなかったかな。個人的には『道』(1954年)『ボッカチオ’70』(1962年)『フェリーニのアマルコルド』(1973年)といった作品の音楽が印象に残っている。フェリーニにしてもヴィスコンティにしてもネオレアリズモの潮流に乗った映画人だけれど、彼らの作品はファシズムへの抵抗、あるいは退廃的社会に対する批判を内含する場合がある。そこから生まれる高い文学性を象徴するかのようなロータの音楽は、やはり文学的であり哲学的でもある。
そんなロータの格調高い音楽と対局をなすのが、アルマンド・トロヴァヨーリの格式ばらないサウンドだ。イタリア映画といえば、なにも文芸作品、歴史映画、あるいはプロパガンダ映画ばかりではない。むしろそれ以上に、ネオレアリズモ・ローザ、イタリア式コメディ、マカロニ・ウェスタン、ジャッロといった、とにかく理屈抜きに楽しめる映画が多種多彩である。そういうエンターテインメント作品の音楽を得意とするのが、トロヴァヨーリなのだ。たとえば、何本かコンビを組んだマルコ・ヴィカリオ監督のお色気たっぷりの映画では、彼がクリエイトする独特のサウンドがきわめて有用。たとえ道徳的に問題がありそうなシーンでも、トロヴァヨーリの小洒落た音楽が流れてくると、なにやら妙に明るくほのぼのとした様相を帯びてくるから不思議だ。
ぼくは特に1960年代のトロヴァヨーリ・サウンドが好きなのだけれど、そのトレードマークといえば、煌びやかなチェンバロであり、弾けんばかりにパーカッシヴなオルガンであり、スタイリッシュな口笛であり、軽妙な「ダバダバ」というスキャットであり、はたまた少々とぼけた「ボヨーン」という口琴である。リズムの面でもジャジーな4ビート、マンボやボサノヴァなどのラテン、ロッキッシュな8ビートから斬新な16ビートまで変幻自在。しかもバロック音楽まで飛び出してくるのだから、さながら音楽のおもちゃ箱といったところだ。ところがこのトロヴァヨーリ、実はモリコーネやロータと同様にサンタ・チェチーリア音楽院の出身なのだ。まあ彼の場合、17歳のときから高級ナイト・クラブでジャズ・ピアノを弾いていたのだけれど──。
ときにモリコーネだが、ロータやトロヴァヨーリよりずっと年下になるが、ちょうどふたりの先輩の中間に位置するような作曲家だ。ひとことで云うと、中庸を行く音楽家ということになる。つまり彼は、芸術音楽と大衆音楽とのどちらにも極端に偏らず、かといってどちらの音楽性においても過不足なく調和のとれた、まことに映画音楽の作曲家に相応しい音楽家なのである。モリコーネの音楽の素晴らしいところは、映像とのマッチングが抜群にいいということ。その点で彼は、フランソワ・トリュフォー監督とのコンビで知られるフランス出身の作曲家、ジョルジュ・ドルリューと並んで、ぼくのもっとも好きな映画音楽の作曲家のひとりということになる。
実はモリコーネはなんでも来いの職人的作曲家である
各々の映画作品の語るべきことが、的確な音楽で表現されるという点で、モリコーネのスコアは他の追随を許さない。平たく云えば、彼は観客に感動を与える達人なのである。そんなモリコーネの音楽が、ヨーロッパやアメリカではもちろんのこと、わが国でも広く知られるようになったのは、ジュゼッペ・トルナトーレ監督の『ニュー・シネマ・パラダイス』(1988年)からだろう。モリコーネのペンによるセンティメンタルでノスタルジックな音楽は、映画への愛情と人生の素晴らしさが謳われたこの感動作を、さらなる高みへ誘った。結果、この映画はアカデミー外国語映画賞、ゴールデングローブ賞外国語映画賞、カンヌ国際映画祭審査員グランプリなどを受賞した。
この『ニュー・シネマ・パラダイス』の音楽において、多くのひとのこころをわしづかみにするものはなにかといえば、自明のことだがそれはノスタルジアである。つまりそれは、異郷から故郷を懐かしむことであり、過ぎ去った時代を懐かしむことでもある。映画でいうと、成長し出世した主人公のサルヴァトーレがローマからシチリア島を想うこと、そこで過ごした幼少期や青春時代を偲ぶこととなる。ラストシーンにおいて、試写室でひとり瞬くスクリーンを見上げながらサルヴァトーレのノスタルジアは全開する。そういう郷愁や追憶、あるいはそれにともなう永らえない寂寥感はだれもが抱えるものだから、大勢の観衆のこころを揺さぶるのだ。そしてモリコーネは、そのようなオーディエンスの感情の高まりをコントロールする術を、ちゃんと知っているのである。
モリコーネがものした『ニュー・シネマ・パラダイス』のテーマ曲は、高い人気を得た。これまでにジャンルを問わず多くのミュージシャンによってカヴァーされているし、CMやテレビ番組においても、これでもかというほど流用されている。でもぼくなら間違ってもそんな人気にあやかって、この曲を自分で演奏したりはしない。なぜならこの曲については、絶対的にオリジナルが至高のヴァージョンであり、映像から切り離してしまうといささか精彩を失うように、ぼくには思われるからだ。反感を買うことを承知の上で云うけれど、モリコーネの音楽には概してそういう性向がある。スクリーンで流れる彼の音楽は得も云われぬ感動を呼ぶが、自宅で音盤を聴いてみると存外それほどでもなかったりする。
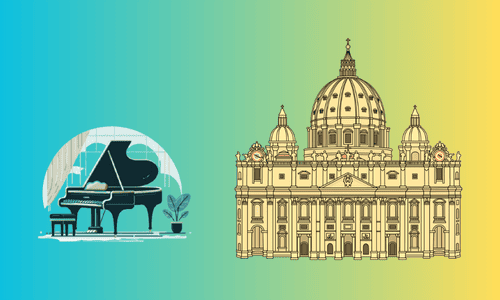
ここで繰り返すけれど、エンニオ・モリコーネは、ぼくにとって映画音楽の神さまのようなひと。平たく云うと、音づけの天才なのである。そのこころの琴線に触れるようなメロディック・ラインにしても、温もりを感じさせるテクスチュアにしても、ひたすら映画音楽のフィールドで経験を積むことによって培われた、いわば職人ワザによるもの。そんなモリコーネに絶大の信頼を置くトルナトーレ監督は、この『ニュー・シネマ・パラダイス』以降すべての作品の音楽において、彼を起用している。このコンビは『明日を夢見て』(1995年)『海の上のピアニスト』(1999年)『マレーナ』(2000年)といった作品で、世界的に高い評価を得たけれど、それ故モリコーネに一面的なイメージが定着してしまったというのも、また事実である。
モリコーネは、1980年代のなかごろからそのサウンドに謹厳実直な匂いを感じさせるようになるけれど、それよりまえはけっこうくだけた音楽も演っていた。ぼくはさきに彼のことを中庸を行く音楽家と云い表したけれど、昔の作品にはそれこそトロヴァヨーリ・サウンドを彷彿させるようなものもある。たとえば、カミロ・マストロチンクェ監督のロマンティック・コメディ『太陽の下の18才』(1962年)で、モリコーネはメランコリックなメロディック・ラインとバウンシーなリズムをもった楽曲を披露している。特にイタリアのシンガー、ジャンニ・モランディが歌った挿入歌「サンライト・ツイスト(Go-Kart Twist)」は、モリコーネの初期の傑作とぼくは観ている。1960年代ならではの、ポップなダンス・ナンバーだ。
個人的には、この曲にあわせて文字どおりツイストする(フランス生まれの)カトリーヌ・スパークのコケティッシュな魅力にやられた。まあそれは置いておいて、このポップ・イタリアーノのちょっと悩ましい調べをよく聴くと、いかにもモリコーネ節なのだ。彼の書く楽曲にはしばしば、美しさのなかにそこはかとなく扇情的なニュアンスが漂うことがある。そのなんとも艶やかなフィーリングが、作品を美辞麗句だけの音楽に終わらないものにしていると、ぼくはかねがね思っていた。たとえばこの曲をテンポを落として弦楽合奏などで演奏したら、ブリランテかつアパッショナートなナンバーとして成立するに違いない。池田満寿夫監督の『エーゲ海に捧ぐ』(1979年)のテーマ曲みたいに、あそこまで官能的にはならないけれど──。
この『エーゲ海に捧ぐ』のサウンドトラック・アルバムは、モリコーネの型破りなスコアをたっぷり堪能することができる、なかなかの逸品だ。ハープとピアノの美しい音色を背景とするソロ・ヴァイオリンと女性スキャットとの絡み、ディスコ・ビートと女性の笑い声との交錯、弦楽器の先鋭的なパフォーマンスと女性の喘ぎ声との錯綜と、彼は変態的なまでに音づけに対する真摯な姿勢を見せている。これにとどまらず、1970年代にモリコーネが手がけた映画音楽には、それこそトロヴァヨーリのように格式ばらないサウンドが満載だ。しかもこの時代のモリコーネは、歴史、アクション、サスペンス、SF、パニック、コメディなどなど、とにかく幅広いジャンルの映画作品にスコアを提供している。
そんななかこれは一例に過ぎないけれど、ぼくの好きなイタリアン・ホラーの巨匠、ダリオ・アルジェント監督の『歓びの毒牙』(1970年)『わたしは目撃者』(1971年)『4匹の蝿』(1971年)といった、まさに戦慄が走るような映像作品においては、ロックから現代音楽まで駆使されて構築されたモリコーネ流スケアリー・ミュージックを満喫することができる。彼の恐怖に対するキレのある感覚や表現方法は、見事に観客の感情を逆なでする。そんなことからも、やはりモリコーネは決して芸術至上主義の音楽家ではなく、定めしなんでも来いの職人的作曲家であると云えるだろう。まあこれもまた、昔からの彼のファンなら、百も承知、二百も合点のことだろう。
さながら音楽の詰め合わせのようなフィルム・スコア
ついでに云わせてもらうと、1960年代のモリコーネのマスターピースといえば、なんといっても数々のマカロニ・ウェスタン作品だろう。彼はこのジャンルにおいては、パイオニア的存在だ。モリコーネとは小学校の同級生でもあるセルジオ・レオーネ監督の『荒野の用心棒』(1964年)のテーマ曲「さすらいの口笛」は、あまりにも有名だ。モリコーネはこの曲において、文字どおり口笛を主軸に鐘や鞭を効果的に使用し、巧妙にメランコリックかつヒロイックなムードを高めている。つづく『夕陽のガンマン』(1965年)のテーマ曲では、エレクトリック・ギター、ワイヤーブラシ、そして口琴なども加えられ、さらにクールさがパワーアップする。この時点でモリコーネは、西部劇のイメージをパーフェクトなまでに定着させてしまったのである。
その後もレオーネ監督は『続 夕陽のガンマン』(1966年)『ウエスタン』(1968年)『夕陽のギャングたち』(1971年)『ミスター・ノーボディ』(1973年)と、立てつづけにマカロニ・ウェスタン映画を撮ったが、音楽はすべてモリコーネが担当している。レオーネはマカロニ・ウェスタンの父であるとともに、徐々にブームが衰退するなかにあってももっとも高品質の作品を生み出した監督だ。モリコーネもまたブームの渦中で、きわめてオリジナリティに溢れたスタイリッシュなスコアを提供していた。さきに挙げた楽器のフィーチュアリングに加え、孤高を象徴するようなトランペットやハーモニカの使いかたは、ほかの作曲家が手がけた作品にも観られるけれど、彼らはモリコーネのエピゴーネンであると云わざるを得ない。
レオーネとモリコーネとのコンビによるマカロニ・ウェスタン映画のサウンドトラック・アルバムはどれも素晴らしい出来で、映画を観ていなくても十分に楽しめるインストゥルメンタル作品だ。そもそも熱心なサントラ盤の蒐集家を生み出す契機となったのは、これらのアルバムをはじめとする西部劇の音盤だったのではあるまいか。いずれにしても、この映画監督と作曲家とのコラボレーションが残したものは、映画界にとって大いなる遺産と云えるだろう。なお『続 夕陽のガンマン』や『ウエスタン』などでは、撮影まえにモリコーネが作曲した楽曲にインスパイアされたレオーネが、そのイメージに沿って映画を撮影するという、ユニークな手法が採られることもあったという。
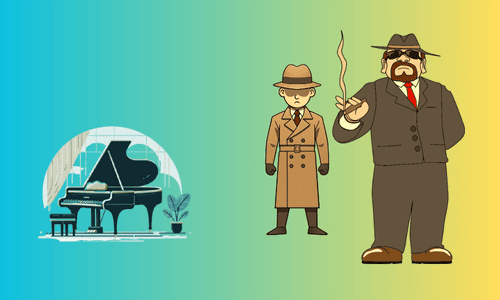
ふたりの絶妙な連携プレイがいまもって語り継がれるのは、なんといっても『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・アメリカ』(1984年)という傑作が世に送り出されたからだろう。この1920年代のはじめから1960年代の後半に至る、ユダヤ系移民のギャングたちの愛と裏切りの叙事詩は、レオーネの遺作にして代表作である。彼は『続 夕陽のガンマン』を撮り終えたころから脚本を書きはじめていたというから、本作はほんとうの意味でレオーネ渾身の作と云える。モリコーネを語るときも、この映画を外すことはできないだろう。ゲオルゲ・ザンフィルのパンフルート、ディキシーランド・ジャズ、あるいはスペイン出身の作曲家ホセ・ラカジェの名曲「アマポーラ」が効果的に使用されるとともに、お得意のノスタルジックな楽曲も盛り込まれた色彩豊かなスコアは、モリコーネの最高傑作と云っても過言ではない。
モリコーネ・ファンにとって『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・アメリカ』のサウンドトラック・アルバムは、間違いなくマストハヴだけれど、それとあわせて個人的におすすめしたい作品がある。ニュー・ハリウッド世代の個性派、ブライアン・デ・パルマ監督の『アンタッチャブル』(1987年)のサウンドトラック・アルバムだ。映画は禁酒法時代のシカゴを舞台に、アル・カポネをボスとする犯罪組織と、財務省のエリオット・ネスをリーダーとする特別捜査班との激闘が描かれた、クライム・フィルム。映像派のデ・パルマにしては珍しくストーリーを最良の形で綴ることに徹しており、映画は調和のとれたエンターテインメントの佳作に仕上がっている。モリコーネはここでもまた、映像とのマッチングが抜群にいいスコアを提供している。
デ・パルマ作品といえば、おなじイタリアの作曲家、ピノ・ドナッジオが音楽を担当することが多いけれど、ここではより地に足のついたモリコーネが抜擢された。しかもモリコーネはこの作品において、マカロニ・ウェスタンに通底するリズミカルでスタイリッシュなサウンド、トルナトーレ作品を彷彿させるセンティメンタルでノスタルジックな旋律と諧調、そして現代音楽の語法まで駆使している。すなわちモリコーネ・サウンドのいいところが満載というわけだ。前述したとおり、モリコーネは映画音楽の神さまのようなひとなのだけれど、このようにさながら音楽の詰め合わせのようなフィルム・スコアを軽々と書き下ろしてしまうところにこそ、ぼくは気安さのようなものを感じるのである。
アルバム・プロデュースはモリコーネ自身が手がけ、選曲、編集、曲順に至るまですべて彼のアイディアが反映されている。それ故、独立した音盤としても楽しむことができる仕様となっている。冒頭の「アンタッチャブル(エンド・タイトル)」は、もっとも重厚で壮麗なオーケストラル・ナンバー。華やかで勇ましい曲調が、アルバムの幕開けに鮮烈なインパクトを与える。つづく「アル・カポネ」では、ホンキートンク・ピアノの音色が暗黒街の顔役の極悪非道さをストレートにイメージさせる。また「ウェイティング・アット・ザ・ボーダー」では、モールス符号のようなベースラインと弦をはじめとする不調和なアンサンブルが緊張感を高める。トルナトーレ作品を想わせる「死のテーマ」では、ソプラノ・サックスによるもの悲しい旋律がこころに染みる。
メイン・タイトルのヴァリエーション「オン・ザ・ルーフトップス」では、動と静のシークエンスにゾクゾクさせられる。つづく「勝者の誇り」では、オーケストラが威風堂々とした雰囲気を放つ。不穏な空気を作る「ザ・マン・ウィズ・ザ・マッチス」では、ストリングスのレガートによる緊迫感溢れる表現が、なんとも素晴らしい。リズミカルでポリメトリックな「正義の力(メイン・タイトル)」では、まさにマカロニ・ウェスタンの遺産が現代的にアレンジされている。ドラムスとピアノとによるビート感、ハーモニカによる重苦しい空気、弦楽器のスリリングな挿入などが渾然一体となって迫る。それとは対照的な「ネスと彼のファミリー」は、フルートやヴァイオリンが優しくも愛らしい調べを奏でる、モリコーネ流ノスタルジアの真骨頂。紛れもなく名曲だ。
さらにアルバムは、アンサンブルが協和融合しないサウンドを響かせる「フォールス・アラーム」オーケストラがもっとも荘厳な響きを奏でる「アンタッチャブル」アルト・フルートとストリングスによる量感のあるレクイエム「フォー・フレンズ」とつづき、最大のハイライト「マシーン・ガン・ララバイ」に至る。映画ではシカゴ・ユニオン駅における、あのベビーカーが階段を落ちていくなかでの銃撃戦のシーンで使用された曲だ。柔らかなオルゴールの音色(シンセ)と不安や恐怖の感情を催させるオーケストラの響きとが絶妙に交錯する。こういう現代音楽の手法がよりドラマティックかつロマンティックに展開されるところも、モリコーネ・サウンドの魅力のひとつ。それが決して小難しく聴こえることがないものだから、ぼくはついつい彼の音楽に気安いものを感じてしまうのである。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。








コメント