デイヴ・グルーシンの弟、ドン・グルーシンのトランスアトランティックな味わいと巧みなシンセサイザー・サウンドが魅力的なファースト・アルバム『ドン・グルーシン』
 Album : Don Grusin / Don Grusin (1981)
Album : Don Grusin / Don Grusin (1981)
Today’s Tune : Number Eight
クリスマス・ソングの雄編「ベター・ザン・クリスマス」の作曲者
いきなり余談で恐縮なのだが、たったいまちょっと古いクラシックのCDを聴きながら、ぼくはひとり幸福感に浸っていた。仕事休みの特にやることもない、日曜日の昼下がりのことである。そろそろブログを執筆しようと思い立ち、プレイヤーからCDを取り出そうと開閉ボタンを押す。すると、ディスプレイにはいつものように「OPEN」と表示されたものの、トレイのほうはまったく駆動する気配がない。何回かボタンを押してみたり、電源を入れ直してみたりしたが、トレイはいっこうに出てこない。実はずっとまえにも同様のトラブルに見舞われたことがあったので、面倒くさいなと思いながらも、さほど慌てずおもむろにプレイヤー本体のカヴァーを外してみた。取扱説明書には、そんなことをしてはダメと書かれているのだけれど──。
ぼくはトレイを駆動させているベルトを外し、それをキッチンにもっていって食器用洗剤を使って軽く洗った。しばらく乾かしておいたベルトをふたたび所定の位置に装着し、開閉ボタンを押してみるとトレイは無事に動いた。こう書くとまるで、あっという間の出来事のように思われるかもしれないが、実際は工具を用意したり、ネジを抜き取ったり捩じ込んだりしているわけで、小一時間ほどかかっているのだ。まったくもって、煩わしい。ちなみにプレイヤーのなかに囚われの身となっていたCDは、グスタフ・マーラーの『交響曲第4番』で、ぼくのもっとも敬愛するコンダクター、クラウディオ・アバド指揮によるウィーン・フィルハーモニー管弦楽団が演奏したもの。独唱はフレデリカ・フォン・シュターデが務めており、吹き込みは1977年5月である。
ということで、CDを交換してブログの執筆に臨むとしよう。一応お断りしておくと、ぼくはブログを書くときは、そこで採り上げる音楽作品を実際に自室のオーディオで再生しながら、筆を走らせているのだ。ときにはおなじアルバムを、何度となく繰り返して聴くこともある。まあ音楽ブログを書いているひとだったら、そのやりかたは似たり寄ったりだろう。それにしてもマーラーのシンフォニーを聴いたあとに、フュージョン作品を流しながら、それについてあれこれ述懐したりするぼくのようなヤツは、ごく稀な存在と云えるかもしれない。どうもぼくの行いには、筋道が一貫していないところがある。音楽を楽しむときも、たまにチョイスするアイテムが、互いにちゃんとした繋がりもなく、行き当たりばったりで手にとったものだったりするのだ。
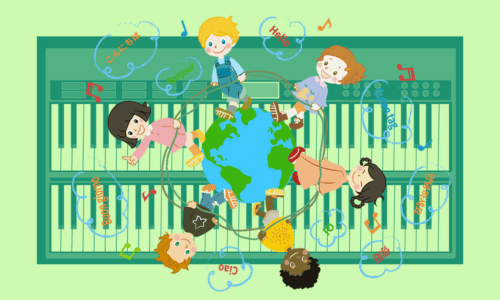
そういう次第で今回もご多分に漏れず、ふとアタマに浮かんだアーティストの作品をご紹介しようと思う。お伝えするのは、1970年代の中ごろからキーボーディスト、コンポーザー、アレンジャー、プロデューサーとして、多くの音楽作品に関わってきたドン・グルーシンのファースト・アルバム『ドン・グルーシン』(1981年)である。中学生のころにいち早くレコードを購入し、大学生のときにCDで買い直した。その機にレコードのほうは自分で云うのもなんだが、気前よく妹にあげてしまった。それゆえ現在ぼくが所持するのはCD盤のみなのだが、さきほどいざそれをプレイヤーにセットしようと思いきや、ご説明したようにとんでもない事態を迎えるに至ったわけだ。でもいまは、自室のオーディオ機器はすべて快調である。
ところで、ぼくがこの『ドン・グルーシン』というアルバムをなぜ不意に思い出したのかというと、ちょっとしたワケがある。ぼくの勤め先では常に音楽が流れているのだけれど、先般より職場に置いてあるプレイヤー内のオーディオファイルが、徐々にクリスマス・シーズンに合わせたものに差し替えられている。まあ、ほとんどぼくと音楽好きの女の子とで選曲しているのだが、実を云うとぼくのセレクションにはグルーシンの曲が含まれている。具体的には「ベター・ザン・クリスマス」という曲で、作曲をグルーシンとナタリー・ルネ、作詞をリチャード・ルドルフが手がけている。ルネはロサンゼルス在住のラテン系女性シンガーソングライター、ルドルフはもとミニー・リパートンの公私にわたるパートナーとして知られるソングライターだ。
このハートウォーミングなバラード・スタイルのクリスマス・ソングは、グルーシンとルネとのコラボレーション・アルバム『ベター・ザン・クリスマス』(2004年)に収録されているが、全面的にルネのヴォーカルがフィーチュアされた作品である。むろん本作の全楽器の演奏、プログラミングは、グルーシンが手がけている。CDアルバムは、ルネの自己レーベルであるナティ・レコードからリリースされた。インディペンデント・レーベルによる限定プレスということで現在は入手困難かもしれないが、収録曲はすべてネット配信で聴くことができる。8割がたグルーシン、ルネ、ルドルフによるオリジナル・ナンバーで構成されているが、どの曲もしっかりクリスマス・スタンダーズの風格を備えている。
さらに補足すると、この雄編「ベター・ザン・クリスマス」に、早い時期から注目していたミュージシャンがいる。ドイツのトランペッター、ティル・ブレナーが自己のリーダー作『ザ・クリスマス・アルバム』(2007年)において、この曲をカヴァーしているのだ。ブレナーはこのアルバムに寄せたコメントのなかで、それとなく「ベター・ザン・クリスマス」が将来名曲と呼ばれるようになるだろうと仄めかしている。ルドルフによる愛と幸福に満ち溢れた歌詞、グルーシンとルネとによる簡潔でありながら気宇壮大な旋律といったソングライティングも然ることながら、知られざるダイヤモンドの原石にしっかり目を向けるというブレナーの情報感度の高さと、上質の音楽を見極めるその慧眼に、ぼくはひとりで嬉しくなってしまった。
なおブレナーの「ベター・ザン・クリスマス」をベルリン・ドイツ交響楽団をバックに、色彩に富んだ声で詩情豊かに歌い上げているのは、女優でシンガーのイヴォンヌ・カッターフェルド。彼女の瑞々しくも風格のある声質は、こころ温まるドリーミーな曲想にピッタリだ。ブレナーのハスキーでエアリーなフリューゲルホーンによるソロとオブリガートもいつになくスウィート。その完成度の高さといったら、オリジナルのそれを凌ぐ勢いである。いっぽうオリジナル・ヴァージョンを歌ったルネは、どことなくコケティッシュな独特の歌声の持ち主で、力強い歌いまわしにもキュートな魅力が溢れている。彼女はグルーシンの全面的なサポートを得て『30マイルズ』(2006年)という、素晴らしいアダルト・コンテンポラリー作品をリリースしている。
いささか長くなってしまったが、以上のようなことから今回はドン・グルーシンのこと、それもファースト・アルバムを含めたその比較的初期のキャリアについて語ってみたい。それはそうと、グルーシンのもっとも新しいアルバムといえば、ぼくの知る限りではオクターヴ・レコードからリリースされたソロ・ピアノ作品『アウト・オブ・シン・エア』(2020年)ということになる。このアルバムは2020年初頭、ドン・グルーシン・スタジオにおいてレコーディングされたもの。実はそれまでロサンゼルスに活動の拠点を構えていたグルーシンは、2015年に故郷であるコロラド州に戻っている。その際に彼は、コロラド州サライダ市のポンチャ・クリークのほとりに、プライヴェート・スタジオを構えた。それがドン・グルーシン・スタジオである。
学究の徒だったグルーシンが本格的に音楽の道を志すまで
この『アウト・オブ・シン・エア』では、DSD方式のレコーディング&ミキシングによって、情趣溢れるアコースティック・ピアノの演奏が臨場感のあるサウンドで再現されている。DSDとは“ダイレクト・ストリーム・デジタル”の略称で、音声をデジタル化する方式のひとつ。音の細かいニュアンスが従来以上に忠実にリプロデュースされた、滑らかで透明感のあるサウンドが魅力的だ。その上質の音響表現から本作は、英国の音楽雑誌『ハイファイ・ニュース&レコード・レヴュー・マガジン』によって、2020年の年間ベストCDの1枚として選出された。音のよさは云うまでもなく、グルーシンのコンポジションとピアノ・プレイとが描き出すイマジナティヴな音世界が素晴らしい。結果的に本盤は、コンテンポラリー・ジャズの枠に収まり切らない、多様性を孕んだ作品に仕上がった。
グルーシンといえば、誰もがすぐにコンテンポラリー・ジャズのキーボーディストであり映画音楽の作曲家でもある、あのデイヴ・グルーシンを思い浮かべるだろう。ドン・グルーシンはその7歳年下の弟だが、兄のデイヴがハリウッドの伝統を汲んだ正統派サウンドをクリエイトしつづけたのに対し、彼はグローバルな視野で音楽をディープに探求してきた。グルーシンはこれまでにコラボレーション作品やライヴ・アルバムを含めると、20枚ほどのリーダー作を発表してきたのだが、それらをあらためて聴いてみると、彼がいわゆる環大西洋音楽を志向していることがわかる。つまりそのサウンドからは、ジャズはもとよりブラジリアン、カリビアン、そしてアフリカンといった、ボーダレスなフレーヴァーが単独ではなく一体となって知覚されるのだ。
グルーシンのアルバムでは多少なりとも、典型的なコンテンポラリー・ジャズのスタイルとはひと味もふた味も違う、民族、国籍、文化などの違いを乗り越えたワールドワイドな音世界が繰り広げられている。その点では、ソロ・ピアノで吹き込まれた『アウト・オブ・シン・エア』も例外ではない。とはいえ、自己の存在証明のごときユニークなアルバムを次々に発表してきたグルーシンではあるが、そのアイデンティティを作品に色濃く反映させるようになったのは1990年以降のことである。まえにも触れたが、彼は1970年代の中ごろから様々なアーティストのバック・ミュージシャンを務めていた。そんな彼は当初、いつも兄のデイヴの陰に隠れていて、どちらかというと名脇役という印象を湛えていた。
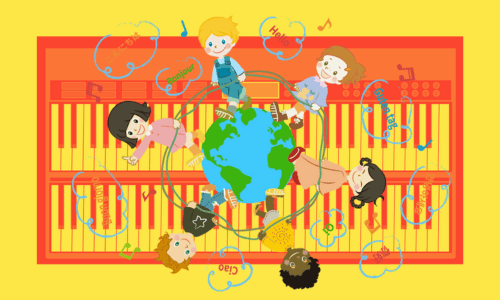
むろんグルーシンは、兄のデイヴのレコーディングやライヴに何度となく参加している。そんなときの彼の役割といえば、兄がアコースティック・ピアノで流麗なメロディを奏でているときに、後方で様々な電子楽器を駆使してサウンドを色彩豊かなものにすることだった。そういう経験もあってグルーシンは、各種のシンセサイザーやコンピュータに精通している。そんなハードスキルも、彼の音楽の幅を拡大するための有力な手立てとなっている。グルーシンのファースト・アルバム『ドン・グルーシン』は、まさにその手腕が遺憾なく発揮された作品と云っていい。トランスアトランティックな味わいはまだ淡白ではあるけれど、シンセサイザーが巧みに扱われたサウンドには、時代の趨勢に流されることのない、グルーシンのセンスのよさが感じられる。
ではここで『ドン・グルーシン』がリリースされるまでのグルーシンの経歴を、簡単に記しておく。ドン・グルーシンは1941年4月22日、コロラド州リトルトン市に生まれた。現在84歳である。父親がニューヨークの弦楽四重奏団のヴァイオリニストだったことから、6歳からピアノを弾きはじめた。クラシックではウラディミール・ホロヴィッツ、ジャズではアート・テイタム、オスカー・ピーターソン、ビル・エヴァンスといったピアニストから影響を受けた。兄のデイヴがひたすら音楽に打ち込む天才肌の努力家であったのに対し、彼はピアノのレッスンも継続していたが、10代のころはどちらかといえば勉学とスポーツにのめり込んだという。当初グルーシンは、音楽家になることを考えていなかったようだ。
ただグルーシンには当時から、ラジオから流れるソウル・ミュージックやファンク・バンドの演奏を愛聴し、アフリカやラテン・アメリカの音楽にも興味をもつという一面もあったという。この経験はのちの彼の独特のサウンドに、少なからず影響を与えたと思われる。ときにグルーシンはコロラド大学へ進学し、社会学の学士号を得たのち経済学の博士号も取得した。さらに彼はそのまま母校で教鞭を執り、それに加えてメキシコのオートノマス大学でフルブライト特別研究員として教壇に立ったこともある。音楽は飽くまで趣味だったが、それでも大学院生のころには、コロラド州デンバー市のジャズ・スポット、セネト・ラウンジにおいて、ゲイリー・バートン(vib)、クラーク・テリー(tp)、ズート・シムズ(ts)らとギグを行ったりしていた。
グルーシンは1972年、サンフランシスコ近郊のフットヒル・カレッジで教職に就きながら、ラテン・パーカッションのカリスマ的存在であり、あのシーラ・Eの父親としても知られるピート・エスコヴェードのグループ、アステカに参加。彼の音楽に観られるクロスカルチュラルな部分は、このときに養われたのかもしれない。学究の徒だったグルーシンをプロ・ミュージシャンの道に引きずり込んだのは、クインシー・ジョーンズだ。彼はジョーンズのリーダー作『メロー・マッドネス』(1975年)でレコーディング・デビュー(兄のデイヴも参加)。同年、ジョーンズ率いるオーケストラの一員として初来日も果たした。アメリカに戻ったあと、グルーシンは本格的に音楽の道を志すこととなった。
このころのグルーシンが参加した音楽作品ですぐに思い出されるのは、スコットランドのロック・シンガー、クリス・レインボウの『ホーム・オブ・ザ・ブレイヴ』(1975年)、ジャズからカントリーまでこなす女性シンガー、ペギー・リーの『鏡』(1975年)、はたまたギタリスト、鈴木茂の『バンド・ワゴン』(1975年)など。鈴木さんのかの有名な「砂の女」で、リズミカルなフェンダー・ローズを弾いているのはグルーシンなのだ。それはともかくその後のグルーシンは、まさに飛ぶ鳥を落とす勢いで様々なレコーディングやライヴ・イヴェントに関わっていく。なかでももっとも重要なキャリアといえば、フュージョン・ギターの雄、リー・リトナーのグループへの参加だろう。ことのはじまりは、リトナーの1977年のレコーディングだった。
グルーシンは1曲のみだが、リトナーのリーダー作『キャプテンズ・ジャーニー』(1978年)に参加している。このアルバムは兄のデイヴが当時主宰していた原盤制作会社、グルーシン/ローゼン・プロダクションの作品だが、兄とともにグルーシンはファンキーな自作曲「ホワット・ドゥ・ユー・ウォント」を堂々とプレイしている。それを機に彼は、リー・リトナー&ジェントル・ソウツのメンバーとなり、グループのダイレクト・ディスク『フレンドシップ』(1978年)において、8分の7拍子と4分の4拍子とを混合した「シー・ダンス」という傑出した曲を提供した。これはグルーシンの初期の代表曲と云ってもいいだろう。ちなみに兄のデイヴがのちに「マウンテン・ダンス」という曲を書いているのだが、あたかもアンサーソングのようで面白い。
ハードスキルが活かされたスペイシーなフュージョン・サウンド
その翌年、リトナーはジェントル・ソウツをフレンドシップと改名し、アルバム『アンサンブル』(1979年)をリリースする。このアルバムでグルーシンは、キーボードはもちろんのことミキシングやプロデュースも手がけている。しかも半分以上の曲を、彼が作曲しているのだ。そもそも本盤は、日本ではリー・リトナー&フレンドシップのアルバムとしてリリースされたが、実際はフレンドシップというバンド名義の作品なのである。グルーシンのこのアルバムでの立ち位置は、いわばリトナーのプロジェクトにおけるコラボレーターといったところなのだろうが、コンテンツ的にはさながら彼がリーダーのような印象を与える。そこにはリトナーの従来のアルバムにはない、トランスアトランティックなジャズ・ファンクといった味わいがあるのだ。
おなじころグルーシンは非常に短い期間だが、キッチンというブラジリアン・ファンク・バンドでも活動した。このグループでは、実際に彼がリーダーを務めた。キッチンはいかにもグルーシンのプロジェクトらしく、ジ・アメリカン・ブリードやルーファスのメンバーだったアル・シナー(g)をはじめ、オクタヴィオ・ベイリー Jr.(b)、クラウディオ・スロン(ds)、パウリーニョ・ダ・コスタ(perc)といったセルジオ・メンデス所縁のミュージシャンで構成されたリズム・セクションに、ソウル系のシンガー、さらにアメリカ西海岸のホーン・プレイヤーが加わった、ハイブリッドなバンドである。そのサウンドといえば、ブラジル音楽とジャズ・ファンクとが融合した、まさしくフュージョンと呼ぶに相応しいものである。
キッチンは1978年にロサンゼルスの中西部サンセット・ブールヴァードにある伝説のクラブ、ロキシー・シアターにおいて、コンサートを行い大好評を博した。さらにこのグループは、シンガーソングライター、キャロル・キングの名作『つづれおり』(1971年)をプロデュースしたことで知られる、ルー・アドラーをエグゼクティヴ・プロデューサーに迎え、A&Mレコードからアルバムをリリースする予定だった。アドラーはロキシー・シアターの共同経営者でもあったのだが、キッチンのパフォーマンスをすっかり気に入ったのだった。しかしながら、アドラーがA&Mからエピック・ソニーへ移籍したため、結局アルバム・リリースは不発に終わった。この稀有なブラジリアン・ファンク・バンドについては、もはやあれこれ想像するばかりである。

ぼくがグルーシンの生演奏をはじめて聴いたのは、1980年3月に開催された“DAVE GRUSIN & THE GRP ALL-STARS with SPECIAL GUEST: SADAO WATANABE”と題された、兄デイヴのジャパン・ツアーにおいて。当時新宿にあった東京厚生年金会館でのライヴに、ぼくは欣々然として足を運んだ。前述のグルーシン/ローゼン・プロダクションは、1978年にアリスタ・レコードと長期開発契約を結んで、GRPレーベルを立ち上げていた。そんなわけでこのツアーのメンバーは、レーベルの所属アーティストで構成されていた。当時グルーシンはフリーランスのミュージシャンだったが、GRPからのアルバム・デビューを目前に控えていたキーボーディスト、バーナード・ライトが体調を崩したため、そのピンチヒッターを務めた。
なおこのツアーのうち、1980年3月16日に行われた大阪市のフェスティバルホールでの公演の模様は、ライヴ・アルバム『デイヴ・グルーシン&GRPオール・スターズ・ライヴ・イン・ジャパン・ウィズ・スペシャル・ゲスト渡辺貞夫』(1980年)として音盤化された。このアルバムには、グルーシンのオリジナル・ナンバー「オッ・オー!」が収録されている。彼のフェンダー・ローズによるリハーモナイゼーションを効かせたダイナミックな即興演奏は、なかなかどうして堂に入ったものである。この曲はもともとグルーシンがアソシエイト・プロデューサーも務めた、リー・リトナーのリーダー作『暗闇へとびだせ』(1979年)に収録されていた曲。この選曲は、まだリーダー作を発表していなかったグルーシンに対する、兄デイヴの配慮によるものだろう。
その翌年タイミングを計ってリリースされたのが、グルーシンの初リーダー作『ドン・グルーシン』だった。本作は日本のJVCレコードによって制作されたが、数々のジャズ/フュージョン作品をプロデュースした田口晃が手がけた1枚である。レコーディングはロサンゼルス郡グレンデール市にある、モントレー・サウンド・スタジオで行われた。エンジニアはグルーシンの作品ではおなじみの、名手ジェフ・ジレットが務めた。パーソネルは、ドン・グルーシン(key, perc, vo)、リー・リトナー(g)、エイブラハム・ラボリエル(b)、アレックス・アクーニャ(ds, perc)、スティーヴ・フォアマン(perc)といった、フレンドシップのメンバーを中心に構成されている。
さらに、オスカー・カストロ・ネヴィス(g)、マイケル・センベロ(g)、ネイザン・イースト(b)、エフライン・トロ(perc)、ゲイリー・ハービッグ(ts)、ケイト・マーコウィッツ(vo)、マイケル・ボディッカー(prog)といった、そうそうたる顔ぶれがサウンドに彩りを添えている。収録曲は全8曲中1曲がカヴァー、残りの7曲はグルーシンによる書き下ろしだ。プロデュースとアレンジはすべて彼が手がけている。グルーシンはオーバーハイム OB-Xを中心に、コルグ ARP 2600、ヴォコーダー、ミニモーグ、ヤマハ GS1といった各種のシンセサイザーを使用。そのハードスキルが活かされた、スペイシーなフュージョン・サウンドがなんとも心地いい。もちろん彼は、アコースティック・ピアノとフェンダー・ローズも弾いている。
アルバムは疾走感溢れる「ナンバー・エイト」からスタート。のちにデイヴ・グルーシン・アンド・ドリーム・オーケストラの『ライヴ・アット・武道館』(1982年)やゲイリー・ハービッグの『アー・ユー・レディ』(1988年)でも採り上げらた。ここではグルーシンが操るシンセ類の温かみのあるテクスチュアが随一。ラボリエルのスラップ・ベース、リトナーのスムースなソロも印象的だ。複数のリズムがクロスする「ホット」は、エスプリの効いた曲調がいかにもグルーシンらしい。ブラジリアンとアフロが交錯するビート感にカラダが揺れる。途中のゴスペル・タッチのピアノ・プレイも軽妙だ。ポリメトリックなイントロと文字どおりシャッフルするリズムが刺激的な「シャッフル・シティ」は、グルーシンの代表曲──。
この曲もやはり『ライヴ・アット・武道館』やギタリスト、ジョー・パスの『カリフォルニア・ブリーズ』(1985年)などでカヴァーされた。ここではハービッグのパッショネートなテナー、リトナーのブルージーなギターがムードを盛り上げる。ボサノヴァとサンバがクロスする「クイダード」では、グルーシンのヴォーカルがフィーチュアされる。作詞はシンガーソングライターのエリック・タッグが手がけている。不意を突くようなコード進行が、サウダージかつアーバンな雰囲気を醸成する。ソリッドなジャズ・ファンク「ナイス・ゴーイング」では、グルーシンの都会的かつ先端的なシンセ・プレイが全開。後半でバトゥカーダ風になるのもクールだ。カントリーとレゲエとのミックス「カウボーイ・レゲエ」は、小気味いいトロピカルなリズムが爽快な曲──。
この曲ではソロをとるOB-Xも然ることながら、バックで使用されているGS1がフレッシュな効果を上げている。そのリズミカルでイリュージョナルなサウンドには、印象に残る鮮やかさがある。ゆったりしたテンポの「コナ」では、リラックスしたムードのなかにもファンキーなテイストが滲む。転調が上手く使われ、清々しさと切なさが交じり合うところは、いかにもグルーシンの曲らしい。テナーとローズとがほどよくコクのあるソロを展開する。ラストの「星の界」は、チャールズ・クローザット・コンヴァースが作曲した有名な賛美歌がアレンジされたもの。アーシーなリフとおおらかな8分の6拍子とがポリメトリックに展開される。テナーとピアノのソロも含めて、アコースティックなリズム・アンド・ブルース調のサウンドに意表を突かれるが、こういうアソビにもグルーシンの音楽家としての懐の深さが感じられる。申し分ない逸品だ。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。









コメント