ジャズ・シーンが誇るピアノのヴィルトゥオーソ、デイヴ・マッケンナによるピアノ・トリオの名盤『ザ・ピアノ・シーン・オブ・デイヴ・マッケンナ』
 Album : Dave McKenna / The Piano Scene Of Dave McKenna (1959)
Album : Dave McKenna / The Piano Scene Of Dave McKenna (1959)
Today’s Tune : Along With Me
ソロ演奏が得意な超絶技巧派──ピアノのヴィルトゥオーソ
新田真剣佑という若手俳優がいる。末次由紀の人気コミックを原作とする実写映画『ちはやふる -上の句- / -下の句-』(2016年)で綿谷新を演じて、第40回日本アカデミー賞の新人俳優賞を受賞した。ぼくは『ちはやふる -結び-』(2018年) とあわせて観たけれど、本来の自分のキャラクターとは異なる性格の役柄を見事に演じ切っていたように思う。確か最初は(姓はなく)真剣佑という芸名だったと記憶する。この映画シリーズでも3作目にして、はじめて新田真剣佑とクレジットされた。この映画シリーズの役名にちなんだ改名であることは、容易に想像がつく。下のほうの真剣佑は本名ということだが、きわめて珍しい響きをもった名前だ。彼は日本とアメリカとの二重国籍の持ち主だが、あちらでは“Mackenyu”という綴りになるとのこと。
新田さんのお父さんは、日本だけでなく海外でも“Sonny Chiba”として活躍した(敢えてそう記載するが)アクション俳優の千葉真一。個人的にはテレビドラマの『キイハンター』(1968年 – 1973年)の風間洋介役が、もっとも印象に残っている。とぼけた性格と、敏捷性と柔軟性を兼ね備えたアクションとのコントラストが、子どものぼくにはとても魅力的に映った。それはともかく、千葉さんはワールドワイドに活躍するひとだったから、もしかすると自分の子どもに世界で通用するような名前をつけたのかもしれない。千葉さんの次男で新田さんにとっては弟にあたる、俳優の眞栄田郷敦もアメリカ国籍をもち向こうでの名前の表記は“Gordon”となる。ふたりとも文武両道でスケールの大きさを感じさせるが、これからの活躍に期待したい。
さて、ここまではまったくのマエフリ。勝手に引き合いに出させていただいた新田さんとそのファミリーには、恐縮するばかりだ。ただ以下に述べることは、ほかのひとにとってはへそで茶を沸かすようなハナシに思えるかもしれないけれど、ぼくにとっては自分でも呆れるほど大マジメなほんとうの出来事。というのもぼくは、新田さんの名前を耳にするとその度ごとに、あるジャズ・ピアニストのことを思い出してしまうのだ。賢明な読者諸兄姉はすでにお気付きのことと思うが、そのピアニストとはずばりデイヴ・マッケンナ(1930年5月30日 – 2008年10月18日)だ。いかにも笑止千万と、軽蔑されても致しかたない。でも繰り返すけれど、これはウソ偽りのないハナシ。
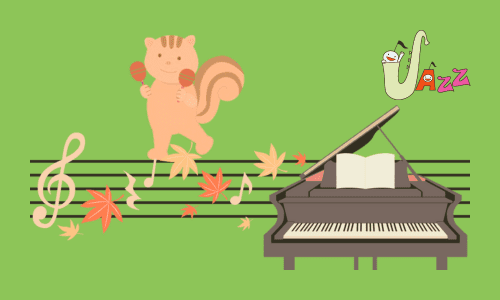
あらためて説明するのも憚られるが、それは“マッケンユウ”から“マッケンナ”を連想するという、駄洒落にもならない所以である。では、“マツケン”からは思い出されないのか?“マツケン”といえば、ええと暴れん坊将軍──ではなかった、松平健だろう。いやいや、まったく思い出さない。それなら松山ケンイチではどうだ?NO!さすがに“マツケン”と“マッケンナ”とに、雲を見て綿菓子を思い浮かべるような類似性はないだろう。というか、そもそも“マツケン”は発音が詰まっていない。“マッケンユウ”と“マッケンナ”とで類似する点で重要なのは、なんといっても促音なのだ。と、そんなことはどうでもいい。ちなみに弟の眞栄田さんからは、テナー奏者のデクスター・ゴードンがイメージされる──わけがない。実にくだらない。
ぼくの場合、こういうたわいない冗談を云っているときは、たいがい疲れているとき。このところ仕事のほうが立て込んでいて、ちょっと心身が弱っているものだから、逆に感情が高ぶってしまうのだろう。深くお詫び申し上げるとともに、気を取り直して以下は音楽のハナシに集中する。くだんのデイヴ・マッケンナだが、彼のレコードがぼくの自室のターンテーブルにのる機会は極めて少ない。というかぼくは、あまり彼の作品を所持していない。理由はマッケンナのリーダー・アルバムといえば、ソロ・ピアノ作品が多いからだ。ソロ演奏が得意というのは、彼がピアノのヴィルトゥオーソであるということを意味する。マッケンナのジャズ・ピアノの格別なテクニックとアビリティは、達人の域に達するものと云える。
しかしながらリスナーの立場からすると、完璧な演奏技巧や卓越した演奏能力と向き合うとき、ソロ・ピアノという演奏形態は思いのほかしんどいと感じられるのではないだろうか。少なくともぼくには、ある種のストレスを感じることがままある。それはぼくが幼いころから20代までピアノのレッスンを受けていたからかもしれないが、ピアノの演奏が華麗な超絶技巧であればあるほど、強い緊張感を覚えるのである。あたりまえのことだけれど、ソロ・パフォーマンスという形態では、聴き手の意識はひとつの楽器に集中するしかない。つまり、耳を逃す場所がないというわけだ。これがピアノ・トリオだったら、ちょっと疲れたときにベースやドラムスに意識を傾けることができるのだけれど──。
ソロ・ピアノでもひとえに音楽性の深みや解釈の秀逸さをたのみとするようなプレイだったら、リラックスして楽しむことができるのだけれど、トリオやコンボ・スタイルにくらべたら、それなりのコンセントレーションを要する。マッケンナの場合、ときにスリーハンド・エフェクトという独特のテクニックを繰り出したりもする。それはメロディを中音域に設定し、高音域にハーモニー、低音域にリズムをともなう手法。当然ピアニストには手は2本しかないのだけれど、あたかも3本の手を使って演奏しているかのような印象を与える弾きかただ。このスリーハンデッド・スウィング・スタイルは、ジャズ・ピアノの発展において重要とされているが、その点でもマッケンナは超絶技巧派と観られている。
モダンでスウィンギーなスタイル──アカンパニストとしても有能
そんなわけでぼくの場合、デイヴ・マッケンナのピアノ・プレイを聴く機会は自ずと少なくなっていった。ぼくがマッケンナの演奏をはじめて聴いたのは1990年代に入ってからだったけれど、そのころの彼は日本でもなかなかの人気者だったと記憶する。当時のマッケンナは、ジャズ・フェスティヴァルでおなじみのカリフォルニアのレーベル、コンコード・ジャズのアーティストとして大活躍していたし、ザ・コンコード・オールスターズのメンバーでもあった。おそらく何度も来日していたから、ファンも多かったのだろう。そんなに評判の高いピアニストなら、一度は聴いてみなければと思い、マッケンナのレコードを手にした。それは中古レコード店で見つけた、ABCパラマウント・レコードからリリースされた『ソロ・ピアノ』(1956年)の日本コロムビア盤。気楽に彼のピアニズムを楽しむことができる好盤だった。
あとで知ったのだが、そのアルバムは偶然にもマッケンナの初リーダー作だった。彼のプレイはまごうかたなきヴィルトゥオーソのものではあるが、聴くぶんには決して小難しいものではない。実際マッケンナには、自分はジャズ・ミュージシャンではなくサロンのピアニスト──という発言がある。彼は激しい即興演奏よりも、楽曲のメロディを尊重して演奏することに重点を置いているというのである。確かにマッケンナのようなハートウォーミングなプレイをする超絶技巧派は、なかなかいない。ただマッケンナにとってソロ・ピアノはライフ・ワークなのだろうけれど、前述のような理由からぼくにはソロ・ピアノを忌み嫌うような傾向があるから、彼の作品をまえにするとついつい及び腰になってしまうのである。
ちなみに、ビル・エヴァンスが世を去ったあと、彼のマネージャーを長年務めたヘレン・キーンと評論家のハーブ・ウォンのプロデュースで『スペシャル・トリビュート・トゥ・ビル・エヴァンス』(1983年)という2枚組のアルバムがリリースされた。生前エヴァンスが敬意を払っていたひと、こころにかけていたひと、そしてプライヴェートで親しくしていたひと──といった14人のピアニストが、エヴァンスゆかりのナンバーをひとり1曲ずつソロ・ピアノで演奏している。そのなかでマッケンナはジョニー・マンデルの名曲「エミリー」において、温もり感に溢れたオーソドックスなバラード・プレイを披露している。これを聴くと、さきに挙げた彼の発言が思い出されるが、そのピアニズムがエヴァンスのそれとはまったく違うものであることもわかる。

マッケンナは、本人の弁によるとアート・テイタム、テディ・ウィルソン、ナット・キング・コールから影響を受けたということだが、スウィング・ジャズのイディオムとハード・バップのモダンなフィーリングとをもちあわせた、いわゆる中間派に属するピアニストということになるのだろう。そんななかでも彼は、鍵盤を縦横無尽に駆け巡る驚異的なテクニックと洗練されたエレガントなスタイルにおいて随一と云える。そんな素晴らしいプレイヤーでありながら、ぼくは彼のピアノを聴く機会をことごとく逸しているのである。サイドメンとしては、トランペッターのボビー・ハケットやドラマーのバディ・リッチのアルバムにマッケンナのクレジットを見出すこともできるが、愛聴盤というほどのものがない。
唯一頻繁にターンテーブルにのるのは、テナー奏者のズート・シムズのワンホーン作品『ダウン・ホーム』(1960年)くらいのものだが、これはスゴくいい。もともとぼくにとってシムズは、ウェストコーストのサクソフォニストのなかでもとりわけ好きなプレイヤー。本盤はワンホーンものということで、そのソフトでスムースなトーンにより愛着が湧く。そして、シムズの歌ごころに溢れたフレージングも然ることながら、マッケンナの実に心地いいモダンなスタイルとスウィンギーなプレイもまた情緒豊かである。それ以外だと個人的には、女優としても活躍したシンガー、ローズマリー・クルーニーのアルバム『ハロルド・アーレン作曲集』(1983年)が愛聴盤となっているが、この作品でもマッケンナのピアノ演奏を聴くことができる。
これは余談だが、クルーニーはあの俳優のジョージ・クルーニーの叔母さん。確かに彼の顔立ちには、あのとびきり美人の面影があるように感じられる。まあその美貌はともかく、クルーニーの中音域というか女性としてはやや低めの声域となる声色が、なんとも魅力的だ。とはいってもあまり性的な魅力を感じさせることはなく、エレガントでアーバンな雰囲気を醸し出すところが、ぼくは昔から好きだ。アーレンのソングブックはコンコード・ジャズ時代のアルバムだが、当時のクルーニーの吹き込みではおなじみのギタリスト、エド・ビッカートが中心となっている。ところがピアノは、ナット・ピアースでもなくジョン・オッドでもなくマッケンナが務めた。彼はここでアカンパニストとしても有能の士であることを証明している。
これらの2枚を楽しんだあと、ややもすると「たまにはマッケンナのアルバムを聴いてみようかな」と、ぼくは思うのであった。そんなきっかけがなければ、マッケンナのレコードを棚から引っ張り出すことがないのだから、とりもなおさず長い間ぼくにとって彼はその程度のピアニストだったというわけだ。ところが最初に述べたとおり、ここ10年くらいは“マッケンユウ”という響きを耳にする度ごとにマッケンナのことを連想してしまうので、自ずと彼のリーダー作を手にとる機会が増えた。またまた繰り返すけれど、これはウソ偽りのないハナシ。そして遅ればせながら、ぼくはマッケンナが実はジャズ・シーンにおいて類まれなるピアニストであると感じるようになったのである。あらためて、新田さんに感謝したい(感謝されても戸惑うだろうけれど──)。
ただ、いざマッケンナのリーダー作を聴こうとすると、まえに述べたような理由からついついソロ・ピアノ作品を敬遠してしまう。マッケンナはバンド演奏と同等のサウンドをピアノ一台で表現することができるひとだけれど、まったく甲斐性のないことに、ぼくは気楽に身を委ねることができるピアノ・トリオ作品ばかりに手を出すのであった。然りとて、彼のピアノ・トリオ作品といえば、選択の余地がない。マッケンナのピアノ+ベース+ドラムスという編成での吹き込みといえば、はっきり云って、前述の『ソロ・ピアノ』につづくセカンド・アルバム『ザ・ピアノ・シーン・オブ・デイヴ・マッケンナ』(1959年)にとどめを刺すような印象が強い。彼にとっては、エピック・レコードからリリースされた唯一の作品でもある。
28歳の明朗快活なピアニストによるアクティヴなエクスプレッション
念のために付言しておくと、ポートレイト・マスターズというレーベルから『ディス・イズ・ザ・モーメント』(1988年)というCDがリリースされているけれど、これは音楽プロデューサーであるボブ・シールが監修を務めた、エピック、ブランズウィック、ヴォカリオンといったレーベルのリイシュー・シリーズのなかの1枚。エピック盤の『ザ・ピアノ・シーン・オブ・デイヴ・マッケンナ』と同一の内容なのでご注意を──。ほかにマッケンナの(ドラムレスやベースレスの異色のトリオ編成を除く)ピアノ・トリオ作品といえば、コンコード・ジャズ時代の吹き込みで、ボブ・メイズ(b)とジェイク・ハナ(ds)をサイドに迎えた『プレイズ・ザ・ミュージック・オブ・ハリー・ウォーレン』(1982年)くらいしか、ぼくは聴いたことがない。
ではエピック盤とコンコード盤とでは、どちらが好みかといえば、圧倒的にエピック盤のほうが、ぼくは好きだ。決してコンコード時代のマッケンナが悪いというわけではない。円熟味が増したピアノ・プレイには、味わい深いものがある。前述のように、マッケンナの日本での人気もこのころからにわかにはね上がったような印象があるから、コンコード時代は彼にとって第2の黄金期と云えるのかもしれない。それに対してエピック盤でのマッケンナは、28歳の明朗快活なピアニスト。アドリブ・ソロにおける滑舌のいい語り口には、度量の大きささえ感じられる。しかもそのアクティヴなエクスプレッションは得も云われぬ潤いに満ちていて、トータル的なサウンドの爽快感は格別だ。さらに云えば、レコーディングの音質もすこぶるいい。
したがってマッケンナといえば、ぼくはまず『ザ・ピアノ・シーン・オブ・デイヴ・マッケンナ』を手にとるのである。ここでこの名盤をものするまでのマッケンナについて、簡単に記述しておく。デイヴ・マッケンナはロードアイランド州ウーンソケット市の、ある音楽好きの家庭に生まれた。郵便局員だった父親は趣味でドラムスを叩き、母親はピアノとヴァイオリンを演奏したという。幼いころから母親の手ほどきでピアノを弾いていた彼は、15歳にして早々と初舞台を踏む。マサチューセッツ州ボストン市に移り、ピアニストでアレンジャーのプレストン・サンディフォードに師事したあと、17歳までの2年間アルト奏者のブーツ・ムッスリのバンドでピアニストとして活躍したのである。
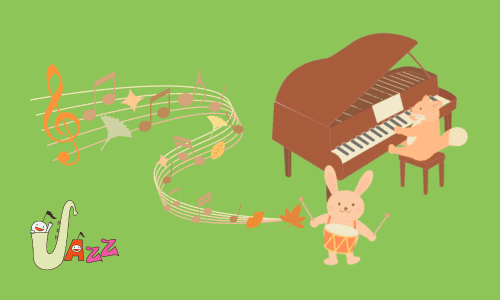
その2年後マッケンナは、テナー奏者のチャーリー・ヴェンチュラのバンドで、さらにその1年後にはクラリネットとサックスをプレイするウディ・ハーマンのビッグバンドで、それぞれ演奏した。1951年から1953年までは朝鮮戦争において兵役に就くが、除隊後はヴェンチュラのバンドに復帰。おなじころ短期間だが、テナー奏者のスタン・ゲッツとも共演している。1955年には前述の初リーダー作『ソロ・ピアノ』のレコーディングを行い、3年後の1958年7月22日と23日にニューヨーク市のコロムビア30丁目スタジオにて『ザ・ピアノ・シーン・オブ・デイヴ・マッケンナ』を吹き込む。サイドにはジョン・ドリュー(b)とオシー・ジョンソン(ds)が迎えられた。では以下は、本盤を具体的に観ていくことにする。
ふたりのサイドメンは、本作では短めのソロも披露するが基本的にはリズム・キープに徹している。その律動が非常にタイトで、マッケンナの機敏な指の動きとよくマッチしている。ベーシストのドリューはイングランド中部シェフィールド市の出身で、渡米してからはドラマーのジーン・クルーパやピアニストのバーバラ・キャロルのバンドで活躍した。吹き込み当時31歳だった彼は、実に的確で安定感のあるプレイを見せている。かたやドラマーのジョンソンはワシントンD.C.の出身で、アレンジャー、シンガーとしても才能を発揮したひと。この吹き込みの直前に、セロニアス・モンク(p)、アーマッド・アブドゥル・マリク(b)とともに、CBSのテレビ番組『ザ・サウンド・オブ・ジャズ』に出演。当時35歳の彼は、本作でブラシ・ワークにおける名人上手の至芸を見せている。
アップテンポのオープナー「ディス・イズ・ザ・モーメント」はドイツの作曲家フリードリヒ・ホレンダーによる映画主題歌。モダンなイントロ、ピアノの高速パッセージ、力強い4バースが素晴らしい。コール・ポーターの「シルク・ストッキングス」はメランコリーなムードでスリーハンデッド・スウィング・スタイルが展開される名演。ターナー・レイトンのミュージカル・ナンバー「遥かなるニューオーリンズ」では行雲流水のごときピアノがチャールストン風になっていくのが楽しい。ルーブ・ブルームのラヴ・バラード「フールズ・ラッシュ・イン」ではピアノがメロディからアドリブまでロマンティックに歌い上げる。トロンボニスト、ベニー・グリーンの「エクスペンス・アカウント」では機知に富んだワイドレンジのピアニズムが小粋だ。
アーヴィング・バーリンのミュージカル曲「レイジー」では原曲のメロディが尊重され淡々とリラックスしたピアノ・プレイが展開される。後半のさり気ない転調も好感がもてる。レコードではここからがB面で、マッケンナのオリジナル「スプレンディド・スプリンター」ではベースのランニングやピアノとドラムスとのソロ交換と、シトラスのようにハード・バップが香りたつ。つづくマッケンナの自作「リケティ・スプリット」では前曲のパターンが超高速で繰り返される。ピアノの粒だちの良さが驚異的だ。ハロルド・ロームの「アロング・ウィズ・ミー」では4ビートにルンバが交じったようなリズムが心地いい。まどろみを誘うような抑制のきいた演奏は、ぼくの好みだったりする。サミー・フェインの「シークレット・ラヴ」はモダニズム溢れるピアノ・トリオの好演。軽くスウィングするところが都会的だ。
ジョンソンのオリジナル「ダダダ・ゴー・ディグ・イット 」では12小節のブルース形式の曲だけにピアノもベースもアルバム中もっともブルージー。ドラムスのポリリズムもアクセントになっている、楽しいトラックだ。ラストのアクセル・ストーダルとポール・ウェストンとによる有名な「アイ・シュッド・ケア」ではマッケンナがゆったりしたテンポに身を委ねながら、一聴華やかさはないが実に奥行きのあるピアノ・プレイを展開。ため息の出るようなモジュレーションも、そこはかとない感動を呼ぶ。ジャズ・シーンではピアノ曲として人気の高いナンバーだが、ぼくはこの演奏が飛び抜けて好き。こうして緩急を交えてプレイされた12曲を聴くと、あらためて本作がピアノ・トリオの名盤であると気づかされる。素直にマッケンナに謝りたい気分になる。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。








コメント