フュージョン史に残る傑作、デイヴ・グルーシンの『マウンテン・ダンス』
 Album : Dave Grusin / Mountain Dance (1980)
Album : Dave Grusin / Mountain Dance (1980)
Today’s Tune : Rag Bag
ジャズ・ピアニストとしてスタート、やがてアレンジャーに転身
べつに満を持してというわけでもないのだが、デイヴ・グルーシンの『マウンテン・ダンス』(1980年)についてお伝えする。云わずと知れたフュージョン史に残る傑作である。繰り返すが、ぼくはこの作品を採り上げるのに、好機を窺っていたわけでもないし、執筆の準備を整えていたわけでもない。本作をもう40年以上も愛聴してきたのだから、弓をたっぷり引きしぼったまま、じっと構える必要もないのだ。ただ正直に云うと、遅かれ早かれこの作品について語らなければならないという使命感に駆られるいっぽうで、下手なことは云えないというプレッシャーのようなものも感じていた。そういう思いから、遅疑逡巡していまに至ってしまった。まったくもって、不甲斐ないものである。
それでも、かつてわが国においても多くのリスナーから愛されたこの傑出した作品が、時間の経過とともに忘れ去られていくのを見過ごすわけにはいかない。刹那的な音楽が流布する日本のミュージック・シーンの現況を鑑みると、なおさらそういう思いが強くなってくる。フュージョン・フリークにかぎらずインストゥルメンタルの愛好家のあいだで定番中の定番だった『マウンテン・ダンス』の音盤が、手軽に入手できなくなっている昨今、そこに収められたときを経ても色褪せることのない音楽を、今回ぼくは自信をもってお薦めしようと思った次第である。いささか前置きが長くなったが、では早速、この作品がリリースされた1980年に遡ってハナシを進めるとしよう。
この『マウンテン・ダンス』はデイヴ・グルーシンにとって、6枚目のスタジオ・アルバムに当たる。それまでにグルーシンが発表したリーダー作は『サブウェイズ・アー・フォー・スリーピング』(1962年)『ピアノ・ストリングス・アンド・ムーンライト』(1962年)『カレイドスコープ』(1965年)『ディスカヴァード・アゲイン!』(1976年)『ワン・オブ・ア・カインド』(1978年)となる。なお『ワン・オブ・ア・カインド』は発売当初『ジェントル・サウンド』という邦題が付されていた。またヴァーサタイル・レコードからグルーシン名義の『ドント・タッチ』(1977年)というアルバムがリリースされているが、これはある種のブートレグである。
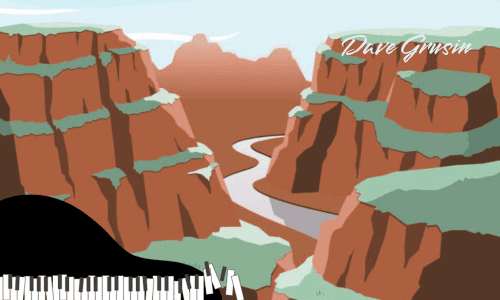
気になる向きもあるだろうから一応触れておくと、実はこのアルバムは著作権者に無断で発売されたものだ。グルーシンのスウィンギーなトリオ演奏を聴くことができるのだが、その音源は1960年代にエピック・レコードにおいて吹き込まれたマスターテープが黙ってもち出されたもの。グルーシンの自作曲や有名なジャズ・スタンダーズの扱いにおいても、曲名や作曲者名が架空のものに変更されていて、本盤の製造販売には明らかに恣意的なものが感じられる。ただこの音盤、一部ピッチがフラットする箇所があるものの比較的音質はよく、おまけにグルーシンのプレイが正規のエピック盤よりも力強く鮮やかに聴こえるから、まったく厄介なシロモノである。皮肉なことに『ドント・タッチ』は、彼が優れたジャズ・ピアニストであることを証明する1枚と云える。
では正規のエピック盤とはなにを指すのかというと、それは『サブウェイズ・アー・フォー・スリーピング』と『ピアノ・ストリングス・アンド・ムーンライト』の2枚。ともにピアノ・トリオでの吹き込みだが、前者はグルーシンのデビュー作。ジュール・スタインが音楽を手がけた、1961年の同名ブロードウェイ作品のジャズ・ヴァージョンだ。後者はグルーシンのオリジナル曲を含む、珠玉のスタンダード集。トリオにストリング・オーケストラが加えられた、カクテル・ピアノ風の作品である。以上のアルバムからもわかるように、グルーシンはそのキャリアをジャズ・ピアニストとしてスタートさせたひとなのだ。つづいてコロムビア・レコードからリリースされた『カレイドスコープ』では、クインテットでの彼のポスト・バップ然としたプレイも聴ける。
この『カレイドスコープ』でドラムスを叩いていたのが、のちにグルーシンとGRPレコードを設立することになるラリー・ローゼン。グルーシンは1963年から1966年まで、テレビの音楽番組『アンディ・ウィリアムス・ショー』において、ミュージカル・ディレクターを務めていたが、ローゼンもまたウィリアムスのバンド・メンバーだった。その後グルーシンは、ジャズ・ピアニストからアレンジャーに転身。1967年からはブラジル出身の音楽家、セルジオ・メンデスのオーケストレーションを担当するようになる。またグルーシンが、彼のもうひとつの側面である映画音楽の作曲家として活動しはじめたのもこのころのこと。バド・ヨーキン監督のコメディ映画『ディヴォース・アメリカン・スタイル』(1967年)が、その記念すべき第1作である。
さらにグルーシンは、1973年からメンデスのレコーディングと並行して、クインシー・ジョーンズの片腕としても働くようになる。かたやブラジリアン・ミュージック、かたやソウル・ミュージックと、彼のヴァーサティリティに富んだ音楽性の一端は、これらの経験によって培われたものと観ていい。シドニー・ポラック監督のサスペンス映画『コンドル』(1975年)のフィルム・スコアにおいて、グルーシンが披露したコンテンポラリー・ジャズのマナーは、そういったミュージカリティが結実したものだ。そして、この時期にカリフォルニアのダイレクト・トゥ・ディスク専門レーベル、シェフィールド・ラボからリリースされたのが『ディスカヴァード・アゲイン!』だった。ある意味で、のちのフュージョン・ミュージックの指針となったアルバムである。
ちなみにダイレクト・トゥ・ディスクというのは、ダイレクト・カッティングという手法で製作されたアナログ・ディスクのこと。レコーディングの際、音声信号が直接カッティング・マシンに入力され、同時にラッカー盤に溝が刻まれるというものだ。音質が格段によくなるというメリットも然ることながら、レコード片面とおしの手に汗握る演奏が生む臨場感が、なにものにも代えがたい。この作品の影響から、フュージョンの歴史的名盤、リー・リトナー&ヒズ・ジェントル・ソウツの『ジェントル・ソウツ』(1977年)が生まれたと云っても過言ではないだろう。スタジオ・レコーディングにライヴ感を与えるというマナーは、ダイレクト・トゥ・ディスクではないが『マウンテン・ダンス』のそれと共通する。
日本での人気が高まる、絶妙のタイミングでリリースされたアルバム
この『ディスカヴァード・アゲイン!』が吹き込まれたころ、グルーシンはローゼンとともに原盤制作会社、グルーシン/ローゼン・プロダクションを発足させている。このプロダクションは様々なレーベルにおいて、アール・クルー(g)、ノエル・ポインター(vln)、パティ・オースティン(vo)、リー・リトナー(g)、それに横倉裕(key)といった、フレッシュなアーティストたちのユニークなアルバムを制作するが、グルーシンの『ワン・オブ・ア・カインド』もまたそれらに連なる作品である。このアルバムは当初ポリドール・レコードからリリースされたのだけれど、契約上の理由で1年足らずで廃盤となった。のちにGRPレコードから装いも新たにリイシュー盤が発売されるが、それまで多くのファンが7年ほど待たなければならなかった。
幸いなことに、ぼくは廃盤になるまえに『ワン・オブ・ア・カインド』の国内盤を入手していたが、数あるフュージョン作品のなかでも、個人的にはバイブルのようなものとなった。なぜならこのアルバムには、キーボード・ワーク、ソングライティング、フィルム・スコアのマナー、そしてアレンジメントと、グルーシン・サウンドを特徴づけるファクターのほとんどが収められているからだ。グルーシンはぼくがもっとも敬愛する音楽家のひとりだけれど、彼の膨大な作品群のなかでもこのアルバムには学ぶべきことが満載だったのである。いずれにしても、当時このレコードを血眼になって探す向きが多かったことからも、すでにグルーシンの音楽が日本でも人気を集めていたことがわかる。
グルーシンが日本で広く知られるようになったキッカケは、なんといっても渡辺貞夫とのコラボレーションだろう。渡辺さんは云うまでもなく日本を代表するアルト奏者であり、世界を股にかけて活躍するジャズ・プレイヤー。現在も“ナベサダ”の愛称で広く親しまれ、わが国においては紫綬褒章まで授与されるほどの国民的音楽家だ。グルーシンは、渡辺さんのリーダー作『マイ・ディア・ライフ』(1977年)にキーボーディストとしてはじめて参加し、つづく『カリフォルニア・シャワー』(1978年)『モーニング・アイランド』(1979年)といった作品では、プレイヤーのみにとどまらず、コンポーザー、アレンジャーとしてもかつてない成果を上げた。ナベサダ・フュージョンのサウンドをスウィートなものにしていたのは、グルーシンなのである。

グルーシンと渡辺さんとは莫逆の友ともいえる仲となり、その後も何度となく共演を果たす。その親密な間柄は、ヤマハのスクーター、ベルーガのテレビCMにふたりが揃って出演していたことから、ご存知のかたも多いと思われる。そんなCMが制作されるくらいだから、グルーシンのわが国での知名度の高さも相当なものだったのだろう。そして、このグルーシンと渡辺さんとの迷コンビネーション(?)が発揮された、ユーモアセンスのあるCMがお茶の間を賑わす1年ほどまえのこと──。絶妙のタイミングでリリースされたのが、ほかでもない『マウンテン・ダンス』だ。1980年3月開催の“DAVE GRUSIN & THE GRP ALL-STARS with SPECIAL GUEST: SADAO WATANABE”と題されたジャパン・ツアーにおける、グルーシンの来日記念盤でもある。
このツアーのうち1980年3月16日に行われた大阪市のフェスティバルホールでの公演の模様は、ライヴ・アルバム『デイヴ・グルーシン&GRPオール・スターズ・ライヴ・イン・ジャパン・ウィズ・スペシャル・ゲスト渡辺貞夫』(1980年)として音盤化された。この日の公演ではツアー・メンバーのリズム・セクション9名に、弦楽器21名、管楽器7名、打楽器1名から成るオーケストラが加えられ、コンサートは1日かぎりの豪華な催しとなった。東京在住のぼくは、当時新宿にあった東京厚生年金会館でのライヴに足を運んだのだけれど、大阪公演を体験したひとたちをたいそう羨ましく思ったもの。ただこの公演は、もともとは朝日放送開局30周年を記念するものだったので、のちにその模様の一部はテレビ朝日で放送された。
いささか余談になるが、あまり語られていないようなのでもう少しこのライヴ・アルバムに付言しておく。このレコードはもともと日本ビクターのグローバルブランドであるJVCレーベルから発売されたものだが、アメリカでは音楽プロデューサーのクライヴ・デイヴィスが当時主宰していたアリスタ・レコードからリリースされた。1978年にグルーシン/ローゼン・プロダクションがアリスタと長期開発契約を結んでいたからである。ただこのアリスタ/GRP盤、ジャケットや曲順に変更があるのはいいにしても、コレクターズアイテム『ワン・オブ・ア・カインド』に収録されていたグルーシンの代表曲である「モダージ」が、3分近くもカットされているのはいただけない。その点でぼくは、圧倒的にオリジナルのJVC盤をお薦めする。
ときに『マウンテン・ダンス』だが、こちらもJVCレーベルからリリースされたものがオリジナル盤。アメリカで発売されたアリスタ/GRP盤は、実は後発品なのである。これは好みの問題になるけれど、ぼくは圧倒的にゲートフォールド仕様のJVC盤が好きだ。ジャケットのグルーシンの顔写真が中心に据えられたグラフィックデザインが、シンプルだがアルバムの洗練されたコンテンツにとてもマッチしているように思われる。実際に音に触れるまえに、あたかも『ワン・オブ・ア・カインド』のポリドール盤のアートワークが承継されたかのようなこのジャケットに、ぼくは胸を躍らせたもの。ちなみに、グルーシンの写真はリプレスの際に変更されたが、ぼくは知性が宿るグルーシンの双眸が魅力的なファースト・プレスの写真のほうが好みだったりする。
それにくらべてアリスタ/GRP盤のジャケットは、ちょっと苦手。一時期ファッショナブルな出で立ちのアーティストの写真があしらわれたジャケットが、GRP作品のトレードマークとなっていたけれど、ご多分に漏れずこのグルーシンのアルバムもまたその流れを汲むもの。テンガロンハットをかぶったカウボーイ然としたウェスタン・ファッションのグルーシンは、観かたによっては洒落っ気があると云えるのかもしれないが、ハッキリ云って『マウンテン・ダンス』のサウンド・イメージにはまったくそぐわない。確かにグルーシンの故郷であるコロラド州リトルトンのカウボーイ・カルチャーを想起させるものではあるものの、ぼくは本作を聴いているとき、どちらかというと摩天楼の群れが広がるニューヨーク市マンハッタンの風景を思い描くのである。
ライヴ感が増す2トラック・デジタル・レコーディング方式を採用
グルーシンといえば、それまでの活動エリアからなんとなく西海岸のミュージシャンという印象があるけれど、このときはすでにグルーシン/ローゼン・プロダクションのオフィスをマンハッタン区ミッドタウン57丁目に構えていたわけで、その音楽制作の拠点はニューヨークだった。この『マウンテン・ダンス』の吹き込みもまた、当時マンハッタンのミッドタウンにあったA&Rレコーディング・スタジオにおいて行われた。レコーディングの期間は、1979年の12月10日から12月17日まで。ニューヨークでは、平均気温が0度前後となるほどの寒さの厳しいシーズンだけれど、ぼくのなかでは、この作品のキリッと引き締まったサウンドと都会の凍てつく寒さとがオーヴァーラップするのである。
アルバムのプロデューサーはトシ遠藤。リー・リトナーの一連のJVC作品、ヤマハが製造する楽器のデモンストレーションの一環として、リトナーのグループによって吹き込まれたダイレクト・トゥ・ディスク『セッション II』(1979年)、やはりダイレクト・カッティングでレコーディングされた、ジョー・サンプル(p)、レイ・ブラウン(b)、シェリー・マン(ds)によるイースト・ウィンド盤『ザ・スリー』(1978年)などを手がけたひとだ。レコーディング・エンジニアはラリー・ローゼンが務めているが、彼は本作の録音において2トラック・デジタル・レコーディング方式を採用している。マルチトラック・レコーダーを使用したレコーディングとは異なり、オーヴァー・ダビングは一切ない。
ローゼンにとってこの『マウンテン・ダンス』は、はじめてのデジタル・レコーディング・アルバムになるわけだが、1982年にアリスタ・レコードから離れGRPレコードを設立したあとも、彼はデジタル・レコーディングに情熱を注ぎつづけた。その熱意はGRPレコードの企業理念へと昇華され、アナログレコードからコンパクトディスクへの移行に関しても、このレコード会社はアメリカにおいて先駆的存在として注目を集めた。それはともかく『マウンテン・ダンス』において、ローゼンのエンジニアリングが生み出したソリッドかつウォームハーテッドなサウンドは、グルーシンの音楽に独特の風合いを与えている。ぼくにはその質感が、実にヒューメインなものに感じられるのである。

レコーディング・メンバーは以下のとおり。デイヴ・グルーシン(p, elp, synth)、ジェフ・ミロノフ(g)、マーカス・ミラー(b)、ハーヴィー・メイソン(ds)、ルーベンス・バッシーニ(perc)、イアン・アンダーウッド(synth)、エドワード・ウォルシュ(synth)と、L.A. フュージョンのトップ・ドラマーであるメイソン以外は、ニューヨークに活動拠点を置くミュージシャンで固められている。前述のようにオーヴァー・ダブのないレコーディングのため、グルーシンのアルバムにしては珍しく優秀なシンセシストが2名加えられている。アンダーウッドはOBXとプロフェット5でメロディやソロを、ウォルシュはオーバーハイムでハーモニーを、それぞれ受けもっている。なおグルーシンが弾いているシンセサイザーは、ミニモーグである。
特筆すべきは、弱冠にして当時のミュージック・シーンを席巻していた、マーカス・ミラーが参加していること。ロニー・リストン・スミスのアルバムなどでその凄腕を知り、ミラーはぼくにとって当時もっとも気になるベーシストとなっていた。それはそうと、ダビングなしの2トラック・デジタル・レコーディングというスタイルは、演奏にほどよい緊張感と軽快感とを合わせもつスタジオ・ライヴのような趣きを与えている。曲目はグルーシンによる書き下ろしが5曲、セルフカヴァーが1曲、他のアーティストの既存曲のカヴァーが2曲、計8曲となっている。どちらかというとグルーシンのキーボード・ワークに焦点が当てられたアルバムと云えるかもしれないが、そこは彼のリーダー作だからコンポジションやアレンジメントにおいても揺るぎない意匠が凝らされている。
オープニングを飾るグルーシンの「ラグ・バッグ」は、ソリッド感が冴えるハードコアなフュージョン・ナンバー。両手のコンビネーションによるピアノのイントロ、ペンタトニック・スケールが活かされたテーマ、疾風怒濤の展開を見せるコーラス、そしてタメの効いたブルージーなギター・ソロと、構成の妙が際立つパーフェクトな1曲だ。サクソフォニストであるロニー・ロウズが1977年に発表したブルーノート盤のタイトル曲「フレンズ・アンド・ストレンジャーズ」は、原曲のダンサブルでソウルフルなサウンドが、ここではよりシャープでソフィスティケーテッドなものとなっている。小気味いいフェンダー・ローズのアドリブも然ることながら、ベースのフィンガリングによるフィジカルでメロディアスなソロが素晴らしい。なお作曲者は、ドラマーでアレンジャーのウィリアム・ジェフリーである。
グルーシンの「シティ・ナイツ」では、やはり両手のコンビネーションによるピアノのリズム・パターンが飛び出す。これはグルーシンの特徴的なキーボード・ワークのひとつ。わりと簡単に弾けるのだけれど、両手はけっこう忙しい。シンセによるオリエンタルなメロディック・ラインが光るテーマ部から、一気にリズムがトロピカルになるコーラス部へ移行するという展開が、得も言われぬ心地よさを生む。グルーシンの「ロンド…イフ・ユー・ホールド・アウト・ユア・ハンド」は、文字どおりロンド形式が意識された曲。とはいっても曲調は、カリプソのスタイルがとられている。ロンド主題のラインから、グルーシンの温かなひと柄が伝わってくる。中間部のしなやかなスラップ・ベースが、すこぶるクールだ。また途中のソロでスティールパンのような音を出しているのは、グルーシンによるミニモーグである。
グルーシンの「マウンテン・ダンス」は、映画『恋におちて』(1984年)のテーマ曲としても使われた、彼のコンサートでは定番の曲である。メジャーのペンタトニック・スケールを効果的に使ったメロディック・ラインは、フォーキーでクラシカル。こういうジャズっぽくない曲を堂々と書いてしまうところもまた、グルーシンらしい。軽快なドラムスと繊細なパーカッションとが打ち出すビート感、ピアノとOBXとのソロのかけ合いがエキサイティングだ。グルーシンの「サンクソング」は、唯一ソロ・ピアノで演奏される。モーダルな響きとパストラールな音世界は、彼のフィルム・スコアに直結するものである。グルーシンの「キャプテン・カリブ」は、もともとギタリストであるアール・クルーの2枚目のリーダー作『リヴィング・インサイド・ユア・ラヴ』(1976年)のために書かれた曲。前述の『ジェントル・ソウツ』でも採り上げられた人気曲だ。
グルーシンにとってはセルフ・カヴァーとなるこのヴァージョンは、いきなりサビからスタートするところがスタイリッシュ。グルーヴ感もこれまでのヴァージョンより、ぐっと垢抜けている。エスプリの効いたミニモーグによるソロと、ゴスペル・タッチのアコースティック・ピアノによるバッキングと、グルーシンが奔走する。ミロノフのロッキッシュなギター・ソロもキャッチーだ。ラストを飾る「イーザー・ウェイ」は、メイソンの曲。もともとは「フリーダム・イーザー・ウェイ」というヴォーカル・ナンバーで、彼の3枚目のリーダー作『ファンク・イン・ア・メイソン・ジャー』(1977年)に収録されていた。ここでは原曲のファンキー・ムードは影をひそめ、都会の夜をイメージさせる洒落たフュージョン・ナンバーとなっている。ピアノによる中間の流麗なソロ、後半のドラマティックなエクスパンションが感動を呼ぶ。そんな余韻に浸りながら、ぼくは何度となく本作の素晴らしさを実感するのである。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。








コメント