ジャズの伝統を受け継ぎながら守備範囲が広いピアニスト、ジャッキー・バイアードの口当たりのいいアルバム『ハイ・フライ』
 Album : Jaki Byard / Hi-Fly (1962)
Album : Jaki Byard / Hi-Fly (1962)
Today’s Tune : Hi-Fly
ジャズ・ピアノの歴史をひとりで抱え込んでしまったようなピアニスト
レコード・コレクターズ誌の2026年2月号では「この曲のピアノを聴け! ジャズ・フュージョン編」という特集が組まれていたが、そのなかでジャッキー・バイアード(ほんとうは“ジャキ”という表記のほうが実際の発音に近いらしい)のアルバム『ヒアズ・ジャッキー』(1961年)が採り上げられていたのが、個人的には気になった。名門プレスティッジ・レコードのサブレーベル、ニュー・ジャズからリリースされたバイアードのデビュー作。この吹き込みが行われたとき、彼はすでに38歳だった。第二次世界大戦に従軍する以前、16歳のときからジャズ・ピアニストとして食い扶持を稼いでいたというから、ずいぶん遅れてのお披露目ということになる。それ故このデビュー作におけるバイアードは、なかなか貫禄のあるプレイを披露している。
ちなみに、バイアードのリーダー作でもっとも早い時期に吹き込まれたアルバムは、おそらくキャンディド・レコードからリリースされたソロ・ピアノ作『ブルース・フォー・スモーク』(1978年)だろう。レコーディングは1960年の12月とされているが、世に出たのは10年以上あとのことだった。ところで『ヒアズ・ジャッキー』のほうだが、ロン・カーター(b)、ロイ・ヘインズ(ds)をサイドメンとして迎えたトリオ作品。ソロ・ピアノでの吹き込みが多いバイアードだけに、トリオ編成のアルバムは珍しくもあり、トリオ好きのぼくにとっても嬉しい1枚である。彼はある意味で、ジャズ・ピアノの歴史をひとりで抱え込んでしまったようなユニークなスタイリストだけれど、どちらかというと地味な存在と云える。
そんなバイアードのプレイが、天下のレコード・コレクターズ誌において、鍵盤がもつ可能性を最大限まで拡張する演奏として注目されたことに、ぼくにはちょっとした驚きと、そのいっぽうですこぶる腑に落ちるところがあった。同誌ではアルバム『ヒアズ・ジャッキー』の冒頭を飾るバイアードのオリジナル曲「シンコ・イ・クアトロ」が採り上げられているが、ラテン・タッチのグルーヴ感が横溢するなかで、ポリメトリックなピアノ・プレイを展開するバイアードは、確かにただならぬ気配を感じさせる。のちにベーシストのチャールズ・ミンガスやマルチリード・プレイヤーのローランド・カークからお呼びがかかるのが、よくわかる。なぜならここでの彼の演奏は、すでにアヴァンギャルドな香りを放っているからだ。
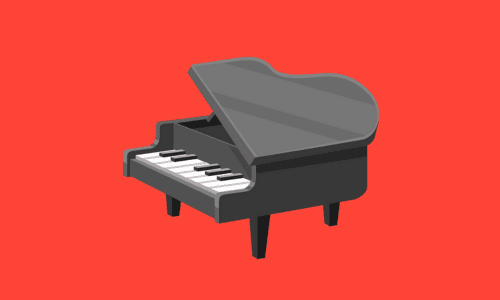
マサチューセッツ州ウースター出身のバイアードは、最初ボストンに演奏活動の拠点を構え、1950年にアルト奏者のチャーリー・マリアーノと共演し、はじめてレコーディングを経験した。その模様はのちに米国のインペリアル・レコードからリリースされたアルバム『チャーリー・マリアーノ・ウィズ・ヒズ・ジャズ・グループ』(1997年)で日の目を見た。バイアードはこの吹き込みに参加していたトランペッター、ハーブ・ポメロイのバンドに1952年から1955年まで参加。さらに1959年から1962年までは、やはりトランペット奏者のメイナード・ファーガソンのバンドに在籍する。彼はこのバンドでピアニスト兼アレンジャーを務めたが、当時からリズム、ハーモニー、そしてインプロヴィゼーションにおいて実験的な嗜好をもっていたため、閉塞感を抱いていた。
そんなバイアードにそのポテンシャルを最大化できる機会を与えたのは、やはりチャールズ・ミンガスだったのではないだろうか。バイアードは1960年にニューヨークに移住し、前述の『ブルース・フォー・スモーク』のレコーディングを行なったが、ちょうどおなじころミンガスとはじめての共演を果たしている。そして1962年から64年にかけて、彼はミンガスと数多くのレコーディングを行った。インパルス!レコードからリリースされた『黒い聖者と罪ある女』(1963年)『ファイヴ・ミンガス』(1964年)といった、ミンガスにとって重要なアルバムにおいてピアニストを務めているのは、ほかでもないバイアード。特に前者では、アヴァンギャルドなプレイが垣間見える。さらに彼は1964年にミンガスのヨーロッパ・ツアーにも同行している。
また、バイアードがこのころ、さきに挙げたローランド・カーク、やはりマルチリード・プレイヤーのエリック・ドルフィー、テナー奏者のブッカー・アーヴィン、おなじくテナー奏者のサム・リヴァースらのレコーディングにサイドマンとして参加したことは、よく知られている。特にドルフィーの『惑星』(1960年)においてのプレイは、彼をモダン・ジャズのピアニストとして最前線に押し上げたとも云える。このドルフィーのアルバムは『ヒアズ・ジャッキー』と同様にニュー・ジャズ・レーベルの1枚だが、彼の初リーダー作に当たる。ドルフィーは本作ですでに、アルト・サックスやフルートとともに、従来クラシック音楽の楽器とされていたバス・クラリネットを使用しているが、のちのジャズ・プレイヤーたちに多大な影響を与えた。
このアルバムを聴くと、ドルフィーがデビュー作からジャズ・シーンにおいて特異なスタイルを、とうに完成させていたことがわかる。その演奏は一般的にフリー・ジャズに分類されるもので、ことにハーモニーに対する観念の類似性からアルト奏者のオーネット・コールマンとよく比較される。とはいってもドルフィーのスタイルは、基本的に音楽理論に則りインプロヴィゼーションを展開するというもの。その点、彼は非常に論理的なミュージシャンと云える。ドルフィーといえばブルーノート・レコードに『アウト・トゥ・ランチ』(1964年)という大傑作を残しているけれど、彼のアヴァンギャルドなプレイは激しく不協和音を奏でていながらも存外聴きやすい。それはドルフィーのスタイルが、音楽理論がしっかり押さえられた上であらためて解体されたものだからだろう。
ところでバイアードにも、ドルフィーと同様の風情が感じられる。ぼくはバイアードをフリー・ジャズ系のピアニストとは思っていないけれど、確かに彼のプレイには既存のジャズ・マナーに加え、フリー・ジャズの即興性や自由なアプローチが縦横無尽に採り入れられている。ぼくは冒頭でバイアードのことをジャズ・ピアノの歴史をひとりで抱え込んでしまったようなピアニストと云ったけれど、実際彼はラグタイム、ストライド、スウィング、ビバップ、そしてフリー・ジャズと、ジャズの歴史におけるあらゆるスタイルを独学でマスターしている。つまり包括的なジャズ・ピアニストなのだ。そんな変幻自在のテクニックの持ち主だからか、バイアードの前衛的な表現のなかには、伝統的なジャスのスタイルがしかと息づいているのである。
特定の音楽学校で正式な英才教育を受けなかったピアニスト
バイアードがプレスティッジ・レコードで吹き込んだ作品に『フリーダム・トゥゲザー!』(1966年)というのがある。実は彼はマルチ・インストゥルメンタリストとして知られるのだが、このアルバムではピアノのほかにフェンダー・ローズ・エレクトリック・ピアノ、チェレスタ、テナー・サックス、ヴィブラフォン、それにドラムスまで操っている。リチャード・デイヴィス(b, vc)、アラン・ドーソン(ds, tim, vib)を従えてのレコーディングだが、アルバム・タイトルからもわかるようにバイアードはこの作品でフリー・ジャズ的なアプローチを見せる。ただしここでの彼は、前衛的な手法を単なる混沌としたもので終わらせるのではなく、スウィング感やブルース・フィーリングと共存させている。しかも彼の遊びごころも相まって、気楽に楽しむことができる演奏となっている。
バイアードのフリー・ジャズに対する解釈は、たとえばおなじピアニストのセシル・テイラーによる現代音楽的なアプローチとはかなり印象を異にする。テイラーのスタイルは完全なる無調、即興に終始するが、それに対しバイアードは、伝統的なジャズの調性やリズムの重要性を理解した上で、その枠組みを自在に崩したり再構築したりするエクレクティックな手法を志向した。そのあたりはミンガスやドルフィーからの影響が強いのだろう。彼らの作品に収録されている実験的で前衛的な楽曲の核を担い、そのフリー・ジャズ的なセッションを支えていたのは、ほかでもないバイアードそのひとなのだから。なおバイアード、デイヴィス、ドーソンといったトリオは、プレスティッジ作品ではおなじみだが、この組み合わせを高く評価する向きも多いようだ。
そんなバイアードの来歴について、飽くまでぼくの知る範囲だが触れておくことにする。ジャッキー・バイアードは1922年6月15日、マサチューセッツ州の中央部にある都市ウースターに生まれた。ウースターは、のちに彼が拠点を置くボストンの西70キロメートルに位置している。両親はともに音楽好きだったが、母親はピアノを嗜み叔父や祖母もピアノを弾いた。特に祖母は、無声映画時代に映画館で演奏していたという。その影響からバイアードも6歳からピアノのレッスンを受けるようになる。ところが家族が大恐慌の煽りを受けたため、彼のレッスンは中断を余儀なくされる。そのいっぽうでバイアードは、父親から譲り受けたトランペットを継続的に吹いていた。

バイアードの少年時代のアイドルは、スウィング・ジャズ時代にもっとも影響力をもったミュージシャンであり、ビバップの先駆者と云われるトランペッター、ロイ・エルドリッジ、トランペット奏者でヴォーカリストとしても活躍したウォルター・フラーだった。そのころ彼は、ウースター近郊にあるクインシガモンド湖で開催されていた、ジャズ・バンドのライヴ演奏を度々聴きにいっていたという。またバイアードはラジオから流れる、ベニー・グッドマン楽団、ラッキー・ミリンダー楽団、チック・ウェッブ楽団といったスウィング・バンドやリズム・アンド・ブルースのバンドの音楽に親しみ、ピアニストではファッツ・ウォーラーの演奏をよく聴いていた。それらが自身のスタイルに少なからず影響を与えたと、彼は後年語っている。
バイアードは、特定の音楽学校で正式な英才教育を受けておらず、音楽理論やジャズ・ピアノのテクニックに関してもほとんど独学。ウースター周辺で活動していたローカル・バンドに参加したり、居酒屋などで演奏したり、兵役中には軍楽隊の一員として活躍したり、とにかく彼は実践的な現場を通じて音楽を学び、その才能を磨いた稀有なジャズ・ミュージシャンだ。特に軍隊在籍中にバイアードは、もともとピアノとトランペットを演奏していたが、新たにトロンボーンを習得。除隊後にはテナーおよびアルト・サックスも演奏するようになる。そのいっぽうで従軍中にバイアードは、フレデリック・ショパンやイーゴリ・ストラヴィンスキーといったクラシック音楽の作曲家の研究にも励んでおり、このことがのちの彼独自のエクレクティックなプレイ・スタイルの礎になったと思われる。
バイアードは1946年に除隊しているが、ときを移さず陸軍時代に知り合ったアルト奏者、アール・ボスティックのバンドに加わり演奏旅行に同行している。その後彼が1940年代後半から1950年代にかけて、チャーリー・マリアーノのグループやハーブ・ポメロイのバンドなどで活躍したしことはすでにお伝えした。それにしても、現代では独学と実践が最速かつもっとも深いスキル習得法などと云われたりするが、バイアードは世に稀なる才能と学習能力とを兼ね備えた人物だったのだろう。その知識と技術は、相当なものと想像される。その証拠に、彼はのちにニューイングランド音楽院、マンハッタン音楽学校、そしてハート音楽院などで教鞭を執ることになる。実はバイアードは、アメリカの音楽院で最初にジャズを教えた教育者のひとりでもあるのだ。
ということで、守備範囲の広い、しかも確たる実力をもったジャズ・ピアニストであるバイアードのリーダー作は千種万様である。彼のアルバムは40枚以上もあるのだけれど、もちろんぼくもそのすべてを聴いてはいない。代表作について語り合ったら、メインストリーム・ジャズ派からフリー・ジャズ派まで、十人十色となるだろう。そんななかで、ぼくが度々ターンテーブルに載せるのは、それこそ個人的な好みで、どうしてもトリオ作品になってしまう。特によく聴いているのは、前述の『ヒアズ・ジャッキー』をはじめ、おなじくニュー・ジャズ・レーベルの『ハイ・フライ』(1962年)、そしてプレスティッジ・レコードからリリースされた『サンシャイン・オブ・マイ・ソウル』(1968年)といったアルバムになる。
なんだ芸がないではないかと思われた向きも多いと思われるが、この3枚は多くのジャズ・ファンのニーズに応えるものであり、自信をもってお薦めできる名盤である。この3枚のうち『サンシャイン・オブ・マイ・ソウル』は、デイヴィッド・アイゼンソン(b)、エルヴィン・ジョーンズ(ds)がサイドに据えられたトリオ作品だが、1曲だけバイアードはギターも弾いている。また、ジョーンズもティンパニを叩いたりしている。そう、ご想像のとおりこのアルバムは、バイアード流のフリー・ジャズが思い切り展開されているのだ。とはいっても、やはり耳を塞ぎたくなるようなところはないのでご安心を──。本作はソウル・ジャズとフリー・フォームなポスト・バップとが融合した、確かにアヴァンギャルドではあるけれど、同時にグルーヴィーでエレガントな作品でもある。
刺激は少ないがそのぶん口当たりのよさでは群を抜いているアルバム
ただ『サンシャイン・オブ・マイ・ソウル』は、どちらかというとダイナミックなパフォーマンスと、そこに生まれるスパイラルなテンションが際立った作品。まあそれが魅力なのだけれど、リスナーの集中力が自然と極限まで高められたりする場合もあるだろう。ここではバイアードのピアノが、アグレッシヴかつポリリズミック。ジョーンズのドラムス、そしてメロディアスだが推進力のあるラインを形成しながら、ときには高速なパッセージを繰り出すアイゼンソンのベースと、互角に渡り合っている。そんなとき、彼のフリー・フォームなアプローチは全開する。そういう激しく展開されるインタープレイに、緊張感が伴うのは当然至極。とはいうものの、このガチンコ対決とも云うべきトリオの全力を出し切った演奏は、爽快感をもたらすのだけれど──。
そういった一面があるいっぽうで『サンシャイン・オブ・マイ・ソウル』というアルバムには、たとえばウィリアム・クリストファー・ハンディが作曲した有名な「セント・ルイス・ブルース」における、バイアードのエスプリの効いた解釈が、こころを和ませてくれたりするシーンもある。1枚で彼のまさにエクレクティックでヴァラエティに富んだピアノ・スタイルが堪能できるという点が、本作の人気を高めているようにぼくは思う。そしてこのアルバムでは、個性的で演奏技術の高いリズム隊による極上のパフォーマンスも然ることながら、さきに述べたようなバイアードの広範囲にわたる音楽的知識と創造性によって、ジャズ作品としてのクオリティが向上させられているように思われる。そういう意味でも本作は、文句なしの名盤である。
そして『ヒアズ・ジャッキー』『サンシャイン・オブ・マイ・ソウル』といった傑作を押さえて、ぼくにとってオールタイム・フェイヴァリットとなっているのが、実は『ハイ・フライ』である。バイアードのアルバムだから、フリー・ジャズはもちろんのことバップやブギウギのエッセンスが含まれている。ただ彼の演奏にしては珍しく比較的端正でリラックスしたものとなっており、そのピアノ・プレイがもつ豊かなエクスプレッションと新鮮なハーモニーを、こころゆくまで堪能することができる作品となっている。しかもその音景はいつになく都会的で、バイアードが放つアーティキュレーションもしごく軽妙洒脱。要は肩の力を抜いて楽しむことができる好盤なのだ。甘ちゃんと云われてしまうかもしれないが、ぼくは抑制の効いたバイアードの演奏に、底知れない含蓄を感じる。

この『ハイ・フライ』のレコーディングは、1962年1月30日、ニュージャージー州イングルウッド・クリフスのシルヴァン・アヴェニュー445番地に所在する、おなじみのヴァン・ゲルダー・スタジオにおいて行われた。云うまでもなくエンジニアは名匠ルディ・ヴァン・ゲルダー。サイドにはロン・カーター(b)とピート・ラ・ロカ(ds)が据えられているが、この組み合わせも絶妙だ。カーターのベースはリズムの安定感を高めているし、ラ・ロカのドラムスはそのリズムの隙間に歯切れのいいフレーズを投入している。このふたりのプレイが、手堅くバイアードのピアノの魅力を引き出していると云っていいだろう。バイアードはブルージーかつテクニカルな、そしてリリカルかつエナジェティックな独創的なフレーズを、遊びごころも交えて気持ちよさそうに綴っている。
アルバムはピアニストのランディ・ウェストンが作曲した「ハイ・フライ」からスタート。イントロのまるで印象派のようなピアノのルバート演奏が美しい。インテンポしてからバイアードは、セロニアス・モンクを彷彿させるアブストラクトなタッチでテーマを奏でたあと、スウィンギーかつパーカッシヴにアドリブを展開していく。そのゆとりのあるプレイが、得も云われぬリラクゼーションを生み出している。個人的には、彼の控えめで品のある演奏が際立ったこの1曲で、このアルバムがもつモダンでソフィスティケーテッドな音世界に引き込まれてしまう。つづくバイアードのオリジナル「ティリー・バターボール」では、バップ・スタイルが基調とされながら、ブルージーなフィーリングとフリー・フォームなアプローチとが、散りばめられている。
そんな程よいブレンド加減のバイアードのピアノ・プレイに惹きつけられているうちに、この曲はあっという間に幕を閉じる。それだけ彼の表現力には、リスナーに対する強い影響力があるのだ。カーターの渋いソロを忘れさせるくらいに──。3曲目の「ヤマクロー」は、ストライド奏法の先駆者と目されるピアニスト、ジェームズ P. ジョンソンの曲。彼が書いたジャズとクラシックとを融合させたシンフォニック・ジャズからの抜粋である。バイアードの弾むようなブロック・コード、そして彼が敬愛するストライド・ピアノのフィーリングが、なんとも心地いい。ラ・ロカとの軽妙な4バースも、楽曲のハッピーなムードをより高めている。A面のラストを飾る「ゼア・アー・メニー・ワールズ」は、バイアードの2曲目のオリジナル。彼の音楽的特徴である、エクレクティックなナンバーだ。
この曲は洗練された都会的センスに溢れたナンバーだが、大胆なコード・ワークと精緻な構成にバイアードの優れたコンポジション・スキルが感じられる。そして彼のピアノ・プレイならではのエレガンスとダイナミクスとを同時に楽しむことができる好トラックでもある。メロディック・ラインがデューク・エリントン風なのも、興味深い。B面はやはりバイアードのオリジナル「ヒア・トゥ・ヒアー」からスタートする。アルバム中もっともフリー・ジャズにアプローチされたナンバー。アブストラクトなパフォーマンスから高速のバップ・スタイルへ移行。バイアードのピアノは激しくアヴァンギャルドなフレーズを繰り出しつづけ、サイドのトリオの熱量も最高潮に達する。中盤からはクールダウンしてリリカルな美しいバラード演奏となる。
つづく「バードランドの子守唄」は、云わずと知れたクール・ジャズ・ピアニスト、ジョージ・シアリングの曲。バイアードは独自のハーモニーとリズムで、そつなくプレイ。ある意味で、シアリングよりもクールでリフレッシングに響くが、その軽妙さに彼の遊びごころが垣間見える。その点、次曲の「ラウンド・ミッドナイト」にも同じことが云える。セロニアス・モンクによるバラードの名曲だが、風変わりな旋律と複雑な和声進行からどちらかというと重たい印象を受ける。ところが、バイアードのプレイは、いい意味で軽い。モダンなハーモニー感覚とクラシックやストライドを織り交ぜた緩急のある語り口が、楽曲をエレガントで色彩豊かなものにしている。それに寄り添う感じのカーターのソロもまた、美しくなだらかだ。
アルバムのラストを飾る「ブルース・イン・ザ・クローゼット」は、ベーシストのオスカー・ペティフォードがピアニストのバド・パウエルのために書いたブルース・ナンバー。バイアードのピアノが、フリー・フォームを交えたユニークなバップ・スタイルで軽快に駆け抜ける。カーターはアルコ・ベースで存在感を示し、ラ・ロカはスティック捌きも歯切れよく軽やかに飛翔する。バイアードとの4バースも痛快。まさにアルバムのラストを締めくくるに相応しい、三位一体のエナジェティックな高速ナンバーである。バイアードのリーダー作のなかでは、本作はどちらかというと刺激が少ないアルバムと云えるのかもしれないが、そのぶん口当たりのよさでは群を抜いていると、ぼくは思う。もし彼の演奏に触れたことがないというのなら、まず本作を手にとることをお薦めする。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。








コメント