ミシェル・ルグラン自身がフィルム・スコアを色彩豊かな交響組曲に発展させロンドン交響楽団が演奏した『交響組曲「シェルブールの雨傘」』
 Album : Michel Legrand, London Symphony Orchestra / Performs His Symphonic Suite From “The Umbrellas Of Cherbourg” & Theme And Variations For Two Pianos And Orchestra From “The Go-Between” (1979)
Album : Michel Legrand, London Symphony Orchestra / Performs His Symphonic Suite From “The Umbrellas Of Cherbourg” & Theme And Variations For Two Pianos And Orchestra From “The Go-Between” (1979)
Today’s Tune : Symphonic Suite From “The Umbrellas Of Cherbourg”
映画『ミシェル・ルグラン 世界を変えた映画音楽家』とリスペクターたち
ミシェル・ルグランといえば、昨年の9月に映画『ミシェル・ルグラン 世界を変えた映画音楽家』(2024年)が日本で公開されたことが記憶に新しい。これは、フランス、カンヌ出身のデヴィッド・ヘルツォーク・デシテスが監督、脚本、製作を手がけたルグランのドキュメンタリー映画。ぼくはこのひとのことはよく知らないけれど、彼は映像の世界で仕事をするまえからルグランの音楽を深く敬愛していたらしい。好きが高じて2017年にルグラン本人とはじめて対面すると、すぐに自らがドキュメンタリー映画を製作することを提案したという。作品のコンテンツは、親族へのインタビューをはじめ、ルグランの残したインタビュー、コンサート、テレビ番組、プライヴェートな16ミリフィルムなど、数1000時間に及ぶ膨大なアーカイヴから構成されたものだ。
映像と音楽が渦巻くなかで、ルグランの生涯と運命が描き出されるこの映画を世に送り出したデシテス監督は、もとはカンヌ市役所の職員として清掃業務に従事していた。1999年に渡米しているが、2000年代のはじめからプロデューサーとして頭角を現した。映像の世界では、製作、脚本、監督、撮影、編集、さらに一部の作品では音楽も手がけるという多芸多才ぶりを発揮。ディズニー・アニメ『トレジャー・プラネット』(2002年)、フランスのコメディ映画『ミッション・クレオパトラ』(2002年)などの製作に関わったり、2004年にはあのデヴィッド・リンチの監督作品『マルホランド・ドライブ』(2001年)のメイキング・ドキュメンタリーを監督したりもしている。まあとにかく、今年53歳を迎えるデシテス監督は、フィルム・インダストリーにおいては幅広い分野に携わっているようだ。
ときに、このドキュメンタリー映画『ミシェル・ルグラン 世界を変えた映画音楽家』の背景音楽といえば、サウンドトラック・アルバムというかコンピレーション・アルバムとしてしっかり商品化されている。実のところぼくは日本で映画が公開されるまえに、デッカ・レコードから発売されたフランス盤『Il était une fois』(2024年)を、映画のサントラ盤とは知らずに入手していた。個人的にはコンピレーション盤に食指を動かす機会があまりないのだけれど、このアルバムには過去に聴いたことのない曲がいくつか見受けられたので、取り敢えず購入した次第。実際、未発表曲が複数収録されているのだが、それにしても選曲がいささかマニアックである。でも逆にこのことから、いかにデシテス監督がルグランの音楽に熱狂的にのめり込んでいるかが、ひしひしと感じられる。
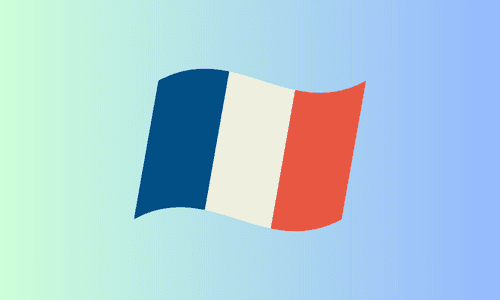
ちなみに、このアルバム・タイトルであり映画の原題でもあるフランス語は、英語で謂うところの“Once upon a time”で、云うまでもなく“むかしむかし”という常套句である。これにはぼくも、ちょっとニヤニヤしてしまった。ルグランのファンならご存じのことと思われるが、彼が書いた有名な曲に「ワンス・アポン・ア・サマータイム」というのがある。もともとはルグランの初期の作品「リラのワルツ」というシャンソンだったが、アメリカの作詞家、ジョニー・マーサーが英詞を書いてそのタイトルが付された。そしてこの曲といえばなんといっても、ジャズ・シンガーのブロッサム・ディアリーがピアノの弾き語りをしたアルバム『ワンス・アポン・ア・サマータイム』(1959年)で、あまねくひとに知られるようになったと云えるだろう。
それはともかく、アルバム『Il était une fois』は、日本での映画公開に併せて『ミシェル・ルグラン 世界を変えた映画音楽家 オリジナル・サウンドトラック』と適切に銘打たれ、めでたく本邦においてもリリースされた。ちょっと毛色の変わったルグランのコンピレーション・アルバムではあるが、彼の音楽をディープに楽しみたい向きは、手にとってみてはいかがだろう。ただ“ベスト・オブ・ルグラン”的なセレクションで構成されたアルバムを求めるかたには、あまりお薦めできない。たとえば、日本で独自に企画された2枚組CD『エッセンシャル・ワークス・オブ・ミシェル・ルグラン』(2020年)あたりのほうが無難かもしれない。なにせルグランのオーソリティとしては日本では最高峰だろう、音楽ライターでアンソロジストの濱田高志が、本盤の監修を務めているのだから──。
個人的によく聴いているのは、マーキュリー・レコードからリリースされた『ル・メイユール・ドゥ・ミシェル・ルグラン』(1999年)。フィルム・スコアはもちろんのこと、ポップ・ミュージック、ジャズ、クラッシックなど、ルグランの音楽を多面的に楽しむことができる。多種多様のルグラン・サウンド23曲が1枚のアルバムにぎゅっと詰まっているが、すべての曲がリマスタリングされたこともあり、プレイリストの進行はいたって自然に聴こえるし、その連続性にはまったく違和感が感じられない。手軽に楽しんでもよし、存分に味わってもよしの、ある意味でハイスペックな1枚と云える。いささかハナシがわき道にそれてしまったが、くだんのドキュメンタリー映画を観たひとなら間違いなく、さらに多くのルグラン・サウンドを欲するようになるだろう。
ところで、映画『ミシェル・ルグラン 世界を変えた映画音楽家』が日本で公開された際に、著名な音楽家たちがコメントを寄せている。その顔ぶれを見ると、実に幅広いジャンルのミュージシャンたちに、ルグランの音楽が影響を与えていることをあらためて知らされる。ちょっと挙げてみると、サクソフォニストで作曲家の菊地成孔、映画やテレビの音楽を多く手がけているゲイリー芦屋、もとピチカート・ファイヴのリーダー、小西康陽、音楽プロデューサーで作曲家の鷺巣詩郎、ジャズ・ピアニストで作曲家の島健、多種多様の映像作品のアンダースコアを手がける服部隆之、ポップス・シーンのヒットメーカー、林哲司、アルファレコードの創設者として知られる村井邦彦、女優としても活躍するシンガーソングライター、森山良子といった具合だ。
なかでも村井さんは、昔からルグランの支持者として知られている。市川崑監督作品である映画『火の鳥』(1978年)でプロデューサーを務め、ルグランにテーマ曲の作曲を依頼したのは氏である。ルグラン自らがタクトを振ったロンドン交響楽団の演奏によるアルバム『火の鳥』(1978年)、シンセシストとして一世を風靡した深町純によるスコアを新日本フィルハーモニー交響楽団が演奏した『火の鳥 オリジナル・サウンドトラック』(1978年)、テーマ曲のカヴァーが収録された『サーカス 1』(1978年)は、アルファレコードからリリースされた。なお、松崎しげるが歌ったイメージ・ソングのシングル盤『火の鳥』(1978年)はビクター・レコードから、やはりカヴァーが収録されたハイ・ファイ・セットのアルバム『SWING』(1978年)は東芝EMIから発売されたが、ともに村井さんのプロデュースによるものだ。
これはいくぶん余談になるが、キーボーディストでシンガーでもある横倉裕が1970年初頭に結成したバンド、NOVOがルグランの作曲した「風のささやき」をカヴァーしている。躍動感のあるブラジリアン・グルーヴが炸裂するユニークなアレンジが、フレッシュで心地いい。いっぽうNOVOは、ポップ・デュオ、トワ・エ・モワが歌った1971年の旭化成のCMソング「愛を育てる」と、フォーク・グループ、赤い鳥が1973年に発表した「窓に明りがともる時」を採り上げている。この2曲はどちらも作詞を山上路夫、作曲を村井邦彦といった黄金コンビによるものだ。その後、横倉さんはアメリカでの事業展開を模索していた村井さんを頼って渡米し、アルファレコードにおいてソロデビュー・アルバム『ラヴ・ライト』(1978年)を発表する。
ルグランの技巧が凝らされた豪華絢爛な音楽表現とフィルム・スコア
その点を踏まえると、NOVOがルグランの「風のささやき」をカヴァーした件に関しても、村井さんが一枚噛んでいるようにも思われる。そんな村井さん、音楽家としては類稀なるメロディメーカーといった印象を与えるが、その楽曲がルグランのそれを彷彿させるのかというと、実はまったくそんなことはない。氏がペンをとった曲といえば、慶應義塾大学ライト・ミュージック・ソサイェティーの出身ということもあり、ジャズの素養が活かされているのだろう、概ね洗練された都会的なイメージをもつ。むろんどちらがいいということではないけれど、ルグランの曲よりもむしろ村井さんのそれのほうが、透明感があって淑やかな感じのものとして、ぼくには受けとられる。それに対してルグランの音楽はすこぶる豪華で、思わず耳を奪われるようなものなのである。
私感では、鷺巣詩郎の音楽にもっともルグランっぽいものが感じられる。鷺巣さんが関わった音楽では、英国のプロデューサー兼キーボーディストのマーティン・ラスセルズと組んだMASHというユニットの作品に、ぼくはもっとも興味をそそられた。このユニットの楽曲では、ファンキーなグルーヴとソウルフルなヴォーカルのフロウとが横溢する背景に、とき折ストリングスのアンサンブルによる彩りも鮮やかなサウンドがレイアウトされたりする。この絶妙なコントラストが、得も言われぬ心地よさを生んでいるように、ぼくには思われるのだ。この弦楽器群による煌びやかなダイナミクスは、一般的に氏の代表作とされる、テレビアニメ『新世紀エヴァンゲリオン』(1995年 – 1996年)のスコアにおいても散見されるが、こういうアレンジはおそらくルグランからの影響だろう。
ルグランがその華麗な音世界をオーケストラで表現するとき、その技法はきわめてユニークと云える。しかしながら彼のアレンジの作法をコピーしても、そう上手くいくものではない。プロの音楽家においても、ルグランのマナーを模倣して失敗している例をしばしば見かける。その点、鷺巣さんのアレンジはごく稀な成功例で、ただただ敬服するばかりだ。ルグランはもっとも合理的かつ効果的にオケを鳴らす方法を知り尽くしていて、さらにそこから飛躍する。むろんジャンプすることも容易ではないが、見事にランディングをキメることのほうが至難の業。ルグランはそれができる数少ない音楽家。おなじフランスの作曲家でヒラメキで流麗な旋律を創出するフランシス・レイが天才ならば、ルグランはさながら天才的な山師といったところである。
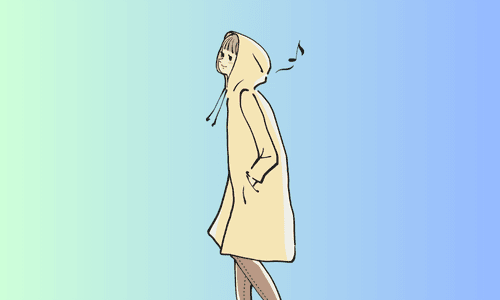
いささか云いかたがわるくなったが、ルグランの技巧が凝らされた豪華絢爛な音楽表現を目の当たりにすると、ぼくはついついそんなイメージをもってしまうのである。すっかりあとになってしまったが、ミシェル・ルグランは、1932年2月24日パリの20区メニルモンタン生まれの音楽家。ジャズ・ピニスト、ポップ・シンガーという側面ももつが、一般的には映画音楽の作曲家として広く知られる。彼は2019年1月26日にパリ西部近郊ヌイイ=シュル=セーヌにおいて、86歳でこの世を去る前年まで映画音楽の仕事をつづけていた。具体的には、巨匠オーソン・ウェルズの未完の映画『風の向こうへ』(2018年)において、ウェルズの親友でもあったルグランは最後の力を振り絞ってスコアを書き上げた。このクラシックとジャズとを織り交ぜたフィルム・ミュージックが彼の遺作となった。
この『風の向こうへ』のサウンドトラック・アルバムは、映画やテレビのサントラ盤でおなじみのララ・ランド・レコードからリリースされたが、そのコンテンツは一聴でルグランの手がけたものとわかる。ただ、ダイナミックなオーケストラの演奏や、スタイリッシュなジャズ・プレイが展開されるなかにも、とき折アヴァンギャルドな面が窺われ、あらためてその感性の瑞々しさに驚かされた。20世紀後半のフランス映画音楽シーンをリードしつづけた音楽家の、まさに面目躍如たる仕事ぶりと云える。ミュート・トランペットが奏でるクールでドライなテーマ曲が印象的なフランソワ・レシャンバックの監督作品『アメリカの裏窓』(1960年)からこの映画に至るまで、ルグランが携わった映像作品の数はテレビも含めると、結局のところ200以上にも上る。
ちなみに『アメリカの裏窓』と『風の向こうへ』の音楽はともに、前述の『ミシェル・ルグラン 世界を変えた映画音楽家 オリジナル・サウンドトラック』に収録されている。やはりこのアルバムからは、デシテス監督のこだわりの強さというか、ルグランに対する深い知識や見識が感じられる。ぼくも小学生のころからルグランの音楽に親しんできたけれど、見識的なことはともかく知識量ではデシテス監督の足もとにも及ばない。ぼくが影響を受けたフランス出身の映画音楽の作曲家といえば、ジョルジュ・ドルリュー、フランシス・レイ、そしてミシェル・ルグランだ。3人のなかでもっとも長い期間、そしてもっとも多くの作品を聴いた音楽家といえば、やはりルグランになるのだろう。しかし彼のすべてが好きかというと、実はそうでもない。
いま思えば、ドルリューやレイの音楽にはじめて触れたときも、いたく感動させられたけれど、ルグラン・サウンドとの出会いには、それをはるかに凌駕するインパクトがあった。小学生とはいえピアノを弾き作曲や編曲にも興味をもちはじめていたぼくは、彼の書くスコアにすこぶる好奇心がそそられたものである。彼のオーケストレーションの非凡なところといえば、音楽上のアイディアに大きなブレークスルーが生み出されているというところ。パリ国立高等音楽院でピアノ演奏とともに和声学を徹頭徹尾学び、同校を首席で卒業したルグランだけに、当然のごとく楽器の組み合わせかたや演奏のさせかたには精通している。ところが彼には、会得した正統的なマナーを打ち破り、飛躍的に前進するような志向がある。ルグランという音楽家が余人をもって代えがたいのは、そういうところがあるからだ。
彼は一般的な音楽理論はもちろんのこと、汲めども尽きぬ知恵の泉をもってして、すべての楽器が渾然一体となった世界を創り上げる。惜しげもなく大きく展開されるルグラン・サウンドは、けっこう派手に聴こえるのだが、決して乱脈を極めることもなく心地よく響く。これはいわば、ルグラン・マジック。そんな劇的効果を出せるのは、世界広しといえども彼だけだろう。だが、それが却ってアダになることもある。ルグランの音楽自体は間違いなく一級品だけれど、映画のアンダースコアとして観たとき、少々まえに出過ぎるきらいがあると感じられるのだ。というのもぼくは、映像作品の劇伴の至上命題といえば、テーマ・ソングやインサート・ソングとは異なり、後方で物語を支えながら作品の世界観を深めることにあると考えるからだ。
それに反してルグランの音楽は、それ自体が絶えず存在感を示している。たとえばジョルジュ・ドルリューには、映画のシーンにおけるアンダースコアの要不要を的確に判断するような風情がある。つまり彼が映画音楽を手がけるとき、そのスコアが劇伴音楽に徹しつづけるケースがままある。いささか地味な作風と受けとられるかもしれないけれど、彼の簡潔で論理的なマナーによって創り出されるメロディとサウンドは、とにかく美しい。個人的には1960年代から1970年代の作品が好みなのだけれど、ハリウッドで仕事をするようになってからも、ドルリューはそういう確固たる個性を音楽に反映させつづけた。そんな傑出した才能にぼくは尊敬の念を抱くのだが、実はこのドルリュー、才華爛発なルグランをして“最高の作曲家”と云わしめたほどスゴいひとなのである。
ルグランの代表作であるミュージカル映画『シェルブールの雨傘』の音楽
ルグランの音楽は、映像やストーリーラインがどうであろうと、作品の華となる。むろんそういう特色が、有益である場合もある。たとえば全編音楽のみでほかのセリフが一切ないミュージカル、ヌーヴェルヴァーグの左岸派とされるジャック・ドゥミの監督作品『シェルブールの雨傘』(1964年)と『ロシュフォールの恋人たち』(1967年)、パリ、ニューヨーク、モスクワ、ベルリンといった4都市を舞台とし、各々の場所での物語がシャンソン、ジャズ、ロシアン・フォーク・ソング、クラシックといった音楽で彩られながら綴られていく、フランス屈指のヴィジュアリストであるクロード・ルルーシュの監督作品『愛と哀しみのボレロ』(1981年)、あるいはシンガーのバーブラ・ストライサンドが監督、製作、脚本、主演を務めたミュージカル映画『愛のイエントル』(1983年)などは、その好例である。
上記の映画は、ある意味で音楽が主役だ。もしそこにルグランの音楽がなかったら、作品は無味乾燥で月並みなものとなっていたかもしれない。なかでも『シェルブールの雨傘』は、第17回カンヌ国際映画祭でグランプリを受賞した、世界的に知名度の高さを誇る作品。わが国での人気も非常に高く、2009年に公開45周年を記念して製作された、初のデジタル・リマスター版が世界に先駆けて公開されたのは日本だった。また、2013年にはデジタル修復完全版がプロデュースされ、第66回カンヌ国際映画祭のカンヌ・クラシックスで上映された。そんな後世に残るような優れた作品ではあるものの、この『シェルブールの雨傘』のシノプシスだけを参照すると、戦争という時代の流れに翻弄される若い男女の悲恋物語という、ちょっと陳腐なものに映る。
そんな使い古されたストーリーの映画を時代を超えた名作に押し上げたのは、セリフをすべてレチタティーヴォやアリオーソあるいはアリアとして役者に歌わせてしまう(実際は歌手に吹き替えで歌わせる)というドゥミ監督のアイディアも然ることながら、なんといっても、彼が書いた歌詞というか台詞に一分の隙もなく華やかで優雅な旋律を載せてしまう、希代の音楽家ルグランのアビリティだろう。ドゥミ監督は、ありふれたひとの営みをミュージカルやファンタジーで表現したロマンティックな作品を多く残しているが、彼が描く世界はある意味で非常に現実離れした情緒的で甘美なもの。そしてドゥミ監督の概念を増幅させているのが、ルグランによる豪華絢爛なサウンドであることは、一目瞭然である。逆にルグランにとってもドゥミは、最高のコンビネーションを発揮する監督と云える。

まあ、ある意味で映画『シェルブールの雨傘』は、従来のミュージカル映画の定石を破った野心的な作品と云えるのだが、この映画をはじめて観たときまだ小学生だったぼくは、1920年代後半からはじまるストーリーラインに沿って俳優が楽曲を歌うというスタイルの映画の歴史や定法について知る由もなかった。正直に云うと、そういう事柄はぼくにとっていまでも枝葉末節なことで、この映画での個人的な最大の留意事項といえば、ルグランによる珠玉の楽曲が満載であるということ。映画『シェルブールの雨傘』をはじめて体験したときのぼくの意識は、どちらかというと映像よりも音楽のほうに終始集中していたのである。その楽曲群の卓越性は、3部構成であるこの映画の第1部「はじまり──1957年11月」だけを採ってみても、遺憾なく発揮されている。
あのだれもが知る感傷的な美しい「テーマ」が粛々と奏でられたあと、軽快な「ガレージのシーン」がジャジーに展開され、さらにスウィート・アンド・ラヴリーな「店の前で」が柔らかに流れはじめるといった最初のシークエンスだけで、ぼくはすっかりルグランの音楽にこころを奪われてしまった。やがてのちに「ウォッチ・ホワット・ハプンズ」というタイトルで知られるようになる、エレガントな「宝石商(デュプール氏)の家で」がマイルドな味わいで歌われる。ちなみにこの曲はもともと、ドゥミ監督のデビュー作で『シェルブールの雨傘』の前日譚にあたる映画『ローラ』(1961年)のために書かれた曲。両作に登場するヨハネスブルグで宝石商として成功を収めた紳士、ローラン・カサールに関連づけての流用である。
第1部はメイン・タイトルの「テーマ」と同一曲である「駅:ギイの出発」によって、離ればなれになる恋人たちの切ない別れが、深い哀しみを湛えた壮大な音像で描き出され締めくくられる。このあまりにも有名な曲は、ノーマン・ギンベルが英語の歌詞を書き「アイ・ウィル・ウェイト・フォー・ユー」といタイトルが付され、世界的なスタンダード・ナンバーとなった。それはさておき、映画は第2部「別離──1958年1月」第3部「帰郷──1959年」とつづくわけだが、ぼくはこの作品をラストまで観届けたときには、ミシェル・ルグランという音楽家にゾッコンになっていた。当然のごとく、サウンドトラック・アルバムを求めていそいそとショップに赴き、どうせならと通常盤ではなく2枚組の『シェルブールの雨傘 完全オリジナル・サウンドトラック』(1964年)のほうを購入した(国内盤は1973年に発売)。
このレコード、ぼくは手に入れた当初はよく聴いていたのだけれど、いまはあまりターンテーブルに載せることがない。現代では多種多様のメディアやオンデマンド配信サービスが存在する。だが当時は映画を観る手段といえば、劇場に足を運ぶかテレビ放送を待つかしかなかった。日常的に『シェルブールの雨傘』の音楽を楽しむには、このレコードだけが頼りだったのである。いまならこの完全盤LPを手にとるくらいだったら、配信サービスで本編を観たほうが、その作品世界をより立体的に堪能することができるのだ。そこでお薦めするのが『交響組曲「シェルブールの雨傘」』(1979年)というアルバム。ルグラン自身が、フィルム・スコアをピアノとオーケストラのための交響組曲にアレンジしたものだ。演奏は、前述のアルバム『火の鳥』で共演済みのロンドン交響楽団である。
ルグランとロンドン交響楽団とは、1978年4月2日にロンドンのロイヤル・アルバート・ホールにおいてコンサートも開催。公演ではルグランが作曲した数々の映画音楽が、彼自身による指揮とピアノ演奏によって披露された。その点、ルグランとこのオーケストラは『交響組曲「シェルブールの雨傘」』でも、息のピッタリ合ったところ見せている。指揮とピアノは、やはりルグラン自らが担当。数々のミュージカル・ナンバーがほぼ映画の進行どおりに、豪華絢爛かつ響徹雲霄なシンフォニック・サウンドで再現される。ときにはビッグバンド・ジャズ風なパフォーマンスもあり、オーケストラにエレクトリック・ギター、ベース、ドラムスといったリズム・セクションも加わる。それこそ天才的な山師のごとき、ルグランのアレンジの妙技をたっぷり味わうことができる1枚となっている。
なおレコーディングは、1979年5月21日から24日にかけてロンドンのEMIスタジオにおいて行われた。この交響組曲は28分強、切れ目なしに演奏されるが、レコードではA面のすべてを占める。B面にはジョゼフ・ロージーが監督したイギリス映画『恋』(1971年)のテーマ曲を、“2台のピアノとオーケストラのための主題と変奏”にアレンジしたものが収録されている。いまひとりのピアニストは、ロンドン交響楽団のロバート・ノーブルが務めた。やはり編曲にルグランのひと並み外れた才能が感じられるが、22分近くひとつのテーマのヴァリエーションを聴かされるのには、正直なところ、ぼくはストレスを感じる。ただそれを差し引いても、このアルバムはルグランの才気が遺憾なく発揮された、鑑賞用音楽として一級品の音盤であることは間違いない。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。








コメント