ヘンリー・マンシーニにとってもっとも好きな自作であり、評論家のあいだでは彼の最高傑作との呼び声が高い映画『いつも2人で』のオリジナル・スコア・アルバム
 Album : Henry Mancini / Two For The Road (1967)
Album : Henry Mancini / Two For The Road (1967)
Today’s Tune : Something For Audrey
ガーシュウィン、エリントン、バーンスタイン、そしてマンシーニ
ぼくの敬愛するデイヴ・グルーシンのアルバムに『酒とバラの日々~ヘンリ-・マンシ-ニに捧ぐ』(1997年)というのがある。文字どおり、グラミー賞やアカデミー作曲賞に幾度となく輝いた映画音楽の作曲家、ヘンリー・マンシーニへのトリビュート作品だ。グルーシンは映画音楽も数多く手がけているけれど、もともとはジャズ・ピアニストで1960年代にモダン・ジャズのアルバムを吹き込み、1970年代以降はおしなべてコンテンポラリー・ジャズ系の作品を発表している。そんななか1990年代には、自己の音楽的ルーツをたどるかのように、立てつづけにトリビュート・アルバムを制作した。その嚆矢となったのは、ジョージ・ガーシュウィンの楽曲が採り上げられた『ガーシュウィン・コネクション』(1991年)だった。
ガーシュウィンといえば、ティン・パン・アレー出身の作曲家で、レビューやミュージカル向けのポピュラー・ソングやシンフォニック・ジャズの草分け的作品で名を馳せたひと。数々のジャズ・スタンダーズやオーケストラルなジャズ作品をものしたこの偉大な作曲家が、プレイヤーでありながらコンポーザー、アレンジャーとしての才能を発揮するグルーシンに、いくばくかの影響を与えたのは、ごく自然なことのように思われる。なおグルーシンはこのアルバムのなかの「メドレー : ベス・ユー・イズ・マイ・ウーマン〜アイ・ラヴス・ユー・ポーギー」において、第34回グラミーの最優秀インストゥルメンタル編曲賞を獲得している。彼のピアノとストリングスとによる、ちょっとノスタルジックな詩情溢れるトラックである。
さらにグルーシンは、デューク・エリントンへのトリビュート・アルバム『デュークへの想い』(1993年)を制作する。エリントンは、云わずと知れた“スウィング・ジャズの帝王”の異名をとるジャズ・オーケストラ・リーダー。しかもピアニストとしても、なかなかの腕前のもち主だ。名作曲家にして名ピアニストであるという点は、グルーシンに直結する。そしてやはり、このアルバムに収録されている「ムード・インディゴ」が、第36回グラミーの最優秀インストゥルメンタル編曲賞に輝いている。さすがと云うしかない。グルーシンのピアノ、エディ・ダニエルズのクラリネットの即興演奏も然ることながら、木管楽器にホルンやチューバが加えられたユニークなオーケストレーションが秀逸だ。

またグルーシンは、上記のマンシーニのトリビュート・アルバムのリリースとおなじ年に『デイヴ・グルーシン・プレゼンツ~ウエスト・サイド・ストーリー』(1997年)という作品を発表している。1957年のブロードウェイ・ミュージカル『ウエスト・サイド物語』の初演から40周年を記念して、名レコーディング・エンジニアとして知られるフィル・ラモーンのプロデュースにより制作された。ジェローム・ロビンズ原案、アーサー・ローレンツ脚本による、このあまりにも有名なミュージカルは、1961年、2021年と2度の映画化がなされた。それ故その楽曲は、世界的な知名度の高さを誇る。作曲を手がけたのは、20世紀後半の西洋芸術音楽シーンをリードした音楽家、レナード・バーンスタインである。
バーンスタインといえば、コロムビア交響楽団とニューヨーク・フィルハーモニックとを従えて吹き込んだ、ガーシュウィンの作品集『ラプソディ・イン・ブルー/パリのアメリカ人』(1959年)が有名だけれど、彼はこのレコーディングでお得意の“弾き振り”を披露している。つまり、ピアニストとコンダクターとを兼任しているわけだ。一般的には指揮者として知られるバーンスタインはピアニストとしてもなかなかいいセンスをもっていて「ラプソディ・イン・ブルー」のカデンツァなどでは、エスプリの効いたジャジーなプレイを展開していたりする。彼はクラシックだけでなく、ジャズをはじめとするあらゆる音楽に造詣の深いひとだが、そういう音楽家だからこそ『ウエスト・サイド物語』のようなジャジーなスコアを書くことができたのだろう。
そんなスコアをグルーシンはただなぞるだけではなく、大ヒット・ミュージカルの音世界を現代的な解釈で蘇らせた。個人的に好きなのは、やはりスティーヴン・ソンドハイムが作詞した「トゥナイト」かな──。ラテン・ポップの女王として世界的にその名が轟きわたる、キューバ生まれのシンガー、グロリア・エステファンがダイナミックなフロウで朗々と歌っている。その感動的な歌唱に加えて、グルーシンの流麗なストリングスを配したアレンジが冴えわたる。ことにその繊細なリハーモナイゼーションによって、ヴィンテージな名曲に現代的なムードが醸し出されているところに、彼の音楽家としての卓越したクリエイティヴィティが感じられる。まあファンにはおなじみの、グルーシンならではの手練が尽くされたスコアリングと云えるのだけれど──。
ただ、この『デイヴ・グルーシン・プレゼンツ~ウエスト・サイド・ストーリー』は、さきに述べた『ガーシュウィン・コネクション』『デュークへの想い』『酒とバラの日々~ヘンリ-・マンシ-ニに捧ぐ』のように、作曲家をトリビュートしたものではない。むろんグルーシンにとって、ガーシュウィン、エリントン、マンシーニらと同様に、バーンスタインもまた敬愛の対象なのだろう。しかしこのアルバムは、どちらかというと『ウエスト・サイド物語』自体へのトリビュート作品という印象を与えるのだ。それはともかく、前置きが長くなってしまったが、今回お伝えするのはグルーシンではなくマンシーニについてである。そういうわけで肝心の『酒とバラの日々~ヘンリ-・マンシ-ニに捧ぐ』について、触れておかなければならない。
実はぼくは、グルーシンがガーシュウィン、エリントンにつづいて、マンシーニの音楽を採り上げるとは、まったく予想していなかった。彼のキャリアを振り返ったとき、次にピックアップされる音楽家としてぼくが思い浮かべたのは、クインシー・ジョーンズだった。アントニオ・カルロス・ジョビンやセルジオ・メンデスという案もあったのだけれど、ふたりともブラジル出身のミュージシャンだから候補から外れた。アメリカの音楽家で特にジャズに関わったひとに限定した上で、活動の全盛期においていささか強引な位置づけをして考えると、1920年代から1930年代までのガーシュウィン、1940年代から1950年代までのエリントンとくれば、1960年代から1970年代のジョーンズということになるのである。まったくの私感だけれど──。
それにグルーシンは、1973年から1978年まで実際にジョーンズのオーケストラで働いていた。彼はA&Mレコードにおけるジョーンズの4枚目のリーダー作『バッド・ガール』(1973年)からキーボーディストを務めた。さらにジョーンズのA&M第6作『メロー・マッドネス』(1975年)以降の作品において、そのオーケストラの中核をなすのは、グルーシンによるキーボードとアレンジだった。ジョーンズはビッグバンドのリーダー、音楽プロデューサーとしてあまねく知られるが、映画やテレビドラマのスコアも数多く手がけている。彼は映画人としては、グルーシンの先輩格にあたるわけだ。またリズム・アンド・ブルースにアプローチした1970年代のジョーンズ・サウンドは、グルーシンのコンテンポラリー・ジャズ作品に強く影響を与えた。
マンシーニとグルーシンとの関係について、いくつかのこと
ということで、ぼくはグルーシンの3枚目のトリビュート・アルバムは、てっきりクインシー・ジョーンズの作品集になるものと思い込んでいた。ところがいざフタを開けてみると、予想に反して作品の対象となったのはヘンリー・マンシーニだった。これにはいささか肩透かしを食らったのだけれど、実のところぼくには得心がいくところもあったのだ。というのも、ぼくはかねてよりテレビシリーズ『0022アンクルの女』(1966年)、テレビドラマ『さそり暗殺命令』(1967年)、映画『ディヴォース・アメリカン・スタイル』(1967年)あるいは『卒業』(1967年)といったグルーシンの初期のフィルム・スコアに、どこかマンシーニの音楽に通じるものを感じていたからだ。それはひとことで云えば、ラウンジ・ミュージック的なフィーリングである。
ラウンジ・ミュージックというのは、文字どおりホテルのラウンジでBGMとして流れているような音楽を指す。むろんそれは、ホテルに限らずカフェやパーティー会場などの歓談などが行われるようなスペースで、会話や社交の妨げにならないような、というかむしろ雰囲気を盛り上げるような、ゆったりとした曲調の音楽の総称である。マンシーニが手がけたスクリーン・ミュージックには、スウィング・ジャズやビッグバンド・サウンドをはじめ、ボサノヴァ、チャチャチャ、マンボ、ポリネシアンといった音楽の要素が盛り込まれている。その点で彼のがクリエイトするサウンドは、ラウンジ・ミュージックというジャンルの音楽に直結する。そしてそれには、従来のヨーロッパの伝統的な作曲技法や演奏法によるスコアとはひと味もふたも違う心地よさがある。
グルーシンが映画音楽の作曲家として頭角を現すのは1970年代の中ごろだが、そのサウンドの根幹をなすのはオリジナル作品と同様にコンテンポラリー・ジャズだった。しかしながら、さきに挙げた1960年代後半の彼のスコアには、ラウンジ・ミュージックにつながるテイストが散見されるのだ。マンシーニは1950年代から映画音楽の仕事をしているけれど、かつてグレン・ミラー楽団でアレンジャー兼ピアニストとして活躍しただけあって、いち早くそのスコアにジャズやラテンを採り入れていた。そんな彼が柔軟思考で創出する軽妙なフィルム・スコアは、それまで単なる劇伴だった映画音楽の既成概念をあっさりと打ち破ってしまった。つまりマンシーニ・サウンドは、スクリーンから離れても鑑賞音楽として成立する上質のものなのである。

これはあとになって知ったのだが、グルーシンは映像の仕事に関わるようになるまえにマンシーニと出会っており、映画音楽のマナーについて手ほどきを受けたことがあるという。グルーシンがテレビの音楽番組『アンディ・ウィリアムス・ショー』において、ミュージカル・ディレクターを務めていたころというから、1963年から1966年までの間の出来事だろう。以来、彼にとってマンシーニは尊敬する師範であり、よき友人となったのである。だからグルーシンの初期の作品がマンシーニのそれを彷彿させるのは、当たりまえのこと。さらに云えば、彼のフィルム・スコアがもつ推進力のあるメロディック・ライン、ウイットに富んだエクスプレッション、聴き手の琴線に触れる温かみのあるテクスチュアなどは、マンシーニから承継されたものなのである。
そして、師と仰ぐマンシーニに対するグルーシンの愛情がたっぷり詰め込まれたアルバムが、まさしく『酒とバラの日々~ヘンリ-・マンシ-ニに捧ぐ』なのである。そのセレクションをあらためて観ると、一般的には地味に映ると思われる。たとえば「ムーン・リヴァー」「シャレードのテーマ」「ピンク・パンサーのテーマ」「ひまわりのテーマ」「刑事コロンボのテーマ」(ほんとうは「NBCミステリー・ムービーのテーマ」)といった人気曲は収録されていない。そういう意味で本作は、“ベスト・オブ・ヘンリー・マンシーニ”的なアルバムではない。しかしながら、未聴のかたにはぜひ聴いていただきたいのだが、ここではマンシーニの作曲家としての魅力が十二分に引き出されている。ほんとうの意味でのいい曲が、しっかり押さえられているのだ。
これまでに挙げたグルーシンの4枚のアルバムのなかでは、この『酒とバラの日々~ヘンリ-・マンシ-ニに捧ぐ』が、ぼくはいちばん好きだ。グルーシンのミュージカリティが、もっともナチュラルに表面化した作品だからだ。平たく云えば、グルーシンの音楽性ともっとも相性がいいのはマンシーニの音楽ということになる。マンシーニは1994年6月14日に70歳でこの世を去ったが、このトリビュート・アルバムも含めてグルーシンの彼に対するリスペクトはつづく。ヘンリー・マンシーニ・インスティテュート・オーケストラのアルバム『ライヴ』(2003年)に、グルーシンはピアニストとしてゲスト参加している。ヘンリー・マンシーニ・インスティテュートは、1996年に作曲家のジャック・エリオットが設立した音楽アカデミーである。
またグルーシンは、自己のリーダー作『イヴニング・ウィズ・デイヴ・グルーシン』(2011年)や、グルーシンの長年のパートナーで音楽プロデューサー兼レコーディング・エンジニアのラリー・ローゼンが企画したアルバム『ジャズ・アンド・ザ・フィルハーモニック』(2014年)でも、ヘンリー・マンシーニ・インスティテュート・オーケストラと共演を果たしている。なお前者では、マンシーニの娘でシンガーのモニカ・マンシーニがソフトな歌声で「ムーン・リヴァー」を披露している。なお彼女は、父親の楽曲ばかりを歌った『モニカ・マンシーニ』(1998年)で、アルバム・デビューを果たしている。かくして、ここまで長々とグルーシンについて語ってきたが、その動因はむろん彼がぼくのもっとも好きな映画音楽の作曲家であるということにほかならない。
とはいえ、グルーシンが手がけた映画音楽に触れるまでのぼくといえば、アメリカの作曲家の作品というとマンシーニのアルバムばかり聴いていたのだ。そして小学校高学年のころから名画座通いをし、すでにクラシック・ピアノのレッスンを受けていたぼくが、好んで弾いていたポピュラー・ミュージックのなかには、マンシーニの楽曲も少なくない。そういう状況においてぼくは、グルーシンの音楽をはじめて聴いたとき、既知感やもの懐かしさとは微妙に異なる感覚にとらわれたのである。まったくおこがましいことなのだが、それはまるで自分自身が作った曲を聴いているような感じだった。振り返ってみれば、その要因はぼくのなかにマンシーニの音楽がすっかり染みわたっていたことにあると思われる。
そんなにグルーシンの音楽とマンシーニのそれとが相似するのかと疑問を呈する向きもあると思われるけれど、ぼくの感覚ではグルーシンのなかにマンシーニを感知する機会がしばしばある。さきに述べたように、グルーシンの1960年代のフィルム・スコアにおいては、そのアンダースコア(劇伴)からストレートにマンシーニっぽさが感じられることがある。1970年代以降の作品では、見たところマンシーニはどこにもいないように思われるかもしれないが、たとえばソース・ミュージック(劇中音楽)に意識を傾けてみると、その極上のラウンジ・ミュージック的なフィーリングは、まさにマンシーニ・タッチである。いずれにしてもグルーシンは、マンシーニからポジティヴな影響を受けた音楽家であり、そのサウンドの最大の理解者のひとりであると、ぼくは思う。
マンシーニをこころ変わりさせたのはヘプバーンだった
ところで、くだんの『酒とバラの日々~ヘンリ-・マンシ-ニに捧ぐ』の原題は『Two For The Road』という。すなわち、オードリー・ヘプバーン、アルバート・フィニー主演、スタンリー・ドーネン監督による1967年公開の映画『いつも2人で』のテーマ曲が、アルバム・タイトルとなっている。タイトルになるだけあってグルーシンのヴァージョンは、テンポ・ルバートでのリリカルなソロ・ピアノ、イン・テンポでのゆったりしたリズムを刻むベースとドラムス、スウィンギーなインプロヴィゼーションを展開するピアノ、そして流麗なカウンター・メロディを綾なすストリングスと、非の打ちどころのないアレンジと演奏とで聴かせる、いわば至高のマンシーニ・サウンドに仕上がっている。マンシーニ・ファンは、必聴である。
ではマンシーニのオリジナルのほうはどうかというと、ミックスド・クワイアによるヴァージョンは、わが国での人気はそれほどでもないが、本国アメリカでの評価は非常に高い。なんと評論家のあいだではマンシーニの最高傑作との呼び声が高いようだが、まあぼくもそこまでではないと思いながらも、この曲に強い愛着を感じている。作詞は名曲「ピュア・イマジネーション」で知られる英国のソングライター、レスリー・ブリッカスが手がけた。なおこの曲も含めたマンシーニのスコアは、ゴールデングローブ賞の最優秀作曲賞にノミネートされた。フィルム・スコアのアルバムは、RCAビクター・レコードからリリースされているが、サントラ盤ではなくオリジナル・レコーディング作品。マンシーニ作品において、この仕様は定例である。
映画はヘプバーンとフィニーとが演じる、ある夫婦の1954年から1966年までの12年間の軌跡が描かれたロード・ムービー。夫婦の愛情の変化が6つの時間軸を通して語られるのだが、カットバック手法が多用されており、各々の時間のエピソードは交錯し、スクリーンのなかのヘプバーンとフィニーは12年間を自由に往来する。そういった当時の映画としては革新的な構造も然ることながら、この作品の最大の魅力といえば、ヘプバーンのもっとも円熟した演技がフィルムに焼きつけられているということ。撮影中に37才の誕生日を迎えた彼女は当時、結婚生活が行き詰まっていたことから悲嘆のどん底にいた。そんな最悪のコンディションでも、共演者のフィニーに励まされたりして、最後まで役づくりに集中したヘプバーンに、ぼくは惜しみない拍手を送りたい。
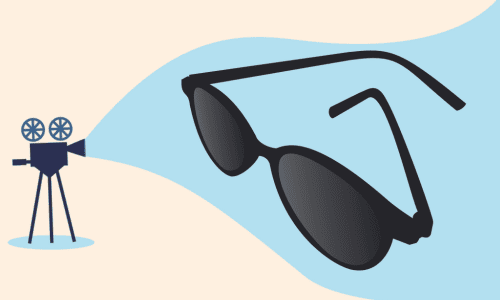
これはのちにマンシーニ自身が述懐したことなのだが、彼は当初この映画の音楽を担当することを断ったのだという。当時のマンシーニはすでに引く手数多の音楽家だったから、常に多忙を極めていたのだろう。真偽のほどは定かではないが、そのころ彼の懐に入り込むことができるのは、ブレイク・エドワーズくらいのものだったという。エドワーズは『ティファニーで朝食を』(1961年)以来、著名な『酒とバラの日々』(1962年)『ピンクの豹』(1963年) などを含む、コメディから文芸映画までそのほとんどの作品でマンシーニとコンビを組んだ映画監督である。それに反してドーネンは、マンシーニとは『シャレード』(1963年)や『アラベスク』(1966年)ですでに繋がりがあったものの、交渉を成立させることができなかった。
念のために云っておくと、マンシーニは決して気難かしいひとではなく、むしろ温厚なひと柄で知られるくらいだから、ほんとうに忙しかったのだと思われる。それはともかく、そんなめちゃくちゃ忙しい彼がこころ変わりしたのは、1通の電報を受けとったから。送り主はだれあろう、主演女優のヘプバーンである。彼女は『いつも2人で』のシナリオの素晴らしさを滔々と語り、この作品に最適な音づけをできる作曲家といえば、マンシーニしか思い浮かばないと告げた。けなげでひたむきなヘプバーンの思いに絆されたマンシーニは、オファーを快諾した。そればかりか彼は、前述のオリジナル・スコア・アルバムのなかに「オードリーのために」というタイトルの曲を収録した。なおマンシーニは、ヘプバーンの次作『暗くなるまで待って』(1967年)の音楽も手がけた。
たぶん、ぼくはヘプバーンの出演作品をほとんど観ていると思うけれど、アカデミー主演女優賞を獲得した名作『ローマの休日』(1953年)のときよりも、どちらかというと30代のころの彼女が好き。ぼくなりにヘプバーンの主演映画ベスト5を挙げると『ティファニーで朝食を』(1961年)『シャレード』(1963年)『おしゃれ泥棒』(1966年)『いつも2人で』(1967年)『暗くなるまで待って』(1967年)となる。以上の作品の音楽は、ジョン・ウィリアムズのペンによる『おしゃれ泥棒』以外は、すべてマンシーニが手がけている。どのスコアにおいても、リラックスした口当たりのいい比類なきマンシーニ・サウンドが展開されているが、そんななかテーマ曲の作風がもっとも異色なのは『いつも2人で』ではないだろうか。
オリジナル・スコア・アルバムの冒頭を飾る「いつも2人で(ヴォーカル)」では、さきにも触れたエレガントなミックスド・クワイアによってジェントルな音景が描き出される。しのび泣くようなヴァイオリンのソロも、こころに響く。なによりもこの曲、テーマのコードが7度からはじまるところにマンシーニのただならぬ才知が感じられる。不意に悲哀感が打ち寄せてくるような感覚に、胸を締めつけられる。平たく云えばこの曲、いきなりサビからはじまるような印象を与えるのである。このユニークな曲について、マンシーニは折に触れてもっとも好きな自作曲と述べている。確かに類稀なる名曲だ。アルバムには、ボサノヴァが基調となっているのは同様だが、ストリングスと鍵盤ハーモニカが印象的な「いつも2人で(メイン・タイトル)」や、シンフォニックな「いつも2人で(インストゥルメンタル)」も収録されている。
ほかにもストリングスをバックにアルトとピアノとがソロをとる「オードリーのために」チャチャチャのリズムと欧州風のメロディが溶け合う「素敵な人生」ヴィブラフォン、オルガン、テナーなどがフィーチュアされるクールな4ビート「ザ・チェイサー」スムースなルンバのリズムと木管と弦とによるアンサンブルが心地いい「サムシング・ルース」ブルージーなオルガンのソロも出来するエスプリの効いた2ビート「愉快なはだしの少年」アルト、トランペット、テナーがソロをとるアフロ・ロック「コンガロッカ」アコーディオンの音色が印象的なボッサ風ワルツ「フランスのいなか者」やはりテナー、トランペット、アルトとソロが繋がれるアフロ・ロック「ザ・ドンク」ヴァイオリンがソロをとるクライスラーの舞曲を彷彿させる「ディン・ディン・ミュージック」と、アルバムは飽きのこない構成となっている。
この『いつも2人で』のオリジナル・スコア・アルバムでは、もちろんメランコリックでハートウォーミングなテーマ曲もマンシーニの傑作と思うのだけれど、ぼくがもっとも好きなのは、やはり「オードリーのために」だ。マントヴァーニのカスケーディング・ストリングス顔負けの美しいサウンド・スケープをバックに、敏捷な指遣いで小気味いいピアノ・ソロが展開されるところには、それこそグルーシンが書いたソース・ミュージックが思い出される。そして映画音楽において、こういうラウンジ・ミュージック的なフィーリングが逡巡せず全開されるのは、マンシーニ・サウンドくらいのもの。とてもお洒落でモダンだ。なおサントラ盤は『ナタリーの朝』(1969年)とカップリングされたお得なCDが、英国のチェリー・レッド・レコードからリリースされているので、気軽に手にとっていただきたい。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。








コメント