バリトン・サックスの名手ジェリー・マリガンがデイヴ・グルーシンの協力を得て吹き込んだ、アラン・コルノー監督作品『メナース』のサウンドトラック・アルバム
 Album : Gerry Mulligan / La Menace Featuring The Music For The Original Soundtrack (1977)
Album : Gerry Mulligan / La Menace Featuring The Music For The Original Soundtrack (1977)
Today’s Tune : Watching And Waiting
テレビの映画番組の華やかなりしころを振り返る
はるか昔、ぼくが映画少年だったことは、ことあるごとにお伝えしてきた。小学校高学年のころから名画座通いをしていたのだけれど、少年にとって映画を楽しむ手段はなにも劇場に足を運ぶことだけではない。とはいっても、動画配信サービスはもちろんのことレンタルビデオさえなかった時代、というかそもそもHi-Fiステレオ・オーディオ機能をもつVHSビデオデッキが一般家庭に普及するのは1980年代に入ってからのことだから、もっぱら頼りになるのはテレビで放送されていた映画番組だった。そういう時代の趨勢から、当時はいまと違って各局が競って劇場映画を放映する番組を制作していた。まあほとんどの場合、映画は番組の放送時間に合わせてコンパクトに編集されてしまうのだけれど──。
それでもお茶の間で気軽に映画鑑賞ができるのだから、実にありがたいものだった。いやいや、思わず気軽にと云ってしまったけれど、実際はそうでもない。録画機器のない時代だからお目当ての映画をもし観逃してしまったら、しばらくのあいだそれを観ることができなかったりする。だからそれがどうしても観たい作品だった場合、放送日のまえから軽い緊張感に包まれたりするのだ。まずもって、家族間でのチャンネル権をしっかり獲得しておくことが重要。そして放送日には、決してほかの予定を入れないように注意する必要もある。若いひとたちからすると実にバカバカしく思われるかもしれないけれど、これが1970年代を少年として過ごしたものの、ごく当たり前のライフスタイルだった。まあ、平和な時代だったと云えるのかな。
ところで、当時テレビで放送されていた映画番組といえば、真っ先に思い浮かべるのは日本テレビ系の『水曜ロードショー』だろう。現在も唯一『金曜ロードショー』として継続されている映画番組だ。解説者として登場する映画評論家、水野晴郎の「いやあ、映画って本当にいいものですね」というセリフが流行った。最近はジブリ作品やハリー・ポッター・シリーズばかりが放映されて、ちょっと淋しい気もする。つづいてフジテレビ系の『ゴールデン洋画劇場』だが、洋画の吹き替えにおいて専門の声優ではなくタレントを起用することが多かった。正直云ってしっくりしない場合がほとんどで、ぼくにとってはもっとも苦手な映画番組だった。なお解説者は、俳優の高島忠夫が務めた。

テレビ朝日系列で放送されていた『日曜洋画劇場』では、なんといっても“ヨドチョー”のニックネームで親しまれた映画評論家、淀川長治の映画愛に溢れた解説が呼びもの。特に番組のエンディングで氏が必ず聞かせる「それでは次週をお楽しみください。サヨナラ、サヨナラ、サヨナラ……」という名調子は、あまりにも有名だ。淀川さんは1998年11月11日、89歳でこの世を去るまでずっと現役で、およそ32年間にわたりこの番組に出演しつづけた。氏が番組で解説した映画は、驚くなかれ計1629本だったという。まさに映画の神さまだ。その人気といったら『日曜洋画劇場45周年記念 淀川長治の名画解説DX』(2012年)をはじめとする、淀川さんの解説のみを収録したDVDが何種類か発売されるほどである。
映画番組の解説者ということでは、TBS系列で放送されていた『月曜ロードショー』におよそ18年間出演しつづけた荻昌弘が、ぼくはもっとも好きだった。荻さんは映画評論家であるばかりか、オーディオ評論家、旅行評論家、そして料理研究家としても活躍したひと。1970年代の後半から、岩城宏之指揮によるNHK交響楽団の定例の催しとなっていた「N響ゴールデンポップスコンサート」においても、映画音楽の解説に弁舌を振るった。荻さんの解説では鋭い見識で的確な考察がなされる。しかも落ち着いた雰囲気で視聴者に語りかけるようなその口調には、氏の高いインテリジェンスをストレートに感じさせるものがあった。残念なことに1988年、体調を崩した荻さんは5月31日放送分をもって番組を一時降板するが、その2か月後の7月2日、肝不全により永眠された。
そんななかもっとも異彩を放っていたのは、テレビ東京。1981年までは東京12チャンネルの名称で親しまれていた。テレビ東京系列で放送されていた『木曜洋画劇場』は、どちらかというといわゆるブロックバスター作品よりも、あまり好きな云いかたではないが、B級映画のほうが多く採り上げられていたように思われる。それは低予算および短期間で撮影された映画で、ときには俳優も監督も無名だったりする。そのラインナップといえば、アクション映画、SF映画、ホラー映画などが中心だった。またこの映画番組は、たまにヨーロッパのちょっとエッチな映画も放映したりして、当時まだ年端のいかないぼくをドキドキさせることもあった。ただ、マイナーな作品あるいは人気のない映画を積極的に放映するという点では、貴重な存在とも云える。
テレビ東京は1982年から『2時のロードショー』という映画番組も放送しはじめたのだけれど、過去に『木曜洋画劇場』で放映された作品の再放送が多かった。平日午後の放送ということもあり、ぼくは学校から帰ってくると必ずと云っていいほど、テレビ東京にチャンネルを合わせていた。もっともこの番組、なんと放送枠が85分だったから、CMや通販番組を除いた映画の放映時間は70分弱。本編は相当ハサミが入れられている。それでもレアな作品を体験できるということで、ぼくはまるで熱に浮かされたようにほぼ毎日この番組を観ていた。なかでも強く印象に残っているのは『呪いの島』(1972年)という劇場未公開映画で、何度も再放送されるものだから何度も観てしまった。
どんな映画かというと、特別チャーター機でとある無人島にバカンスでやって来た数人の男女が、なぜか島から抜け出せなくなってしまうという怖いおハナシ。みな何度も脱出を試みるが、だれひとりとして島から出られない。やがて彼らは、その島が現世のものではないと悟るのだった──。一種のホラームービーなのだろうけれど、テレビ放送用の映画だからスケールは小さいしハードな描写もまったくない。メガホンをとったポール・ウェンドコスは、テレビシリーズ『インベーダー』(1967年 – 1968年)を手がけたひとで、劇場映画も何本か撮っているけれどテレビ映画の監督を専業とした。いずれにしても、ひとびとが煉獄をさまようような展開を見せる『呪いの島』は『インベーダー』と同様に、ぼくにとってはトラウマ映画となっている。
そんなマニアックな映画を堂々と放映してくれるテレビ東京という放送局は、映画少年のぼくにたくさんの刺激を与えたけれど、きっと多くの熱心な映画ファンにとっても重宝したのではないだろうか。マニアックといえば『木曜洋画劇場』は、その解説陣にも通好みの渋さがあった。たとえば、ウェスタン通で知られる辛口評論家の深沢哲也などは、失礼ながらどう見てもテレビ映えしないように思われる。それよりちょっとあとに解説を担当した映画評論家、木村奈保子の「あなたのハートにはなにが残りましたか?」というキメ台詞も、どこか野暮ったい。また彼女は、ホラー映画を放送するときに「子どもは寝ましょうね」と、変な気遣いを見せたりもする。とにもかくにもそんな既成の枠にとらわれない演出は、テレビ東京ならではだ。
アラン・コルノー監督のフレンチ・フィルム・ノワール作品
さらに付言すると、テレビ東京は『日本映画名作劇場』という映画番組も放送していたのだけれど、これがまた映画に造詣の深いひとにしか好まれないようなプログラムだった。映画雑誌『キネマ旬報』の元編集長で映画評論家である白井佳夫の「みなさん、日本映画のほんとうの面白さをご存じでしょうか?」というキメ台詞につづく解説が、邦画礼賛派の氏だけに正鵠を射たものではあるが、少年のぼくにはいささか高尚に感じられた。あとを引き継いだやはり映画評論家の品田雄吉に至っては、知性の高さにマイルドな云いまわしが加わり、まるで大学の先生が講義をしているような感じだった。この番組はATG作品を多く採り上げていたけれど、芸術志向が強かったのかもしれない。非商業主義的な映画にもスポットを当てるという点は、確かに意義深い。
さて、すっかり長くなってしまったが、実はテレビ東京系列で放送されていた『木曜洋画劇場』や『2時のロードショー』において何度か放映された映画で、強く印象に残っている作品が1本ある。それはフランスの映画監督アラン・コルノーの作品で『メナース』(1977年)というアクション映画。フランスとカナダとの合作映画で、日本でも1979年にちゃんとロードショーで公開された。コルノーはノワール派の監督としてフランスではいまでも語り継がれるているようだけれど、日本では知るひとぞ知る存在で、この『メナース』も往年の映画ファンでないかぎり観たひとはほとんどいないのではないだろうか。とはいってもDVD化もされているようなので、興味のあるかたはぜひご覧いただきたい。
ついでに云っておくと、ノワール派とはフレンチ・フィルム・ノワールを撮る映画監督のこと。そしてフレンチ・フィルム・ノワールは、大まかに云うとフランス製のギャング映画のこと。第二次世界大戦後にフランスで隆盛を誇った、セリ・ノワール(暗黒小説)と呼ばれるギャングものの犯罪小説から影響を受けてはじまった映画ジャンルである。コルノーは奇しくも『セリ・ノワール』(1979年)という映画も撮っているのだけれど、暗黒小説の巨匠ジム・トンプスンの小説『死ぬほどいい女』(1954年)を原作としたまさにフィルム・ノワールと呼ぶべき作品だ。この映画をあのリュック・ベッソン監督が若いころに観て、たいそう感銘を受けたということだが、そういう意味で本作は、ニュー・フレンチ・アクション・シネマの原点と云えるのかもしれない。

個人的には、コルノー作品では17世紀のふたりのフランスの音楽家、宮廷作曲家サント=コロンブとヴィオラ・ダ・ガンバ奏者マラン・マレとの師弟愛、そして確執が描かれた『めぐり逢う朝』(1991年)がもっとも好きだ。それ以前にもコルノーは、イタリアの作家アントニオ・タブッキによる1984年発表の同名小説を映画化した『インド夜想曲』(1989年)において、精神的な世界を描いて従来の作風を一転させたのだが、この『めぐり逢う朝』もまた粛然たる美しさが際立った、1990年代のフランス映画を代表する芸術作品となった。まあその後コルノーは、ノワール派では先輩格に当たるジャン=ピエール・メルヴィルの映画『ギャング』(1966年)をリメイクした『マルセイユの決着』(2007年)を撮ったりもしたのだけれど──。
とにもかくにもコルノーは『めぐり逢う朝』でルイ・デリュック賞を受賞、さらにセザール賞では7部門を獲得、2004年にはフランスの国立学術団体アカデミー・フランセーズから、その永年の業績に対して第11回ルネ・クレール賞を授与された。そんなわけで「なんだ、めちゃくちゃ巨匠じゃないか!」という声も聞こえてきそうだけれど、実のところぼくも優れた映画監督であると思っている。でも『メナース』を撮ったとき、35歳のコルノーといえば日本ではまだ無名に近かった。ぼく自身、コルノーが『真夜中の刑事 PYTHON357』(1976年)の監督であると知って「ああ、あの映画を撮ったひとなのか」と思う程度だった。しかもぼくが『メナース』をはじめて観たのは、劇場ではなく『木曜洋画劇場』において。1982年2月のことである。
ところで『メナース』は、フランスのボルドーを舞台に、恋人の無実を証明するために奮闘しつづけるオトコのおハナシ。運送会社の女社長に愛され副社長の地位にいるトラック運転手が、若い女性と恋に落ち独立を決意。それを知った女社長は断崖から身を投げる。ところが警察は他殺と断定し、運転手の若い恋人を容疑者とする。運転手は自分が真犯人であると装って恋人を逃がし、その後カナダへ逃亡する。そして運転手は、自分がトラック強盗に遭って死んだという偽装をしようとするのだが──。そんないささか回りくどいストーリー展開に(というか運転手の行動に)嫌気が差すのだけれど、押しなべて面白い映画である。特にトラックのバトル・シーンは迫力満点で観応えがある。ちなみに“メナース”は、“脅威”を意味するフランス語だ。
なぜか女性にモテるイケオジのトラック運転手を、イタリア出身でフランスを活動の拠点に置いた俳優、シャンソン歌手のイヴ・モンタンが演じている。モンタンは『真夜中の刑事 PYTHON357』にも出演していて、オルレアン警察の部長刑事を演じている。この映画が好評を博したことから、コルノーはふたたびモンタンをメインキャストとした『メナース』を制作するに至った。なお脚本家のダニエル・ブーランジェも、前作からの続投である。そういった事情はもちろんのこと、ぼくはこの映画をはじめて観たとき、コルノーの名前さえ知らなかった。しかもぼくはこの作品を『木曜洋画劇場』や『2時のロードショー』において、まるで安く売り払われるように何度も放送されたことから、迂闊にもB級映画と勘違いしていたのである。
恥ずかしながら、ぼくがコルノー作品を再評価するようになるのは、前述の『インド夜想曲』や『めぐり逢う朝』を観てからのこと。それでも『メナース』がぼくの脳裏に焼きつけられた要因といえば、映画の面白さも然ることながら、目の覚めるようなメロウネスが横溢するフィルム・スコアだった。音楽を担当したのは、バリトン・サックス奏者のジェリー・マリガン。この映画のスコアはすべて彼のペンによるものだし、しっかり自身のバリトンがフィーチュアされたものである。ぼくははじめて『メナース』を観たとき、すでにマリガンのことは知っていたけれど、彼がジャズ・プレイヤーでありながら映画音楽を手がけていたことには、少しも驚かなかった。彼がコンポーザー、アレンジャーとしても非凡な才能のもち主であると認識していたからだ。
マリガンといえば1950年代の前半、トランペッターのチェット・ベイカーと組んだピアノレスのクァルテットが有名だし、ウエストコースト・ジャズのトレンドを牽引したミュージシャンという印象が強い。確かに彼はいっとき西海岸に拠点を置いて、ひたむきにバリトンをバリバリ吹きまくっていたのだけれど(ダジャレではないよ)、もともとニューヨーク出身のひとで、若いころはペンシルヴェニア州のフィラデルフィアでダンス・バンドのアレンジを手がけたりしていた。実際マリガンは1950年代の後半にニューヨークに戻って、徐々に自身の演奏スタイルを変えていく。緩やかなウネリのなかで、まろやかに格調を高めていくようなそのプレイが際立ったのは、やはり名盤『ナイト・ライツ』(1963年)においてだろう。
マリガンのリーダー・アルバムとしてリイシューされたサントラ盤
ぼくが最初に手に入れたマリガンのレコードが、この『ナイト・ライツ』だった。このアルバムのなかにフレデリック・ショパンのピアノ作品がアレンジされた「プレリュード ホ短調」という曲が収録されているのだけれど、このトラックが過去にTOKYO FMのラジオ番組『アスペクト・イン・ジャズ』(1973年 – 1979年)のテーマ曲として使われていた。ぼくがジャズを聴きはじめたころでもあり、奇しくも名画座通いをはじめたころでもある。パーソナリティを務めた、日本のジャズ評論の第一人者とも云われる油井正一のトークも妙々たるものだが、なんといっても夜のしじまに響き渡る、軽快なボサノヴァのリズムと物憂げなバリトンのトーンが心地いいテーマ曲が胸を打つ。ぼくは、この曲聴きたさに『ナイト・ライツ』を購入した。
この『ナイト・ライツ』のアルバム・タイトル・ナンバーが、またなんとも静謐を湛えた美しいメロディをもったバラードなのだけれど、マリガンのオリジナルである。彼はここでバリトンではなく、ピアノを演奏している。マリガンは西海岸時代からたまにピアノをプレイしていたのでなんということもないのだけれど、副業のわりにはそれなりの技量はもっている。それよりも注目すべきは、前述のように彼のソングライティングが決して凡手の業ではないということ。メロディアスでシンプルな構成の「ナイト・ライツ」は、何度聴いても飽きのこない名曲。そしてこの曲に横溢するジェントルなムードは、映画『メナース』のスコアで窺えるセンチメンタルなバラード曲にストレートにつながるものだ。
繰り返しになるけれど、ぼくは最初この『メナース』を、テレビ東京の映画番組で放映されたことに加えて、イヴ・モンタンが主演俳優とはいえ、明らかにブロックバスター狙いの作品とは一線を画すその仕様から、たとえばミニシアターで上映されるようなマイナーかつ小規模な映画と勝手に思い込んでしまった。だからぼくは、いくらかつて西海岸で一世を風靡したジェリー・マリガンが音楽を手がけているとはいえ、この映画のサウンドトラック・アルバムが発売されているとは夢にも思わなかった。ところがそれから日ならずして、都内の中古レコード店において投げ売りされている『メナース』のサントラ盤と、ぼくははからずもご対面となったのである。外観はかなりくたびれていたが、逡巡せず購入した。
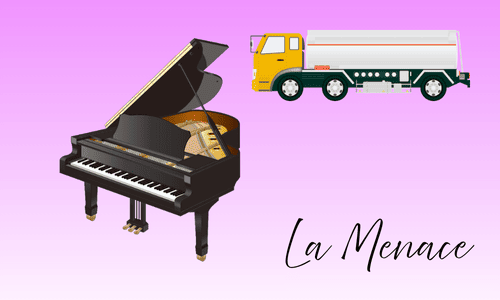
ぼくが入手したレコードは、フランス盤でCBSレコードからリリースされたものだった。おそらく日本では映画公開時にも、サントラ盤の発売はなかっただろう。このオリジナル盤のジャケットのフロントには“Featuring The Music For The Original Soundtrack Composed And Played By Gerry Mulligan”と記載されており、バックにはマリガンの写真が掲載されている。しかし裏ジャケットにフランス語で記されたレコーディングに関するコンテンツからは、大した情報は得られなかった。せいぜいマルチ・インストゥルメンタリストのドン・エリオットがレコーディング・エンジニアを務め、コネティカット州ウェストンにある彼の所有するスタジオにおいてレコーディングが行われたことが分かったくらいだ。
実はこのサウンドトラック・アルバム、ニューヨークに拠点を構える大手インディペンデント・レーベル、DRGレコードによって1999年にCD化されている。音源はリマスタリングが施されたが、内容は曲順も含めてオリジナル盤と同一。ただしアルバム・タイトルとジャケットは、まるで原形をとどめていない。なんとDRGはCBSのサントラ音源を、ジェリー・マリガンのリーダー・アルバム『ウォッチング・アンド・ウェイティング』としてリイシューしたのだ。したがってカヴァー・アートのほうも、表裏ともにマリガンの写真があしらわれた。事情を知らないひとが見たら、間違いなく彼のオリジナル・レコーディングと勘違いするだろう。ただこのCDには、レコーディング・メンバーの記載がある。その点は、褒め称えたい。
パーソネルは、ジェリー・マリガン(sax, key, synth)、デイヴ・グルーシン(key)、デレク・スミス(p)、トム・フェイ(p, elp)、ジェイ・レオンハート(b)、ジャック・シックス(b)、ボビー・ローゼンガーデン(ds)、マイケル・ディ・パスクァ(ds)、ピート・レヴィン(synth)、エドワード・ウォルシュ(synth)。マリガンと所縁のあるミュージシャンが、中心となっている。なおシンセサイザーについては、レヴィンがモーグを、ウォルシュがオーバーハイムを、各々受けもっている。ここでもっとも注目すべきは、グルーシンの存在。マリガンとグルーシンとはこの作品で親交を結ぶが、のちにフュージョン作『リトル・ビッグ・ホーン』(1983年)、マリガンの最後のリーダー作『ドラゴンフライ』(1995年)をともに制作する。
DRG盤ではマリガンの3人目の奥さまで、フォトジャーナリストのフランカ・ロータ・マリガンがライナーノーツを執筆しているが、そこでマリガンがプロデューサーであるドニーズ・プティディディエからフィルム・スコアの完成に与えられた時間が、たったの15日だったことを明かしている。結局、たまたまドン・エリオットのもとを訪れていたグルーシンが、マリガンの楽曲を映像の雰囲気に合わせたトラックにまとめ上げたようだ。すでに映画音楽を数多く手がけていたグルーシンにとって、この手の仕事はお手のものだったのだろう。彼はマリガンの依然として魅力的なメロディック・ラインをもった楽曲に、ドラマティックな躍動感を与えている。しかも利他的にサウンドをクリエイトしているところは、さすがと云うしかない。
たとえば、不安や緊張を誘いながら気品のある旋律が奏でられる「ダンス・オブ・ザ・トラック」そのヴァリエーション「トラッキング・アゲイン」洗練されたムードを纏いながらバウンスする「イントロスペクト」そのヴァリエーション「イントロスペクト – リプライズ」手に汗握る展開を見せる「ザ・トラップ」荘重なメロディと軽快なリズムが絡み合う「メナースのテーマ」といったダイナミズム溢れる色彩が施されたトラックでは、背後にグルーシンの影が見え隠れする。それらとは対照的なバラード・ナンバー「ウォッチング・アンド・ウェイティング」には、情緒に訴えかけるような美しさと切なさが横溢する。とはいっても、決して甘さに流されないところが、いかにもマリガンらしいしフィルム・ノワールによくマッチする。
それは「ウォッチング・アンド・ウェイティング – リプライズ」「ニュー・ワイン」「ヴァイン・オブ・ボルドー」「ヴァイン・オブ・ボルドー – リプライズ」といったトラックにも同じことが云える。そんななかマリガンは、ピアノをフィーチュアした軽やかで清涼感のあるボサノヴァ「ザ・ハウス・ゼイル・ネヴァー・リヴ・イン」や、ノスタルジックなシャンソン風ワルツ「ザ・パントマイミスト」といった曲も書いており、芸域の広さを感じさせる。サウンドトラックとはいえ本盤の収録曲はどれも、ジャズマンとしてのマリガンのユニークでクリエイティヴな音楽性と、メロディアスで繊麗さと上品さが漂うサックス・プレイをしっかり味わわせてくれる。ぼくにとっては、にわかに映画少年だったころを思い起こさせる懐かしい1枚でもある。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。








コメント