ストレート・アヘッドなジャズからメロウなスムース・ジャズまでこなす名ギタリスト、チャック・ローブの音楽性がナチュラルに表れたハードコアなフュージョン・バンド、メトロの『グレイプヴァイン』
 Album : Metro / Grapevine (2002)
Album : Metro / Grapevine (2002)
Today’s Tune : Yikes!
トータル・サウンドを見据え泰然自若の構えで臨むギタリスト
私事で恐縮だが、先日、久々にぼくのほうから親友のNくんにLINEで音信をしたのだけれど、用件はともかくそのときふと思ったことがある。それはギタリストのチャック・ローブがこの世を去ってから、どれくらいの年月が過ぎたのかということだった。というのも、もう四半世紀もまえのことになるのだが、ぼくは、Nくん、後輩で当時シンガーソングライターとして都内のクラブで歌っていたTくん、そして現在のぼくの妻とともに、はじめてローブの生演奏を聴いた。なぜかそのときのことが、にわかに思い出されたのである。ぼくにとって、音楽は切っても切れないもの。たとえとりとめのない日常であっても、自分のそばにはいつも音楽がある。自らの来しかたを振り返れば、自ずとそのときに聴いていた音楽が聴こえてくるというわけだ。
ところで、ぼくたち4人がローブの演奏に触れたのは、当時から有名だったジャズ・クラブ、南青山骨董通り界隈にあるブルーノート東京において。1999年の晩秋のことだ。どちらかというとファッションに無頓着なNくんが、茶色系のコーデュロイ・スーツに身を包んで現れたのには、たいそう驚かされた。ぼくはそういうことはよく覚えているので、古くからの知己にはよく感心される。まあそれはさておきローブの生演奏についてだが、彼が出演したブルーノート東京でのライヴは、キーボーディストであるボブ・ジェームスの来日公演だった。当時のジェームスはニュー・アルバム『ジョイ・ライド』(1999年)を発表したばかりだったが、これは従来セルフ・プロデュースが当たりまえの彼にとって、はじめて全面的に他人に下駄を預けたアルバムとなった。
このアルバムのプロデュースを手がけたのは、ギタリストのポール・ブラウン、キーボーディストのマイケル・コリーナ、サクソフォニストのデイヴ・マクマレイ、音楽プロデューサーでソングライターでもあるハーヴィー・メイソン・ジュニア、マルチ・インストゥルメンタリストのマーセル・イーストと、錚々たる顔ぶれだけれど、ローブもまた2曲においてプロデューサーを務めている。もちろんギターも演奏しているし、キーボードやドラムのプログラミングも彼の手によるものだ。そんな事情から、彼はジェームスのバンド・メンバーとして来日したのだった。なおローブ自身もこの年にリーダー作『リッスン』(1999年)をリリースしているのだが、こちらにはジェームスが自作曲を引っさげてゲスト参加している。
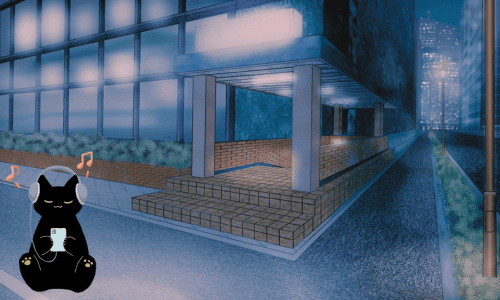
ときにブルーノート東京でのライヴは、シンコペーションの効いたグルーヴィーな「レイズ・ザ・ルーフ」からスタート。スティーヴン・デュービン、ティム・ハインツ、ポール・ブラウンによる共作だが、ときはスムース・ジャズの全盛期、このフォーマットにおいてはお馴染みのメンツだ。アルバム『ジョイ・ライド』に収録されていたオリジナルのほうは、いかにも作り込まれた感じのスムース・ジャズだった。それがわるいわけではないけれど、ライヴでの自由闊達で即興性に富んだ演奏のほうが、ヴィヴィッドな音楽としてより魅力的に感じられた。まあジェームスの場合、大概スタジオ・アルバムがよく練り上げられているのに対して、ライヴ・パフォーマンスは思いのほかハードでインプロヴァイゼーショナルなのだけれど──。
こういう現象はほかのスムース・ジャズ系のアーティストにおいても、しばしば見受けられる。優れたミュージシャンほど、アルバムではビジネスライクにラジオ・ステーションのフォーマットに則って抑制の効いたプレイをこころがけ、ライヴではクビキから解き放たれ、自身のもつ演奏能力を十二分に発揮するものなのだ。チャック・ローブもまた、卓越したギターのテクニックをもちながら、そんな礼節をわきまえるようなミュージシャンだった。くだんのライヴでは当然のごとく、ジェームスの『ジョイ・ライド』からのナンバーが中心に演奏されたが、ローブの『リッスン』に収録されていた彼のオリジナル「ハイ・ファイヴ」も採り上げられた。ローブのギターがスタジオ・レコーディングのときよりも、縦横無尽に駆けまわったことは云うまでもない。
ライヴが終わったあと、ぼくたちは店を変えて飲みなおしたのだけれど、そのときの話題といえば主役のジェームスよりもローブに集中した。それだけみな、彼の鮮烈なギター・プレイに衝撃を受けたのだろう。ぼく自身、すでにローブの演奏はリーダー作をはじめとする様々な音盤で耳馴染んでいたものだったが、正直に云うとその晩目撃した彼の華麗な超絶技巧には結びつかなかった。というのも、ローブはこのころすでにギタリストであるとともに音楽プロデューサーとしても腕を振るっていたので、どちらかというとトータル・サウンドを見据えるひと、たとえ緊迫した空気に包まれるようなレコーディングにも、泰然自若の構えで臨むプレイヤーという印象を与えていたから。やはり優れたミュージシャンの手腕は、ライヴを観てみないとわからないものだ。
そんなローブは2010年、コンテンポラリー・ジャズのトップランナーが集結したバンド、フォープレイに参加する。ボブ・ジェームスをはじめ、ギタリストのリー・リトナー、ベーシスト兼ヴォーカリストのネイザン・イースト、ドラマーのハーヴィー・メイソンの4人によって、1990年に結成された。必ずといっていいほど、ビルボード誌のコンテンポラリー・ジャズ・チャートを賑わす、数々の名作を残した人気グループだ。ギタリストにおいては、リトナー、彼の替わりに1997年から参加したラリー・カールトンと、1970年代の半ばからフュージョン・シーンを席巻してきた2大スター・プレイヤーがそのポストを占めた。カールトンの後任にローブが選ばれるという出来事は、ぼくにとって意外でもあり、同時に当然と思われるものでもあった。
ハッキリ云ってローブには、リトナーやカールトンのような大スターの貫禄はない。それでいてギターのテクニックでは、ふたりの先輩にまったく引けをとらない。コンポジションやアレンジメントにおいても同様である。たださきのふたりと異なる点は、ローブが音楽プロデューサーとして、類まれな才能を発揮したということ。彼はハードコアなフュージョンからスムース・ジャズやコマーシャルな音楽までしっかり成功に導く手腕のもち主。コンスタントに自己のリーダー作を制作するかたわら、プロデューサーとして多くのアーティストの作品を手がけた。さきに述べたように、ぼくがローブのことをトータル・サウンドを見据える音楽家と観るのは、実は彼のそんな側面からなのである。
音楽院でドロップアウト、その後スタン・ゲッツのバンドで活躍
ローブがプロデュースしたアーティストを思いつくままに挙げると、キーボーディストでは、ボブ・ジェームスをはじめ、ウォーレン・バーンハート、ミシェル・カミロ、セルジオ・サルバトーレなど。なぜかサクソフォニストが非常に多くて、ネルソン・ランジェル、クリス・ハンター、ウォルター・ビーズリー、ガトー・バルビエリ、キム・ウォーターズ、ジェイ・ベッケンスタイン、ジェフ・カシワといった具合。ほかにもクラリネット奏者のエディ・ダニエルズ、トランペッターのティル・ブレナー、ギタリストのポール・ブラウン、ベーシストではチャーリー・モレノやジェラルド・ヴィーズリー、ヴォーカリストではカルメン・クエスタ(ローブの奥さま)やマイケル・フランクス、バンドではスパイロ・ジャイラ、アコースティック・アルケミー、それにファットバーガーなどが挙げられる。
リトナーにしてもカールトンにしても秀逸な解釈と卓越した演奏能力によって、自己の音楽性に深みを与えるようなギタリスト。しかしながら彼らは、ともするとそのパーソナリティを前面に押し出しがちになる。それに反してローブは、利他的にサウンドをクリエイトすることができるミュージシャンなのだ。いまから思うと、フォープレイが音楽的にもっとも充実していたのは、実は彼がバンドに在籍していた時代だったとさえ感じられる。ぼくとしては、フォープレイのアルバムのなかでは『レッツ・タッチ・ザ・スカイ』(2010年)がいちばん好きなのだけれど、ローブにとってはこのバンドでの最初のレコーディング作品にあたる。このアルバムには、ローブのオリジナル・ナンバーが2曲収録されているが、どちらも傑出した楽曲である。
その後ローブはフォープレイのメンバーとして『エスプリ・ドゥ・フォー』(2012年)『シルヴァー』(2015年)といった2枚のアルバムを吹き込む。そのいっぽうでおなじころ、彼はキーボーディストのジェフ・ローバーと共同でプロデュースしたジャズ・スタンダーズ・アルバム『BOP』(2012年)をレコーディングし、ストレート・アヘッドなジャズにアプローチしてみせた。また、ローブとローバーは『BOP』に参加したサクソフォニスト、エヴァレット・ハープを加えたユニット、ジャズ・ファンク・ソウルを結成。2枚のアルバム『ジャズ・ファンク・ソウル』(2014年)『モア・シリアス・ビジネス』(2016年)をリリースした。さらにローブは、サクソフォニストのエリック・マリエンサルとのコラボレーション・アルバム『ブリッジス』(2015年)も制作している。

その間ローブはリーダー作のほうも、ドラマーのハーヴィー・メイソン、オルガニストのパット・ビアンキと組んだトリオによる本格的ジャズ・アルバム『プレイン・アンド・シンプル』(2011年)、4つの異なるバンドを率いて制作した『シルエット』(2013年)、曲ごとにそれまでローブが関わったミュージシャンや自身のファミリーをフィーチュアした、ある意味で集大成的作品とも云える『アンスポークン』(2016年)と、順調に発表していた。そんな彼にぼくが異変を感じたのは、日本のショップに『アンスポークン』の輸入盤が入荷して間もなくのこと。2016年の10月、東京シーサイド・ジャズ・フェスティヴァルにおけるフォープレイの公演の際、ローブは急病で出演を辞退。急遽ラリー・カールトンが代役を務めた。
結局、ローブは2017年7月31日に、悪性腫瘍のため61歳という若さでこの世を去った。フォープレイはしばらく沈黙を守ったあと、2018年1月公式サイトにおいて、2018年は活動休止し2019年に再編するとのスケジュールを公表した。かたやジャズ・ファンク・ソウルのギタリストは、ポール・ジャクソン・ジュニアに交替。2019年にアルバム『ライフ・アンド・タイムス』がリリースされた。同作はローブの思い出に捧げられた。それに反して、フォープレイの活動はいまだ再開されていない。ということで長々と語ってしまったが、チャック・ローブという不世出の名ギタリストが天上の楽士となってから、すでに8年という歳月が流れたわけだ。まさに光陰矢のごとしである。
そんなわけでぼくは今回、はからずもよみがえったローブの思い出から、彼について自分なりに語ってみたいと思った次第である。チャック・ローブは1955年12月7日、ニューヨーク州ロックランド郡のナイアックに生まれた。ハドソン川の景観が美しい小さな村だが、かつてはニューヨーカーの避暑地として賑わったという。明媚な湖や緑豊かな自然が広がる地で、おおらかに感性が育まれたであろう少年時代のローブ、11歳のときにギターを手にし16歳のときにはすでにジャズを弾いていた。バークリー音楽院に進学した彼は、ジョー・ピューマ、ジム・ホールといったヴェテラン・ジャズ・ギタリストに師事したほか、彼とは同世代でありながら18歳から講師を務めていたパット・メセニーにもレッスンを受けた。
しかしながら、その後のローブからは想像できないのだけれど、彼は2年間でドロップアウトしてしまう。同音楽院を退学したローブは、ボストンからニューヨークに戻り1970年代の半ばからフリーのプレイヤーとして働きはじめた。音楽シーンにおいてローブの名前が広く知られるようになるキッカケは、彼が1979年からの2年間、テナー奏者のスタン・ゲッツのバンドに在籍したことだった。当時の吹き込みとしてもっとも早いものは、おそらくコロムビア・レコードからリリースされた『フォレスト・アイズ』(1980年)だろう。ゲッツ名義のアルバムではあるけれど、実はオランダの作曲家ユレ・ハーンストラが、父親のベルト・ハーンストラが監督した映画『エン・パック・スラー』(1979年)のために書いた楽曲集である。
このアルバムの「ドロージー」というストリングス入りのボサノヴァ・チューンで、ローブのギター・プレイを聴くことができる。ただここでのローブは飽くまで伴奏者にとどまっており、ゲッツも相変わらず熟達したプレイを披露してはいるものの、どこかしっくりこない。それよりもお薦めするとしたら、毎年フランスのカンヌで開催される、世界最大規模の国際音楽産業見本市「ミデム」における1980年1月22日のライヴ演奏。このパーム・ビーチ・カジノを会場とした実況録音盤『ホワイト・ヒート – ジャズ・ガーラ 1980』(1980年)では、スタン・ゲッツ(ts)、アンディ・ラヴァーン(key)、チャック・ローブ(g)、ブライアン・ブロンバーグ(b)、ヴィクター・ジョーンズ(ds)による白熱するコンテンポラリー・ジャズを堪能することができる。
このライヴ・アルバム、ゲッツのリーダー作としてはフュージョン期のものということで、1950年代半ばから1960年代のはじめまでの彼がクール・ジャズやボサノヴァを演奏していたころの作品を愛でる向きには、まともに取りあってもらえないようだ。ところが、そのアパッショナートなプレイを高く評価するコアなファンもいるようで、何度となくリイシューされている。その度にタイトルやジャケットが変更されるのには、ほとほと参ってしまうのだけれど──。ちなみにぼくが所持するのは日本のRVCレーベルから発売されたもので、同時にポール・ホーンのフルートやゲイル・モランのヴォーカルがフィーチュアされた『スタン・ゲッツ・アンド・フレンズ – ジャズ・ガーラ 1980 Vol. 2』(1980年)もリリースされた。
ローブの音楽性がナチュラルに表れたハードコアなフュージョン
当時フュージョンを好んで聴いていたぼくにとって、これらのアルバムは理屈抜きに楽しめるものだった。いまから思うとゲッツは、このライヴにおいてまだ無名だったローブをプレイヤーとして前面に出すばかりでなく、彼のオリジナル・ナンバーまで採り上げており、まったくもって懐の深い音楽家だった。そしてぼくは、ローブのギター演奏を聴いたのはこれがはじめてだったけれど、彼の名前をその鮮やかなパフォーマンスとともにしっかり脳裏に焼きつけた。それから数年後、ぼくはヴィブラフォニストのマイク・マイニエリを中心とするコンテンポラリー・ジャズ・バンド、ステップス・アヘッドの『モダン・タイムス』(1984年)において、ゲスト・プレイヤーとして参加したローブのクレジットを発見した。
ローブはこのアルバムでは1曲のみのサポーターにとどまったが、次作の『マグネティック』(1986年)では、解散したばかりのウェザー・リポートのもとベーシスト、ヴィクター・ベイリーとともに正式メンバーとなっている。ステップス・アヘッドには、それまでフュージョン系アーティストによるストレート・アヘッド・ジャズ志向のバンドといった風情があったが、このアルバムからよりフュージョン色の強いコンテンポラリー・ジャズに回帰している。そういうサウンド面での変化を遂げたこのバンドにおいて、ベイリーともどもローブの存在感はかなり強かった。とはいってもローブは、このバンドからすぐに離脱してしまう。ソロ活動に専念するためだろう。ローブの後釜にはあのマイク・スターンが座った。
ローブはその後、パトリック・ウィリアムズ・ニューヨーク・バンドのアルバム『10th アヴェニュー』(1987年)の吹き込みに寄り道したあと、満を持して初リーダー・アルバムのレコーディングにとりかかる。なお『10th アヴェニュー』は、伝説の音楽プロデューサー、フィル・ラモーンと映画音楽やテレビの音楽を数多く手がけた作曲家、パトリック・ウィリアムズとがタッグを組んで、ニューヨークのファースト・コール・ミュージシャンを集めて制作したビッグ・バンド・スタイルのコンテンポラリー・ジャズ作品。そのレコーディング・メンバーのオールスター・キャストぶりには驚かされるが、いま思えばそこに名を連ねるほどだから、ローブはこのころからすでにイッパシのセッション・ミュージシャンとして信望を集めていたのだろう。

それはそうとローブはドイツのレーベル、ジャズ・シティからリリースされた『マイ・シャイニング・アワー』(1989年)で、ソロ・アーティストとしてデビューを果たした。当時チック・コリア・エレクトリック・バンドのメンバーだった、ベーシストのジョン・パティトゥッチとドラマーのデイヴ・ウェックルとをリズム・セクションに迎え、ストレート・アヘッド・ジャズからコンテンポラリー・ジャズまでヴァーサタイルなギター・プレイを披露。彼がいかに鋭敏なセンスと卓越したテクニックとを併せもつミュージシャンであるかが、この1枚でわかる。その後ローブはDMP、シャナキー、ヘッズ・アップといったレーベルにおいて、晩年までコンスタントにリーダー作を発表していく。サウンド的には、フュージョンからスムース・ジャズへと変遷する。
ローブのリーダー作は、どれもよく練り上げられており甲乙つけがたい。ちなみに、いま自室の棚をチェックしてみたら彼のアルバムは、コラボレーション作品やコンピレーション・アルバムを除くと17枚あった。またローブはソロ活動と並行して、ザ・ファンタジー・バンド、メトロといったバンドでも旗手となりプレイした。前者はスムース・ジャズ、後者はハードコアなフュージョンと、各々もち味が出されたバンドである。実はローブの関わった音盤で、ぼくがもっともお薦めしたいのが、メトロのアルバムなのだ。なぜなら、コンポジションやギター・プレイにおいてもっともローブの音楽性がナチュラルに表れるのは、このバンドのレコーディングのときだから。そしてその独特のサウンドは、ときの移ろいにまったく左右されることはなかった。
メトロのアルバムは『メトロ』(1994年)『トゥリー・ピープル』(1995年)『メトロカフェ』(2000年)『グレイプヴァイン』(2002年)『ライヴ・アット・ジ・Aトレイン』(2004年)『エクスプレス』(2007年)『ビッグ・バンド・ブーム』(2015年)といった7枚。このバンドでは、ローブ、ニューヨーク出身のキーボーディスト、ミッチェル・フォアマン、ドイツのヴンジーデル出身のドラマー、ウォルフガング・ハフナーといった3人が、パーマネント・メンバー。ベーシストは、アンソニー・ジャクソン、ヴィクター・ベイリー、メル・ブラウン、ジェリー・ブルックス、ウィル・リー、ニコラス・フィズマンと変動した。また、過去にローブ、フォアマン、ベイリーが参加した『プティート・ブロンド』(1992年)というライヴ・アルバムがあるが、案外メトロの原点かもしれない。
メトロのアルバムでぼくがもっとも好きなのは、4作目の『グレイプヴァイン』である。楽曲と演奏とのバランスが、もっともいいように思われる。このときはベーシストを、メル・ブラウンが務めた。アルバムはフォアマンの「トランス」からスタート。アフタービートの効いたアーバン・フュージョン。ローズ、ベース、ギターが熱くソロを繋いでいく。ローブの「ザ・サード・ロー」はフューチャリスティックなフォークロック。アコースティック・ギターとエレクトリック・ギターとのコントラストが鮮やかだ。グラディス・ナイト&ザ・ピップスの「アイ・ハード・イット・スルー・ザ・グレイプヴァイン(悲しいうわさ)」は8ビートのニュージャズ風にアレンジされている。スラップ・ベースのソロが花を添える。
フォアマンの「キャン・ユー・ヒア・ミー・ナウ」はこころ温まるパストラール。ピアノとギターとが絡み合うサウンドが美しい。ローブの「ヤイクス!」は爽快なフュージョン・ブギー。ソウルフルなリフやコーラス部のハーモナイゼーションが巧妙な名曲だ。ハフナーの「クリーム」はアンビエントな感覚に溢れたスロー・ナンバー。こころを揺さぶるようなインスピレーションを与える。フォアマンの「ミスター・フルーティ」はアップテンポのジャズ・ロック。高速で駆けまわるローズ、ロッキッシュなギターが素晴らしい。ローブの「ウェア・シー・ワズ」はゆったりしたメロディアスな曲。憂いに沈んだ前半からドラマティックな後半への展開が感動的だ。やはりローブの「ラグーン」はエキゾティックなボッサ風。ギターのレイジーなブルース・フィーリングが絶妙だ。
フォアマンの「ザ・シャイン」はアルバム中もっともイマジナティヴな曲。クラシックやロックのテイストが採り入れられた、映画音楽のような壮大なナンバーだ。やはりフォアマンの「アズール」はアコースティックなサウンドが際立つリリカル・チューン。ピアノとギターとの対話が心地いい、さながら一服の清涼剤といったところ。ローブの「ワン・オブ・メニー」は軽快なリズムの次世代ジャズ。バンドのインタープレイが冴えるなか、ここでもっとも突出しているのはドラムス。ポリリズムからソロまでその躍動感は絶品だ。フォアマンの「パトリオット」はピアノとギターとのデュオ。短尺な曲ではあるが、アルバムに余情を残す。いつも思うのだけれど、メトロのメンバーはみな、ソロ活動のときよりも表現力の振幅を大きくする。ローブのパフォーマンスもまた然りである。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。









コメント