名門ブルーノートにおいてコンポーザー、アレンジャー、プロデューサーとして活躍したデューク・ピアソンがトリオで吹き込んだデビュー作『プロフィール』
 Album : Duke Pearson / Profile (1960年)
Album : Duke Pearson / Profile (1960年)
Today’s Tune : Like Someone In Love
コンポーザー&アレンジャーとしての才能を発揮したピアニスト
気軽に聴くことができるということで、真っ先に手にとってしまうのが、デューク・ピアソン(1932年8月17日 – 1980年8月4日)のアルバムだ。ピアソンはトランペッターのドナルド・バードのグループのピアニストとして名を馳せたひとだけれど、そういえば彼が参加したバードの作品もまた、おなじようなこころもちで、ついついターンテーブルにのせてしまう。ふたりの関係は、1961年にピアソンがバードのグループにおけるピアニストのポストをハービー・ハンコックに譲ってからもつづいたが、たとえばバードのリーダー作『ア・ニュー・パースペクティヴ』(1964年)などで、その絶妙のコンビネーションを確認することができる。ここでのピアソンは、ピアノ演奏のほうはハンコックにお任せして、コンポーザー&アレンジャーに徹している。これがまた、いい仕事をしているのだ。
バードがアイディアを数年間温めていたという『ア・ニュー・パースペクティヴ』は、ジャズとゴスペル・ミュージックが交錯する既成の枠にとらわれない、実によく練られた作品。アメリカではこのアルバム、あのマーティン・ルーサー・キング・ジュニアの葬儀をはじめ、大きな宗教的儀式において幾度となく使われているのだという。ぼくもはじめてこのアルバムを聴いたとき、大胆にも男性4名、女性4名からなるゴスペル・クワイアが導入されていることに驚きを禁じ得なかったし、宗教的色彩を感じなかったといえばウソになる。ではスピリチュアルな音楽なのかといえば、まったくそんなことはなくて、ソフィスティケーテッドなソウル・ジャズとして気楽に楽しめるものだった。
きっとバードはこの大胆なコンセプトを成功させるために、すでに袂を分かっていたピアソンを敢えて呼び寄せたのだろう。レギュラー・クインテットにケニー・バレルのギターやドナルド・ベストのヴィブラフォンを加えたのも、ひょっとするとピアソンの思いつきなのかもしれない。そうはいっても彼のアレンジにはまったく気負ったところがなく、飽くまで自然体でサウンドに彩りが添えられている。しかも全面的に洗練されたフィーリングが横溢するのだから、さすがと云うしかない。本来だったらアクの強いものとして響きそうな聖歌隊のコーラスにしても、なんだかとてもオシャレに聴こえてくるから不思議だ。そいった点で本作は、ピアソンのアレンジャーとしてのセンスが光る1枚と云えるだろう。
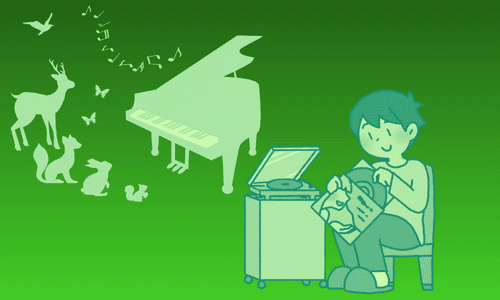
そんなピアソンの作編曲家としての実力が遺憾なく発揮されるのは1960年代の後半あたりからで、自己のリーダー作だとなんといっても『ザ・ライト・タッチ』(1968年)を筆頭に挙げたい。彼は1960年代の前半にもブルーノート・レコードやアトランティック・レコードに何枚か吹き込みを残しているけれど、一般的にはあまり評価される機会がなかったように思われる。ところがこの『ザ・ライト・タッチ』は、非常に高い人気を誇る。トリオに5ピースのホーン・セクションが加えられた色彩豊かなサウンドと4ビート・ジャズ以外にも多様な音楽スタイルが導入されたヴァラエティに富んだリズムとが、作品を充実させている。楽曲のすべてがピアソンのペンによるものというのも、一段とオリジナリティを高める要因となっている。
このアルバム、誇り高きクラブDJだったら必ずや所持しているであろう1枚と云われている。冒頭の「チリ・ペッパーズ」などは、ホットなダンス・チューンとしてクラブ・シーンを大いに揺るがせた。ホーン・セクションのアンサンブルによるクールなサウンドや、ジーン・テイラーのベースとグラディ・テイトのドラムスとが打ち出すグルーヴィーなビート感が、幅広い層の音楽ファンのこころを鷲掴みにするのだろう。ほかにも本作は、パッショネートなラテン・ナンバー「ロス・マロス・ホムブレス」のようないわゆる踊れる曲や、甘美で軽快なボサノヴァ・チューン「マイ・ラヴ・ウェイツ」のような心地よさが際立つ曲など、ピアソンのコンポーザーとしての本領が発揮されたナンバーを収録する。
個人的にすごく影響を受けたのは、その後『イントロデューシング・デューク・ピアソン・ビッグ・バンド』(1968年)を挟んでリリースされた『ザ・ファントム』(1968年)で、本盤はロンドンのDJ、ジャイルス・ピーターソンの寵愛を受けたことで知られる1枚だ。こちらはトリオにジェリー・ドジオンのフルート、ボビー・ハッチャーソンのヴィブラフォン、サム・ブラウンおよびアル・ガーファのギター、ヴィクトル・パントーハおよびカルロス “パタート” ヴァルデスのコンガとギロが加えられて、清涼感のあるサウンドが生み出されている。クインシー・ジョーンズのクロスオーヴァー作品を彷彿させる「ザ・ファントム」や、ブラジリアン・ミュージックを基調とした「ブンダ・アメラ」「ザ・ハッピー・アイズ」などがフレッシュに響く。
さらには、ブルージーなアフロ・キューバン「ブルース・フォー・アルヴィナ」メランコリックでエレガントなトリオ・ナンバー「セイ・ユーアー・マイン」アフロポリリズムが全開する「ザ・モアナ・サーフ」と、この『ザ・ファントム』は多彩な佳曲で構成されている。ぼくは、これらの楽曲におけるピアソンのアレンジの着想には、学ぶべきところが多々あると考えるし、たとえ単なるリスナーとして向き合っても、本作は何度聴いても楽しみ尽くすことのない実によく出来たアルバムと思うのである。もちろんピアソンはたくさんの引き出しをもった音楽家だし、どの曲にもしっかり意匠が凝らされているわけだけれど、決して大上段に構えたりはしない。彼の音楽は、いつでもシンプルでソフィスティケーテッドなものだからこそ、気軽に聴けるのだ。
それと同時にピアソンは、懐の深い音楽家でもある。彼はバードの『ア・ニュー・パースペクティヴ』のときもそうだったけれど、音楽ビジネスにおいてどんなニーズにも応え、あまつさえほとんどの場合、及第点に達する作品を作り上げる。たとえば、その後リリースされたリーダー作『ハウ・インセンシティヴ』(1969年)では、これまで以上に狭義でのジャズという範疇にとらわれることなく、ゴスペルやボサノヴァが積極的に採り入れられている。また本作では、シンガーのジャック・マンノ率いる17名からなるニューヨーク・グループ・シンガーズ・ビッグ・バンドによるコーラスが、大きくフィーチュアされている。そのサウンドは至極ポピュラーで、ジャズに関心のないリスナーにも親しみやすいものと思われる。
プロデューサー、ミュージカル・ディレクターとしても活躍
そういうまるで清濁併せ呑むような音楽に対する姿勢と、コマーシャルな作品をしっかり成功に導く手腕を買われたピアソンは、1963年から1970年まで名門ブルーノート・レコードによってリリースされた数多くのアルバムにおいて、セッション・ミュージシャン、アレンジャー、そしてプロデューサーとして活躍した。そういう意味でこのころの彼は、ピアニストというよりもトータルなミュージシャンだった。そのいっぽうで彼は同レーベルにおいて、それまでテナー奏者のアイク・ケベックが担当していたA&R部門を引継ぎ、才能あるアーティストたちの発掘に尽力した。それはピアソンが、あらゆるジャンルを超えて音楽の本質や裏側を見極める、優れた聴力と感性とをもち合わせた音楽家であることを示す、なによりの証拠ではなかろうか。
考えてみれば、ジョージア州アトランタ生まれのピアソンは、ニューヨークに進出してから一時期ではあるが、テナー奏者のベニー・ゴルソンとトランペッターのアート・ファーマーとによる双頭バンド、ジャズテットのメンバーだったことがある。それまでピアニストを務めていたマッコイ・タイナーが、ジョン・コルトレーンのグループに参加するためにバンドを脱退した1960年の初夏のことである。ところでゴルソンといえば、生粋のハード・バッパーであるとともにコンポーザー、アレンジャーとして腕を振るったひと。ハード・バップの最盛期における代表的なジャズの作編曲家として、オリヴァー・ネルソン、クインシー・ジョーンズ、はたまたラロ・シフリンなどと並び称される。そんなゴルソンから、ピアソンは少なからず影響を受けたと思われる。
さらに云えば、ピアソンは1961年から1962年にかけて、イギリス出身のフレッド・ノースワーシーが立ち上げたジャズ・ライン・レコードにおいて、ミュージカル・ディレクターを務めた。このレーベルは短命に終わったけれど、ミュージシャンを指導し原盤制作を管理する役割をピアソンに与えるというノースワーシーの采配はなかなかのもの。というかそれは、このころからすでにピアソンがクリエイター、オーガナイザーとして、すでに頭角を現していたということなのだろう。彼はこのレーベルで『ハッシュ!』(1962年)というオーソドックスなハード・バップ作品を吹き込んでいるけれど、フロントにトランペット奏者をふたり据えたサックスの入らないクインテットという編成には、すでにユニークなクリエイティヴィティが感じられる。
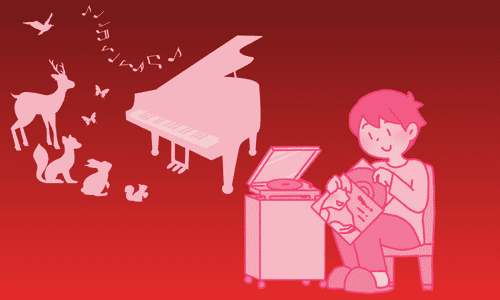
その後ピアソンは、ジャズ・ライン・レコードの廃業にともない、バードの『ア・ニュー・パースペクティヴ』に参加したあと、今度はブルーノート・レコードで『ワフー』(1964年)というリーダー作を制作する。ホーン・セクションが、僚友であるバードのトランペットに加え、ジョー・ヘンダーソンのテナー、ジェームス・スポールディングのアルトとフルートといった3管で構成されている。特にスポールディングのフルートに、高い訴求力が感じられる。のちにデューク・ピアソン・ビッグ・バンドの重要なレパートリーとなるジャズ・ロック「アマンダ」も然ることながら、ニュー・メインストリーム的なアプローチが光る「べドゥイン」が素晴らしい。いま聴くとこのサウンド、CTIレコードのクロスオーヴァー作品に通じるものが感じられる。
そんなコンポーザー、アレンジャーとして才気煥発なピアソンのアルバムには、当然のことながら駄作として片付けられるようなものは1枚もない。断定的に云ってしまったけれど、少なくともぼくは過去にそんな作品に出会ったことはない。しかもどのアルバムにも云えることだが、たとえ意匠の凝らされた新奇な曲が収録されていても、それらに戸惑いを覚えさせるような晦渋なエクスプレッションは微塵もない。だから冒頭でも述べたように、ぼくにとってピアソンのレコードは、気軽に聴くことができるということで、真っ先に手にとってしまうものなのである。ではピアニストとしての彼はどうだろう。ひとことで云えば、ピアソンは出しゃばらないピアニスト。とはいっても、消極的という意味ではないのだけれど──。
ピアソンのピアノ・プレイは、いつも奥ゆかしい。周囲が熱くなっていても、自分は決して弾きまくったりしない。その抑制の効いた端正なタッチは、優美で品位があってきわめて洗練された印象を与えるけれど、そんな音の錦糸を淡々と紡ぎ出すような佇まいからもまた、ピアソンはジャズ・シーン屈指のスタイリストとして捉えられる。まさに“デューク”の名に相応しい。これは余談だけれど、彼の本名はコロンバス・カルヴィン・ピアソン・ジュニアという。幼少から類稀な楽才を発揮していたピアソンのことを、親戚のおじさんがスウィング・ジャズの帝王、デューク・エリントンになぞらえて“デューク”と呼んでいたのだが、それがそのまま彼の通り名となった。エリントンのほうもニックネームなのだけれど──。
それはともかく、ピアニストとしてのピアソンに目を向けるとき、多くのジャズ・ファンがそうであるように、ぼくもご多分に漏れずドナルド・バードのアルバムを手にとる。故郷のアトランタからニューヨークに出てきたばかりのピアソンは、幸運なことにアート・ファーマーやベニー・ゴルソンといった人気プレイヤーと共演する機会をもち(のちにジャズテットにも参加)、さらに星の巡り合わせがいいことに、彼はたまたまステージに上がっているところをバードに見初められた。それからほどなくしてピアソンは、バードからバリトン奏者であるペッパー・アダムスとの双頭クインテットに参加することをオファーされる。なおピアソンの最初のレコーディングは、1959年10月4日に行われたバードのリーダー作『フュエゴ』(1960年)のセッションである。
ピアソンが参加したバードのアルバムのなかで、ぼくがもっとも高頻度でターンテーブルにのせるのは、間違いなく『ハーフ・ノートのドナルド・バード Vol.1』(1961年)と『ハーフ・ノートのドナルド・バード Vol.2』(1963年)の2枚だろう。1961年11月11日、当時ニューヨーク市マンハッタン区ダウンタウン、ハドソン・ストリート289番地とスプリング・ストリートとの交差点で営業していたジャズ・クラブ、ハーフ・ノートにおいて実況録音されたものだ。ついでに云うと、このクラブがあったソーホーという地域は、ちょうどこのころから芸術家やデザイナーが多く住む街として知られるようになった。名門ハーフ・ノートはセット・タイムを設定しないクラブで、ミュージシャンたちは好きなだけステージでプレイすることができた。
このライヴ・アルバムは、レギュラー・メンバーによるドナルド・バード&ペッパー・アダムス・クインテットの、最初のブルーノート録音。敢えてそのメンバーを記させていただくと、ドナルド・バード(tp)、ペッパー・アダムス(bs)、デューク・ピアソン(p)、レイモン・ジャクソン(b)、レックス・ハンフリーズ(ds)となる。当時はどちらかというとプリミティヴな側面を前面に押し出していたバードにとって、この顔ぶれは実に理想的だったと思われる。このクインテットによる、はじけるようなファンキー・フィーリングとさり気ないモダン・テイストが光るハード・バップ・スタイルの演奏には、ジャズのストレートアヘッドな魅力を伝えるものがある。そしてそれは、リスナーにジャズを聴く醍醐味を味わわせるものでもあるのだ。
選曲と楽曲に対する解釈のよさが際立つトリオ作品
このライヴでは、伸びやかなバードと切れ味のいいアダムス、堅実なジャクソンと歯切れのいいハンフリーズ、そしてスマートさのなかにもひとかたならぬ熱量を孕んだピアソン──と、各々の個性が一体となって、メロディアスでソフィスティケーテッドなアンサンブルと、ホットでハードドライヴィングなアドリブとが、余すことなく繰り広げられている。思えばこの2枚のライヴ盤は、高校時代にジャズを独学していたぼくにとって、管楽器の入ったコンボ・スタイルのあるべき姿が捉えられた作品として、コロムビア盤の『ザ・ジャズ・メッセンジャーズ』(1956年)と並んで、もっとも影響を受けたアルバムと云える。ぶっちゃけマイルス・デイヴィス・クインテットのアルバムより、ずっと好きだった。
当時のザ・ジャズ・メッセンジャーズにはバードをはじめ、のちの彼のレコーディングでは常連となる、テナー奏者のハンク・モブレーとベーシストのダグ・ワトキンスが参加している。なんだオマエは結局バードが好きなだけなんだろ!──という声が聞こえてきそうだが、敢えて否定はしない。でもそんなぼくだって、アート・ブレイキーの“ナイアガラ・ロール”と呼ばれる豪快なドラミング、ホレス・シルヴァーの抜群のリズム・センスやクリエイティヴなリフにも、すこぶる魅力を感じているのだよ──。ただピアノ演奏についてはどちらかというと、シルヴァーのアグレッシヴなアプローチよりも、ピアソンのモデレートなそれのほうが、ぼくの好みなのである。
いずれにしても、このハーフ・ノートにおけるライヴ・パフォーマンスは素晴らしい。そして、ここでもっともクールに響くナンバーといえば、なんといっても「マイ・ガール・シャール」と「ジーニーン」だろう。それぞれ、レコードではVol.1、Vol.2のトップを飾っているが、実はどちらもピアソンによって書かれた。ともに彼のコンポーザーとしてのセンスと才能とが結実した、非の打ちどころのない名曲である。これもまた余談だが、Vol.1の冒頭に収録されているステージMCは、ラジオDJのルース・メイソンによるもの。彼女は、のちにブルーノートの創始者アルフレッド・ライオンの2番目の奥さまになるひと。ちょっと取り澄ました感じがキマッテいて、スタイリッシュなジャズの饗宴をイントロデュースするものとして相応しい。
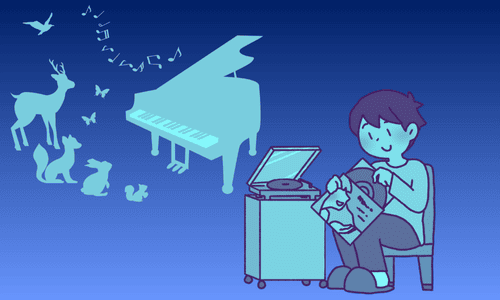
さて、すっかりあとになってしまったが、ピアニストとしてのピアソンに集中するのだったら、すべからくピアノ・トリオ盤を聴くべきだろう。ただ残念なことに、彼のトリオによる吹き込みはたったの3枚しかない。バードの『フュエゴ』の録音から21日後にブルーノートに吹き込まれた初リーダー作『プロフィール』(1959年)、その後2か月も経たないうちにおなじメンツでレコーディングが行われたブルーノート第2弾『テンダー・フィーリンズ』(1960年)、そして1961年にジャズ・ラインに吹き込まれたもののレーベルの廃業とともにお蔵入りとなり、のちに英国のポリドール・レコードの尽力により日の目を見た『エンジェル・アイズ』(1968年)といったラインナップである。
ピアソンにはクリスマスにちなんだ『メリー・オウル・ソウル』(1969年)という素敵なアルバムもあるけれど、ピアノ・トリオにアイルト・モレイラによるパーカッションが加えられていることから、一般的にトリオ作品には数えらていない。ピアソンがピアノのほかにチェレスタも弾いているチャーミングな1枚で、ぼくなどはオフシーズンでもついつい手にとってしまう次第。それはそうと、上記の3枚のうちどれがベストかというと、ダントツで『テンダー・フィーリンズ』を最高傑作と云う向きが多いようだけれど、ぼくにとってこの3枚はおっつかっつで、自室では同頻度でターンテーブルにのる。むしろ3枚つづけて聴くことが多い。強いて1枚を選ぶとなると選曲と楽曲に対する解釈のよさという点で、ぼくは『プロフィール』に軍配を上げる。
パーソネルは、デューク・ピアソン(p)、ジーン・テイラー(b)、レックス・ハンフリーズ(ds)となっている。テイラーはホレス・シルヴァーのレコーディングで知られるひとだけれど、ハンフリーズと同様に曲調にあわせて、たおやかな表現から煌びやかな演出まで使い分ける器用なプレイヤー。アレンジの妙で聴かせるピアソンにとっては、ふたりとも理想的なサイドメンだ。オープニングを飾るジミー・ヴァン・ヒューゼンの「ライク・サムワン・イン・ラヴ」では、とにかくミッドテンポに乗って伸びやかに歌うピアソンのピアノがエレガント。途中ビートがワルツにモジュレートされるところもオシャレ。ウィントン・ケリーのような極上のスウィング感はないけれど、そのぶんピアソンのフレージングは可憐に映る。
ソニー・バークの「ブラック・コーヒー」では、レイジーなムードが漂うなかピアソンがほどよくブルージーなフレーズを綴っていく。こういう彼の抑制の効いた端正なタッチが、まさに洗練された印象を与えるのだ。キューバの作曲家、マルガリータ・レクオーナの「タブー」では、アフロポリリズムが採り入れられたアレンジが鮮やか。粒立ちのいいベースのリフが、耳に残る。ピアソンはこういうリズミカルな曲でも、やはり弾きまくったりはしない。そういうプレイが、聴き手に得も云われぬリラクゼーションを与えるのだろう。ジミー・ドーシーの「アイム・グラッド・ゼア・イズ・ユー」では、ピアソンのひたすら愛らしいバラード・プレイを堪能。愛くるしいけれど決して甘さに流されないところが、また彼らしい。
レコードではここからがB面──。ピアソンのオリジナル「ゲイト・シティ・ブルース」からスタートする。のちにバードの『バード・イン・フライト』(1960年)で再演された、12小節のブルース。スウィングというよりもシャッフルな感じのリズムが、ポップに響く。ピアソンのフロウはファンキー色は薄めで、余裕をもって巧妙にジャジーなイディオムを並べていくといった印象を与える。それには、ダンディズムのようなものさえ感じられる。やはりピアソンの自作曲「トゥー・マイル・ラン」は、アルバムのハイライト。アップテンポの軽快な進行のなか、ランニング・ベースや4バースも出来する。ここでのピアソンの小気味いいアドリブには、バド・パウエルに通じるバップ・スピリッツを感じさせる。
ラストを飾るピアニスト、サイ・コールマンの「ウィッチクラフト」では、これまたピアソンらしいすっきりとした上品な味わいを感じさせるプレイが展開される。ほどよく跳ねるベースのソロも小粋。ピアソンのピアノはどこまでも流麗だが、特にコーダにおけるまるで彼自身が後ろ髪を引かれているかのようなエクスプレッションには、こころをくすぐられる。この曲、ビル・エヴァンスの名演もあるけれど、ぼくは断然ピアソンの演奏のほうが好きだ。エヴァンスがリリカルでありながら意欲的なのに対し、ピアソンはひたすら可憐。さながら欅坂46と乃木坂46との違いみたいなものだ(わかるひとにはわかる?)。いずれにしてもおそらく、ぼくはこういう感覚からピアソンのアルバムを気軽に聴けるものとして、真っ先に手にとってしまうのだろう。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。








コメント