聴いて怖く、踊って楽しく──ジャパニーズ・グルーヴとして再評価された、横溝ワールドがイメージされたコンセプト・アルバム
 Album : ミステリー金田一バンド / 横溝正史MM〈ミュージック・ミステリー〉の世界 金田一耕助の冒険 (1977)
Album : ミステリー金田一バンド / 横溝正史MM〈ミュージック・ミステリー〉の世界 金田一耕助の冒険 (1977)
Today’s Tune : 悪魔の手毬唄
もとは横溝ブームに便乗した企画モノ、いまはレア・グルーヴの大名盤
ぼくは、過去にこれほど愉快なレコードにお目にかかったことがない。この『横溝正史MM〈ミュージック・ミステリー〉の世界 金田一耕助の冒険』(1977年)というアルバム(以下『金田一耕助の冒険』と表記)は、ぼくがもうすぐ中学校に入学するという時期に、地元の小さなレコード屋さんの陳列箱にひっそりと収められているのを発見し、ちょっと迷いながらも購入に至った一枚。ぼくは本盤をながらく愛聴してきたが、10年近くまえ、部屋が手狭になってきたことからアナログ盤を大量に処分することを決心し、その際ついに手放すことにした。実は2000年に発売されたCDを購入していたので、それほど未練たらしくなることもなくレコードのほうはディスクユニオンさんに引き取っていただいた。
ぼくは、これでもレコードのよさを知っているつもりだけれど、アナログ盤でなければダメというほどのコダワリもない。そんな贅沢を云えるほど裕福でもないし、ある程度音質が保持されていればCDで構わない。つまり、聴ければいいのだ。だから、CDと重複したレコードは、たとえそれがオリジナル盤であってもすべて処分してしまった。ところが、ディスクユニオンさんから届いた明細書を見てちょっと驚いた。数々のモダン・ジャズの名盤を抑えて、思いのほか高額で買取りされていたのが『金田一耕助の冒険』だったのである。これには、あまり音楽に関心のない妻も目を丸くしていた。まったく愉快だ。
このレコードは、タイトルからもわかるように折からの横溝ブームに便乗した、いわゆる企画モノだ。横溝とは云うまでもなく、日本を代表する探偵小説作家であり名探偵金田一耕助の生みの親である、横溝正史(1902年 – 1981年)のこと。本作が発売されたのは1977年の7月のことだが、角川文庫の横溝作品は、その前年にはすでに累計発行部数が1,200万部を突破していたという。映画化作品では『本陣殺人事件』(1975年)『犬神家の一族』(1976年)『悪魔の手毬唄』(1977年)のヒットにつづき、『獄門島』(1977年)『八つ墓村』(1977年)の公開が間近に迫っていた。また、全6作のテレビドラマ『横溝正史シリーズ』(1977年4月 – 1977年10月)も4作目に突入。音楽業界にとっても、この機を逸する手はないというわけだ。
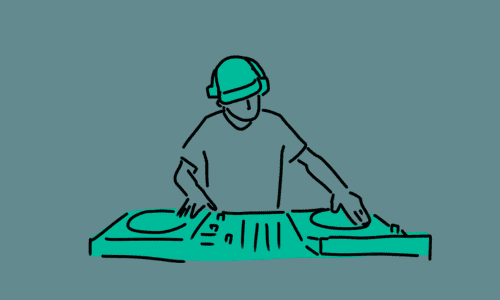
まことにそそっかしいことに、ぼくは実際に音を聴くまで、このレコードを映像作品の楽曲で構成されたコンピレーション・アルバムと勘違いしていた。ところが、レコードをかけてみたらこれがまったくのオリジナル曲ばかりだったので、衝撃と戸惑いを同時に覚えた。まあ、これは完全にぼくの早合点が招いたことで、ジャケットのバックカヴァーをちゃんと確認していれば、事前に中身のほうも想像できたというもの。なんとそこには、横溝先生の推薦文が添えられていたのだ!ぼくは店頭では、文庫の表紙も手がけた杉本一文によるフロントカヴァーのおどろおどろしいイラスト(『悪魔が来りて笛を吹く』がイメージされたもの)ばかりに気をとられていて、それにまったく気づかなかったのである。
その横溝先生の詞藻豊かなおコトバのなかに「小説から受ける印象をいきなり音楽にするというのだから、私は戸惑いを感ずると同時に、いっぽう興味を覚えたこともたしかである」というクダリがある。つまり、本作はある種のイメージ・アルバムだったのである。さらに、バックカヴァーをよく見てみると「[企画 協力]角川春樹事務所」という記載がある。それすなわち、本作は「角川商法」と呼ばれるメディアミックス戦略の一環で制作されたアルバム──ということのなによりの証拠だ。いや、それだけではなく本作のリリースは、それ以降に映像化されるであろう横溝作品とその音楽の販促活動をも兼ねていたのかもしれない。まったく如才がない。
そんな40年以上もまえにリリースされた横溝ブームに肖ったコンセプト・アルバムが、なぜ現在も高額で取り引きされているのか?それは、音楽の内容がDJによってジャパニーズ・グルーヴとして再評価されているからだ。ぼくもあとで知ったのだが、本作はクラブ世代にとって、いわゆる「和モノ」と呼ばれるレア・グルーヴの大名盤となっていたのである。しかも、踊れる日本産音源ということで、海外のアーティストにもネタとして使用されているという。リッチなグルーヴが満載の本作は、いまもなお国内だけでなく海外の音楽関係者たちも血眼になって探しまわるコレクターズ・アイテム。そんな熱い思いが成就し、2015年にアナログ盤が復刻。さらに、2019年にリプレスされた。
フュージョン全盛以前のオリエンタル&ファンキー・フュージョン
ぼくの場合、たいがいそういう騒動の渦中に巻き込まれることはないのだが、内容の素晴らしさを知っているものからすると、ちょっとした嬉しい事件ではある。まあ、リアルタイムでその音を体験したぼくにとって本作は、クレート・ディガー垂涎のアイテムであろうとなかろうと、名盤であることに違いはないのだけれど──。なんといっても、(おどろおどろしい横溝ワールドがイメージされただけに)委細構わず大胆にオリエンタル・テイストが加味された、ファンキーなフュージョン・サウンド──なんて、ほかに類を見ないのだから。しかも、当時の日本ではまだフュージョンという音楽ジャンルは定着していなくて、いま思えば1969年に結成された稲垣次郎とソウル・メディアが演っていたジャズ・ロックが、その先駆けだったように思う。
本作がリリースされた1977年に至っても、日本ではまだフュージョンというコトバは一般的ではなく、クロスオーヴァーというしかつめらしい名称が使われていた。そんなニュー・ジャンルで名を揚げていたのは、シンセサイザーのトップアスリート、深町純くらい。彼は、エンジニアの行方洋一によるマルチ・レコーディングが駆使されて話題になった、東芝EMIのプロユース・シリーズから、数枚アルバムをリリースしていた。そういえば、同シリーズの鈴木宏昌の『スキップ ステップ コルゲン』(1977年)は、ちょうど本作とおなじころに発売されたものと記憶する。日本を代表するギタリスト、渡辺香津美が坂本龍一とともに制作したフュージョン・アルバム『オリーヴス・ステップ』(1977年)は、まだ世に出ていなかった(それよりまえの彼の作品は、どちらかというとエレクトリック・ジャズといった趣きだった)。
本作と同様のクロスオーヴァー/フュージョン系の企画モノとしては、SF映画やアニメ作品のテーマ曲をカヴァーした『スペース・ファンタジー』(1978年)と『ライヴ・スペース・ファンタジー』(1978年)がすぐに思い出される。これらはもともと、マニピュレーターの松武秀樹を中心とした、当時趨勢を占めていたシンセサイザー・サウンドがフィーチュアされたプロジェクトだった。しかしながら、後者のライヴ盤は、それこそ深町純や渡辺香津美、それにレジェンダリー・ドラマー、村上“ポンタ”秀一が参加したこともあり、熱心なフュージョン・ファンのあいだでは長いあいだ隠れた名盤とされてきた(スタジオ録音盤とライブ盤が2枚1セットでCD化済み)。ただ、この2作が発表されたのは『金田一耕助の冒険』がリリースされた翌年のことである。

そんな状況を鑑みると『金田一耕助の冒険』で繰り広げられた音楽は、当時、新しかったのだな──と、いまさらながら感心させられる。しかもそのサウンドは新しいだけではなく、繰り返しになるが、西洋音楽にときにほどよく、ときに思いきりよく和の味つけがなされるというユニークなもの(制作費も破格だった?)。それもサウンドトラックのように映像に合わせるという制約もないから、どの楽曲にも実に豊かなイマジネーションが感じられる。前述のように、このアルバムを映像作品にちなんだものと勘違いしていたぼくは、はじめてこのサウンドに触れたとき衝撃と戸惑いを同時に覚えた。だが、そのときの感想をもっともったいぶらずに云えば、横溝映画のサントラ盤よりずっとカッコイイ!──というふうになる。
本作のレコーディング・メンバーといえば、まずリズム・セクションが日本を代表する敏腕スタジオ・ミュージシャンたちでがっちり固められ、それにホーンズ&ストリングス、女性コーラス、和楽器、それに地謡などが加えられるという、なんとも贅の尽くされた編成となっている。結果、実に安定した演奏のクオリティの高い音楽が出来している。楽曲の作曲とアレンジを担当したのは、高田弘(3曲)、成田由多可(2曲)、羽田健太郎(5曲)の三人。高田さんと成田さんは、どちらかというとポップスというか歌謡曲を多く手がける作曲家だったので、ぼくにはあまり縁がなかったのだが、のちに“ハネケン”の愛称で親しまれるようになる羽田さんは当時から注目していたアーティストのひとり。
羽田さんの名前は、稲垣次郎&ヒズ・フレンズの『ファンキー・ベスト』(1975年)や、8人の鍵盤奏者が20台のシンセサイザーをプレイするというとんでもない企画モノ『エレクトロ・キーボード・オーケストラ』(1975年)で、ぼくの記憶にとどめられていた。しかし、その個性はまだあまりよくわからなくて、羽田さんの音楽性に惹かれるようになったのは、この『金田一耕助の冒険』からだった。というのも、このプロジェクトにおいて高田さんと成田さんは楽曲提供のみの参加だが、羽田さんは作編曲だけでなく全曲でキーボードを担当している。もちろん、ミステリー金田一バンドは、その野暮ったいネーミングは便宜上のもので、その場かぎりの楽隊だろう。ただサウンドの統一感から、バンドを仕切っていたのは羽田さんと思われる。
羽田健太郎によるフュージョンという点でも希少性が高い
羽田さんは、桐朋学園大学音楽学部ピアノ学科を首席で卒業しながら、ときを移さずポピュラー・ミュージックの世界に飛び込んだ変わり種。その音楽理論に裏打ちされた作編曲法と高度なテクニックを有するピアノ演奏から、音楽ビジネスの世界では引っ張りだことなる。にもかかわらず、フュージョン系のリーダー作は皆無なので、その点でも本作は非常に希少性が高いと云える。それでは、各曲を順番に観ていこう。オープニングは高田さんの「金田一耕助のテーマ」で、イントロの吹きつのる風、パトカーのサイレン、そして急ブレーキといったSEが効果的。水谷公正のファンキーなギター、羽田さんのワウワウ感いっぱいのクラヴィネット、ユーミンのレコーディングにも参加したコーポレーション・スリーによるスタイリッシュな女性コーラスなどが印象的なソウル・ディスコだ。金田一をヒップな風来坊と捉えると、こうなる?
つづく成田さんの「八つ墓村」は、篠笛、琵琶、ミュージカル・ソー、そしてスキャットの女王、伊集加代子(現在は伊集加代)の悲鳴まじりの女性ソロといった凝った道具立ての、アルバム中もっとも怪奇ムードが横溢するナンバー。とはいっても武部秀明のベース、羽鳥幸次(tp)や新井英治(tb)などの名手によるブラス・アンサンブルが、ファンキーなグルーヴを生み出している。高田さんの「仮面舞踏会」はもっともポップな曲で、軽快な4つ打ちに乗って、羽田さんによるチェンバロ風の音色のキーボード(2コーラス目はストリングス)がセンチメンタルなテーマを、伊集さんのスキャットがリフレッシングなサビを、それぞれ歌い上げている。やはり高田さんの「本陣殺人事件」は抜群のレア・グルーヴで、後半のローズとギターのソロ・バトルが楽しい。エフェクターが深くかかった京琴(ゲゲゲの鬼太郎サウンド)もインパクトあり。
前半最後の成田さんによる「獄門島」では、なんとも禍々しいムードが全開。鼓と謡がゴスペル・タッチのピアノと絡む。いやいや、ストリングスとホーンズの“ジャジャジャジャ”という盛り上げ、演っているほうは楽しいのだろうな。でもなんといっても、ディストーション&ファズで歪みまくるギターがいい。そしてアルバムは後半となるが、ここからはすべて羽田さんの曲。フュージョン・ブギー「悪魔の手毬唄」は、ぼくのいちばんのお気に入り。村岡建のアルトと市川秀男のローズのアドリブがジャジー。ストリングスとホーンズのアンサンブルがすごくゴージャス。羽田さんのクラヴィネット、川島和子のハイトーン・ヴォカリーズ(宇宙戦艦ヤマト序曲サウンド)も、とてもいい感じ。

つづく「迷路荘の惨劇」は、ムソルグスキーの組曲『展覧会の絵』の「プロムナード」の引用から『ゴッドファーザー PART II』(1974年)のテーマ曲「愛は誰の手に」を彷彿させる哀愁が漂うメロディに移るハードボイルドなナンバー。数原晋のフリューゲルホーンの音色が美しい。次の「悪魔が来りて笛を吹く」では、意外にもフルートは少なめ、なぜか能菅と琴が登場。むしろ森谷順によるドラムスが打ち出すスピーディなリズム・パターン、羽田さんが弾く電子オルガンの音色、ネオクラシシズムなホルンのアンサンブルのほうが印象的。さらに「三つ首塔」は、メロウでセンシティヴなナンバー。メロディを歌うモノホンの口笛がクール過ぎる。それに負けないくらい、名ジャズ・プレイヤー、中牟礼貞則のアコースティク・ギターがエレガントだ。余談だが、この曲ではイントロからテーマに入るときにキーが(E→Fという具合いに)半音上がるが、こういう手法はぼくも好きでアレンジをする際によく使ったもの。
そしてラストの「犬神家の一族」は、ショパンやベートーヴェンの曲をイメージさせられる幻想的で情熱的なクラシカル・ナンバー。ハープの音色がいたく瑞々しく、弦楽器のアンサンブルもいたって流麗だ。この原作小説の過去の映像化作品において、映画では大野雄二、テレビドラマでは佐藤允彦が、それぞれ印象的なテーマ曲を作った。羽田さんはピアノ・コンチェルト風という正攻法で臨み、このピースを既存の作品とはまったく違う素晴らしい曲に仕上げている。クラシック出身のアーティストである彼の面目躍如といったところか──。それにしても、レコードのタスキに記されたセールスコピーの「聴いて怖く、踊って楽しく──」というクダリは、実に云いい得て妙。世代を超えて、各々が好きな楽しみかたをすることできる──というところが、本作の最大の魅力と云えるのではないだろうか。
ちなみに羽田さんの楽曲は、彼が劇伴を手がけたテレビアニメ『スペース・コブラ』(1982年 – 1983年)やテレビドラマ『西部警察 PART-II』(1982年 – 1983年)などで、音楽監督の鈴木清司によって流用された。なお本作はCD化の際に、金子由香利の「愛のバラード」「仮面」、塚田三喜夫の「愛の女王蜂」「少女夜曲」、茶木みやこの「まぼろしの人」「あざみの如く棘あれば」「あなたは何を」、古谷一行の「糸電話」「見えない雨の降る街を」といった、計9曲の「横溝=金田一」関連のヴォーカル曲が追加された。この『金田一耕助の冒険』はサントラ盤ではないから、本来ここで採り上げるべき作品ではなかったのだが、これらの貴重な音源であるボーナス・トラックに免じて、お許しいただきたい。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。








コメント