アストラッド・ジルベルトを偲んで、ボサノヴァのみにとどまらない、その魅力について語る
 Album : Astrud Gilberto / Windy (1968)
Album : Astrud Gilberto / Windy (1968)
Today’s Tune : Dreamy
彼女は「イパネマの娘」を英語で歌った
アストラッド・ジルベルトが、天上の歌姫となった。2023年6月5日、フィラデルフィアの自宅でのこと。83歳だった。出生名はアストラッド・エヴァンジェリーナ・ワイナート。ブラジルのバイーアに生まれ、リオ・デ・ジャネイロで育った。1959年にシンガーでギタリストのジョアン・ジルベルト(1931年6月10日 – 2019年7月6日)と結婚して、いまの名前になった(まだ19歳だった)。しかしながら、ジョアンの不倫が原因で、1964年にふたりは離婚。ブラジルのマスコミは、“ボサノヴァの神様”であるジョアンを擁護し、アストラッドを扱き下ろした。1963年にアメリカへ移住していた彼女は、それ以降、母国でパフォーマンスすることは一度もなかった。
彼女は、よく“ボサノヴァの女王”と呼ばれるけれど、ぼくはちょっと違うと思う。もと夫のジョアンが、生涯ボサノヴァのリズム、サウダージ感覚、そしてポルトガル語にこだわりつづけたのに対し、アストラッドは、その歌唱スタイルにサンバ・カンソンやボサノヴァのテイストを含みながらも、モダンでポップな感覚が冴えわたるようなシンガーだ。彼女の歌には、太陽と大地と海の匂いはどちらかといえば控えめで、むしろ摩天楼がそびえ立つ都市風景さえ想起させられるような、洗練されたところがある。それは単純に、彼女が積極的に英語で歌ったからというのは、あながち否定できない。
彼女が、すでにボサノヴァを演奏していたテナー奏者のスタン・ゲッツと共演したボサノヴァ作品『ゲッツ/ジルベルト』(1964年)は、グラミー賞4部門を獲得した大ヒット作。もちろんアルバム・タイトルにある“ジルベルト”とは、ジョアンのこと。ほかにアントニオ・カルロス・ジョビン(p)、セバスチャン・ネト(b)、ミルトン・バナナ(ds)が参加している。そして、プロデューサーは、あのクリード・テイラーだ。そのサウンドは、どんなに時が移ろうとも決して朽ちることはなく、ずっとグリーンでありつづけている。ことにアストラッドが英語詞のパートを歌った「イパネマの娘」は、アメリカで爆発的な売り上げを記録した。

アメリカでボサノヴァがポピュラーな音楽になったのは、まさにこのとき。いま当時を思い返してみると、アストラッドの存在は、ブラジリアン・ミュージックとジャズやアメリカン・ポップの橋渡しの一端を担ったと云える。しかしながら、ここにひとつ問題が発生した。ジョビン/モライスの名曲に、あのロバータ・フラックの「やさしく歌って」の作詞で知られる、ノーマン・ギンベルが英語詞をつけた「イパネマの娘」──シングル盤では、ジョアンがポルトガル語で歌ったパートが、全面的にカットされてしまったのである。ブラジルのひとにしてみれば、神様が切られた──ということになる。
またそのいっぽうで、アルバムではゲッツによる即興演奏が大きくフィーチュアされているので、アメリカのひとたちの間に変な誤解が生まれた。内田樹×高橋源一郎の著書ではないけれど、嘘みたいな本当の話とは、こういうことを云うのだろう。つまり、テナーの演奏が目立ち過ぎたせいで、ボサノヴァはジャズの新しいスタイルであり、ゲッツがその創始者である──という、とんでもない誤認識がアメリカ国民に与えられてしまったのだ。しかもさらに、アストラッドは、ボサノヴァの代表的なシンガーと記憶されてしまった。このセッションが、彼女にとってはプロの歌手としての初仕事だったのに──。
彼女のキャラクターはガーリー
アメリカ延いては世界中で、ボサノヴァのイメージを背負ったアイドル的存在となったアストラッドも、そんな誤解と英語で歌ったことが災いして、生まれ故郷、ブラジルでの評価はあまりにも低い。でも、彼女のシンガーとしての本当の素晴らしさは、たとえ名作とはいえ『ゲッツ/ジルベルト』を聴いただけでは、わからないと思う。アルバムの枚数は、それほど多くはないけれど、2002年にリリースされた、彼女のオリジナル曲を中心にまとまられたラスト作『ジャングル』まで、一枚一枚コンセプトが明確にされ丁寧に吹き込まれている。彼女はこの年、ニューヨークで開かれていた国際ラテン音楽の殿堂での表彰を機に、引退宣言をした。
ぼくは、わりと早い時期からブラジルの音楽に親しんでいたのだけれど、アストラッドの英語の歌唱に違和感を覚えたことはない。当時ぼくは、彼女とおなじバイーア生まれで同世代のシンガー、マリア・クレウーザ(本来は“クレウザ”と発音する)のアルバムをよく聴いていたが、マリアのほうは一途にポルトガル語で歌っていた。マリアのそれと比較しても、アストラッドの英語で歌うボサノヴァがしっくり来ないと感じたことは、一度もなかったな。おなじウィスパー・ヴォイスでも、ちょっとセクシーに感情を込めて歌うマリアに対して、可憐だけれど淡々と歌うアストラッドは、格段に都会的。だから、英語でもイケるのかも──。
まあ、ぼくの場合、やはり同世代のリオ生まれのピアニスト、セルジオ・メンデスのレコードで、すでに英語で歌われるボサノヴァに慣れていたのだけれど、それでもどうにも釈然としないケースもある。たとえば、またぞろリオ生まれのMPBのシンガーソングライター、イヴァン・リンスには『ラヴ・ダンス』(1988年)という大半を英語で歌ったアルバムがあるが、これはダメだ。ついでに云うと、元シーウィンドのラリー・ウィリアムズがアレンジした、AOR風のサウンドもいただけない。イヴァンは独特なソフィスティケーテッドなコード進行の曲を書くけれど、ヴォーカルのほうにはアーシーな味わいがある。その魅力は、なんといってもポルトガル語でないと発揮されないのだ。

あとひとり、日本ではおなじみのサンパウロ出身のソニア・ローザも、アストラッドやマリアとともに、当時のぼくのフェイヴァリット・シンガーだ。ソニアはブラジルで、トロピカリアの数々の名作を手がけたアレンジャー、シキーニョ・ヂ・モラエスと『ア・ボサ・ローザ・ジ・ソニア』(1967年)というアルバムを制作したあと、日本へ移住した。彼女を招聘したのは、サンパウロでクラブを経営していた、小野リサのお父さんであることは、あまりにも有名。その後、渡辺貞夫クァルテットや大野雄二トリオと共演したけれど、彼女はポルトガル語はもとより、英語や日本語でも歌った。そのボサノヴァ・サウンドといえば、どの言語でもバランスがとれていた。
結局、ポルトガル語以外のことばで歌われたボサノヴァに違和感を覚えるかどうかは、シンガーの個性によるのではないだろうか。あたりまえといえば、あたりまえだね。各々のキャラクターを独断専行で云わせてもらえば、ソニアはキュート、マリアはコケティッシュ、そしてアストラッドはガーリーといったところ。ぼくにとってアストラッドは、実際はずっと年上だけれど、永遠に女の子なのだ。実は恥ずかしながら、そのガーリッシュな魅力にあてられて、思わずジャケ買いしてしまったレコードがある。それは大学に通いはじめたころのことだったと記憶するが、ぼくはそれをショップの売り場で発見するやいなや、レジにもっていったもの──。
彼女は確たる存在感をもったシンガー
そのアルバムは『ザ・エッセンシャル・アストラッド・ジルベルト』(1984年)という、ロンドンのポリドールからリリースされたコンピレーション(未CD化)。収録曲は『ゲッツ/ジルベルト』からは云うまでもなく、ファースト・アルバム『おいしい水』(1965年)、セカンド作『いそしぎ』(1965年)、サード作『ルック・トゥ・ザ・レインボウ』(1966年)、ゲッツとのライヴ盤『ゲッツ・オー・ゴー・ゴー』(1964年)、ワルター・ワンダレイとのコラボ作『サマー・サンバ』(1966年)といった、ヴァーヴにおける初期の作品からチョイスされている。なかなか気の利いた仕様だ。
このレコード、内容もいいけれど、なんといってもカヴァー・アートが素晴らしい。ベレー帽、ノースリーヴのトップス、グレンチェック柄のスカート、リボンパンプス、肩にはハンドバッグという出で立ちのアストラッドが、どこかの飛行場の鉄柵に腰掛けてカメラに視線を向けている。バックにBOACキュナード航空のボーイング707が見えるから、ロンドン・ヒースロー空港あたりなのかもしれない。ぼくはファッションのことはよくわからないけれど、この装いを見るとアストラッドは、その音楽性も含めて、1960年代の象徴だったようにさえ思えてくる。どこにでもいそうな小柄な女性──ものすごい美人ではないけれど、なんともいえず可愛らしい!
このLP盤を見てニヤニヤしながら、そんなことを思い、でも実はいま違うアルバムをプレイしている。アストラッドの作品のなかでは、それほど人気盤ではないけれど、ジャケットのイラストはともかく、内容的にはとても好きな一枚だ。ぼくは最初に彼女のことを、ボサノヴァの女王ではなくモダンでポップな感覚が冴えわたるようなシンガーと云ったが、この1968年にリリースされた『ウィンディ』(全編英語歌唱)を聴くと、ますますそう信じて疑わなくなるのである。なぜなら本作には、ブラジルの曲も採り上げられてはいるものの、もはやボサノヴァ作品という風情がほとんどないからだ。というかこれは、モダンなハーモニーとポップなリズムがミックスされた、ソフトロック・アルバム。アストラッドのアンニュイなささやきは、健在だけれど。
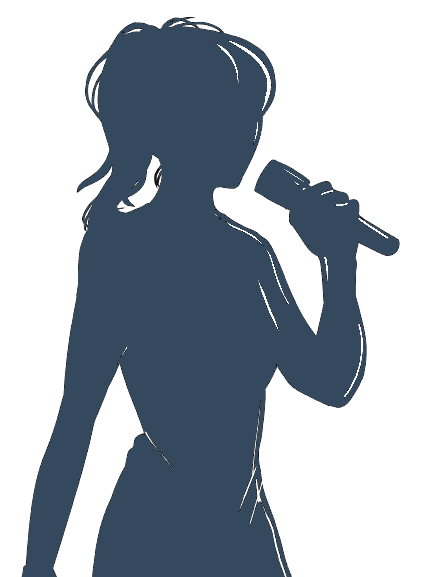
本作でまず目を引くのは、プロデューサーがアストラッドのこれまでの作品を手がけたクリード・テイラーではなく、当時ソウルやポップスに携わっていたピート・スパーゴであること。本作がポップに仕上がっているのは、この点に起因する。テイラーのほうはすでに、A&Mレコード傘下のCTIレーベルに移籍していたからね。ただし楽曲のアレンジは、テイラーとつながりの深い、エウミール・デオダートとドン・セベスキーがそれぞれ5曲ずつ担当している。映画『水色のビキニのマドモアゼル』(1968年)からの美しいスローボッサ「ロンリー・アフターヌーン」のみ、作曲者のパトリック・ウィリアムズが自らアレンジしている。数多くの映像作品を手がけたウィリアムズだけに、ストリングスのアレンジはお見事。
個人的には、本作ではデオダートのアレンジがもっとも好きだ。ルイス・ボンファの「ドリーミー」マルコス・ヴァーリの2曲「チャップ・チャップ・アイ・ガット・アウェイ」と「クリケット・シング・フォー・アナマリア」ワルター・ワンダレイも吹き込んだデオダートの自作「オン・マイ・マインド」といった、ブラジリアン・ナンバーはよりポップに、逆にソフトロック・バンド、アソシエイションのヒット曲「ウィンディ」はジャズ・ロック風にアレンジされている。それはとても都会的なサウンドで、のちのクロスオーヴァーの原点でもある。ここではアストラッドのヴォーカルを、よりお洒落に引き立てている。
かたやセベスキーのほうは、やはりアソシエイションの「かなわぬ恋」サンズ・オブ・チャンプリンの「シング・ミー・ア・レインボウ」ビートルズの「イン・マイ・ライフ」ロビン・ウィルソンの「ホエア・アー・ゼイ・ナウ」といったポップ・ナンバーを、正攻法でアレンジ。なかでもディズニー・アニメ『ジャングル・ブック』(1967年)の挿入歌で、ディキシーランド調の「ベア・ネセシティ」が楽しい。アストラッドとジョアンの子どもで、当時7歳のマルセロとのデュエットが、とても微笑ましい。いまこれを聴くと、胸を締めつけられる思いがする。アストラッドは技巧的に優れたシンガーではないけれど、確たる存在感をもった可愛らしいひと。ああ、それも永遠のこととなってしまったのか──。ここに、こころから哀悼の意を表する。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。









コメント