サントラ盤、クリスマス・アルバムでありながらもジャズ史上世界セールス2位を記録したヴィンス・ガラルディの『スヌーピーのメリークリスマス』
 Album : Vince Guaraldi / A Charlie Brown Christmas (1965)
Album : Vince Guaraldi / A Charlie Brown Christmas (1965)
Today’s Tune : Christmas Time Is Here (Instrumental)
楽しくもあり苦くもある私的『ピーナッツ』の思い出
今年もクリスマスのシーズンがやってきた。非キリスト教徒の気持ちを配慮すると、ホリデーシーズンといったほうがいいのかな。まあ今回はクリスマスにちなんだレコードをご紹介するので、ここはクリスマスシーズンと云わせていただく。それにホリデー・アルバムなどと云ったら、日本人にはなんのことやらわからない。やはりクリスマスを題材にした音楽作品集は、クリスマス・アルバムと呼ぶべきだろう。無益なおしゃべりはほどほどにして、早速今年もクリスマス・アルバムを1枚ご紹介しよう。この『スヌーピーのメリークリスマス』は、テレビアニメのサウンドトラック盤であると同時に、ジャズ・ピアニスト、ヴィンス・ガラルディ(1928年7月17日 – 1976年2月6日)の(ブラジルのギタリスト、ボラ・セチとの共作を含めると)8枚目のスタジオ・レコーディング作品でもある。実に気の利いた仕様だ。
原題は『A Charlie Brown Christmas』となっているが、日本では過去に『スヌーピーのクリスマス』というタイトルで発売されていた。近年は『スヌーピーのメリークリスマス』というタイトルに改題されているので、ここでは便宜上こちらで統一させていただく。本作はチャールズ M. シュルツの漫画『ピーナッツ』を原作とした、テレビアニメのサントラ盤。アメリカのCBSによる1965年12月9日のクリスマス特番放送にあわせて、同年12月の第1週に早々とファンタジー・レコードから発売された。ちなみにこのアニメは『ピーナッツ』関連の映像作品としては2本目であるが、いわゆるパイロット・フィルムだった。本作が好評を博したことが、シリーズ化のキッカケとなった。
このクリスマス・スペシャルは日本でも何回かテレビ放映され、メディア化もされている人気作品。ことあるごとにタイトルが『チャーリー・ブラウンのクリスマス』『スヌーピーのクリスマス』『ゆうつなクリスマスだチャーリー・ブラウン』『クリスマスだよ、チャーリー・ブラウン』などと変更されているのが面白い。個人的にはそれほど『ピーナッツ』が好きなわけではなかったけれど、小学校に入学するくらいからNHKで放映されていた日本語吹き替え版アニメをなんとなく観ていた。バカな子どもだったからか、ぼくにはその面白さがよくわからなかった。ただ主人公のチャーリー・ブラウンに俳優でコメディアン、そしてジャズ・トロンボニストの谷啓が声を当てていて、妙にオッサンくさい子どもだなと取るに足らない感慨を催したもの。
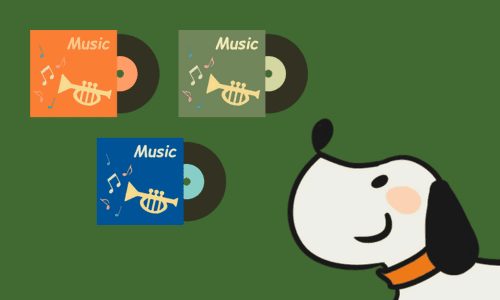
ぼくと『ピーナッツ』との繋がりは、はっきり云って希薄だ。それでも少年時代に、ささやかな思い出がある。小学校5年生のとき、母かたの叔母さんから誕生日祝いに『ピーナッツ・ブックス』の何冊かをプレゼントされた。いまはもうない出版社、鶴書房が発行していたシリーズで、翻訳にはあの詩人の谷川俊太郎も関わっていた。このシリーズは“和英対訳まんが”と銘打たれていて、漫画のコマのなかのセリフやオノマトペは日本語訳で記されていて、枠外にはオリジナルの英語表記があった。ぼくは勉強はまったくできなかったけれど、英語だけは得意だった。その恩恵は、幼いころから洋楽に親しんでいたこと、当時から名画座に通っていたこと、そしてこの漫画を読んでいたことから受けたものだったように思われる。
それでも当時のぼくは、長谷川町子の漫画『サザエさん』がそうであったように、数多の賞を獲得した人気漫画『ピーナッツ』のほんとうの面白さを理解していなかったように思う。いまあらためて読んでみると「なるほど」と思うところが多々あるから、もしかすると『ピーナッツ』は端から子ども向けの漫画ではなかったのかもしれない。そのあたりは、ぼくもあまり詳しくないので想像の域を出ない。それはともかく『ピーナッツ』に関しては、実はぼくにとっていまいましい思い出もあるのだ。それはやはり、小学校5年生のときのことだった。当時ぼくはすでにピアノを弾くようになっていたのだけれど、ある日、学校の音楽室でピアノをいじっていたぼくのことを、クラスメイトのひとりがシュローダー(正確にはシュレーダー)と呼んだのである。
もちろんぼくはシュローダーのことが嫌いだったわけではない。そうかといって特別な思い入れもなかったけれど──。クラスメイトにしても悪意があったわけではなく、単にぼくのことをからかっただけなのだろう。でもおちゃらかしたほうは面白がっていたけれど、こちらはちっとも面白くない。あのころのぼくは、まだ純粋で傷つきやすかったのだ。確かに当時の日本ではピアノを習っている男子は少なかったかもしれないけれど、奇異の目で見られるのはかなり気持ちが沈む。まあぼくも変わり者だったのかもしれない。思えばぼくは、べつにいじめられていたわけではないのだろうが、いまように云えばいじられキャラだったのかもしれない。なにかあるたびに、揶揄するようなあだ名をつけられることがあったのである。
ぼくは中学生のとき、授業中によく鼻血を出していた。きっと鼻のなかの粘膜がひとより弱いのだろう、いまでも突然、鼻腔から出血することがある。そんなところから、当時ぼくにつけられたあだ名は“出血多量”だった。高校時代にはなぜか“スナフキン”と呼ばれた。確かに自分には自由気ままなところがあると自覚しているし、独りでいることもけっこう好きだ。しかしひとにそれを指摘されるのは、あまり愉快なことではない。そして大学時代のあだ名がもっとも酷い。大して親しくもない同学部生から“クサったジョン・レノン”と呼ばれたことがある。ただのレノンならまだマシだけれど、クサったレノンだからね──。それにレノンさまにも失礼だ。ちなみに、クサったとはクサクサしているという意味らしい(いちいち説明するなよな)。
無駄バナシはこれくらいにするけれど、とにかく小学5年生のぼくにとって、シュローダーと呼ばれることは心外だったのである。むろん愛すべきキャラクターであるシュローダーには、なんの罪もない。シュローダーくんはルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンをこよなく愛しているようだけれど、実はぼくはベートーヴェンのピアノ・ソナタをちゃんと弾いたことは一度もない。ぼくは当時からモーリス・ラヴェルやクロード・ドビュッシーのピアノ作品が好きで、グレードの高い曲が多かったのだけれど先生に無理を云って弾かせもらっていた。それにしてもトイ・ピアノであれだけの演奏をするシュローダーくんは、まさに天才少年。ぼくなどはその足元にも及ばない。ぼくがシュローダーと呼ばれることに抵抗を感じたのは、そんな彼に対するやっかみがあったからかも──。
ガラルディの正統な後継者デヴィッド・ベノワ
まあそれが理由というわけでもないのだけれど、以来ぼくは『ピーナッツ』とはしばらく疎遠になる。再会するのは、大学生になってからのこと。それは当時、輸入盤を扱うショップを賑わせていた、デヴィッド・ベノワの7枚目のリーダー作『ディス・サイド・アップ』(1985年)において。アメリカはテキサス州オースティンのマイナー・レーベル、スピンドルトップからリリースされたこのレコードは、モノクロームの地味なジャケットとはウラハラに、中身のほうはメジャー・レーベルの作品にまったく引けを取らない贅沢で華やかな出来栄えだった。ベノワはいまでこそ西海岸のコンテンポラリー・ジャズにおける大御所ピアニストとして周知されているが、当時はまだまだ知名度が低かった。日本ではまったくの無名だったと思う。それがこのアルバムのリリースを機に、わが国でも一気に人気者となったのである。
この『ディス・サイド・アップ』というレコード、当時は国内リリースがなかったけれど、収録曲の「ライナス・アンド・ルーシー」と「ビーチ・トレイル」がそれぞれ、ニッポン放送のラジオ番組『斉藤由貴 ネコの手も借りたい』のOPとEDで使用され、人気に拍車がかかった。そしてこの「ライナス・アンド・ルーシー」こそが、ヴィンス・ガラルディがCBSが製作した60分のテレビ・ドキュメンタリー映画『ア・ボーイ・ネームド・チャーリー・ブラウン』(1963年)のために書いた楽曲だった。実はこの映画、放送が見送られたまぼろしの作品。それにもかかわらずサウンドトラック・アルバムのほうは、ファンタジー・レコードから発売された。ガラルディにとっては6枚目のスタジオ・アルバムとなる。
このヴィンス・ガラルディ・トリオ名義の『チャーリー・ブラウン オリジナル・サウンドトラック(Jazz Impressions Of “A Boy Named Charlie Brown”)』(1964年)は、人気の高い作品で日本でもたびたびリイシューされている。ぼくは大学時代に本盤を知り合いの芸術系大学に通う女の子から借りて、はじめて聴いた。それは上記のベノワによるロックンロールとフュージョンとが交錯するようなヴァージョンの原曲が、いったいどんなものなのか興味が湧いたからだ。過去にぼくはヴィンス・ガラルディ・トリオの演奏といえば、ファンタジー盤の『黒いオルフェ』(1962年)しか聴いたことがなかったけれど、それと同様に『チャーリー・ブラウン オリジナル・サウンドトラック』も、ひとことで云えば軽妙なウェストコースト・ジャズ作品だった。

そういえば『黒いオルフェ』のなかに「風にまかせて」というガラルディのオリジナル・ナンバーが収録されているのだけれど、この曲、1963年のグラミー賞で最優秀オリジナル・ジャズ作曲賞を受賞している。テレビアニメ『ピーナッツ』のエグゼクティヴ・プロデューサーを務めたリー・メンデルソンは、この曲をラジオで聴いてガラルディの起用を決意したという。また、ベノワもこの曲をジョン・パティトゥッチ(b)、ピーター・アースキン(ds)というスゴいピアノ・トリオで吹き込んでいる。この演奏はベノワの12枚目のリーダー作『ビル・エヴァンスに捧ぐ』(1989年)で聴くことができるが、アルバムはフュージョン畑の彼にしては珍しく本格的なモダン・ジャズ作品に仕上がっている。ぜひ聴いていただきたい。
ベノワはガラルディ・フリークというかピーナッツ・フリークだ。彼はGRPレコードが漫画『ピーナッツ』の生誕40周年に寄せたコンピレーション・アルバム『ハッピー・アニヴァーサリー、チャーリー・ブラウン&スヌーピー!』(1989年)に参加している。自己のリーダー作でも『ヒアズ・トゥ・ユー・チャーリー・ブラウン&スヌーピー〜50グレイト・イヤーズ!』(2000年)『チャーリー・ブラウン・クリスマス〜40周年記念』(2005年)『ジャズ・フォー・ピーナッツ〜チャーリー・ブラウン&スヌーピー・TVテーマ』(2008年)と3枚もリリースしているのだ。なお1枚目は『ピーナッツ』生誕50周年を、2枚目はテレビアニメ放映40周年を、3枚目は日本でのコミック化40周年をそれぞれを記念するものである。
ベノワはもはや『ピーナッツ』に関して、ただの愛好家ではない。彼は1992年から2015年まで『ピーナッツ』のアニメ作品のミュージカル・ディレクターを務め、ガラルディが創造した特徴的な音世界を拡大させた。彼が13歳のときにピアノのレッスンを受けはじめるキッカケは、ズバリ『スヌーピーのメリークリスマス』をはじめとするテレビアニメで聴いたガラルディの楽曲に感化されたことだったという。ベノワは上記の『ヒアズ・トゥ・ユー・チャーリー・ブラウン&スヌーピー〜50グレイト・イヤーズ!』でも「ライナス・アンド・ルーシー」を採り上げているのだけれど、このテイクはまさに彼のガラルディに対する深い敬愛の念が込められたものと云える。
なにせベノワはこのテイクで、ガラルディ本人とヴァーチャル・デュエットを果たしているのだから──。どういうことかというと、前述の『チャーリー・ブラウン オリジナル・サウンドトラック』に収録されている「ライナス・アンド・ルーシー」のオリジナル・パフォーマンスに、ベノワのトリオによる演奏がミックスされているのである。左チャンネルのガラルディのプレイに、途中から右チャンネルのベノワのピアノが加わるところには、ちょっとゾクゾクさせられる。ちなみに冒頭のカウント・アラウドは、ガラルディ本人の声だ。このユニークな趣向というか粋な計らいは、まさにときを超えた夢の競演。いずれにしてもベノワはガラルディの正統な後継者であり、彼こそシュローダーと呼ばれるに相応しいひとと、ぼくは思う。
ということでベノワのハナシはこれくらいにして、ここからは本家ヴィンス・ガラルディ・トリオの『スヌーピーのメリークリスマス』についてお伝えしていこう。前述のように、本作はクリスマス特番のテレビアニメのサントラ盤だけれど、純然たるクリスマス・アルバム、そしてガラルディのリーダー作としてもしっかり機能する好盤だ。もちろん、クリスマスなのにふさぎ込んだチャーリー・ブラウンが、おなじみの仲間たちに支えられながら“クリスマスの本当の意味”を見出していくという、およそ25分のハートウォーミングなアニメ映画を体験すれば、より感慨深い音盤となるだろう。ぼくがこのレコードを手に入れたのは、前述の『チャーリー・ブラウン オリジナル・サウンドトラック』にはじめて触れたときとほぼ同時期で、大学時代のことだった。
ガラルディのジャズ──難易度は高くないが、演奏は一流
シュルツによる可愛いイラストがあしらわれたこのレコードを中古レコード店で発見したとき、ぼくはまったく迷わずに購入したもの。そのときはクリスマス・アルバムを聴くにはオフシーズンだったけれど、そんなことはどうでもよかった。ジャケットにはしっかりオリジナル・サウンドトラックとの表記があり、当時ぼくはまだ映像のほうは未見だったが、それもまたまったく差し支えなかった。ジャケットにヴィンス・ガラルディの名前が記載されていること、それがもっとも重要なのである。なぜなら『チャーリー・ブラウン オリジナル・サウンドトラック』において、ガラルディのプレイするジャズがいい意味でイージーでクリアなこと、彼が描く『ピーナッツ』の世界が単純に素敵でもあり滋味豊かでもあることを、ぼくはすでに知っていたからだ。
ガラルディのピアノ演奏は、実にわかりやすい。ピアノを弾く母親とビッグ・バンドのリーダーを務めるふたりの母かたの叔父からの影響で、彼は幼少から音楽に親しんでいた。カリフォルニア州サンフランシスコ市ノース・ビーチで育ったガラルディは、7歳からピアノを弾きはじめたが、その後リンカーン高校からサンフランシスコ州立大学へと進学しているので、特別な音楽教育プログラムは受けていないのかもしれない。また彼は朝鮮半島の連合軍軍政期に、現地で米陸軍の料理人として働いたという。ガラルディの音楽にロジカルな色合いがなくイージーゴーイングな気分が漂うのは、そんな来歴と因果関係がありそうだ。
ガラルディが奏でるジャズ・ピアノには、幾ばくかのインテリジェンスも感じられるが、なんといっても鷹揚さが際立つ。文字どおりまさに鷹が悠然と空を飛ぶように、ゆったりと気韻生動で簡潔明瞭なフレーズを紡いでいく。そのわかりやすさ故か、アメリカでの人気に反して日本では過小評価されているガラルディだが、もしぼくが子どもにジャズ・ピアノを教えるとしたら彼の演奏を教科書代わりにするだろう。たとえば、ギター入りドラムレスのオールド・スタイルで吹き込まれた『ヴィンス・ガラルディ・トリオ』(1956年)や『ア・フラワー・イズ・ア・ラヴサム・シング』(1957年)などは、ジャズを気軽に楽しめる好盤だ。でも実はガラルディの演奏から学ぶべきことはまだまだたくさんあるように、ぼくは思うのである。

この『スヌーピーのメリークリスマス』もまた、ジャズはハードルが高いという先入観をもっているひとにこそぜひ聴いていただきたい、お洒落で楽しい作品。そしてさらに具眼のジャズ・リスナーのかたには、ガラルディのプレイを再吟味することを、ぼくはお勧めする。彼は紛れもなくデイヴ・ブルーベックやカル・ジェイダーと同様に、サンフランシスコのジャズ・シーンを牽引するジャズ・プレイヤーだったのだから──。たとえば『スヌーピーのメリークリスマス』の冒頭の「もみの木」を聴いていただきたい。ドイツの古い民謡にエルンスト・アンシュッツによって手が加えられ世界的に親しまれるようになったこのクリスマス・キャロルを、ガラルディは見事にジャズ・スタンダーズの1曲に加えた。つまりここでは祝歌の構造が保持されながらも、ジャズのハーモニーが鮮やかに展開されているのである。
ガラルディの伝統的なクリスマス・ソングに対する発想力豊かな解釈と機知に富んだアレンジ、シンプルでリフレッシングなピアニズムは、極上と云える。ドラムスのブラシからスティックへのもち替えもケレン味がなくて自然。途中のベース・ソロもなかなか味わい深い。このピアノ・トリオのサイドを務めているのは、フレッド・マーシャル(b)とジェリー・グラネリ(ds)。なお本作はオリジナル盤では全11曲だが、1988年に発売されたジャケット違いのリイシュー盤では末尾に「グリーンスリーヴス」が追加された。このボーナス・トラックと「ライナス・アンド・ルーシー」の2曲のみ、サイドがモンティ・バドウィック(b)とコリン・ベイリーに交替する。こちらはさきの『チャーリー・ブラウン オリジナル・サウンドトラック』のレコーディング・メンバーだ。
2曲目の「ホワット・チャイルド・イズ・ディス」は、イングランド民謡「グリーンスリーヴス」にウィリアム・チャタートン・ディックスが歌詞をつけてこのタイトルになった。結局インストだから「グリーンスリーヴス」のままでいいと思うのだけれど──。それはともかく、ここでトリオはこの曲を冷厳なジャズ・ワルツとして演奏。ピアノのアルペジオが美しくもどこか荒涼たるイメージを与える。つづくヴィンスのオリジナル「マイ・リトル・ドラム」では、ボサノヴァのリズムに乗ってピアノと児童のコーラスが交錯。素朴な曲調に愛らしさが増す。歌っているのは、カリフォルニア州サンラファエル市にあるセント・ポール聖公会教会の児童合唱団だ。4曲目はくだんの「ライナス・アンド・ルーシー」で、ラグタイムとロックンロールとのブレンド、ラテンや4ビートへのメトリック・モジュレーションがコンパクトに収まった、文句なしの名演である。
A面ラストのガラルディの自作曲「クリスマス・タイム・イズ・ヒア」は、3拍子の清澄なジャズ・バラード。リリカルなピアノからメロディアスなベースへとソロがつながれ、エレガントでメランコリックなムードが横溢する。まさに『ピーナッツ』から生まれた、エヴァーグリーンな名曲だ。B面のトップではこの「クリスマス・タイム・イズ・ヒア」が、今度は児童合唱団によって歌われる。作詞はリー・メンデルソンが担当した。おなじくガラルディの自作「スケーティング」は、軽快なジャズ・ワルツ。シンコペーテッドなリズムとピアノによるカスケード効果が特徴的なナンバーだ。フェリックス・メンデルスゾーン作曲、チャールズ・ウェスレー作詞の「天には栄え」は、児童合唱団によるストレートなクリスマス・キャロル。ガラルディはオルガンを弾いている。
ガラルディのオリジナル「クリスマス・イズ・カミング」は、ラテン・タッチでありながらポップ・フィーリングが溢れるいかにも彼らしいダイナミックなナンバー。サビではボサノヴァ、ピアノのアドリブ・パートではスウィングと、大胆な構成が楽しい。つづいてベートーヴェンの「エリーゼのために」を挿み、メル・トーメとロバート・ウェルズとの共作「ザ・クリスマス・ソング」へ。ロマンティックだけれど、こざっぱりとしたバラード・プレイがガラルディらしい。ボーナス・トラックの「グリーンスリーヴス」は、さきのヴァージョンよりもぐっと落ち着いた感じ。その分ジャズ度は増している。ここでのガラルディのプレイなどは、いかにもセンスのよさで聴かせるようなもの。難易度は高くないが、演奏は一流。それが彼のジャズなのである。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。








コメント