モリス・ナントンのプレスティッジにおける最後の吹き込み──ソウル・ジャズのフルコース『ソウル・フィンガーズ』
 Album : Morris Nanton / Soul Fingers (1967)
Album : Morris Nanton / Soul Fingers (1967)
Today’s Tune : The Lamp Is Low
ナントンはプレスティッジ・レコードの諸作を聴かなければ語れない
ぼくのなかで、いまだ謎だらけのピアニストのひとりが、モリス・ナントン(1929年9月28日 – 2009年11月15日)だ。もう10年以上もまえのことになるが、ワーナーミュージック・ジャパンが提供する“JAZZ BESTコレクション 1000”という、廉価盤CDのシリーズがあった。アトランティック、ワーナー・ブラザース、リプリーズ、エレクトラ・ミュージシャンといった、ワーナーミュージックが販売権を有するレーベルのジャズ作品を復刻するという企画。その膨大なカタログから、誰もが知る名盤とマニア垂涎のレア盤が中心に厳選されたとのこと。確かにマニアックなセレクションも、垣間見られる。ただラインナップにナントンのアルバムを発見したとき、ぼくはちょっと不思議に思ったのである。
当時、果たしてナントンの作品を聴きたいと思うひとが、どれほどいたのだろう?きっとセレクターの聴いてもらいたいという思いからのCD化なのだろうと、そのときのぼくは勝手に推測した。もしかすると、セレクトしたかたもアルバムを所持しておらず、実はいちばんそれを欲していたのはご本人なのでは──と、ちょっとイジワルな想像までしてしまった。なにせナントンといえば、日本ではまったくと云っていいほど知られていないジャズ・ピアニスト。確かにここで復刻されたワーナー・ブラザース盤2枚はその昔、中古市場において高値で取り引きされていたこともある。でもこの2枚に関しては内容的に観ても、大枚をはたいたり血眼になって探すような類いのレコードではないと、ぼくは思う。
この2枚のワーナー・ブラザース盤は、ともに有名なブロードウェイ・ミュージカルのジャズ・ヴァージョン。昔はこういう1本のミュージカル作品の楽曲がまるごと採り上げられたジャズ・アルバムが、けっこうあった。本国では、売れたのだろう。ナントンのアルバムは2枚とも、ピアノ・トリオで演奏されている。おそらく彼のデビュー作にあたる『フラワー・ドラム・ソング』(1959年)は、リチャード・ロジャース作曲、オスカー・ハマースタイン2世作詞による、同名のブロードウェイ作品の楽曲集。ちなみにこのミュージカルは、1961年に映画にもなっている。本盤のレコーディングは1958年、ニューヨークにおいて、モリス・ナントン(p)、ノーマン・エッジ(b)、オシー・ジョンソン(ds)によって行われた。

かたや『ロバータ』(1959年)は、ジェローム・カーン作曲、オットー・ハーバック作詞による、1933年初演の有名ミュージカルのオリジナル・ジャズ・パフォーマンス盤。ここにも収録されている「煙が目にしみる」や「イエスタデイズ」は、すっかりジャズ・スタンダーズと化している。やはりこのミュージカルも1935年に映画化されているのだが、本盤では映画版のオリジナル曲も採り上げられている。レコーディングは『フラワー・ドラム・ソング』とおなじく1958年、ニューヨークで行われた。トリオはドラムスがオシー・ジョンソンからチャーリー・パーシップに交替している。グリーンの背景色に女性モデルがあしらわれた美麗なジャケットということで、けっこう人気があるらしい。
まあ、ぼくにはそれほどいいジャケットとも思われないけれど、ワーナーミュージック・ジャパンの商品説明にはそう記されていた。そんなことよりも、この説明文のなかで見過ごすわけにはいかないのは、本盤がモリス・ナントンの最高傑作と明言されているところ。確かにご高説のとおり、ナントンは軽妙なタッチとソウルフルなスタイリストだ。しかしながら、2枚のワーナー・ブラザース盤におけるナントンのプレイはちょっと大人しめ。それをエレガントと云ってしまえばそれまでというか、ものは云いようなのだけれど、後年の彼の演奏と比較するとまだまだ十人並みの力量しか発揮されていないように感じられる。決してわるくはないのだが、この『ロバータ』は最高傑作にはほど遠い作品と、ぼくは思う。
強いてナントンの最高傑作の名に相応しい作品を挙げるとするならば、個人的な見解では『サムシング・ウィヴ・ガット』(1965年)を選ぶのが妥当と思われる。繰り返すけれど『ロバータ』はなかなかの佳作だと思うし、どちらかといえば好きなアルバムだ。でもナントンの素晴らしさは、プレスティッジ・レコードの諸作を聴かなければ語れないと、ぼくは思う。たとえば、ナントンに興味をもったリスナーが、2枚のワーナー・ブラザース盤のうちのどちらかで、彼の演奏にはじめて触れたとする。率直に云うけれど、それで満足するのはまだ早い。というか余計なお世話かもしれないが、それで彼の作品を追いかけるのを終わりにしてしまうのは、あまりにももったいないと、ぼくは思うのである。
ナントンのプレスティッジ盤はどれも、このレーベルにおけるピアニストの作品のなかでも出色の出来。どれもと云っても、実はプレスティッジに残されたナントンのリーダー作は、たったの3枚しかない。まったく謎である。とにかくその内訳は、さきに挙げた『サムシング・ウィヴ・ガット』のほかに『プレフェス』(1964年)と『ソウル・フィンガーズ』(1967年)といった、計3作品にとどまる。すべて作曲家でもあるカル・ランプリーがプロデュースを担当しているが、彼はマイルス・デイヴィスの作品を手がけたことで知られるひと。レコーディングのほうも全作品を、名匠ルディ・ヴァン・ゲルダーがエンジニアを務めている。特にヴァン・ゲルダーによる温もり感と存在感のあるサウンドは、いつも以上に際立っている。
いまだ未CD化の憂き目を見ているナントンの3枚のプレスティッジ盤
3枚のうち1作目の『プレフェス』と2作目の『サムシング・ウィヴ・ガット』はトリオ編成、3作目の『ソウル・フィンガーズ』ではトリオにコンガが加えられている。さらに3作目には1曲のみプーチョ・アンド・ヒズ・ラテン・ソウル・ブラザーズが参加している。このバンドは、ティンバレス奏者のヘンリー “プーチョ” ブラウンによって1959年に結成された、ラテン・ジャズやリズム・アンド・ブルースをプレイするグループ。いっときチック・コリアが在籍していたことでも、よく知られている。彼らの音楽は当時、ブーガルーと呼ばれニューヨークを中心に人気を博していたのだが、1990年代ごろ英国のクラブシーンにおいても重宝されたので、ご存知のかたも多いだろう。
プーチョ・アンド・ヒズ・ラテン・ソウル・ブラザーズは、1966年にプレスティッジ・レコードと契約し7枚のアルバムを吹き込んでいるけれど、彼らのプロデューサーを務めたのがカル・ランプリーだった。そんな経緯から、このグループはナントンのアルバムに参加することになったのだろうが、こういうコラボレーションはごく稀な出来事と思われる。バンド・サウンドが好きなランプリーの采配ではあるけれど、それこそ軽妙なタッチとソウルフルなスタイリストであるナントンだからこそなし得た共演だったと、ぼくは感じる。その点では、ザ・スリー・サウンズのジーン・ハリスや、ラテンやソウルが得意なラムゼイ・ルイスがイメージされるが、ナントンはハリスよりも力強くルイスよりも上品だ。
プレスティッジ・レーベルの1作目の『プレフェス』は、比較的オーソドックスなピアノ・トリオ作品だが、選曲と楽曲解釈が際立った名盤だ。まず映画のテーマ曲をいくつか採り上げているのがユニーク。しかもそのポピュラー・セレクションのどれもが、思いのほかしっくりくるものだから、あらためてナントンが卓抜な音楽センスの持ち主であると実感させられる。たとえば、モーリス・ジャールの「アラビアのロレンス」は、軽快なラテン・ナンバーに様変わりしている。ルイス・ボンファが作曲した『黒いオルフェ』の主題歌「カーニバルの朝」は、スッキリとしたモダン・ジャズの装いが凝らされている。なによりもトリストラム・ケリーが音楽を担当した『サミー南へ行く』の「序曲」が、小気味いいサンバで演奏されているのには驚かされた。
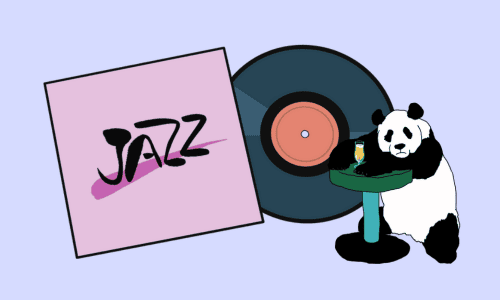
かたやよく知られたスタンダーズでも、ナントンは個性的な演奏を展開している。たとえば個人的にも好きな曲、ブロニスラウ・ケイパーの「インヴィテーション」が、ロマンティックなバラードに仕上げられている。ミッドテンポやアップテンポではないところがレアだし、曲調のコケティッシュな美しさに拍車がかかる。デューク・エリントン楽団のクロージング・テーマとしておなじみの「昔はよかったね」では、ナントンの躍動する鍵盤捌きがかつてないほど生命力に溢れたムードを作り出している。世に星の数ほどの吹き込みがあるが、これは隠れた快演と云えよう。また、リチャード・ロジャースの「甘き調べ」では、終始ブロック・コード奏法が逡巡することなく繰り出され、元ネタであるヨハネス・ブラームスのピアノ協奏曲を圧倒する勢いだ。
ちなみに、このアルバムのB面のトップを飾るボブ・カールトンの1918年のヒット曲である「Ja-Da(ヤダ)」は、1968年にアメリカが打ち上げたアポロ7号の機内で流されたという。ここでトリオはザ・スリー・サウンズを彷彿させる、ファンキーでグルーヴィーそしてハッピーな演奏を展開。ソウルフルでありながらどことなく垢抜けた感じがするのも、ナントンの特徴のひとつ。ロケットの搭乗員たちは、この覚えやすいシンプルでチャーミングなメロディック・ラインに癒されたのだろうか?いずれにしても、この曲はラジオ局においてもかなりの再生数を誇り、シングルカットもされるほどの人気ナンバー。これまでに述べた点を慮ると、当然『プレフェス』はとうにCD化されているものと思われる。しかし、実際はそうではない。
これもまた、謎である。実はこの『プレフェス』を含むナントンの3枚のプレスティッジ盤は、いまだ未CD化の憂き目を見ている。まさか通俗的な作品と評価され、封印されているわけでもないのだろうが、まったく合点がいかない。そういえば、廃業して久しいレコード販売店WAVEが、1980年代の終わりから1990年代のはじめ“ウェイヴ・ジャズ・クラシックス(WJC)”という企画を推進していた。(プレスティッジを買収した)米国のファンタジー・レコードが所有するマスターを、日本でレコード・プレスして商品化するというものだ。ファンタジーといえば、ジャズ・レーベルの再発シリーズ、OJC(オリジナル・ジャズ・クラシックス)が有名だけれど、それよりWAVE盤のほうが盤質もジャケットの紙質もはるかにハイクオリティだった。
社会人になったばかりのぼくは、毎日のように会社帰りに、当時西武百貨店池袋店内で営業していたWAVEに立ち寄っていた。当然WJCのコーナーが特設されているわけだが、そこでナントンの3枚のプレスティッジ盤も何事もなかったかのように陳列されていた。まことにいい時代というか、ジャズ・ファンにとってはまるで天国のようだった。それにしてもWJC盤のリリース以降、ナントンのプレスティッジ盤はどこかでリイシューされたのだろうか?謎である。ウワサでは、ナントン本人がファンタジー・レコードにリーダー作すべての原盤権を買い取るよう申し出たところ、あっさり断られたらしい。ということは、ファンタジーは将来的にナントンの作品を復刻するつもりがあるのだろうか?謎が謎を呼ぶ。
ちょっと話題が横道に逸れたが、ハナシを本題に戻そう。ぼくはさきにナントンの最高傑作の名に相応しい作品として『サムシング・ウィヴ・ガット』を挙げたけれど、そのわけはこのアルバムではこの上なく、彼の黒いジャズ・スピリッツがメラメラと燃え上がっているからだ。ドラマーが前作の名手オリヴァー・ジャクソンからアル・ベルディーニに替わっている。ベルディーニのことはあまりよく知らないが、有名な『ジ・インクレディブル・カイ・ウィンディング・トロンボーン』(1960年)で、タイコを叩いていたひと。ジャクソン同様、当意即妙で無駄のないドラミングに好感がもてる。なおベーシストは、ノーマン・エッジで固定。ナントンの吹き込みには常に彼がいる。ふたりは50年以上もおなじ釜のメシを食った仲だ。
いま何をおいても真っさきにCD化されるべきナントンのリーダー作
それはそうと本作では、冒頭のスローな8分の6拍子「サムシング・ウィヴ・ガット」にノックアウトされる。ナントンのオリジナルだが、曲自体はなんの変哲もないブルース。でもここでナントンは、およそ8分間ブルージーな音楽表現を全開させている。サイドのグルーヴ感も含めて、徐々に高まるアパッショナートなプレイが感動を呼ぶ。その点、デューク・エリントンの「ムード・インディゴ」やジョージ・ガーシュウィンの「マイ・マンズ・ゴーン・ナウ」にも、同様に熱いブルース・フィーリングが横溢する。ミシェル・マーニュの「地下室のメロディ」におけるアフロ・リズム、マルガリータ・レクオーナの「タブー」のルンバ風のアレンジはともに小気味がよく、ナントンのピアノもブルーな色合いを強めている。
そして唯一、アリー・リューベルの「マスカレード・イズ・オーヴァー」だけが、マンボ調のバウンシーなリズムにはじまりスウィンギーな4ビートへと進行する、軽やかで洒落た感じの演奏となっている。ここでのナントンは、華麗なブロック・コードとブルージーでもありリルティングでもあるシングル・トーンとを、上手く使い分けている。ブルース魂がアルバムをとおして溢れんばかりにみなぎるなか、まるで箸休めのようなサッパリした感じの演奏はありがたい。ぼくにとってこの曲は、フェイヴァリット・ソングでもあるのだが、インストものにはなかなかお目にかかれない。すぐに思い出すのは、レッド・ガーランドの演奏。ガーランドもブロック・コードが得意だけれど、ナントンとは左手のコンピングのパターンがまったく違っていて、両者の演奏は似て非なるものだ。
はっきり云って、ナントンのスタイルはガーランドほど独創的ではない。そのかわり多種多様なテクニックで、リスナーを楽しませるようなところがある。少なからずバド・パウエルから影響を受けているのだろうが、パウエル派という印象は薄く両手を駆使したテクニックなどの豪華絢爛ぶりはオスカー・ピーターソンを想起させる。でもピーターソンほどエラそうではなくて、むしろそんなところがぼくは好きだったりする。盟友のエッジの証言によると、ナントンは控えめな性格らしい。トリオのスポークスパーソンは、常にエッジが務めていたという。ニュージャージー州パースアンボイ市出身のナントンにとって、ニューヨークはきらびやか過ぎたのか、1970年代以降の彼は地元である湾岸都市に引っ込んでしまう。
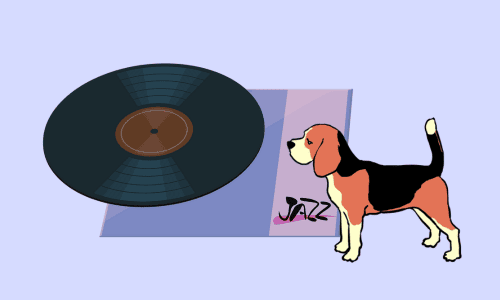
朝鮮戦争中に陸軍第5師団の音楽隊で演奏し、その後ニューヨーク市の名門ジュリアード音楽院で学んだナントンは、在学中よりプロとして活動していた。前述の『フラワー・ドラム・ソング』でデビューしたときは、29歳だった。ぼくの知るかぎりリーダー作は、さきに挙げたワーナー・ブラザースの2枚とプレスティッジの3枚のみ。そう、彼の吹き込みは、たったの5枚しかないのだ。プロフィールやキャリアの情報も含めて、ほんとうに謎だらけのひとだ。ニュージャージーに戻ってからのナントンといえば、盟友のベーシスト、エッジらとともに、コーヴというアットホームなライヴ・スポットや、上海ジャズという中華料理を提供するジャズ・クラブなどに出演していたという。彼は80歳でこの世を去ったが、最後の誕生日の前日までピアノを演奏した。
ということで、最後になってしまったがもう1枚、ナントンのプレスティッジにおける最後の吹き込み『ソウル・フィンガーズ』についてお伝えしよう。個人的にはイチオシの作品であり、殊に若いひとにはぜひとも聴いていただきたい1枚。そして、狭量な音楽観にとらわれることのないリスナーであれば、間違いなく楽しめるアルバムでもある。そういう点では『サムシング・ウィヴ・ガット』以上の傑作だと、ぼくは思う。前述のようにパーソネルには、ナントン(p)、エッジ(b)、ベルディーニ(ds)に、コンガ奏者のジョニー・マレー・ジュニアが加わっている。つまりスクエア・ビートが大胆に展開された、ナントン作品ではもっともキャッチーでエンジョイアブルなアルバム。いま何をおいても真っさきにCD化されるべきは、本作だろう。
オープナーはジェイ・ダグラスの「トラブルズ・オブ・ザ・ワールド」だが、さきに述べたプーチョ・アンド・ヒズ・ラテン・ソウル・ブラザーズとのコラボ・ナンバー。ハンドクラップまで飛び出すソウル・ジャズ。バンド・サウンドに意表を突かれるが、一気にこころをつかまれる。気の利いた前フリとして、軽く楽しむのがいい。ナントンも、クルマでいえば暖機運転中。次いでジョニー・マンデルの「いそしぎ」は、ミッドテンポの8ビート。カウベルの叩き出すラテンの律動に乗って、ナントンの黒いジャズ・スピリッツが徐々に燃え上がる。つづくホーギー・カーマイケルの「我が心のジョージア」は、スローな8分の6拍子。ピアノの哀愁に満ちたブルース・フィーリングが、シャッフルするサイドとともにフルスロットルに達していく様が感動的だ。
バート・ハワードの「フライ・ミー・トゥー・ザ・ムーン」では、長めのバロック風のイントロからシンコペーションが軽快なテーマ部への展開が鮮やか。グルーヴ感の溢れるブラジリアン・ジャズに気分が高揚するかのごとく、ナントンのプレイは次第にヒートアップしていく。A面ラスト、ジーン・デ・ポールの「四月の想い出」では、アップテンポのアフロ・キューバンから4ビートへと高速で駆け抜けていくコンガとピアノが痛快。ドラムスとの8バースもゴキゲンだ。ナントンの自作「ホイッスル・ストップ」では、スピーディーにラテンの複合リズムが展開されるなか、ライトトーンのピアノのアドリブがひたすら清々しい。ヘンリー・メイヤーの「サマー・ウィンド」では、おおらかなマンボ風のリズムと軽妙なタッチのピアノがスタイリッシュ。
ベルト・ケンプフェルトの「ラヴ」は、ハッピーなラテン・ジャズ。推進力のあるリズムと小気味よくドライヴするピアノに、ダンス・ミュージックへの本能的な反応が引き起こされる。モーリス・ラヴェルの「亡き王女のためのパヴァーヌ」のモティーフが流用された「ザ・ランプ・イズ・ロウ」では、唯一生粋のジャズが演奏される。モダンなムードとエレガントなフレージングは、元来スウィンガーであるナントンの面目躍如といったところ。ラスト、バート・デ・コトーの「ソウル・フィンガーズ」は、愁いを帯びたモーダルなワルツ。トリオ各々のソロが静かで激しい臨場感を溢れさせる、現代的な美しさをもったナンバーだ。以上、本作はソウル・ジャズのフルコースとでもいうべき贅沢なアルバムだが、ナントンに食指が動いたのならこれを食さない手はない。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。








コメント