不朽の名作映画『砂の器』──映画の感動を呼び起こす名盤『ピアノと管弦楽のための組曲「宿命」』
 Album : 菅野光亮 / 松竹映画『砂の器』サウンドトラックより ピアノと管弦楽のための組曲「宿命」 (1975)
Album : 菅野光亮 / 松竹映画『砂の器』サウンドトラックより ピアノと管弦楽のための組曲「宿命」 (1975)
Today’s Tune : ピアノと管弦楽のための組曲「宿命」
松竹映画『砂の器』は、果たして名作か駄作か?
1974年10月19日に公開された松竹映画『砂の器』は、果たして名作か駄作か?ぼくは、素直に名作だと思う。この作品──小学生のころ、父の勤め先があった東銀座の映画館、松竹セントラルにおいてロードショー時に、家族で鑑賞した。この映画館は、歌舞伎座のすぐ近くに在ったいまはなき松竹の旗艦劇場。現在跡地には銀座松竹スクエアという超高層ビルが建っている。あのころ子どもだったぼくは、スクリーンの大きさと座席の多さに激しく感動した覚えがある。そして、当時は映画を封切りで観にいくというのは、ちょっとした贅沢だった。ぼくと妹は母に連れられて、仕事を終えた父との待ち合わせ場所へ──。普段はあまり化粧っけのないの母だったが、その日はちゃんと着飾っていて、なんだか別人のようだった。ぼくと妹も、しっかりめかし込んで出かけたもの。
それから30年あまりのときを経た2005年6月18日のこと。『砂の器』のデジタルリマスター版が劇場公開された。撮影監督の川又昂監修のもと、当時の最新デジタル技術が用いられ再度マスタリングされたものだ。なお音声のほうもステレオ原盤から5.1chにリミックスされていた。実はこのときも、ぼくは映画館に出向いた。同伴者は、結婚するまえの妻。もちろんお洒落などはせず、ラフな格好で出かけた。時代が変わったのだ。ただこのときの上映館は東劇だったが、最寄り駅が東銀座ということで、なにか因縁めいたものが感じられた。そして、時代が移ろうとも変わらないものもある。この映画でいえば親と子の絆だ。それを確認するためではないけれど、ぼくはふたたびこの映画を観たくなった。やはり、人間の本質は変わらないのである。
繰り返しになるが『砂の器』は、果たして名作か駄作か?ぼくは、いま述べたようなことから、素直に名作だと思うのである。最初に公開されてから間もなくのことだが、この作品を「いも映画」と云った批評家がいた。たしかに監督の野村芳太郎の演出に、あか抜けたところはない。旧来の映画作法を打破するような斬新さや、映像の主体性を重視するようなスタイリッシュな感覚は、まったくもち合わせていないのである。また豪華なアクターたちの演技においては一部、過剰な身ぶり、意味もなくたたみかけるような口調、そして棒読みのセリフなど、その滑稽さを指摘したくなるところがある。野暮ったいと嘲りを受けるのも、わからないでもない。

しかしながら、野村監督といえば、もともと松竹大船撮影所で、職人的手腕を振るっていたひと。寅さんシリーズでおなじみの山田洋次と同様に、いわゆる大船調の家族で楽しめるような映画をたくさん撮ってきたのだ。そんな監督が、超大作映画、しかもサスペンス・ミステリーというジャンルに分類されるような作品を手がけたとき、事件の謎解きよりも、親と子の切っても切れない絆、あるいは人間の逃れることのできない宿命に焦点を当てるのは、ごく自然なこと。だからこそ『砂の器』は、多くの観客の涙腺を刺激する。おそらくミステリー映画というジャンルにおいて、この作品ほど観客を泣かせ、そして感動させた映画はほかにないだろう。ぼくのように、ときを経てふたたびこの作品を鑑賞したひとも、けっこう多いと思う。
やはり映画『砂の器』は名作だ。こう云っては失礼だが、どちらかといえば無味乾燥な松本清張の社会派推理小説を、よくぞここまで胸に迫る感動巨編に仕上げたものだ。いやいや、誤解しないでいただきたい。これは、清張作品にはほかにもっとスゴイ傑作がたくさんあるのに──という意味合いでの述懐である。とにもかくにも、この映画の成功要因のひとつは、共同脚本を務めた橋本忍と山田洋次による原作の大胆な改変であることは間違いない。ふたりは、小説の「親子の浮浪者が日本中をあちこち遍路する」という一節を作品の根幹的なテーマに据え、この親子の放浪を、日本の美しくも厳しい四季と重ねた壮大な映像詩に拡大したのである。なお、日本の春夏秋冬をフィルムに収めるのに、1973年の冬から翌年の初秋まで、およそ10カ月を要したという。
松竹は松本清張の小説ををずいぶん映画化しているが、野村監督がメガフォンをとることが多かった。そのなかでも、特に傑作として高く評価されるのは、やはり『砂の器』だ。もっとも、ミステリー映画として捉えると、とても巧妙に作られているとは云い難い。ミステリーといえば、序盤で事件が発生し、その犯人はいったいだれか、動機はなにか、どのように犯行に及んだのか──といった謎が不可思議な様相を呈したまま物語が進行し、終盤でそれらがすべて解き明かされるというもの。ところが、この映画にはそんなサスペンスフルでスリリングな展開はまったくなく、映画を観ていて不安や緊張を抱くような心理状態にさせられることはない。ただのお涙頂戴映画という批判は、この点に起因するのかもしれない。
芥川也寸志は音楽監督、ジャズ・ピアニストの菅野光亮が作曲を担当
でも、お涙頂戴のなにがいけないのだろう。観客に感涙を誘うような演出をするのは、決して容易いことではない。それにぼくだったら、映画館でおもいっきり泣かせてもらえたら、幸甚の至りである。劇場の座席では、スクリーンの光が反射するのみの薄暗がりだから、人目を憚ることなく泣ける──これこそ、映画館で映画を観る醍醐味だ。そして実際ぼくは、スピーカーからの音声が反響する劇場内において、まわりの座席から伝わってくる、静かで柔らかなすすり泣きの重奏を、たしかに耳にした。ぼく自身、この映画の山場(残り40分強)では、ついに涙を堪えることができなかった。
上映開始からおよそ1時間30分が経過したところで、映画ではいよいよ犯人に対して逮捕状が請求される。さらにその12分後、新進気鋭の作曲家の渾身の作、ピアノ協奏曲「宿命」が、作曲家自身のピアノ演奏と指揮によって初演される。彼には、他人には云えない暗い過去があった。それは──もう二度と会うことのできない父親との長く過酷な放浪の旅、旅の終わりとともににわかに訪れる父との別離、そして孤独な流浪への旅立ち、その後手に入れた偽りの人生と音楽家としての成功──という、彼がまだ6歳のときから現在に至るまでの体験である。涙なくしては観ることができないラスト40分強では、捜査会議と逮捕執行、コンサート会場での演奏、そして作曲家の回想が「宿命」という曲によってシンクロする。
脚本家も監督も、これをやりたかったのだろう。つまりそれは、べつべつの場所で起こる三つ出来事(シーン)が、音楽によってひとつのものとして分かちがたく結びつくということである。そして、この「宿命」という曲、原作小説には出てこない映画のオリジナルだ。小説における音楽家の肩書きは、前衛作曲家であり電子音響楽器研究家でもある。つまり彼の作品は、いわゆるミュージック・コンクレートのようなものだったのだろう。現代音楽が決してわるいわけではないが、さすがにここで不協和音を鳴らされたり無調音楽を流されたりしたら、映画は台なしだ。観客の感動を呼び起こすためには、音楽家を天才ピアニスト兼ロマン派の作風をもつ作曲家に設定変更することが、必須だったのである。そしてその計らいは、見事に成功した。
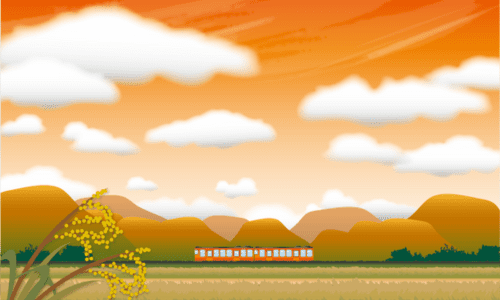
このクライマックスの高揚感あるいはカタルシスみたいなものは、とても言葉と映像だけでは生み出すことができなかったであろう。結局のところ、観客の感情を押し開き深層から真情を引き出すのは、音楽なのである。本作の音楽監督を務めたのは、日本を代表するクラシックの作曲家で指揮者でもある芥川也寸志。野村監督とタッグを組むことが多く、これまでに『ゼロの焦点』(1961年)*『左ききの狙撃者 東京湾』(1962年)『影の車』(1970年)*『砂の器』(1974年)*『八つ墓村』(1977年)『事件』(1978年)『鬼畜』(1978年)*『配達されない三通の手紙』(1979年)『わるいやつら』(1980年)*『震える舌』(1980年)『疑惑』(1982年)*と、計11作の野村作品の音楽を手がけた(*印は松本清張の小説が原作)。
とはいっても、芥川さんは『わるいやつら』ではヤマハポピュラーソングコンテスト(ポプコン)のアレンジャー&コンダクターとして知られる山室紘一と、さらに『疑惑』では日本を代表する現代音楽家、武満徹のアシスタントを務めた毛利蔵人と、それぞれ共同で音楽を制作している。また、芥川さんはその多忙さゆえか、音楽監督としてアドヴァイザーの立場にとどまることもあり、実際『事件』ではエレクトーン奏者の松田昌が、『震える舌』ではやはりエレクトーン奏者の小熊達弥が、それぞれ作曲を担当している。ちなみに、芥川さんはエレクトーン協奏曲ともいうべき「GXコンチェルト – GX-1とオーケストラのためのコンチェルト・オスティナート -」(1974年)という曲を作曲しているし、氏の三番目の奥様、江川真澄はエレクトーン奏者だった。
ところで、芥川さんは『砂の器』のときも音楽監督のポジションに収まり、作曲を東京藝術大学音楽学部の後輩にあたる菅野光亮に依頼した。菅野さんは、クラシック音楽の作曲法を学びながらも、大学卒業後はジャズ・ピアニストとして活躍するという変わり種。映像作品も多数手がけたが、残念なことに過労による体調急変のため、44歳という若さでこの世を去った。日本の美意識をジャズで表現した『詩仙堂の秋』(1973年)、唯一のピアノ・トリオ作『ホエン・ザ・ワールド・ワズ・ヤング』(1978年)、ゲイリー・フォスター(as, ss)をゲストに迎えたダイレクト・ディスク『ビューティフル・フレンドシップ』(1979年)、森寿男とブルーコーツとの共演盤『ドン・キホーテの詩』(1980年)、大野三平こと大野肇(p)、小説家とは別人の菊地秀行(as)も参加した『冬の終わりに A LA FIN D’HIVER』(1981年)といった、数少ないジャズ作品は、どれも出色の出来栄えだ。
クラシック作品の枠に収まらない音楽性をもつピアノ協奏曲「宿命」
そこで、注目したい曲がある。『ホエン・ザ・ワールド・ワズ・ヤング』に収録されている菅野さんのオリジナル曲「ティアドロップス・オブ・ジ・エンジェル」は、リリカルでセンチメンタルなメロディ・ラインが『砂の器』の音楽を彷彿させる。また『冬の終わりに A LA FIN D’HIVER』のラストを飾る「翳 La Part D’Ombre」という曲──オリジナルは、ヴォーカル・グループ、ロイヤルナイツの1966年から1977年にかけてのソ連公演に同行した菅野さんが、現地で吹き込んだもの。その際はクラリネットとギターを加えたクインテットでボサノヴァ風に演奏された。実はこの曲の一節が『砂の器』の音楽に流用されている。塩山付近を走る中央線の車窓から紙吹雪(実は紙ではなかった)が撒かれるシーン、さらに亀嵩駅で親子が抱擁し惜別する場面で流れる、あの美しい曲だ。
ほんとうに菅野さんの書く曲は、いつも叙情味に溢れていて淀みなく美しい。しかも難解なところがなく、一度聴いただけで口ずさめるようなメロディをもつ。そしてそれは、ピアノ演奏にもおなじことが云える。テディ・ウィルソンを敬愛する菅野さんのピアノ・プレイは、メロディアスでタッチが力強く、聴くものに鮮烈な印象を与える。ジャズ作品においては、モダンなコードとフレーズを次々に繰り出して、よくスウィングする。シングル・ノート、オクターヴ、ブロック・コードを上手く使い分けて盛り上げていく展開には、それこそスウィング・ピアノの巨人ともいうべきウィルソンのプレイを連想させるものがある。そのブリリアント・ピアノは、ジャズ・シンガー、上野尊子のデビュー・アルバム『グッド・モーニング・ハートエイク』(1977年)において、アカンパニストの立場でも大いに発揮された。
そんな菅野さんの独自のジャズ・センスは、クラシックの音楽観が下敷きとなっている──ということは明白だ。もし彼が純粋なジャズ・ミュージシャンだったら、現代音楽と日本の伝統音楽とをジャズ・スピリッツで融合させる──といったコンセプトのもと制作された、前述の『詩仙堂の秋』のような作品において、あれほど素晴らしい成果を上げることはできなかったであろう。逆に、菅野さんが純音楽の作曲家だったら、随所にロマンティシズムが横溢するような『砂の器』の音楽は書けなかったかもしれない。たしかに劇中に登場するピアノ協奏曲「宿命」には、ラフマニノフのピアノ協奏曲第2番をイメージさせるところがあるけれど、それは単に互いに甘美なメロディをもつという共通点があるから──。

ピアノ協奏曲「宿命」は、ピアノと3管編成のオーケストラによって演奏される。後期ロマン派から近代音楽にかけて、クラシック作品ではもっとも主流なスタイルだ。ただ「宿命」からは、純粋なクラシック作品の枠に収まらない音楽性が感じられる。それはこれまでにお伝えしてきた、作曲者である菅野光亮のひとつところにとどまらない音楽性そのものなのである。たとえば、現場検証のシーンで使用された音楽には、電子楽器が使用されており、ミュージック・コンクレートの要素が感じられる。ピアノのカデンツァには、ジャズのマナーが現れる。なによりもこの壮大な曲からは、西洋音楽にはないに日本的情緒が強く伝わってくるのだ。この点、芥川作品にもおなじ匂いが感じられることから、氏の助言が影響していると想像される。いずれにしても、映像との絶妙なマッチングにより感動を呼び起こす名曲、名演である。
演奏は、熊谷弘の指揮による東京交響楽団(映画にも出演している)。ピアノ演奏は菅野さん自身による。サントラ盤はいろいろリリースされているが、大別すると3タイプ。まず『砂の器 サウンドトラック』(1975年)──音楽、登場人物のセリフ、江角英明のナレーション、映画未使用の菅原洋一の歌唱曲「白い道」と「影」(作詞は岩谷時子)が収録されている。ホームビデオのない時代ならではの仕様だ。フィルムスコアリング手法によって吹き込まれたトラックの音盤(音楽のみのサントラ盤)は、CD時代まで待たなければならない。この『砂の器 映画オリジナル音楽集』(2014年)には、フィルム用ソースのほとんどが(映画での使用順に)収録されている。おすすめするのは、やはり『松竹映画 砂の器 (サウンドトラックより) ピアノと管弦楽のための組曲「宿命」』(1975年)のほう。フィルム・ヴァージョンとは別に、二部構成の組曲として吹き込まれた。鑑賞用(純粋なシンフォニー作品)としては、本作がベスト。
ということで、名作映画『砂の器』の名曲「ピアノと管弦楽のための組曲『宿命』」を、いま聴きながら、こんなことを思う──。前述の捜査会議のシーンで、刑事が、事件の全容解明において親と子の絆について触れたとき、感極まって不意に涙をこぼしてしまう。まあ、あまり現実的な描写ではない。もしかすると、馬鹿馬鹿しいとさえ思うひともいるかもしれない。なにせ「いも映画」と云った批評家がいるくらいだから──。でも、ぼくだったら一緒に泣くだろう。そんな自分に、ちょっと安心したりもする。そして、親子の放浪の原因となったハンセン病──現在は適切な治療によって治癒が可能になっている。この物語の父親のような患者はもうどこにもいないけれど、いないからこそ忘れてはいけない──と、ぼくは思う。『砂の器』とは、そんな思いとともに繰り返し観る作品なのである。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。








コメント