ピアノと管弦楽のための主題と変奏──ミシェル・ルグランのマスターピース『真夜中の向う側』
 Album : Michel Legrand / The Other Side Of Midnight (1977)
Album : Michel Legrand / The Other Side Of Midnight (1977)
Today’s Tune : Noelle’s Theme
ドルリューやレイをはるかに凌駕するインパクトをもつルグラン
ぼくが影響を受けたフランス出身の映画音楽の作曲家といえば、すぐにこの3人を挙げることができる。ジョルジュ・ドルリュー、フランシス・レイ、そしてミシェル・ルグランだ。小学校高学年のころから名画座通いをはじめたぼくが、最初に覚えたフランス映画の監督はフランソワ・トリュフォー。云うまでもなくヌーヴェルヴァーグを代表する監督のひとり。もちろん当時のぼくは、ヌーヴェルヴァーグの意味など知らなかったし、コトバ自体なんとなく聞き覚えがあるという程度だった。それでもトリュフォーの映画はジャン=リュック・ゴダールの作品にくらべれば、ずっと解りやすかった。だから当時から好きだったし、いまも好き。そしてトリュフォーといえば、ドルリューの音楽ということになる。
そんなわけで、小学生のぼくが最初に覚えた映画音楽の作曲家は、ドルリューだった。彼の音楽のいいところは、これまた解りやすいところ。音楽の知識がなくても、音楽に興味さえなくても、だれもが映画を観て、そこで流れる美しく洗練された音楽に感動を呼び起こされるだろう。ドルリューの創出する音楽は、そういうものだ。フランスでは、観客はドルリューの音楽を聴くために映画館へ足を運ぶとも云われる。なんともエスプリに富んだ云いまわしではないか。個人的には1960年代から1970年代の作品が好みなのだけれど、彼の簡潔で論理的なマナーによって創り出されるメロディとサウンドは、とにかく美しい。そんな素敵な才能の持ち主であるドルリューは、ルグランをして“最高の作曲家”と云わしめたほどだ。
ドルリューはときにジャズの要素を採り入れたりすることもあるけれど、どちらかというとヨーロッパの伝承音楽や芸術音楽の粋を集めたようなスコアを書くひとだ。その点で彼の音楽は、オーソドックスなスタイルとも云える。なんでもそうだけれど、正統派というものはいつの時代においても、案外古くならない。また、そういった様式の音楽を年をとってから聴くと、あらためてその素晴らしさに気づかされることさえあるのだ。音楽鑑賞もまた、亀の甲より年の功なのだろうか。それに自分が当てはまるかどうかは定かでないが、ぼくも最近またドルリューの音楽を聴き直したりしている。ところが10代前半のぼくといえば、すぐに目新しい音楽に惹かれてしまう。飽きっぽくて移り気が多いのは、やはり若さ故だろう。
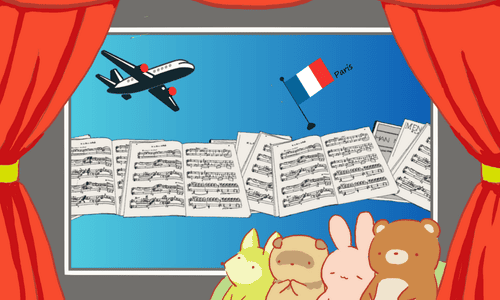
ぼくの関心は、ドルリューからフランシス・レイに移行する。レイはクロード・ルルーシュ監督とコンビを組むことが多かった。ぼくの場合もご多分に漏れず、ルルーシュの代表作『男と女』(1966年)をはじめて観たとき、すっかりレイの音楽のとりこになってしまった。ちなみにルルーシュはぼくにとって、昔もいまもフランス映画においてもっとも好きな監督だ。彼はデビュー当時、映画批評誌『カイエ・デュ・シネマ』に酷評されたこともあるけれど、ぼくにとっては人生の過酷さ、素晴らしさをリアルに、そしてスタイリッシュに教えてくれるメンターのような存在。映像が瀟洒であれば、音楽もまたあか抜けている。レイが書く曲をひとことで云えば、とにかくお洒落。ルルーシュ作品における映像とのマッチングは絶妙だ。
レイは天才的な音楽家だ。彼はヒラメキで音楽を創るひと。もともと彼はアコーディオン奏者で、画家たちが集まることで知られるパリのテルトル広場あたりで、路上パフォーマンスをやっていた。そんなレイ、実は楽譜を読むことも書くこともできないのだ。それでも創出される曲は、いつも流麗な旋律をもっている。その点で、彼は稀代の天才メロディメーカーと云うことができる。フランスの香りが漂う哀愁を帯びた曲調は、他の追随を許さない。当然のことながら、レイが生み出した数々の名曲のオーケストレーションは、本人のペンによるものではない。多くの作品は、作編曲家のクリスチャン・ゴベールがアレンジを担当している。ゴベールのアレンジは、柔らかく心地いい甘さをもちながら都会的でもある。レイが生み出す、美しい調べとの相性は抜群だ。
そして最後になるが、ぼくが3人のなかでもっとも長い期間、そしてもっとも多くの作品を聴いたひとといえば、ミシェル・ルグランだ。ルグランにもさきのふたりと同様に、ジャック・ドゥミという最高のコンビネーションを発揮する監督がいた。彼もまたヌーヴェルヴァーグのひととされているけれど、ひとの営みをミュージカルやファンタジーで表現したロマンティックな作品を多く残している。名画座で『シェルブールの雨傘』(1964年)と『ロシュフォールの恋人たち』(1967年)を立てつづけに観たぼくは、その独特の映像世界とそれを彩る数々の音楽に、すっかりこころを奪われてしまった。ドゥミ作品で描かれるのは、ある意味で非常に現実離れした、情緒的で甘美な世界。ルグランの華麗なサウンドが、それを上手くもち上げている。
レイが天才ならば、ルグランは天才的な山師だ。いささか云いかたがわるくなったが、彼の技巧が凝らされた豪華絢爛な音楽表現を目の当たりにすると、ついそんなイメージをもってしまう。ドルリューやレイの音楽にはじめて触れたときも、いたく感動させられたけれど、ルグラン・サウンドとの出会いには、それをはるかに凌駕するインパクトがあった。小学生とはいえピアノを弾き作曲や編曲にも興味をもちはじめていたぼくは、彼の書くスコアにすこぶる好奇心がそそられたもの。しかしながら実際には、ルグランのアレンジを真似しても絶対に上手くいかない。プロの音楽家においても、彼のマナーを模倣して失敗している例をしばしば見かける。ルグランはもっとも合理的かつ効果的にオケを鳴らす方法を知り尽くしていて、さらにそこから飛躍するのである。
管弦楽の魔術師ルグランの才気煥発の極みといえばアレンジメント
そう、ルグラン・サウンドが、通常のオーケストレーションとひと味もふた味も違うのは、音楽上のアイディアに大きなブレークスルーが生み出されているというところ。彼は実に要領よくハッタリを利かせる。パリ国立高等音楽院でピアノ演奏とともに和声学をしっかり学び、同校を首席で卒業したルグランだけに、楽器の組み合わせかたや演奏のさせかたに精通しているのは当然のこと。彼は一般的な音楽理論はもちろんのこと、汲めども尽きぬ知恵の泉をもってして、すべての楽器が渾然一体となった世界を創り上げる。惜しげもなく大きく展開されるルグラン・サウンドは、けっこう派手に聴こえるのだが、決して乱脈を極めることもなく心地よく響くから不思議だ。そんな劇的効果を出せるのは、世界広しといえども彼だけだ。
またルグランの特徴として、ソングライティングにおいてモティーフ・ディベロップメントが多用されることが挙げられる。おそらくルグラン自身にとってはお茶の子さいさいな技法、というかもはや無意識にやっていることなのかもしれない。彼がピアノに向かい左手でコードをラフに進行させながら、右手でつぎつぎにメロディを展開させていく光景が目に浮かぶようだ。それもなんとなく鼻歌まじりにやっていそう。と、これは飽くまで音を聴いたときのぼくの空想で、実際はちゃんと作曲しているのだろう。いずれにしても、ルグランの十八番とも云える、ひとつのモティーフを展開させるようなパターンには、楽曲を一聴したリスナーのハートに強く刻みつける作用がある。そんな点からも彼のことを、モーリス・ラヴェルではないが、音の魔術師と云いたくなる。
さらにドルリューやレイにはないルグランの強みは、ジャズを素材として扱うのではなく本格的に演奏することができるということ。26歳のルグランは新婚旅行を兼ねてアメリカを訪れた際、マイルス・デイヴィス(tp)、ジョン・コルトレーン(ts)、ビル・エヴァンス(p)ほか、ニューヨークの敏腕ジャズメンたちとともに、名作『ルグラン・ジャズ』(1958年)を吹き込んでいる。ルグランはアレンジと指揮に徹しているが、彼らしくハープなども入れたりしてユニークなモダン・ジャズを披露した。曲目がジャズ・プレイヤーが好みそうな渋めのセレクションで、実に興味深い。その20年後の吹き込み『ジャズ・ルグラン』(1979年)では、全曲彼のオリジナルでまとめられている、ルグランならではのビッグバンド・サウンドが冴えわたる好盤だ。

ついでだから云っておくと、ルグランはジャズ・ピアニストとしても何枚かアルバムを残している。1990年代には日本のレーベル、アルファ・ジャズからピアノ・トリオ作品をリリースして好評を得た。もっとも有名なのは、名門ヴァーヴ・レコードからの1枚『シェリーズ・マン・ホールのミシェル・ルグラン』(1968年)だろう。ピアノ・トリオでの吹き込みだが、レイ・ブラウン(b)、シェリー・マン(ds)といったサイドメンの人気からか、日本では評価が高い。マンがオーナーを務めるハリウッドの有名クラブでの実況録音盤だが、ライヴのせいかミュージシャンたちはかなり自由に演っている。ただルグランのピアノは、ちょっとデリカシーに欠けていて、うんざりさせられる。お得意のスキャットにも、気分がわるくなってくる。
きっぱりと云うけれど、ルグランはジャズ・ピアニストとしては、ぼくの苦手なタイプなのだ。もっとハッキリ云えば、彼はピアノ演奏が、あまり上手くない。これでもかというほど指を動かしているけれど、オーケストラのアレンジのときとは違い混沌たる音の氾濫に、思わず耳を覆いたくなる。ジャズのレコードとしては、パブロ・レコードからリリースされた『アフター・ザ・レイン』(1983年)のほうがまだ聴ける。セプテットによる吹き込みで、ジョー・ワイルダー(tp, flh)、ズート・シムズ(ts)、フィル・ウッズ(as, cl)らがフロントを務めている。ルグランはピアノのほかにフェンダー・ローズやオルガンを弾いているが、バッキングに徹している。それでいい。全曲ルグランのオリジナルにしては、いぶし銀の選曲となっており、却って好感度が高い。
いずれにせよ、ルグランの才気煥発の極みといえば、アレンジメントなのである。オーケストレーションの天才であり、しかもそのメソッドは異能異才と云える。ぼくはまえに彼のことを、ラヴェルの異名を拝借して音の魔術師と呼んだけれど、厳密には管弦楽の魔術師と云うほうが正解なのかもしれない。では、そんなルグランのマスターピースはなにかというと、ちょっと選ぶのが難しい。なぜなら、彼の手がけた音楽作品が、まあとにかく膨大な数に上るからだ。サウンドトラック以外の個人名義のアルバムだけでも相当ある。デビュー作である、ミシェル・ルグラン・アンド・ヒズ・オーケストラの『アイ・ラヴ・パリ』(1954年)はあまりにも有名だが、ルグランはまだ22歳だった。
ちなみに、このアメリカのコロムビア・レコードからリリースされたアルバムには、実は続編がある。すぐに『ホリデイ・イン・ローマ』(1955年)と『ヴィエナ・ホリデイ』(1955年)が立てつづけに制作され、そして『キャッスルズ・イン・スペイン』(1956年)、さらには『ルグラン・イン・リオ』(1957年)が発売された。フランスにはじまり、イタリア、オーストリア、スペイン、ブラジルと、音楽の世界旅行を楽しむことができるといった趣向が凝らされたシリーズだ。どれも良質のイージーリスニング作品だが、そこにはまだ極めて独自性の高いルグラン・サウンドはない。しかしときおり、ストリングスの動きなどに彼らしさが垣間見られる。個人的には、各国の名曲を知る上で大いに役立った。
ぼくがよく聴いていたのは、当時日本でも発売されていた、ベル・レコードからリリースされた『ブライアンズ・ソング』(1972年)と『トゥエンティ・ソングス・オブ・ザ・センチュリー』(1974年)、RCAレコードからリリースされた『パリの恋人たち』(1972年)と『ミシェル・ルグランの世界』(1976年)、さらにルグランとは共演歴の多い、アルト奏者のフィル・ウッズがフィーチュアされた『イメージ』(1975年)といったレコード。特に聴きこんだのは2枚組の『トゥエンティ・ソングス・オブ・ザ・センチュリー』だ。収録曲はルグランの自作が「シェルブールの雨傘」のみで、残りの19曲は20世紀を代表する名曲のカヴァーとなっている。ルグランのアレンジのマナーを知るには、あつらえ向きの作品だった。
ロマン主義音楽のスタイルに徹したルグランのマスターピース
ぼくはこの作品を昔から、とてもエキサイティングなアルバムだと思っている。どこがといえば、たとえばヘンリー・マンシーニの「ムーン・リヴァー」やザ・ビートルズの「イエスタデイ」あるいはサイモン&ガーファンクルの「明日に架ける橋」といったオリジナルの完成度が高い楽曲が、まるでルグランの自作曲のように聴こえてしまうところ。ジョゼフ・コズマのシャンソン「枯葉」に至っては、あの有名な主題が見事に変奏され、まるで管弦楽のための音楽作品のような様相を呈している。この手があったかと、目からウロコが落ちた。なお当時のぼくは『パリの恋人たち』を、実はクリストファー・マイルズ監督のイギリス映画『ア・タイム・フォー・ラヴィング』(1972年)のサントラ盤であると知らずに聴いていた。日本盤にはそれに関する記載が、まったくなかったからだ。
この『パリの恋人たち』というレコードが日本で発売されたのは、英国でオリジナル盤がリリースされてから5年後の1977年のこと。映画は日本では未公開だったし、ルグラン本人をはじめ、英国のポップ・シンガー、マット・モンローや、ロックの殿堂入りを果たした女性シンガー、ダスティ・スプリングフィールドがフィーチュアされているものだから、本作が純然たる音楽作品と勘違いされるのもよくわかる。ちなみにヴォーカル・ナンバーはすべてルグランが作曲、南アフリカケープタウン市出身のソングライター、ハル・シェーパーが作詞したものだ。シェーパーは、アルバムのプロデューサーも務めている。インストのほうも、クラシック、ミュゼット、ディキシーランド、クール・ジャズといった鮮彩な構成となっており、存分に楽しめる。
結果的には『パリの恋人たち』はサントラ盤だったわけだが、ぼくは本作をまったくサウンドトラックとは意識せずに聴いていた。よくよく考えると、ぼくはルグランの音楽を、サウンドトラックであろうとオリジナル・レコーディングであろうと、フラットな感覚で受けとめていたように思う。それはピアノ演奏はともかく、彼のサウンドクリエイターとしての魅力が、どんなシテュエーションにあっても恒常的に保たれているからだろう。ルグランの音楽は、いつもルグランしているのだ。では、この『パリの恋人たち』と同様に、ぼくが鑑賞用音楽として聴きつづけているサントラ盤のなかで、特に思い入れのある作品をご紹介しておこう。ただぼくの好みは、作品の知名度に依存することがないので、いささか地味なセレクションと云われるかもしれない。
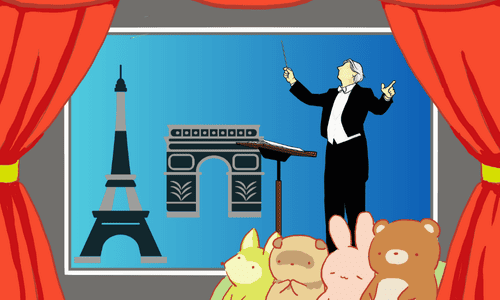
1950年代から膨大な本数の映画にスコアを提供してきたルグランだけに、ぼくが彼の作品を聴きはじめたころには、日本でもすでにその名がとどろきわたっていた。もちろんぼくも、ジャック・ドゥミ監督作品を中心に、数々の名曲に触れていた。しかしながら、個人的な好みを告白すると、過去の名盤よりもリアルタイムで聴いた『真夜中の向う側』(1977年)『火の鳥』(1977年)『ベルサイユのばら』(1979年)のほうが、いまに至るまで愛聴盤となっている。市川崑の監督作品『火の鳥』は、主題曲とそのヴァリエーション風に仕立てられた交響組曲という構成。ルグランの指揮によるロンドン交響楽団の演奏は、聴きごたえがある。映画とはなんの関係もない、アーヴ・ロイがアレンジしたフォー・オン・ザ・フロア「ルグラン・ヒット・メドレー」の収録も嬉しい。
ジャック・ドゥミの監督作品『ベルサイユのばら』では、厳かな管弦楽をはじめ、ロココ調の軽やかな音楽、優雅な宮廷音楽など、18世紀のフランスが意識されたクラシカル・ナンバーが並ぶ。そのいっぽうで、レコードのAB面各々のトップに置かれた「ベルサイユのばら -メインテーマ-」と「王子ルイ・ジョセフのテーマ」のようなオーケストラル・ポップもあり、アルバム全体の印象に彩りの美しさが際立つ。ところが『火の鳥』にしても、この『ベルサイユのばら』にしても、映画自体は成功しているとは云い難い。どちらも日本産の作品だが、それぞれアルファレコードの村井邦彦、キティ・レコードの多賀英典といった伝説の音楽プロデューサーが、製作に携わっている。だからサントラ盤は、映画の出来とは関係なく高品質なのだ。
そして最後になったが、英国出身のチャールズ・ジャロットが監督したアメリカ映画『真夜中の向う側』について──。フランスの女優マリー=フランス・ピジェと、アメリカの女優スーザン・サランドンとによる美の競演。日本では超訳シリーズで人気を博したシドニィ・シェルダンのミステリー仕立ての大河小説が原作。申し訳ないが、映画は長過ぎでちょっと退屈した。だが音楽は、ことごとく素晴らしい。ぼくにとっては、数あるルグランの作品のなかでも、これぞというマスターピースだ。ただリズム・セクションの入らないオーケストラによる、ロマン主義音楽のスタイルに徹しているところは、彼のスコアとしては珍しい。アルバムは、ルグランの作品を多く手がけたノーマン・シュワルツのプロデュースのもと20世紀レコードからリリースされた。
アルバム冒頭の「プロローグ(ノエルの物語)」は、地中海地方の民族音楽風のイントロからストリングスによるロマンティックな主題へと進行。ダイナミックなシンフォニック・サウンドを堪能することができる。映画全体のテーマとなる曲だが、半音階、反復進行、そして転調といった、ルグラン節のトレードマークが満載だ。8分音符と4分音符との「タタタン タタタン」というフレーズが延々とつづくのだ。6小節のモティーフがメジャーからマイナーへ変化するところも彼らしい。ルグランの作品では、この曲がぼくはいちばん好きだ。実は「ラリーの帰還」「パリのモンタージュ」「デメリスのもとへ」「ラリーとノエル」「エピローグ(さよならノエル)」といった曲はすべて、このテーマの変奏となっている。
そんなヴァリエーションのなかでも白眉は、ピアノの協奏的ラプソディ「ノエルのテーマ」(長短の2ヴァージョン収録)だろう。コントラバスのバウンスとハープのアルペジオがリズム感と深みを演出するなか、弦と管がゆったり主題を奏でる「デメリスのパーティー」も、なかなか心地いい。そのほかの曲といえば、ストリングスのアンサンブルによる軽妙なワルツ「ノエルの唄」モーツァルトのセレナーデ風「デメリスの晩餐会」やはりクラシカルな優雅と静謐を湛えた「晩餐のあとで」といったソース・ミュージックしかない。だからぼくはこの音楽作品を、ピアノと管弦楽のための主題と変奏みたいに楽しいんでいる。それだけ、このテーマ曲は素晴らしい。ビル・エヴァンスの『アフィニティ』(1979年)で、早々にカヴァーされたくらいだ。このトゥーツ・シールマンスのハーモニカがフィーチュアされたエヴァンス版も絶品なので、ぜひ本家ともどもご賞味あれ。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。








コメント