ロバート・レッドフォードの監督、マーク・アイシャムの音楽で送る、テレビ番組のスキャンダルが描かれた社会派サスペンス『クイズ・ショウ』のサウンドトラック・アルバム
 Album : Mark Isham / Quiz Show From The Original Motion Picture Soundtrack (1994)
Album : Mark Isham / Quiz Show From The Original Motion Picture Soundtrack (1994)
Today’s Tune : Your Secret’s Safe With Me
あのジャズ・スタンダーズが象徴的に使用された重厚な人間ドラマ
ジャズ・スタンダーズのなかに「モリタート」という有名な曲がある。ジャズ・ファンだったら真っ先に思い浮かべるのは、テナー奏者、ソニー・ロリンズのアルバム『サキソフォン・コロッサス』(1956年)の収録曲であるということ。ロリンズらしく明るくて温かみのある演奏は、何度聴いても気持ちがいい。個人的には、サイドメンを務めたトミー・フラナガンのピアノ・プレイに影響を受けた。この曲は多くのジャズ・プレイヤー、ことにシンガーに採り上げられているけれど、もともとは1928年初演のミュージカル『三文オペラ』の劇中歌。ドイツの劇作家、ベルトルト・ブレヒトが戯曲を書き、やはりドイツの作曲家であるクルト・ヴァイルが音楽を手がけた。この劇中歌、当初は「メッキー・メッサーのモリタート」というタイトルだった。
原曲のドイツ語の歌詞はブレヒトが書いたものだったが、1954年のニューヨーク公演の際、アメリカの作曲家、マーク・ブリッツスタインが英語詞を付して「マック・ザ・ナイフ」というタイトルで知られるようになった。その昔「匕首マック」というスゴい邦題が付いていたけれど、匕首(あいくち)などと云われても、いまのひとにはなんのことやらさっぱりわからないだろう。要はツバのない短刀のことで、サメのような歯を真珠色に光らせているオトコ、マックはそれとおなじようなジャック・ナイフを忍ばせているヤツ──と歌われているところからきている。このミュージカルの主人公、マック・ザ・ナイフことメッキー・メッサーは貧民街の顔役、いわゆるギャングなのである。なおこのミュージカル、何度か映画化もされるほどの人気作である。
この曲、すでにあのサッチモことルイ・アームストロングが歌っていたのだが、大ヒットしたのは俳優でもあるシンガーのボビー・ダーリンが歌ったとき。彼が1959年に発表したシングル「マック・ザ・ナイフ」は、ビルボード誌のホット100において10月5日からの9週間、第1位を記録するメガヒットとなった。当時のポップス・シーンにおいては、驚異的な記録と云える。 またダーリンは、翌1960年にこの曲でグラミー賞の最優秀レコード賞を獲得している。さらにダーリン版の「マック・ザ・ナイフ」は、1999年にグラミーの殿堂入りを果たしている。なおこの曲は、ダーリンのセカンド・アルバム『ザッツ・オール』(1959年)に、有名な「ビヨンド・ザ・シー」とともに収録されているので、ぜひ聴いていただきたい。
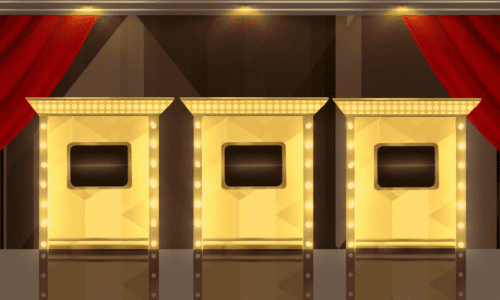
ところで、このボビー・ダーリンが歌った「マック・ザ・ナイフ」こと「モリタート」だが、ある映画のオープニングのシーンで使用されている。それは1950年代に実在したNBCの人気テレビ番組『21(トウェンティワン)』をめぐるスキャンダルが描かれた、社会派ドラマ『クイズ・ショウ』(1994年)という作品。ジョン F. ケネディおよびリンドン・ジョンソン政権でスピーチライターや補佐官を務めた、アメリカの政治顧問で作家のリチャード N. グッドウィンの著書『60年代アメリカ衝撃の真実』(1988年)が映画化されたものだ。監督は俳優のロバート・レッドフォードが務めた。レッドフォードが惜しまれくも89歳で、2025年9月16日の朝、ユタ州プロボ郊外の自宅において就寝中に死去したことは、まだ記憶に新しい。
ちなみに映画のなかで、原作者のグッドウィンは立法管理小委員会の捜査官、ディック・グッドウィンとして描かれている。1991年から1993年まで3年連続でゴールデングローブ賞テレビドラマ部門最優秀男優賞にノミネートされたことで、当時熱い視線が注がれていた俳優、ロブ・モローが演じた。むろん、ジョン・タトゥーロ演じる、テレビ番組の不正を告発するハービー・ステンペル、そしてレイフ・ファインズ演じる、自らが番組のやらせに加担したことを告白する元コロンビア大学の講師、チャールズ・ヴァン・ドーレンも、ともに実在の人物。クイズ・ショウ・スキャンダル(1956年 – 1959年)は、ケネディ暗殺事件(1963年)、ウォーターゲート事件(1972年 – 1974年)とともに、アメリカの20世紀後半における国民的な信頼の崩壊を招いた、重要な出来事なのである。
この映画のメガホンをとったレッドフォードは、ハリウッド屈指の二枚目俳優として広く知られているけれど、その演技力も然ることながら製作人としても傑出した能力を発揮したひと。監督としては、自身の出演作で確立したイメージに依存することなく、この『クイズ・ショウ』もそうだが多くの場合、アメリカ社会の歪みや真実を批判精神をもって描き出していた。たとえば、監督としてのデビュー作であり、アカデミー作品賞および監督賞、ゴールデングローブ監督賞を受賞した『普通の人々』(1980年)では、アメリカのどこにでもある家庭の家族間の崩壊と再生、そして人間の内面的な葛藤を繊細に描いた。しかも一般的なハリウッド作品のような派手な演出はせず、物語の本質を誠実に伝えることに集中している。その控えめで静かなトーンには、ぼくも大いに感銘を受けた。
ほかにも、環境破壊と開発をテーマとしたファンタジックな作品『ミラグロ/奇跡の地』(1988年)、古きよきアメリカの自然や家族の絆が叙情的に描かれた『リバー・ランズ・スルー・イット』(1992年)、現代的な都会生活のストレスに対する癒しとこころの再生の物語『モンタナの風に抱かれて』(1998年)、政治とメディアの責任を問うリアルな現代ドラマ『大いなる陰謀』(2007年)といったレッドフォードの監督作品では、一貫して人間の尊厳や道徳、あるいは誠実さが追求されている。どれも観客を圧倒するような視覚的なインパクト、壮大なアクション、煌びやかな世界観とは無縁だが、観るものに静謐を湛えた深い感動と社会的な視点を与える。そういうレッドフォード監督作品の特徴は、彼の人間性の現れでもあるのだ。
ということで、この『クイズ・ショウ』もまた、いかにもレッドフォードの監督作品らしいメディアの功罪や正義、誠実さとはなにかを問いかける重厚な人間ドラマとなっている。むろん本作は、1950年代後半を舞台とするテレビ番組のやらせスキャンダルが描かれた実話ベースのサスペンスとしても、あるいは緊張感溢れる生放送のクイズ番組が再現された心理エンターテインメントとしても十分に楽しむことができる作品に仕上がっている。実話に基づいた物語は、人気テレビ番組『21』に出演する一般人で知識豊富なクイズ王、ステンペルを、番組側サイドが視聴率低下を理由に降板させようとするところからはじまる。番組のプロデューサーは、新たなクイズ王としてステンペルから見栄えのいい大学講師、ヴァン・ドーレンへ交代させるため、彼にクイズの解答を事前に教えようとする──。
ジャズとクラッシックとの両ジャンルにまたがってスコアを書く音楽家
冷遇され憤慨したステンペルは番組の八百長を大陪審に告発するが、なぜか封印されてしまう。封印ということに疑問を覚えた、立法管理小委員会の捜査官、グッドウィンはテレビ局の不正を暴こうとニューヨークに向かう──。まあこれ以上ストーリーをお伝えするとネタバレにもなるので、この辺でやめておくことにするが、本作では視聴率のためなら嘘も厭わないテレビ業界の裏側、テレビの全盛期のアメリカ国民の異常な熱狂、そして不正が明るみに出る過程の緊迫感が、鋭いタッチでリアルに描写されている。情報量の多さから主に前半では作品世界に集中しにくい部分もあるが、レッドフォードの冴えた演出が功を奏し、最後まで観客を飽きさせない構成となっているので、未見のかたにはぜひともご覧いただきたい。
さて、ここでハナシを音楽に戻すが、映画の冒頭といえば、自動車の展示場でグッドウィンがクルマの仕様について販売員から説明を受けているシーン。やがて彼をコックピットに座らせるまでに至ったそのクルマとは、1958年型のクライスラー、すなわちピカピカの最新モデルだ。そして豪華な自動車は、当時のアメリカン・ドリームの象徴でもある。クライスラーのラジオからは、ソビエト連邦が開発した世界初の人工衛星スプートニク1号の打ち上げ成功を伝えるニュースが聞こえてくる。そしてグッドウィンがラジオのボタンを押し直すと、ボビー・ダーリンの歌う「マック・ザ・ナイフ」が流れ出す。それはあたかも、やがてアメリカの全国民が感じることになる、完璧だった日常の揺らぎから生まれる不安を、暗示するかのような場面だ。
よくよく考えてみると、公職に就くグッドウィンが、自分の給料では到底買えない高級車を眺めるというこのシーン、この映画のテーマを上手く表している。つまり一見物語に直接関係のないように思われるこの場面、実は名声や金銭の誘惑、そしてそれに関わる道徳的葛藤を、視覚的に提示したものなのである。そこにきて、ボビー・ダーリンの「マック・ザ・ナイフ」だ。ダーリンの小気味いい歌唱が牽引する軽快でスウィンギーなサウンドが流れるなか、ひきつづきスタジオの観客の歓声、カメラのフラッシュ、司会者の熱気、クイズ挑戦者の緊張の面持ちなどがダイナミックに展開されていく。そしてギャングのことを軽快に謳ったこの曲は、その時代の雰囲気を醸し出すものであるのと同時に、クイズ番組の不正という、裏にあるダークな要素を暗示するものでもあるのだ。

ただし、このダーリンが歌った「マック・ザ・ナイフ」こと「モリタート」は、映画のサウンドトラック・アルバムには未収録なので、聴きたいかたは前述のアルバム『ザッツ・オール』を手にとっていただきたい。アトランティック・レコードのサブ・レーベルであるアトコ・レコードからリリースされたこのレコードは、もちろん日本でも発売されたしすでにCD化もされている。なお『クイズ・ショウ』のサントラ盤のほうには、ライル・ラヴェットが歌ったヴァージョンが収録されている。ラヴェットはオルタナティヴ・カントリー系のシンガーソングライターだが、俳優としても多くの映画作品に出演しているひと。特にロバート・アルトマンの監督作品では常連となっており、顔を見たら「ああ、あのひとか」と思う向きも多いだろう。
ラヴェット版の「モリタート」は映画のエンドクレジットで使用されているが、映画のために新たに吹き込まれたものだ。アレンジは映画のアンダースコアも手がけた作曲家、そしてトランペッターのマーク・アイシャムが担当。映画のエンディングに漂う、スキャンダルの真相が暴かれたあとの虚無感と皮肉とが交じり合った、ほろ苦く静かなムードをそのまま表現したアイシャムのアレンジが素晴らしい。オープニングで使用されたボビー・ダーリンの明るく軽快なヴァージョンとのコントラストが、より高まっている。こんなにビターな味わいの「モリタート」は、あとにもさきにもこのヴァージョンしかないのではなかろうか。終盤で華やかなテレビ業界の裏側に潜む人間の弱さと、組織の非情さが浮き彫りになるという、社会派映画らしい苦味のあるあと味にピッタリだ。
それでは、ここからは映画『クイズ・ショウ』の音楽、サウンドトラック・アルバムについてお伝えしていこう。物語の背景になっている1950年代後半を音楽で描写するには、ダーリンの「マック・ザ・ナイフ」と同様に当時のヒット曲を並べるという方法もあっただろう。しかしながら監督のレッドフォードは、ほかの作品でしばしば見られるそんな常套手段を好まなかった。その代わり彼は、ビッグバンドやコンボによるスウィンギーかつモダンなジャズ・サウンド、そしてオーケストラによるシリアスあるいはリッチなクラシカルなスコアを採用した。もちろんオリジナル曲ばかりである。そして、そんなジャズとクラッシックとの両ジャンルにまたがってスコアを書く音楽家として、白羽の矢が立ったのがマーク・アイシャムである。
このときアイシャムにとって、レッドフォードの監督作品の音楽を手がけるのは、はじめてのことではなかった。ノーマン・マクリーンの自伝的処女作『マクリーンの川』(1976年)を原作とした、まだ無名だった俳優のブラッド・ピットの出世作でもある『リバー・ランズ・スルー・イット』のノスタルジックでちょっとセンチメンタルなスコアは、アイシャムによるもの。レッドフォードにとっては監督第3作に当たるが、アカデミー賞において撮影賞を獲得している。あのモンタナ州の雄大な自然とフライ・フィッシングの美しい描写において、古風ではあるが素朴で温かみのある音楽で彩りを添えていたのは、アイシャム。つまり『クイズ・ショウ』の音楽担当は彼にとって、レッドフォード監督作では2度目の登板だったのである。
それまでのレッドフォードといえば、第1作『普通の人々』ではマーヴィン・ハムリッシュ、第2作『ミラグロ/奇跡の地』ではデイヴ・グルーシンと、過去に自分が俳優として主演を務めた映画の音楽を手がけた作曲家を起用している。ハムリッシュはレッドフォード主演の『追憶』(1973年)の音楽を担当、アカデミー作曲賞を獲得している。かたやグルーシンは『コンドル』(1975年)『出逢い』(1979年)『ハバナ』(1990年)と、レッドフォードが出演した3作品の音楽を手がけている。興味深いのは、いま挙げた都合4作品はすべてシドニー・ポラックがメガホンをとった映画であること。実はレッドフォードはポラックのことを、お互いの感性とリズム感を深く共有し合える、もっとも信頼できるコラボレーターと、高く評価していたのだ。
クァルテット、ビッグ・バンド、オーケストラと、3つのスタイルで録音
ポラックの映画といえば、社会的にはリベラル、政治的にはモデレート、そしてストーリーラインはとてもリアルだ。ラヴ・ストーリーを描いても甘口にはならないし、サスペンス・スリラーを取り扱っても過剰な演出はしない。この辺りは、レッドフォードの監督作品とも共通する。そしてポラックが厚い信頼を寄せていた作曲家といえば、ほかでもないグルーシンである。25年ほどつづいたふたりの名コラボレーションをあらためて振り返ると『ザ・ヤクザ』(1974年)『コンドル』(1975年)『ボビー・デアフィールド』(1977年)『出逢い』(1979年)『スクープ 悪意の不在』(1981年)『トッツィー』(1982年)『ハバナ』(1990年)『ザ・ファーム 法律事務所』(1993年)『ランダム・ハーツ』(1999年)と、9本を数える。
さらにポラックがメガホンをとらず製作総指揮を手がけた『恋のゆくえ/ファビュラス・ベイカー・ボーイズ』(1989年)でも、グルーシンが音楽を担当した。ハリウッドのコマーシャリズムとは一線を画すようなポラックの作風が、ぼくは大好きなのだが、グルーシンもまたハリウッドの伝統を汲みながら、ちょっとそこから逸脱するような多様性と革新性をもった音楽家。そういう点で、ポラックとグルーシンとの相性は抜群だった。そして『ミラグロ/奇跡の地』におけるレッドフォードとグルーシンとのコンビネーションも、また絶妙。物語の舞台となったニューメキシコの風土が反映されたグルーシンのスコアは、ラテン・ジャズやフォークロアのエッセンスが採り入れられた詩情豊かな美しいサウンドを極めていた。
なおグルーシンはこの映画で、アカデミー作曲賞を受賞、ゴールデングローブ賞の作曲部門にもノミネートされた。グルーシンは個人的にもっとも敬愛する音楽家なのだけれど、ぼくは当然のように『ミラグロ/奇跡の地』で見事栄冠に輝いた彼が『リバー・ランズ・スルー・イット』でも起用されるものと、勝手に思い込んでいた。でもフタを開けてみると、スコアを一任されたのはアイシャムだった。実はレッドフォードは、音楽が物語を説明し過ぎることを好まず、映像の邪魔をすることなく、それでいて情緒を深めるような、控えめなサウンドを求めていたのだ。むろんグルーシンの音楽も決して出しゃばるようなことはないが、彼は映画音楽の作曲家であると同時に、コンテンポラリー・ジャズ・シーンの押しも押されもせぬ人気アーティスト。そのサウンドは、すでに強い個性を放っていた。

その点、アイシャムは当時まだそれほど手垢のついていないアーティストだったし、シンプルさと繊細さをもってして物語の感情的な核心を支える能力に長けていた。彼は過去にトランペッターとして、ECMレコードにおいてパフォーマンス・アートのアンサンブル、ウィンダム・ヒル・レコードではニューエイジといった、どちらかというとフレキシブルな音楽をクリエイトしていた。また、ヴァージン・レコードからリリースされたアイシャムの2枚のオリジナル・アルバム『カスタリア』(1988年)『幻想秘夜』(1990年)では、彼のトランペットによってジャジーなフレーズがつぎつぎと繰り出されるいっぽうで、トータル・サウンドはアンビエント・ミュージックのようなムードとリズム・セクションのジャムアウトするプレイとが交錯するようなものだった。
いずれにしても、アーティスティックなインスピレーションやリラクゼーションを喚起するような、ある種の音響芸術とも云うべきアイシャムの音楽作品は、その映画のアンダースコアに直結する。そんなアイシャムの抑制の効いた感情表現を好むレッドフォードは『リバー・ランズ・スルー・イット』以降も『クイズ・ショウ』をはじめ、前述の『大いなる陰謀』そしてリンカーン大統領暗殺事件を題材にした歴史映画『声をかくす人』(2010年)で、彼を起用した。その点ではレッドフォードの慧眼は、なかなかのもの。それまで金管楽器、シンセサイザー、そしてエレクトロニクスを巧みに操り、プログレッシヴ・ロック、ミニマル・ミュージック、あるいはアンビエント・ミュージックにカテゴライズされるようなオリジナル作品を発表してきたアイシャムを、映画音楽の作曲家として定着させたのだから──。
アイシャムが映画業界に足を踏み入れたのは、1980年代の前半のことだけれど、その頭角を表したのは1990年代に入ってから。ここでアイシャムの手がけた映像作品を列挙することは控えるが、その数はテレビ番組も含めると200本以上に上るという。恥ずかしながらぼくは、最近まで60本程度かと思っていたのだが、それはまったくの勘違いだった。いずれにしてもアイシャムはいまや映画音楽の老練家であり、音楽家としての本領が発揮された作品といえば、やはりフィルム・スコアの数々だろう。いま振り返ると彼は、1980年代から2000年代にかけて、ぼくがもっとも多くの作品を聴いた映画音楽の作曲家でもあった。そしてこの『クイズ・ショウ』のサウンドトラック・アルバムは、間違いなく彼の代表作のひとつだ。
アルバムのプロデュースはアイシャム自身が手がけており、楽曲のアレンジは彼自身と、トロンボーン奏者のケン・クーグラー、そしてオーケストレーターのキム・シャーンバーグとで分業している。アイシャムの作品では、お馴染みのチームワークだ。レコーディングは、マーク・アイシャム(tp)、デヴィッド・ゴールドブラット(p)、ジョン・クレイトン(b)、カート・ウォートマン(ds)といったクァルテット、20名からなるスウィンギーなビッグ・バンド、そしてクラシカルなオーケストラと3つのスタイルで行われた。オーケストラの編曲と指揮は、毎度のごとくクーグラーが担当している。CDアルバムは、現在ウォルト・ディズニー・カンパニーの傘下にあるハリウッド・レコードがリリース。日本での販売権は当時、ポニーキャニオンが所有していた。
アルバムは前述のラヴェット版「モリタート」からスタート。クールでアーバンな響きが琴線に触れる。つづく「世界一の賢者」は、ビッグ・バンドによる煌びやかなサウンドが爽快。コンテ・カンドリのトランペットとピート・クリストリーブのテナーとが、小気味いいソロをとる。クァルテットによる「オーバーサイト・ブルース」では、アイシャムのミュート・トランペットとゴールドブラットのピアノとが、ブルージーなムードを高める。ビッグ・バンドによる「敗者」は、スウィンギーだがややダークな雰囲気。やはりカンドリとクリストリーブとがフィーチュアされる。ソロ・ピアノによる「秘密を守って」は、ゴールドブラッドの美しく切ない語り口が極上。アイシャムの右腕である彼は、個人的にも贔屓のピアニストである。
ビッグ・バンドによる「ハンティング・イン・ユア・アンダーウェア」では、やはりカンドリとクリストリーブとがフロントに立つ。ジャジーだがちょっとシニカルな感じなのが映像的。以下はオーケストラによる演奏がつづくが、内省的な「ショルダーズ・オブ・ライフ」では、短尺ながらアイシャムが美しいトランペット演奏を披露する。その後、エレガントな「ブックス・アンド・ラーニング」ピリピリした空気が漂う「人生におけるチャンス」より張り詰めたムードの「委員会の呼び出し」不安定な響きを醸し出す「偽りの言葉」とつづいていく。後半の3曲では、アイシャムがフィーチュアされる。さらにシリアスで重厚な「テレビの試練」やるせなさに溢れた「全ての代償」とつづき、アルバムは締めくくられる。アイシャムによるトランペットが人間の悲哀を表現しながらも、ほのかな爽やかさを残すところは感動的。さすがである。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。








コメント