情報を制す者 世界を制す──ハッキング映画の原点『スニーカーズ』の音楽を立体的に楽しむ
 Album : James Horner / Sneakers (1992)
Album : James Horner / Sneakers (1992)
Today’s Tune : Playtronics Break-in
モード・ジャズの傑作『カインド・オブ・ブルー』が使用された映画
ぼくがジャズを本格的に聴きはじめたのは、小学校高学年のころ。10歳以上年長の従兄の家でバド・パウエルやビル・エヴァンスのレコードを聴かせてもらったのを機に、ジャズのとりこになった。当時のぼくは、クラシック・ピアノの個人レッスンを受けながら、ポピュラー・ピアノも弾いていたのだけれど、ジャズ・ピアノについてはまったく未経験だった。かろうじてジャズというコトバは知っていたし、無意識のうちにジャズの一端には触れていたのだろうが、知識のほうはゼロだった。ぼくがジャズに激しく興味をそそられたのは、やはり従兄がレコードをかけながらジャズとはこういう音楽だと説明してくれたときだろう。まあ説明といっても、理路整然と話したわけではなかったのだけれど。
無論ぼくがジャズに惹かれたのは、実際にスピーカーから聴こえてくる音を聴いてのこと。とりあえず従兄から説明されたアドリブについては、すぐに理解することができた。ポピュラー・ピアノを弾いていたこともあり、簡単なコードの知識をもっていたぼくは、アドリブというものがコードとスケールとの相互関係によってなされるものと、容易にイメージすることができたのだ。ただ当時のぼくは、まだコードスケール理論などを学んでいなかったから、アドリブというものを単にプレイヤーの解釈で自由に演奏されるものと、解釈するばかり。アドリブがインプロヴィゼーションとも云われ、確たる音楽理論に基づき組み立てられるものであると知るのは、何年かさきのことだった。
実はぼくは即興演奏をその程度しか理解していなかったので、アドリブについてはちょっとカッコイイ演奏と感じるくらいだった。ではジャズにおいて、ぼくの感性をもっとも揺さぶったのものはなにかといえば、それはジャズ特有のハーモニー。ジャズ・ プレイヤーのピアノ演奏では、ぼくがよく知っているコードの上にさらに特定の音が積み重ねられて、緊張感をもったサウンドが生み出されていた。具体的にそれは、音を3度でI、III、V、VIIと堆積させた上に、さらにIX、XI、XIIIを載せるやりかた。すなわちテンションノートのことなのだけれど、そんなことは知る由もない。とにかくその美しい響きに、ぼくはこころを奪われたのである。それは、ぼくがクラシックでは印象派の作曲家が好きだったこととも、関係があると思う。

いずれにしても、ジャズという音楽に出会ったとき、ぼくがもっとも執心したファクターは和声だった。それはいまもあまり変わっておらず、異なる音が互いに調和して響き、新鮮な雰囲気が醸成される瞬間に、ぼくは素直に感動を覚えるのである。その点でひときわ美しさを感じるのが、モダン・ジャズの帝王の異名をとるマイルス・デイヴィスのアルバム『カインド・オブ・ブルー』(1959年)。マイルスの代表作であり、モダン・ジャズの歴史に残る名作だ。ぼくはマイルスの技巧に走ることなく叙情性に重点を置くようなプレイが好きなのだけれど、音楽のスタイルに一貫性がないからか、彼の音楽にのめり込むことはなかった。そんなぼくでも、この『カインド・オブ・ブルー』だけは、繰り返し聴いている。
これほど耽美的なジャズ作品がほかにあるだろうか。ひとことで云えばシンプル。本盤は一般的にモード・ジャズの傑作との呼び声が高いけれど、モード手法は本来シンプルなもの。シンプルだからなんの意匠も凝らされないと、ただのつまらない作品に終わる。そこは帝王の作品だけに、モードに広がりを与えるようなアイディアが、随所にちりばめられている。もしそれに気がつかなかったとしても、なんとなくいいと感じればそれでいい。ぼくなどは、全体的には宙に浮いたような感じを与えながら、ところどころに美しいイディオムを交えるようなところに、センスのよさを感じる。それにアルバム・タイトルがいい。なんとなくブルーな感じという意味なのだろうけれど、音楽のそこはかとない感じを上手く表している。
ところで、この『カインド・オブ・ブルー』のラストに「フラメンコ・スケッチ」という美しいバラードが収録されている。フリジアン・モードの最初の半音が、フラメンコ発祥の地であるスペインのアンダルシア地方の音楽をイメージさせるところから、その名がついたのだろう。モードを使用した管楽器の静謐を湛えるソロの連鎖も然ることながら、ビル・エヴァンスのピアノが奏でる美しいハーモニーに、ぼくは得も云われぬ心地よさを覚える。このエヴァンスのコード感覚が、アルバム全体のサウンドに大きな広がりをもたせているように、ぼくは思う。そして今回、このレコードを聴いていて、ふと思い出したことがある。それは、くだんの「フラメンコ・スケッチ」が、ある映画のワンシーンでかかっていたということである。
さて、すっかりジャズのハナシになってしまったが、ここからは映画の話題。マイルスの「フラメンコ・スケッチ」が使用されたのは、フィル・アルデン・ロビンソンが監督したクライム・アクション映画『スニーカーズ』(1992年)において。スニーカーズとはもちろん運動靴のことではなくて、クライアント企業のセキュリティシステムに実際に侵入し、その盲点を検証するハイテク・エキスパート・チームのこと。ストーリーはそのスニーカーズたちが、究極の暗号解読機を巡る陰謀に巻き込まれていくというもの。映画はまだインターネットが普及する以前の時代が舞台となっていて、多少の古めかしさを感じざるを得ない。しかしながら、当時のハイテク描写が満載された手に汗握る頭脳戦は、いま観ても充分に楽しめる。
いまになってみると、このひとクセもふたクセもあるスニーカーズのメンバーを演じた俳優たちが、スゴイ顔ぶれだったことに気づかされる。指名手配中につき匿名を名乗るリーダーのビショップをロバート・レッドフォード、元CIAで唯一家庭もちのクリースをシドニー・ポワチエ、19才のハッキング・マニア、カールをリヴァー・フェニックス、ビル侵入とメカのプロ、マザーををダン・エイクロイド、そしてオーディオの天才で盲目のホイッスラーをデヴィッド・ストラザーンが、各々演じている。さらにスニーカーズ以外では、ビショップの昔の恋人で数学に詳しいリズをメアリー・マクドネル、25年まえビショップの親友だった玩具会社プレイトロニクスの社長、コズモをベン・キングズレーが、それぞれ演じた。
気の利いたコメディリリーフと気になるソース・ミュージックが満載
主役のロバート・レッドフォードといえば、往年のハリウッド屈指の美男俳優。だが、この映画が公開されたときは、すでに56歳になっていた。その甘いマスクにも、ずいぶんとシワが増えたように思われた。それでもレッドフォードはいくつになってもレッドフォード。ブルーのワークシャツにジーンズという出で立ちできびきび動く姿は、やはりカッコイイ。とはいえ、さすがにスタジャン姿はいかがなものかと思っていたら案の定、われらがレッドフォードは映画の序盤で金融機関のビルに侵入した際、カウンターを飛び越えようとして敢なく転倒する。そのときの彼といえば「もう年だ」と、ちょっとぼやいてみせたりする。そんな自虐的なシーンをさらっと演ってしまうレッドフォードに、ぼくは拍手を送りたくなったもの。
思えばそれまでのレッドフォードといえば、どちらかというと知的で信頼性のある役柄が多く、役者としても無駄のない演技をするひとというイメージが強かった。そんな彼も、アイヴァン・ライトマンの監督作品『夜霧のマンハッタン』(1986年)において、やり手の地方検事を演じたときには、ふんだんにコミカルなセリフや所作を披露した。映画の出来はともかく、レッドフォードの滑稽味のある演技は新鮮だった。その点『スニーカーズ』もまた然り。世界を左右する究極のコンピュータ・チップの争奪戦が描かれた本作では、内容的に当然シリアスなシーンもあるわけだが、緊迫した場面の合間にレッドフォードの軽妙な演技がしばしば挿入される。そんな気の利いたコメディリリーフがあるからこそ、この映画は痛快な作品に仕上がったのだろう。
本作ではレッドフォード以外の俳優たちも、各々のキャラクターを活かしながら同様の効果をあげていて、観るものを存分に楽しませてくれる。社会派映画『野のユリ』(1963年)でアカデミー主演男優賞を獲得したシドニー・ポワチエのクールなたたずまい。ティーンエイジャーのライフスタイルを象徴するようなリヴァー・フェニックスのホットな魅力。コメディアンとして本来のもち味を発揮するダン・エイクロイドのナチュラルな存在感。どんな役でもこなすデヴィッド・ストラザーンのいぶし銀のパフォーマンス。と、実に贅沢な気分を味わうことができる。さらに華やかな美しさと気丈な気質を兼ね備えたメアリー・マクドネルと『ガンジー』(1982年)でアカデミー主演男優賞を受賞したベン・キングズレーが加わり、作品は一段と豪華さを増した。
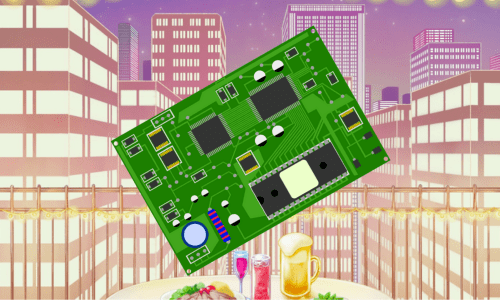
とにもかくにも、映画『スニーカーズ』は決してブロックバスターではないけれど、いろいろと楽しめる作品。未見のかたは、ぜひ一度お試しあれ。ということで、だいぶハナシが横道にそれたが、話題を本筋に戻すとしよう。スニーカーズはNSA(国家安全保障局)を名乗る男たちの依頼で、高等数学者が開発した超高性能の暗号解読器、通称ブラック・ボックスを盗み出す。その成功を祝して催されたパーティの場面で、酒宴の盛り上がりが落ち着いたころ、BGMとしてマイルスの「フラメンコ・スケッチ」がさりげなく流されている。ああ、マイルスのレコードもこういうシテュエーションで流れると、とてもいい雰囲気になるんだ──と、ぼくはこの映画をはじめて鑑賞したとき、目からウロコが落ちる思いがした。
この映画では「フラメンコ・スケッチ」のほかにも気になるソース・ミュージックがあって、ミュージック・スーパーヴァイザーのセンスのよさが感じられる。たとえば冒頭の、学生時代のビショップとコズモがハッキングを行っているシーン。彼らは大統領や政府機関の銀行口座から寄附という名目で大金を動かしているのだが、1969年の出来事ということで、バックにブルージーなロック・ナンバー「リアリー」が流れている。この曲、マイク・ブルームフィールド、アル・クーパー、スティーヴン・スティルスによるブルース・ロックの名盤『スーパー・セッション』(1968年)に収録されているのだが、当時のムードがうまく伝わってくるなかなかいい選曲だと、ぼくは思う。
次に、ビショップが高等数学者の講演会に行くため、数学に詳しいかつての恋人のリズのもとを訪れるシーン。最初リズがピアノを弾いているかのように思わせて、あとから実際は彼女の膝の上で小学生の女の子が弾いていることを明かす──という洒落た仕掛けのある場面。ここで演奏されているのは、フレデリック・ショパンの「ワルツ第14番 ホ短調」。鮮烈で華麗な曲調が、場面転換において一気に空気を変える効果をあげている。なおピアノ演奏は映画に出演した女の子本人のもので、彼女はオクラホマ州タルサ市生まれの浅井純というひと。映画の役名には“ピアノの神童”とクレジットされているけれど、おそらく当時の彼女は10歳くらいだろうから、まさに神童の名に相応しい。浅井さんは現在プロのピアニストとして活躍している。
また、前述のパーティでスニーカーズの面々がリズを相手に、順番に個性的なダンスを披露するカットのつなぎがある。まったくストーリーに関係がないのだけれど、そのユニークなダンス・スタイルからそれそれの性格が浮き彫りになるようで、巧妙でもあり小粋でもあるシーンと、ぼくは思う。ちなみに、(目が不自由な役なので)ストラザーンはほとんど回っているだけだし、(元カノが相手では気まずいからか)レッドフォードは踊っていない。それはともかく、ここでかかっている曲がいい。このグルーヴィーなナンバーは、女性ソウル・シンガー、アレサ・フランクリンが1967年に発表したヒット曲「チェイン・オブ・フールズ」で、彼女のアルバム『レディ・ソウル』(1968年)にも収録されている。
この「チェイン・オブ・フールズ」は個人的にも大好きな曲なのだけれど、本作のソース・ミュージックのなかではもっともインパクトが強いと思われる。パンチの効いた曲だからか、アラン J. パクラ監督の『ペリカン文書』(1993年) をはじめ、度々映画作品で使用されている。ついでに云うと『スニーカーズ』では、この「チェイン・オブ・フールズ」が流れた直後、ボブ・ディランの「雨の日の女」が聴こえてくる。アルバム『ブロンド・オン・ブロンド』(1966年)にも収録されている、BBCで放送禁止歴のあるあの曲だ。映画ではディランの歌唱は確認できないが、バックのトロンボーンやチューバによるブルージーなフレーズでそれとわかる。ディランは、いわゆるプロテスト・ソングの旗手。スニーカーズの連中が支持するのは、然もありなんと思われる。
ジェームズ・ホーナーが作曲したスッキリしたあと味のスコア
面白いというか、思わず笑ってしまうのは、中華料理店の生バンドのシンガーが、なぜかジョージ・チェンであるということ。中国系アメリカ人の彼は、東洋人の役でハリウッド作品はもちろんのこと香港や日本の作品にも出演する、知るひとぞ知るバイプレーヤー。とにかく様々な映画に現れ出る。本作でもワンカットだが、フォークロックのシンガーソングライター、ジム・クロウチのヒット曲「リロイ・ブラウンは悪い奴」を気持ちよさそうにカヴァーしている。しかも中国語の歌詞で“悪い奴”を軽快に歌いあげているのだ!確かに陽気な調子の曲ではあるが、これほどにもチェンのキャラクターにハマるとは──。でも名盤『ライフ・アンド・タイムス』(1973年)に収録されている原曲は、決してコミックソングではない。念のため──。
それはそうと、この中華料理店ではリズとプレイトロニクスの社員、ウェルナー・ブランデスがコンピュータ・デート(死語?)の真っ最中。プレイトロニクスに侵入するために、社員のIDカードと声絞を手に入れるのがリズの目的だ。ウェルナー役は性格俳優のスティーヴン・トボロウスキーだが、いい具合に風采の上がらない男を演じている。デートは延長戦にもつれ込み、ふたりはウェルナーの自宅へ──。そこでムードを高めるために彼が用意したBGMが、ジャズ・ギタリスト、チャーリー・バードの当時の新作『ボサノヴァ・イヤーズ』(1991年)。このシーンでは、このアルバムに収録されている「イパネマの娘」と「コルコヴァード」が流れている。ともにアントニオ・カルロス・ジョビンの名曲だ。
そのほかのソース・ミュージックとしては、ヨハン・ゼバスティアン・バッハの「ヴァイオリン協奏曲第2番 ホ長調 BWV 1042」や、ベドルジハ・スメタナの「弦楽四重奏曲第1番 ホ短調 わが生涯より」といったクラシック・ナンバーが挙げられる。以上の音源は、ハリウッド作品においてよくリリースされる、映画にちなんだコンピレーション・アルバムとしてまとめられることはなかった。2023年にサウンドトラック専門のレーベル、ラ・ラ・ランド・レコードによって、サウンドトラック・アルバムのリマスター&拡張盤(CD2枚組)が発売されたけれど、収録曲はフィルム・スコアとその別ヴァージョンのみ。個人的には、印象に残るソース・ミュージックも、アンダースコアとあわせて楽しみたかったというのが本音である。

スコアのほうは、ジェームズ・キャメロンやロン・ハワードの監督作品で知られるジェームズ・ホーナーが作曲と指揮を手がけている。カリフォルニア大学ロサンゼルス校で教鞭を執っていただけに音楽理論に強く、クラシックからジャズまで幅広い音楽スタイルを駆使する、ハリウッド御用達の音楽家だ。本作ではリズム・セクションが引き立つパートもあるが、基本的にはシンフォニック・サウンドを主体としたドラマティック・アンダースコアが展開されている。オーケストレーションを担当しているのは、サックス奏者のブラッド・デクターと打楽器奏者のフランク・ベネット。演奏はハリウッド・スタジオ交響楽団による。観客に作品世界の臨場感を与える、ある意味でハリウッドの典型的なサウンドトラックと云える。
映画公開当時コロムビア・レコードから発売されたサントラ盤は、実にまとまりよく編集されており鑑賞音楽としても申し分なく楽しめる。よほどのホーナー・ファンでなければ、既存のサントラ盤の音源、それと同一曲のフィルム・ヴァージョン、エクステンデッド・ヴァージョン、オルタネート・テイクがずらり並ぶ、前述のエクスパンデッド・エディションは必要ないかもしれない。なお本作のスコアでは、コロムビア・レコードの看板スターだったジャズ・プレイヤー、ブランフォード・マルサリスのソプラノ・サックスがフィーチュアされている。ほかにも、サックス奏者のジョエル・ぺスキン、ピアニストのラルフ・グリアソン、シンセシストのイアン・アンダーウッド、パーカションニストのマイク・フィッシャーなどのパフォーマンスが際立っている。
ミステリアスでもありアンクシャスでもある「メイン・タイトル」は、物語の発端である1969年の大雪の夜をストレートにイメージさせる。ソプラノ・サックスの音色が玲瓏。耳につく女性コーラスはサンプリングだろうか?いずれにしてもフックとしては絶妙だ。つづく「トゥー・メニー・シークレッツ」では、ピアノやパーカッションによるパターン化された音型が反復されるなか、ソプラノが前曲のメロディを奏でる。後半は強烈なサウンドや複雑なリズムが大胆に展開される。オケとソプラノとが水天一碧 な「スニーカーズのテーマ」は、爽やかなナンバー。クセモノでありながら気持ちのいい連中、スニーカーズにピッタリだ。アンサンブルが静寂に沈む「コズモ」では、犯罪組織と関わりをもつに至った、コズモの静かで激しい心の闇が見事に表現されている。
スリリングなムードを高めるハード・ドライヴィングな「ハンド・オフ」では、ハリウッドの正攻法が全開。深沈たる「プランニング・ザ・スニーク」では、さきの「スニーカーズのテーマ」のモティーフがパターン化、反復される。中盤の空気が徐々に張りつめていく感じが素晴らしい「プレイトロニクス・ブレイク・イン」では、ホーナーのスコアの特徴とも云えるミニマルとポリリズム、それにマーチング・ドラムロールが効果的に使われる。それと対照的なポスト・ロマン主義風の「エスケイプ/ホイッスラーズ・レスキュー」は、もっとも高揚感を与えるトラック。ちょっとスピルバーグ作品の音楽を彷彿させる。それを鎮静するような「グッドバイ」は、ソプラノ・サックスの美しいフロウが静かな感動を呼ぶ。
ラストの「アンド・ザ・ブラインド・シャル・シー」では、エンドロールの曲ということで「スニーカーズのテーマ」や「プレイトロニクス・ブレイク・イン」などがメドレーでリプライズされる。この曲が流れる映画のエンディングでは、ブラック・ボックスを巡って、スニーカーズとNSAとで取引が行われる。その際、スニーカーズの面々が提示する報酬がウィットに富んでいて痛快。その後、彼らの活躍が経済に世界レベルの影響を与えたことが暗示される。実はぼくの音楽仲間たちの間では、ホーナーの音楽はパクリの宝庫とも云われているのだけれど、本作のスコアは紛れもなくクライム・アクションに、リフレッシングでハートウォーミングなテイストを加味する役割を果たしている。映画ともどもスッキリしたあと味に、ぼくは好感もつ。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。








コメント