そうだ今日は、グルーヴで聴かせるピアニスト、ホレス・パーランの名盤の誉れ高き『アス・スリー』を聴こう!
 Album : Horace Parlan / Us Three (1960)
Album : Horace Parlan / Us Three (1960)
Today’s Tune : Us Three
アートワークがノリノリ──音楽もノリノリのウレシイ一枚
2024年、最初の記事である。正月三が日といえば、初詣や挨拶まわりで案外バタバタする。仕事をしているときよりも、却って心身に負荷がかかっているようにも感じられる。帰宅するとすぐにソファにバタンと倒れて、いったん目を閉じる。さてなにを聴こうかと思案する。まあこういうとき、あれこれ考えをめぐらせるのは時間の無駄というもの。直感的にアタマに浮かんだレコードを棚から引っ張り出すばかりだ。今回はさっと名案がひらめいた。要因はこんなこと──。ぼくの場合、正月休みはほとんど家族と過ごすのだが、そんなひとときに、長女の幼いころにまつわる、ちょっとしたエピソードが思い出されたのである。それには、一枚のブルーノート盤が関わっている。
ものごころがつくまえの長女は、よくぼくの部屋にやってきては棚からレコードを無作為に選び出し、ジャケットを見てひとりでニヤニヤしていたもの。ときには大きな口を開けたアート・ブレーキーの顔を見て、けらけら笑っていることもあった。いまでは、彼女がぼくの部屋に入ってくることはほとんどないし、逆にぼくが彼女の部屋に入るときは許可を要する。ちょっと淋しい気もするが、父娘の関係とはそんなものなのだろう。しばし過ぎ去った日々を懐かしんでいると、にわかにこのレコードのことが思い出された。ホレス・パーラン(1931年1月19日 – 2017年2月23日)の代表作『アス・スリー』(1960年)が、まさに長女のお気に入りの一枚だったのである。きっと当の本人は、そんなことはすっかり忘れているのだろうが──。
とんでもないことに、幼児期の長女はいつの間にか紙と鉛筆もってきて『アス・スリー』のジャケットを手本に、数字の書きかたを学習しはじめたのだ。幸いなことに、直接ジャケットに落書きをされることはなかったが、いささか慌てた。それにしても、ジャケットに描かれている数字は大小の切り貼り状態なのに、よくそれが数字とわかったもの。まったく、子どもを侮るべからずである。それはともかく、侮れないというか、まったく軽んじることができないのは、ブルーノート・レコードのジャケット・デザインである。実際にオーディオで音を出すまえから、リスナーを魅了してしまうようなアートワーク群には、ちょっと怖いくらいに存在感がある。
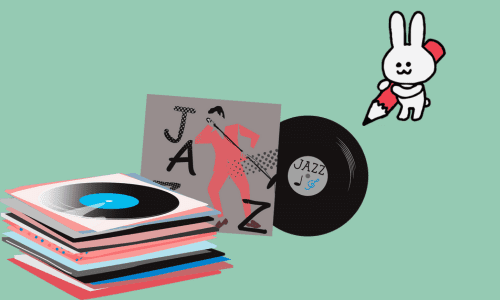
その鮮烈なインパクトの秘密は、配色であると同時に文字の体裁を整えるスゴ技だろう。そんな技芸を誇るのは、グラフィックデザイナーのリード・マイルスだ。ジャズの愛好家だったら誰もが、彼の存在の大きさを認めていることだろう。彼はブルーノート作品のうち、レコード・ナンバー1500番台と4000番台前半の大半のデザインを手がけている。写真が使用される場合もあるが、撮影はドイツ生まれのフランシス・ウルフによる。彼もまた有名人だ。いずれにしても、タイポグラフィと写真のトリミングにおける大胆かつ斬新な手法には、マイルスの人並外れたセンスのよさが光る。そんなジャケットを眺めているだけで幸せな気分になっている自分を省みると、子どものイタズラを咎めることもできなくなる。
面白いのは、マイルスというひと。彼は自らそのデザインをブルーノートの経営者であるアルフレッド・ライオンのもとに持ち込んでおきながら、ジャズにはほとんど興味がなかったという。音楽はもっぱらクラシックばかり聴いていたそうだ。おかしいな。ぼくには、彼のモダニズムが溢れるデザインからは、モダン・ジャズしか聴こえてこないのだけれど──。まあそれは置いておいて、早く音を出そうではないか。『アス・スリー』は外観も楽しいが、中身のほうも胸がすくほど気持ちがいい。ぼくにとっては、なんといってもアタマを使わずに聴くことができるのがウレシイ。レコードをターンテーブルにのせて針を落としたら、ふたたびソファにバタンと倒れて目を閉じるだけである。
ジャズのレコードについて、よく看板に偽りなしと云われるけれど、この『アス・スリー』はまさにその典型。外見と実質とが一致している。アートワークがノリノリで楽しければ、中身の音楽のほうもノリノリで調子がいい。そういえば長女も、このレコードを聴かせたら、曲のリズムに乗って体を揺すりながら、それこそシャンシャン手拍子足拍子していたな。それでいい。このアルバムを、どう聴くか──ミミで聴く?アタマで聴く?ココロで聴く?──いやいや、案外うちの娘のようにカラダで聴くのが正しいのかもしれない。聴くというよりは、感じると云ったほうがいい。ここにある音楽には、明らかにアーティストの独特のグルーヴィーな感覚が、遺憾なく発揮されている。理屈はいらない、それに乗っかればいいだけだ。
グルーヴで聴かせる──それはハンディを背負ったが故の独自の技巧
ホレス・パーランというピアニストは、グルーヴで聴かせるひと。ピアノを弾くぼくにとっては、フィンガリングとかヴォイシングとか、とにかくピアノのテクニックについて考える余地を与えない、心地よいリズムの躍動感やうねるようなグルーヴの高揚感のほうがずっと魅力的に映る、数少ないピアニストのひとりだ。そんな特徴は、彼の書くオリジナル・ナンバーにも顕著に見られる。「アップ・イン・シンシアズ・ルーム」「アップ・アンド・ダウン」「ヘディン・サウス」「バック・フロム・ザ・ギグ」といった曲は、特別な趣向が凝らされているわけでもないのに、とにかくクールだ。メロディもリズムもシンプルで、ただただグルーヴィーだからこそ、思わず体を動かしたくなってしまうのだろう。
本作の冒頭を飾るアルバムのタイトル・ナンバー「アス・スリー」は、そんな特徴的なパーランのオリジナル曲のなかでも最たるもの。とにかくグルーヴィー。やたらとカッコいい。しかもとてもファンキーだ。彼のピアノ・プレイには、アーシーな感覚が色濃く現れるし、独特なドライヴ感覚も発揮される。たとえば、彼はデビュー作『ムーヴィン・アンド・グルーヴィン』(1960年)において、デューク・エリントンの「Cジャム・ブルース」をトリオで演奏している。この曲はレッド・ガーランド・トリオによるスウィンギーな快演があまりにも有名だけれど、その聴き慣れた演奏と比べると、パーランのほうはテンポと構成は類似するものの、ことのほか泥くささとアクの強さを感じさせる。
このデビュー作の収録曲には、上記の曲も含めて有名なスタンダーズがズラリと並ぶ。こういう選曲は、レーベルが新参のアーティストをイントロデュースする際の常套手段。ところが、パーランはよく知られた名曲の数々を、どれもソウルフルなフィーリングで味付けして従来のイメージを覆すような曲に料理してしまっている。そうかといって泥くさいばかりではなく、ときおり洗練された一面を覗かせることもある。実際、1970年代初頭に渡欧(デンマークの首都コペンハーゲンに定住)してからのパーランの演奏には、ソフィスティケートされた美しさと優雅さが目立つ。それも悪くはないのだが、パーランの唯一無二の魅力が失われているように感じられるのも、また事実だ。やはり彼の作品を聴くなら、ブルーノート盤だろう。

パーランは、上記の『ムーヴィン・アンド・グルーヴィン』を皮切りに、今回ご紹介するセカンド作にあたる『アス・スリー』のほか『スピーキン・マイ・ピース』(1060年)『ヘディン・サウス』(1962年)『オン・ザ・スパー・オブ・ザ・モーメント』(1962年)『アップ・アンド・ダウン』(1963年)『ハッピー・フレイム・オブ・マインド』(1986年)と、ブルーノートに計7枚のアルバムを立てつづけに吹き込んでいる。1stと2ndではトリオのみ、4thではレイ・バレット(cga)、3rdと5thではトミー・タレンタイン(tp)&スタンリー・タレンタイン(ts)、6thと7thではブッカー・アーヴィン(ts)&グラント・グリーン(g)がそれぞれ参加。編成は変わっても、セッションに横溢するアーシーなドライヴ感は少しも揺るがない。
ちなみにブルーノートの最終作『ハッピー・フレイム・オブ・マインド』については、一時期、コレクターたちが血眼になって探し回ったという逸話がある。都市伝説のごとく、いくら探しても見つかるはずもない。なぜならこの作品は、レコーディングは1963年2月15日に行われレコード番号も4134と決まっていながら、実際は発売を見送られたのだから。この音源がはじめて日の目を見たのは、1976年のこと。やはりお蔵入りしていたブッカー・アーヴィンの1968年5月24日のセッション(レコード番号4314)の音源とまとめられて、アーヴィン名義の2枚組『バック・フロム・ザ・ギグ』として発売された。パーラン名義の単体でのリリースは、1986年まで待たなければならなかった。なおアーヴィン名義の単体は、2005年に『テックス・ブック・テナー』としてCDでリリースされた。
ときにホレス・パーランは、12歳のときからピアノを弾きはじめたが、実はそれ以前にポリオを患い右手の薬指と小指の自由を奪われていた。もともと機能回復訓練の一環としてはじめたピアノ演奏において、彼は独自の技巧を生み出した。たとえば、限られたフレーズを反復することで自己の感情を熱っぽく表現するようなスタイルは、ハンディを背負ったからこそ発見することができたものだろう。また、右手が不自由なぶん左手によって繰り出される和音はすこぶる刺激的。それと対置するように右手によって勢いよく突き出される楽句も、曲が進行するとともにどんどんリズミカルになっていく。その迫力たるやほかに類を見ない。リスナーはその圧倒的なグルーヴに身を委ねるのみである。
鬼気迫る演奏──まずはリズムやフィーリングだけで楽しもう!
そんなパーランの気迫に満ちたプレイをもっとも堪能することができるのは『アス・スリー』だろう。もともとブルーノートというレーベルにはピアノ・トリオの作品が少ないけれど、トリオ編成でこれほどエクスプローシヴな音を出しているアルバムはほかにないように思われる。特にアルバム冒頭のパーランのオリジナル・ナンバー「アス・スリー」の鬼気迫る演奏には、それ1曲の存在だけでも本作を名盤の誉れ高きものにするほどのインパクトがある。技巧に走るわけでもないのに、太くてキレのいい音だけでスゴミを利かせるジョージ・タッカーのベース。さらに緊張を煽りたてるようなアル・ヘアウッドのブラシ。そしてパーランの泥くささ丸出しでトレモロするピアノ。そんなイントロだけで、しつこいくらいジャジーな世界に一気に引き込まれる。
くり返すが、ここにある音楽はアタマを使わずに聴く部類のものである。出だしから有無を云わせぬ存在感に気圧されてしまうから、ぼくとしてもただ目を閉じて、テーマへとなだれ込んでいく三人に身を任せるしかない。まあ、そんな瞬間がとても気持ちがいいのだけれど──。やがて、アドリブ・パートでのパーランのピアノが叩き出すフレーズが反復しはじめる。それにタッカーのしなやかなベースとヘアウッドの軽快なブラシとによる、畳みかけるようなリズムが呼応する。これを聴いていると、まるでトランス状態に陥るような不思議な感覚におそわれるから、ちょっとマズい。ここでの終始一気に駆け抜けるトリオの演奏は、一度聴いたらやみつきになるのだ。
4分半と「アス・スリー」のプレイタイムはそれほど長くはないが、その間リスナーの気分は最大限まで高揚させられる。アルバムは興奮冷めやらぬまま2曲目へ──。イントロの愁いに沈むようなアルコ・ベースの音色がいい。打って変わってバラードである。チルアウトするのに効果的な、このツナギがぼくは好きだ。曲は「アイ・ウォント・トゥ・ビー・ラヴド」で、パーランの選曲のセンスのよさが発揮された。サヴァンナ・チャーチル&ザ・センチメンタリスツによる1947年のR&Bのヒット曲だが、ジャズで採り上げられることは極端に少ない。シンプルなメロディック・ラインと精緻なコード・ワークのコントラストが見事。その美しさからこの曲を、ぼくは本アルバムにおいて次点に推す。
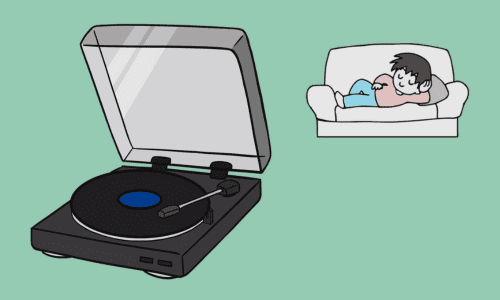
3曲目の「カム・レイン・オア・カム・シャイン」は、ハロルド・アーレンの超有名曲。すっかり手垢のついた曲。だがパーランは奇を衒うようなことはしない。シングル・トーンにしてもブロック・コードにしても、肩の力が抜けていていい。ちょっと上品な感じのテーマ部、軽快に歩き出すようなアドリブ・パートといった構成が、それとなく洒落ている。それなりにブルージーになるけれど、終始ゆったりと構えているところに、胸がすうっとする。つづくパーランの自作曲「ウェイディン」はまるで飾り気のないブルースだが『スピーキン・マイ・ピース』でも再演された。前の曲を引き継ぎ、軽やかに歩くようなテンポが快適。タッカーとヘアウッドによる安定したリズム・キープと、そこにたまに飛び出すキューに導かれて、パーランは静かにそれでいて激しく黒いジャズ魂を燃やすのである。
B面になると、ちょっと空気が変わる。ロジャース&ハートによるおなじみのミュージカル・ナンバー「ザ・レディ・イズ・ア・トランプ」が、作品に明るく澄んだ鮮やかなカラーを加える。胸が騒ぐモーダルなイントロから、こころが弾むテーマ部へ。ベースの軽妙なシンコペーション、ブラシの滑らかなタッチ、ピアノの小気味いいフレーズと、どこをとっても爽快だ。途中リズムがアフロ・キューバン調になり、トリオはさらにグルーヴィーに──。リムとタムの音が、心地よく響く。ベース・ソロも弾ける。つづく「ウォーキン」でパーランは、このあまりにも有名なブルースを臆する色もなく、お得意のファンキーなプレイでそつなくこなしている。タッカーとヘアウッドのソロも正攻法。その堂々としたアプローチが、名演の風格すら漂わせている。
ラストの「リターン・エンゲージメント」もパーランのオリジナル曲。前述のようにぼくは彼の書く曲が大好きなのだが、それらに力作という言葉は似合わない。この曲もご多分に漏れず、ただただ軽妙洒脱。ドラムスの短いソロからはじまる明るく爽快なアップテンポ・ナンバーで、パーランのピアノも上機嫌で饒舌になる。ヘアウッドとの4バースも、高く舞い上がるような感じ。このなんとも晴れやかな気分にさせられる演奏は、クロージングを飾るのにふさわしい。云うまでもなく、音楽にはメソッドやテクニックも大事だけれど、そういうことは置いておいて、まずはリズムやフィーリングだけで楽しむことができる、パーランの作品はやはり手にとりやすい。つぎは『アップ・アンド・ダウン』を聴こうかな──。そしてまたまた、ぼくはソファにバタンと倒れて目を閉じるのである。
あとになりましたが、あけましておめでとうございます。2024年も変わらぬお付き合いのほど、よろしくお願い申し上げます。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。








コメント