ヘンリー・マンシーニの美しくも切ない音楽がこころに残る映画『ひまわり』のサウンドトラック・アルバム
 Album : Henry Mancini / Sunflower (1970)
Album : Henry Mancini / Sunflower (1970)
Today’s Tune : Love Theme From “Sunflower”
ウクライナの広大なひまわり畑がいまも目に焼きついている
久々にヘンリー・マンシーニの作品である。しかも、ぼくにとってはちょっと厄介な1枚なのだ。理由は後述するとして、まずはレコードをご紹介。ヴィットリオ・デ・シーカ監督による1970年公開の映画『ひまわり』のサウンドトラック・アルバムだ。この作品はイタリア、フランス、ソビエト連邦、アメリカ合衆国による合作映画だけれど、日本でも早々に公開されて大ヒットとなったらしい。らしいというのは、リアルタイムでこの映画を観た父からの聞きかじりだから。ぼくがこの映画を観たのは、それより10年近くあとのことだったと思う。小学校高学年になって名画座通いをはじめてから、何年か経ったころだ。スクリーンに映された、主人公のジョバンナが訪れた広大なひまわり畑は、いまも目に焼きついている。
ジョバンナを演じたソフィア・ローレンは、イタリア映画アカデミーが主催するダヴィッド・ディ・ドナテッロ賞を受賞している。イタリア映画における、最高の名誉とされる賞だ。ローレンといえば、ぼくはあまり彼女の主演映画を観ていない。この『ひまわり』を劇場で鑑賞するまえに観た作品だと、ジーン・ネグレスコが監督した1957年公開の『島の女』くらいのもの。このある種の海洋冒険映画にしてもローレンに惹かれたからではなく、ジュリー・ロンドンが歌った主題歌「イルカに乗った少年」がたまたま好きな曲だったから、興味をもったまで。ちなみにこの主題歌、ギリシャの作曲家タキス・モラキスが書いた既存の曲にポール・フランシス・ウェブスターが英語詞をつけたものである。
そういえばその昔、この「イルカに乗った少年」をジャズ・ピアニストの大野雄二が、スタジオ・アルバムやライヴで演奏していた。きっとお気に入りの曲だったのだろう、異国情緒が漂ういい曲だものね──。異国風といえば音楽もそうだけれど、海に潜って海綿をとっているローレンのルックスもまた、とてもエキゾティック。というかその顔立ちときたら、神秘的でさえある。しかもその容貌風姿は、肉感的な印象を与える。ちょっと怖いくらいだ。当時はそんな彼女に夢中になった日本の男性ファンも多かったようだけれど、確かに客観的に見ればスゴい美人である。でもこれは好みの問題になるのだけれど、ぼくにはちょっとアクが強すぎる。いずれにしてもローマ生まれのローレンにとって、この『島の女』はハリウッド進出第1作となった。
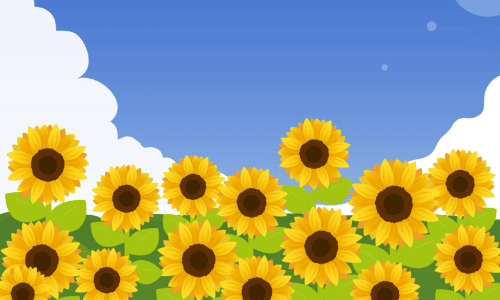
ということで、ハナシを『ひまわり』に戻す。この映画のサウンドトラック・アルバムは、アヴコ・エンバシーというアメリカのレーベルからリリースされている。この映画のアメリカにおける配給会社、アヴコ・エンバシー・ピクチャーズによって設立されたレコード・レーベルだ。オリジナル盤のジャケットには『Sunflower』と英語のタイトルが付されており、おなじ1970年に日本ビクターから発売されたジャケット違いの国内盤のほうにもまた然りである。だからぼくは実際に映画を観るまで、この映画の原題が『Sunflower』だと思っていた。しかしながら、この映画のオリジナルのタイトルは『I Girasoli(イ・ジラソーリ)』という。まあ、イタリア語で『ひまわり』を意味するのだから、とりたてて騒ぐほどのことでもないか──。
そもそもメガホンをとったヴィットリオ・デ・シーカは、イタリア映画の巨匠だものね──。デ・シーカ作品については、ぼくも『ひまわり』を観るまえから、すでに『靴みがき』(1946年)や『自転車泥棒』(1948年)などで親しんでいた。いまではこれらの作品が、ファシズムやナチズムに対する抵抗として現実社会を描き出すという、いわゆるイタリア・ネオリアリズムの代表的な映画であると認識しているけれど、当時のぼくはまだ小学生──そんなことは知る由もない。というか、わかるはずがない。しかしながら、デ・シーカ作品のストーリーは子どもにもよくわかる。ことに貧困にあえぐ子どもたちについてのリアリスティックな描写は、小学生だったぼくのこころにも深く刻まれた。
そんなデ・シーカ作品の1本である『ひまわり』は、やはり戦争が生んだ様々な問題をはらんだ映画。概括的に云いあらわすと、第二次世界大戦の東部戦線でのイタリア旅団の悲劇を絡めた恋愛映画だ。ローレン演じるナポリ娘、ジョバンナがソ連戦線へ出征したきり行方不明となった夫の消息を尋ねまわり、厳しく悲しい現実に直面するというストーリー。ジョバンナは夫を捜し求めて、当時まだ社会主義国家だったソ連にまで足を運ぶ。そして彼女は、かつてイタリア軍が戦闘していたというウクライナの村にたどり着くのだけれど、そこで地平線の彼方までつづく広大なひまわり畑を目の当たりにする。そう、それでこの映画のタイトルは『ひまわり』というのかと、小学生のぼくも理解した。ひまわり畑が、戦争が生んだ悲劇の象徴であるということも含めて──。
このひまわり畑の下には、多くのイタリア兵やロシア人捕虜たちが眠っているという。そしてジョバンナは外国貿易省の役人に案内されて、無数の墓標が並ぶ丘の上に立つのだが、どうしても自分の夫がその地に眠っているとは思えなかった。このイタリア兵墓地のシーンについては、当初ソ連サイドからカットするよう要請があったという。だが結局のところデ・シーカは、このシーンを切ることはしなかった。この問題は様々な波紋を呼んだようだけれど、このシャシンからひまわり畑や墓地が切りとられるというのは、この映画のテーマを象徴する意匠が失われることに等しい。もちろん、映画『ひまわり』が意義ある作品として認められる要因は、社会風刺だけではないとぼくは思うけれど、それが物語に厚みを増していることもまた事実である。
冷戦時代にイタリアのスタッフがソ連ロケを認められたという点でも、映画『ひまわり』の存在価値は高いと思われるし、とにかくウクライナの大地に力強く咲き誇るひまわり畑のシーンはあまりにも美しい。この映画のサウンドトラック・アルバムに針を落として、ぼくが真っ先に思い浮かべるのは、なんといっても雄大なスケールをもつひまわり畑。なにしろオープニングクレジットからして、ひまわり畑の映像と流麗な主題曲とが絶妙にシンクロナイズするのだから──。ちなみにエンディングでは、一輪のひまわりのクローズアップがひまわり畑の全景にディゾルヴする。繰り返しになるけれど、デ・シーカ作品のストーリーは子どもにもよくわかる。そして彼はその経緯に、メッセージ性をもたせるのが上手い監督なのだね──。
マンシーニの曲のなかでも特に好きな「ひまわり 愛のテーマ」
そういった作りだからか、この『ひまわり』はいまもわが国においてなかなかの人気を誇る。2020年には日本の映画配給会社であるアンプラグドによって、フィルムのデジタル修復も行われた。この『ひまわり 50周年HDレストア版』は、日本全国で順次劇場公開された。またこれは不測の事態ではあったけれど、2022年、まさにひまわり畑のシーンが撮影されたウクライナへロシア連邦が軍事侵攻した。それを受けて、日本の映画館や地方自治体によって『ひまわり』のチャリティ上映会が各地で開催されたことは、まだ記憶に新しい。映画『ひまわり』は男女の運命的な別離が描かれた恋愛映画だけれど、ふたりを引き裂いたものは戦争だった。そして現代においてもこの映画が、戦争とはなにかを伝え多くの共感を得るものであると、ぼくもあらためて知った次第である。
ところで、ぼくがこの映画に興味をもったのは、云うまでもなく『島の女』を観てソフィア・ローレンの色香にあてられたからではない。自分で云うのもなんだが、まだいたいけな少年だったぼくにとって、ローレンは凛とした芯の強い女性というイメージだったから、かなり近寄りがたい存在のように思われたもの。というか、オトナになったいまでも気後れしてしまうのだけれど──。その点、ジョバンナのようにコトバも通じない異国の地に足を踏み入れ、決して諦めることなく愛する夫を捜しつづけるという勇猛果敢な女性像は、ローレンの与える印象によくマッチしている。名作に水を差すようだけれど、当時のぼくはどちらかというと、ロシア生まれの女優でバレリーナであるリュドミラ・サベーリエワのほうに、淡い思いを寄せたもの。
サベーリエワはセルゲイ・ボンダルチュク監督の『戦争と平和』(1965年 – 1967年)で、ナターシャを演じたひと。それ以前のイタリア/アメリカ版(1956年)では、おなじ役をオードリー・ヘップバーンが演じていた。個人的には、サベーリエワのほうが原作(レフ・トルストイの小説)のイメージに近いと思う。4部構成のこの映画、やたらと長くてぜんぶ観るのに7時間以上もかかる。ぼくはやはり『ひまわり』を鑑賞するまえに、この映画をすでに観ていた。テレビの映画番組において放送されたときに、ロシア文学に傾倒していた父にいや応なく観せられたのだ。もちろん放送枠にあわせて一部のシーンはカットされていたのだろうが、映画は3週に分けて放送された。しかも思いのほか、夢中になって観てしまった覚えがある。

そのときから、ぼくはサベーリエワに惹かれていたのかもしれない。恥ずかしながら、ぼくが『ひまわり』を観るためにいそいそと名画座に足を運んだ理由のひとつは、サベーリエワに再会するためだったのだから──。どうでもいいことだけれど、前述の日本ビクターから発売された国内仕様のサウンドトラック・アルバムのジャケットでは、ローレンよりもサベーリエワのほうが大きく写っている。ほんとうに、どうでもいいことだね──。それはともかく、夫を捜してジョバンナがたどり着いた一軒の質素な佇まいの家──そこで静かに暮らしていたのが、サベーリエワ演じるマーシャ。彼女は、雪原で凍死しかけていた敗走中のジョバンナの夫を救った張本人だったのである。そして──。
すっかりあとになったが、ジョバンナの夫であるアントニオを演じたのは、戦後イタリア映画を代表する二枚目スター、マルチェロ・マストロヤンニ。恋愛に開放的な、それでいて憎めない感じのイタリア男性であるアントニオは、実生活で多くの女性と浮名を流したマストロヤンニにピッタリの役どころと云える。でもそんな彼もシリアスになると、知的な雰囲気が漂いはじめるから不思議だ。ラストを飾るミラノ中央駅のシーンで、動きはじめた汽車の窓辺に立ったままジョバンナを見詰めるアントニオのひたむきな眼差しもまた、忘れることのできないもの。そしてこのシーンでもまた、あの流麗な主題曲がエモーショナルに奏でられるのである。サベーリエワも好きだけれど、実はぼくが映画『ひまわり』においてもっとも惹かれるのは、このテーマ曲なのである。
この映画の主題曲「ひまわり 愛のテーマ」を、ぼくは本編を観るまえから知っていた。前述の日本ビクターから発売されたサウンドトラック・アルバムもすでに所持していた。それよりもさらにまえ、ぼくはこの曲を実際にピアノで演奏したこともあった。当時ぼくはクラシック・ピアノのレッスンを受けながら、ポピュラー・ピアノにも片足を突っ込んでいたのだ。その端緒を開いたのは、まさに映画音楽。名画座通いをはじめた小学校高学年のころのことだけれど、当時はジョルジュ・ドルリュー、フランシス・レイ、そしてミシェル・ルグランといったフランスの作曲家の作品が好みだった。そんななかアメリカの作曲家だけれど、ヘンリー・マンシーニの音楽はダントツで好きだったな──。
しかもマンシーニの曲のなかでも「ひまわり 愛のテーマ」は、特に好きだった。マンシーニといえば、まず思い浮かべるのは『ティファニーで朝食を』(1961年)『シャレード』(1963年)『いつも2人で』(1967年)『暗くなるまで待って』(1967年)といったオードリー・ヘプバーン主演の映画作品。というのも、ぼくは映画少年になって間もく、ヘプバーンの映画をことごとく観たから。当時の名画座では、ヘプバーンの特集は定番中の定番だったのだ。ぼくはヘプバーン作品でマンシーニ・サウンドの虜になったわけだが、上記の4本における彼のスコアはどれも好きだ。ちなみに、やはりヘプバーンが主演した『おしゃれ泥棒』(1966年)の音楽も、当初マンシーニのペンによるものと思いきや、実は違った。
この『おしゃれ泥棒』の音楽、確かにマンシーニっぽいところもあるのだけれど、彼のスコアにしてはラッパが鳴り過ぎのようにも思えた。実は音楽を担当したのは、あの『スター・ウォーズ』(1977年)の作曲家、ジョン・ウィリアムズだったのだ。プロデューサーはもちろんのこと、ヘプバーン自身も大のマンシーニ・ファンだったらしく彼の登板を望んだようなのだけれど、実際は都合がつかなかった。ということで、マンシーニに師事したことのあるウィリアムズが起用されたというわけだ。ウィリアムズは、マンシーニが音楽を手がけたテレビシリーズ『ピーター・ガン』(1958年 – 1961年)の音盤で、ピアノを弾いていたりする。とはいっても、当時のぼくといえば「ジョン・ウィリアムズってだれよ?」などと思うばかりだったのだけれどね──。
マンシーニのこだわりが感じられるこころに残る名盤
それはさておき、ぼくにとって「ひまわり 愛のテーマ」は、上記の4本のヘプバーン作品のどの主題曲と比較しても格段に好きな曲である。スタイリストのマンシーニのオリジナルにしては、珍しく哀切きわまりない曲。不適切な云いかたになるかもしれないけれど、その旋律はストレートにお涙ちょうだいの音楽に類するものだ。さきに挙げた作曲家で云うと、たとえばフランシス・レイの『ある愛の詩』(1970年)や、ミシェル・ルグランの『シェルブールの雨傘』(1964年)などのテーマ曲も、同じ類いの音楽と云える。まあ映画自体が悲恋の物語を扱った作品だから、作曲家が観客を泣かせにかかるのは当然のこと。実際どちらの曲も、涙を誘うどころか胸が締めつけられるような悲哀感さえ横溢する。
でもぼくは、そういう直情的な音楽が実はちょっと苦手だったりする。ご多分に漏れず「ひまわり 愛のテーマ」もまた、思い切り泣ける曲。戦争によって引き裂かれた男女の悲哀が直線的に表現されている。しかしながら、ぼくはこの曲が狂おしいほど好きなのだ。その理由を敢えて説明すると、一聴、この曲は通俗的かつ情緒的にも響くのだけれど、実はマンシーニらしく現代的で新しい感覚もしっかり鏤められているのだ。実際にピアノで演奏してみるとよくわかるのだけれど、たとえばテーマのトップ・ノート(メロディ)がコードに対して、3小節の3拍目がフラットファイヴ(♭5)に、6小節のアタマがテンション・ノート(♭9)になっていたりする。これらの音が入ることによって、曲がとてもモダンに聴こえるのだね──。
まあこの場でこの曲について、これ以上楽理的な考察を深めてもあまり意味がないと思われるし、マンシーニ自身も音楽理論を意識しながら作曲したわけではないだろうから、理屈っぽく駄弁を弄するのはここで控えることにする。ただ「ひまわり 愛のテーマ」は上記のような作りであるが故に、大して演奏技術もない小学生のぼくがピアノで弾いても、なんとなく瀟洒に響くという実に美味しい曲なのである。だから、これは余計なお世話かもしれないけれど、日頃からもっとピアノをカッコよく弾いてみたいと思っている、ことにビギナーのかたには、ぜひともこの曲をお試しいただきたい。いずれにしても、この「ひまわり 愛のテーマ」は個人的には大のフェイヴァリット・チューンであり、一般的にもエヴァーグリーンな曲であると云える。
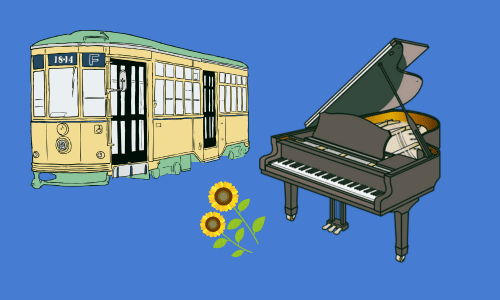
それはそうと、ぼくは冒頭で映画『ひまわり』のサウンドトラック・アルバムを、ちょっと厄介な1枚と云い表した。それはなぜかというと、このレコードが正真正銘のオリジナル・サウンドトラック盤だからだ。おそらくマンシーニのレコードにあまり馴染みのないかたは「えっ、どういうこと?」と、思われたのではないだろうか。どういうことかというと、このレコード、オリジナル盤にしても前述の国内盤にしても、ジャケットには“AN ORIGINAL SOUND TRACK RECORDING”と記されている。これはそれまでのマンシーニの音盤においては、ごく稀なこと。彼がスコアを手がけた映画の音盤といえば、たいてい“MUSIC FROM……”と表記されている。つまり、それらは厳密にはサントラ盤ではないのである。
これはマンシーニのこだわりなのだろう、それまでの彼といえば、音盤にはフィルム用に録音された音源をそのまま使うことはなく、わざわざ新たにスタジオ・レコーディングを行い、鑑賞用音楽と同等のレベルのトラックを仕込んでいた。そういう仕様だから、従来のマンシーニが手がけた映画音楽のレコードは、映画から離れても良質のイージーリスニング作品として楽しむことができるものばかりだったのである。ところが『ひまわり』の音盤は、そっくりそのままサウンドトラックでまとめられている。思わず小躍りしたくなるような、それまでの軽妙洒脱なアルバムとはいささか趣きを異にするのだ。思えばこのころのマンシーニ は、オシャレにならざる作品も手がけるようになっていたな──。
そういう映画については、マンシーニもサントラ音源をそのままメディア化したほうが、アドヴァンテージが高いと考えたのかもしれない。マンシーニ・サウンドの洗練された華麗な響きから鮮烈な陰影を湛えたトーンへの移行には、ぼくも戸惑いを感じたけれど、彼にとっては新たな挑戦だったのだろう。ただこれだけは云える。映画『ひまわり』のサウンドトラック・アルバムは、気軽に楽しむような類いの作品ではないけれど、マンシーニのスゴい手腕が発揮された深い味わいのある11のピースがセレクトされた傑作である。もちろん曲によっては、彼の洗練されたセンスが光る瞬間もある。アルバム冒頭の「ひまわり 愛のテーマ」が、まさにその典型と云えるのではないだろうか──。
この曲では、サビのあとの主題がピアノではなくハープシコードで奏でられる。些細なことのように思われるかもしれないが、こういうところにもマンシーニのセンスのよさが感じられる。後半の転調は常套手段だが、しっかり曲を盛り上げている。つづく「マーシャのテーマ」では、アコーディオンによるメロディとストリングスのオブリガートとが静かに寂寥感を漂わせる。軽快な「ジョバンナのテーマ」では、サンバのリズムに乗ってアコーディオンがアドリブを展開。はじけるようなオルガンのバッキングもいい。アルバム中、もっともマンシーニらしい曲だ。逆に「アントニオを捜して」では、ロシア民謡調の旋律を歌い上げるオーケストラがひたすら重苦しいムードを醸成する。
さらに「砂上の恋」では、センシティヴなピアノ・ラインが主題曲のサビに引き継がれていく。軽くラテンのビートが刻まれていくなかストリングス、ハープシコード、アープ・オデッセイ風のキーボードなどが、哀愁を帯びたメロディを綴っていく。レコードでは、つづくロシアの民族舞踊スタイルのナンバー「モスクワの新居」をもってして、A面が締めくくられる。B面は「二人の女」からスタート。前出の「マーシャのテーマ」に主題曲がインサートされる。そしてアルバムは、重厚で厳粛なオーケストラル・ナンバー「退却」から軽妙なソース・ミュージック「招待」へとつづくが、前者はこれまでになくシリアスなマンシーニ・サウンド。後者はソロ・ヴァイオリンがフィーチュアされたスロー・タンゴで、いかにもマンシーニの曲といった感じ。その対比が面白い。
さらに「アントニオを助けだすマーシャ」ではまたまた「マーシャのテーマ」が登場。アコーディオン、ストリングス、そしてバラライカが、物語の終局に向けて切々と運命の悲愴を歌いあげていく。ラストを飾る「ミラノの別れ」では、当然のごとく主題曲が、静かなアコースティック・ギターのソロ、品のあるピアノとそれに絡む柔らかなストリングス、そして金管楽器をバックにエモーショナルに歌う弦楽器群といった具合に、徐々に盛り上げられていく。さらにオーケストラによるダイナミックなエンディングが付されて、アルバムは映画と同じように幕を閉じる。アルバム・プロデュースは、マンシーニ自身が手がけているのだけれど、曲によってはフィルム未使用のテイクが採用されていたりする。ここにもまた、マンシーニのこだわりが感じられる。本作はそのあたりもちょっと厄介なのだけれど、こころに残る名盤であることは間違いない。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。








コメント