ラジオ・ステーションでは欠かせない存在、グレッグ・カルーキスの魅力がナチュラルに表出した『ルッキング・アップ』
 Album : Gregg Karukas / Looking Up (2005)
Album : Gregg Karukas / Looking Up (2005)
Today’s Tune : Corner Club / Clube Da Esquina
NACの先駆的グループ、クルーズ・コントロールのキーボーディスト
ぼくがもっとも敬愛する音楽家は、デイヴ・グルーシンとボブ・ジェームスである。ことあるごとに、そう宣言してきた。ふたりとも、主にコンテンポラリー・ジャズにおいて、コンポーザー、アレンジャー、プロデューサー、そしてキーボーディストとして活躍するアーティストだ。ぼくは彼らの音楽を、小学校高学年のころからずっと聴きつづけている。では、その後続のミュージシャンで、ぼくの感性にフィットするようなひとといえば、だれになるのだろう?ちょっと、考えてみた。これが単にジャズ・プレイヤーの場合は、案外簡単に答えが出る。ぼくがもっとも影響を受けたジャズ・ピアニストといえば、やはりビル・エヴァンス。そして現在、ぼくのこころにスムースに響くのは、ラーシュ・ヤンソンのピアノ演奏ということになる。
ところで、グルーシンやジェームスのような総合的な音楽家ということになると、なかなか自分と同じような感受性と志向性をもったひとを見つけるのは難しい。なぜなら、外界の刺激や印象を受けいれる能力や、音楽に対するスタンスや考えかたなどの価値観が、ある程度一致しなければならないからだ。そんなわけで、必ずしも適当な人選ではないかもしれないが、作曲や編曲、ピアノの演奏、そして(これがもっとも重要なのかもしれないが)音楽に対する向き合いかたにおいて、もっとも素直にシンパシーを感じるアーティストということで、メリーランド州出身のギリシャ系アメリカ人、グレッグ・カルーキス(1956年5月18日 -)を挙げさせていただく。思えば、カルーキスの演奏にはじめて触れてから、すでに28年も経過していた。ときが経つとともに、彼の音楽に対するぼくのエンパシーは強くなっていった。
順を追っておはなしすると、1986年まで遡ることになる。それはまだスムース・ジャズとかNAC(ニュー・アダルト・コンテンポラリー)というコトバが使われるようになるまえのこと。当時、青山にあったミュージック・カフェ「Paul’s Bar」のオーナー、ポール森田がエグゼクティヴ・プロデューサーを務める、ベイクド・ポテト・レーベルがスタートした。レーベル第1作は、クルーズ・コントロールというグループの『ムーン・ライディング』(1986年)。この未知のグループのリーダーは、テネシー州ナッシュヴィル出身の26歳、ギタリストのラス・フリーマンだった。内容的にはコンテンポラリー・ジャズに属するのだろうが、従来のフュージョンとは明らかに異なり、熱い即興演奏よりも聴き心地のよさに重点が置かれていた。
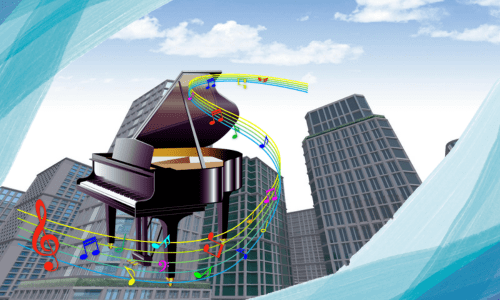
その少しあと順序は逆になるが、フリーマンが1985年に吹き込んだデビュー・アルバム『ノクターナル・プレイグランド』(1986年)も、日本国内で発売された。このアルバムはもともと、カリフォルニアのマイナー・レーベル、ブレインチャイルド・レコードからリリースされた作品で、日本ではベイクド・ポテト・レーベルの発売元でもある、アルファレコードがディストリビュータとなった。この2枚のアルバムをあらためて聴くと、当然のことながら非常によく似ているのがよくわかる。フリーマンは自身で作曲やアレンジを手がけるし、楽器演奏においてもギター以外にキーボードも弾くし、コンピュータのプログラミングも行う。そんな多様性も然ることながら、フュージョンをポップ・インストゥルメンタルにシフトしたサウンドが、新鮮だった。
ぼくは、このフリーマンの音楽こそが、のちのスムース・ジャズへとつながるスターティング・ポイントだったように思う。フリーマンはギタリストでありながら、その楽曲において自己のギターを主軸に据えていないところが、とてもユニーク。たとえば『ムーン・ライディング』では、自分はバッキングにまわることが多く、デヴィッド・ベノワ(p)、ケニー・G(ss)、ブランダン・フィールズ(as)といった、ゲスト・プレイヤーのほうがまえに出ている。ただ、そのプレイヤーたちのソロは、インプロヴィゼーションを際立たせるようなものではなく、トータル・サウンドに溶け込むようなパフォーマンスとなっている。その点、フリーマンは、ギタリストというよりはサウンド・クリエイターという印象が強い。
なお、この『ムーン・ライディング』は、のちにフリーマンが率いるウェストコーストの人気グループ、ザ・リッピントンズのアルバムの1枚として、パスポート・ジャズ、さらにGRPレコードによってリイシューされる。その際、音源はリミックスされ、ジャケットはおなじみのビル・メイヤーによる“ジャズ・キャット”のイラストがあしらわれたものに変更され、アルバム・タイトルも『ムーンライティング』に改変された。スムース・ジャズの原点とも捉えられる、この作品から溢れ出す軽快なリズムとポップなメロディが光彩を放つ爽やかなサウンドは、エヴァーグリーンなもの。コンテンポラリー・ジャズの歴史が語られるとき必ずや挙げられるであろう、時代を超えて愛されるつづける名盤である。
ところで、オリジナルのほうの『ムーン・ライディング』のジャケットのバックカヴァーに、クルーズ・コントロールのメンバーが記載されている。そこには、ラス・フリーマン(g, synth)、ビル・ランフィア(b)、トニー・モラレス(ds)、スティーヴ・リード(perc)らとともに、グレッグ・カルーキス(key)のクレジットがある。まあ、リイシュー盤の『ムーンライティング』においては、カルーキスの扱いがフィーチュアリング・アーティストのひとりとなっているので、彼がグループの正式メンバーであったかどうかは定かでない。しかしながら、カルーキスはこのレコーディングのすべてのトラックに、キーボーディストとして参加している。1970年代半ばからスタジオの仕事をしていたカルーキスではあるが、ぼくが彼に興味をもったのは、このときがはじめてだった。
全体的にエレクトリックな響きが冴えわたる初リーダー・アルバム
その翌年、グレッグ・カルーキスの初リーダー・アルバム『ザ・ナイトアウル』(1987年)が、なんともいいタイミングでリリースされた。ロサンゼルスのマイナー・レーベル、オプティミズム・インコーポレイテッドからの発売だったが、輸入盤として日本のショップでも販売された。オプティミズムのカタログには、のちにスムース・ジャズ系のラジオ・ステーションを賑わせることになるサンディエゴのグループ、ファットバーガーのファースト・アルバム『ワン・オブ・ア・カインド』(1986年)や、ボブ・ジェームスの重要なバンド・メンバーで、37歳でこの世を去ったトランペッター、マイク・ローレンスの『ナイトウィンド』(1987年)といった貴重な作品もある。ぼくはその2枚はもちろんのこと、ほぼ同時期にカルーキスのアルバムも入手した。
むろんぼくは、前述のクルーズ・コントロールのメンバーとして、カルーキスの名前をアタマにインプットしていたから、彼のリーダー作を手にとったわけだ。もしそうでなかったら、この『ザ・ナイトアウル』について、ぼくは購入の機会を逸していたかもしれない。人生で出会える音楽家の数は限られるが、ぼくがその後カルーキスの音楽と深くつながっていくことを考えると、なにか不思議な縁のようなものを感じてしまう。それは、グルーシンやジェームスの場合にもおなじことが云えるのだけれど、もともと出会いとはそういうものなのだろう。ただこの作品を聴いたときはまだ、いずれカルーキスがぼくの敬愛する音楽家になるとは想像だにしなかった。彼がフリーマンと同様に、サウンド・クリエイトに立脚している点には、シンパシーを感じたけれど──。
カルーキスは『ザ・ナイトアウル』では、プロデュースとレコーディングを自身で手がけ、楽曲のすべてを作曲、アレンジしている(一部共作もある)。参加ミュージシャンは、ケン・ナヴァロ(g)、ジェイ・デュラニー(b)、スティーヴ・サミュエル(perc)、ゲイリー・ミーク(ss, ts)のみ。それ以外の色彩豊かなサウンドは、カルーキスによるデジタル・シンセサイザーをはじめ、彼がプログラミングしたドラムマシン、パーカッションのサンプリング音を再生させたシーケンサーによるものだ。カルーキスはアコースティック・ピアノも弾いているが、全体的にはエレクトリックな響きが冴えわたる。このあたりは、フリーマンのマナーと共通する。無名時代のジェフ・ぺシェットが1曲歌っている(作詞もしている)が、AORファンは要チェックだ。

これはまったく、自分の早計な独断だったからカルーキスには詫びなければならないのだが、恥ずかしながらぼくは『ザ・ナイトアウル』を聴いた時点で、彼のことをバックオペレーションに徹するようなミュージシャンと、勝手に思い込んでしまったのだ。なぜなら、カルーキスがキーボードやプログラミングだけでなくレコーディングやミキシングまで自らそつなくこなしているところから、花形アーティストの作品でいかさま簀子の下の舞となるであろう、有能なサウンド・クリエイターというイメージが湧いたからだ。逆の云いかたをすれば、このアルバムでカルーキスは敢えてそうしたのかもしれないが、プレイヤーとしての自己の内面的なもの、主観的なものを前面に出していなかったのである。
それからしばらくの間、不覚にもぼくのなかでカルーキスの存在は、すっかり忘却の彼方に追いやられていた。そんなぼくがハッとさせられたのは、4年後のこと。それは『愛は哀しみの中に』(1991年)というアルバムを聴いたときだった。この作品は、ニューヨークで活動するカリオカ女性シンガー、ケニアの4枚目のリーダー作で、日本コロムビアのレーベル、ポートアズールからリリースされた。ぼくはこのアルバムが好きでいまでもよく聴くのだが、冒頭の2曲「セレブレイト・ザ・ナイト(フェステジャール・ナ・ノイチ)」と「愛は哀しみの中に」のソングライティングとアレンジを手がけたのは、だれあろうカルーキスなのである。実はこれらの曲をはじめて聴いたとき、ぼくはふと、彼が自分の敬愛する音楽家になると予感したのだった。
この2曲がとにかく出色の出来で、カルーキスの作編曲のマナーがこれまでになくソフィスティケーテッドでスタイリッシュに感じられる。軽快なテンポの「セレブレイト・ザ・ナイト(フェステジャール・ナ・ノイチ)」は、ニューヨリカンのジョン・ペーニャ(b)とブラジリアンのテオ・リマ(ds)とが打ち出す刺激的な16ビートに、パーカッション群やホーン・セクションが応酬するサンバ・フュージョン。かたや「愛は哀しみの中に」は、クールでアーバンなハーモニーが光るAORナンバー。いずれにしても、シンセサイザーやプログラミングが多用された以前のカルーキス・サウンドとは異なる、ミュージシャンたちのパフォーマンスが際立つライヴ感が横溢するトラックである。
ちなみに「愛は哀しみの中に」のほうは、早々にカヴァーされている。ハワイ出身のフュージョン・バンド、シーウィンドの女性ヴォーカリスト、ポーリン・ウィルソンのファースト・ソロ・アルバム『愛の瞬間』(1992年)の2曲目に、この曲が収録されている。このアルバムは日本のポニーキャニオンからリリースされたのでご存知のかたも多いと思うが、本作のプロデュースを手がけたのは、キーボーディストでシンガー、そして琴も弾くYUTAKAこと横倉裕だ。横倉さんは長年活動の拠点をロサンゼルスに置くミュージシャンだが、ワールドワイドな音楽センスをもったひと。彼のペンによるリズムとストリングスのアレンジが、このカルーキスの名曲によりポピュラーな響きを与えている。
作編曲、ピアノの演奏、そして音楽に対する向き合いかたがナチュラル
そんなふうにグレッグ・カルーキスに対するぼくの見解が飛躍的にあらたまりつつあるとき、あれよあれよという間に今度は彼のセカンド・アルバム『キー・ウィットネス』(1991年)が、あつらえ向きにリリースされた。結論から云うと、この作品を聴いてぼくはすっかりカルーキスの熱烈な支持者となった。前作同様、各種のシンセサイザーをはじめ、サンプリングされたベース音、プログラミングされたドラムスとパーカッションなど、テクノロジーの粋が集められているが、トータル的には生演奏の魅力が引き立てられている。云ってみれば、前作で強調されていたヴァーチャルなサウンドは、ここでは楽曲に彩りを添える役割りにとどまっていて、よりリアルな音空間がクリエイトされている。メイン・キーボードもアコースティック・ピアノになり、結果的にカルーキスのジェントルな音楽性が明瞭になった。
レコーディング・メンバーを観てみると、前作に引きつづいてジェイ・デュラニー(b)、ゲイリー・ミーク(ts)、ジェフ・ぺシェット(vo)らのクレジットを見出すことができるが、なんといっても目を引くのは、エリック・マリエンサル、ロン・プライス、ゲイリー ハービッグ、デイヴ・コーズ、リチャード・エリオットといった、フィーチュアリング・サクソフォニストの顔ぶれの豪華さ。いまではスムース・ジャズ界のスターとなっているプレイヤーも見受けられるが、当時の彼らはまだ頭角を現わしはじめたばかりだった。そのフレッシュでパワフルなパフォーマンスを、気軽に聴き比べできるというのは、ちょっとした贅沢でもある。そしてカルーキスは本作以降、この路線をしばし踏襲することになる。
さらに本作には、その後もカルーキスとパートナーシップを継続させていく、ふたりのシンガーが参加している。ひとりは1960年代に「私のエンジェル」や「風の吹くまま」などのヒット曲で人気を博した、ノース・ハリウッド出身の女性シンガーソングライター、シェルビー・フリント。いまひとりは1980年代初頭にシンシナティのジャズ・シーンで注目を集め、スティーヴ・シュミット・トリオを従えて『ファースト・ライト』(1984年)というリーダー作を発表した男性シンガー、ロン・ボーステッド。ふたりのアダルト・コンテンポラリーなヴォーカルは、1990年代のカルーキスのアルバムのトレードマークとなる。その豊潤なトラックの数々は、日本のカンゼン・レコードによって未発表曲が追加され『スムース・ジャズ・ヴォーカル』(2002年)としてまとめられた。

カルーキスは、ケン・ナヴァロが主催するレーベル、ポジティヴ・ミュージックに吹き込んだ『キー・ウィットネス』を含む3枚のリーダー作において、自己の音楽のスタイルを確立したと云える。その後、彼はファーレンハイト・レコードに移籍し、フリントのヴォーカルをフィーチュアしたピアノ・トリオ作品『ホーム・フォー・ザ・ホリデイズ』(1993年)と、日本でのデビュー作となった『ユール・ノウ・イッツ・ミー』(1995年)を発表。さらにリー・リトナーのレーベル、i.e. ミュージックに『ブルー・タッチ』(1998年)、フィル・ラモーン、デイヴ・グルーシン、ラリー・ローゼンらが設立したレーベル、N2K エンコーデッド・ミュージック(のちのN-コーデッド・ミュージック)に『ナイトシフト』(2000年)『ヒートウェイヴ』(2002年)といった作品を吹き込んでいる。
ときはスムース・ジャズの全盛期にあり、クールでリフレッシングな感覚とリラクゼーションが横溢するカルーキスのアルバムは、ラジオ・ステーションにおいてヘヴィローテーションとなる。そしてこのころには、すっかりアコースティック・ピアノとカルーキス自身がモディファイしたフェンダー・ローズが、サウンドの主軸に据えられるようになっていた。バークリー音楽院で音楽理論を学びながらも、早い時期からライヴ・パフォーマンスやスタジオワークを豊富に経験したカルーキスのピアノ・プレイは、いじましい教養などは微塵も感じさせない。その鷹揚な音楽性が彼の最大の魅力と、ぼくは常々感じている。そして、聴くものを自然に引き込むようなそのピアニズムが、もっとも顕著に現れているアルバムといえば、10作目の『ルッキング・アップ』(2005年)だろう。
ということで、最後にこのアルバムについて簡単にメモしておく。個人的には、カルーキスの13枚のリーダー作でもっとも好きなアルバムだ。本作はUKのスムース・ジャズ系レーベル、トリッピン・アンド・リズム・レコードからリリースされた。この作品の特徴といえば、リカルド・シルヴェイラ、ピーター・ホワイト、トム・ロテラ、リチャード・スミス、マイケル・オニールといった5人のギタリストがフィーチュアされていること。そのうちシルヴェイラとオニールは、カルーキスの作品には欠かせないミュージシャンと云える。あとはリック・ブラウン(tp)とアンディ・スズキ(sax, fl)がサポーターを務めているが、ベース、ドラムス、そしてパーカッション類は、カルーキスがプログラミングしたものだ。彼のレコーディングとしてはイレギュラーなスタイルだが、そのぶんピアノ・プレイにフォーカスが合わされている。
作曲とアレンジはすべてカルーキスによる。オープニングはゆったりしたアフロ・キューバン「ガール・イン・ザ・レッド・ドレス」で、ピアノによる陰影を湛えた美しいメロディック・ラインがムード満点。ヒップホップ調の「ロンドン・アンダーグラウンド」では、ローズやオルガンが彩りを加えるなか、ピアノとオニールのギターが軽快に跳ねる。哀愁が漂うボサノヴァ「ルッキング・アップ」では、心地よくフローするピアノも然ることながらロテラのジャジーなギターがいい。エレクトリックな16ビート「リレントレス」では、ローズがファンキーに歌いオニールのギターがクールに鳴く。安らいだ気配が漂う「ファースト・フライト・ホーム」では、ブラウンのミュート・トランペットがビーターな味わいを添える。ポップな「ショウ・ミー・ザ・ウェイ」では、典型的なカルーキス節が全開する。
サウダージ感覚が横溢する「コーナー・クラブ/クルービ・ダ・エスキーナ」は、白眉の出来。ミルトン・ナシメントへの想いが溢れたソングライティング、ピアノとギターのアドリブ、すべてパーフェクト。シンセの音色が余韻を残す「イザベラ」は、コード進行で聴かせる清涼感のある曲。軽やかなサンバ「クロスローズ」は、文字どおりローズの独擅場。アコースティックな響きが爽やかな「ディープ・イントゥ・ユー」では、ホワイトのアコギとスズキのフルートが愁いを帯びたムードを演出。ラストの「ロスト・イン・ネグリル」は、タイトルどおりストレートなレゲエ。スティールパンとオルガンの音色、ピアノのオクターヴ演奏が雰囲気を出している。いずれにしても本作では、カルーキスの作編曲、ピアノの演奏、そして音楽に対する向き合いかたがナチュラルだ。そこに、ぼくは強く惹かれるのである。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。








コメント