名優アル・パチーノが正義感溢れる弁護士を熱演した映画『ジャスティス』におけるデイヴ・グルーシンの傑出したフィルム・スコア
 Album : Dave Grusin / …And Justice For All (1979年)
Album : Dave Grusin / …And Justice For All (1979年)
Today’s Tune : Ballad For God
デイヴ・グルーシンが音楽を手がけたアル・パチーノ主演映画
またぞろデイヴ・グルーシンのサウンドトラック・アルバムを1枚ご紹介してしまおう。好きなのだから仕かたがない。映画は1979年に公開された、アル・パチーノ演じる若き弁護士が、腐敗した法曹界に対し公正と真実を問う法廷ドラマ『ジャスティス』である。メガホンをとったのはカナダの映画監督、ノーマン・ジュイソン。ぼくにとっては『夜の大捜査線』(1967年)『華麗なる賭け』(1968年)『屋根の上のバイオリン弾き』(1971年)など、わりと好きな作品を撮っているひと。グルーシンとは『ディナー・ウィズ・フレンズ』(2001年)において、20余年のときを経てふたたびコンビを組んだ。脚本は監督、俳優としても知られるバリー・レヴィンソンと、彼の当時の奥さまであるヴァレリー・カーティンとが共同で執筆した。
なおこの映画は、第52回アカデミー賞で主演男優賞と脚本賞にノミネートされた。個人的にこの映画でもっとも印象に残っているのは、幅広い演技力を見せたパチーノも然ることながら、法廷で銃をぶっ放すというエキセントリックな行動に出る、高所恐怖症ならぬ高所平気症の裁判官を演じたジャック・ウォーデン。ぼくはこの映画をはじめて観たのは中学生のときだけれど、すでに映画少年として名画座通いをしていた。そしてむろん偶然だろうが、それ以前に鑑賞した映画のなかで自分が好きな作品には、なぜかウォーデンが出演していることが多かった。しかも当時の彼は人間味のある役どころを多く演じており、自然と好感をもってしまったもの。彼が『ジャスティス』で演じた判事は明らかに奇人だけれど、やはり憎めないのである。
ちなみに『ジャスティス』のまえに鑑賞済みとなっていたウォーデンが出演した映画のなかで、ぼくが好きな作品といえば『大統領の陰謀』(1976年)『天国から来たチャンピオン』(1978年)『ナイル殺人事件』(1978年)『チャンプ』(1979年)などが挙げられる。もちろん『十二人の怒れる男』(1957年)のやる気のない陪審員も印象に残っているけれど、あれはキャラクターが当時のそれとずいぶん違うし、彼もまだまだ若く精悍な風貌だったからね──。まあそれはともかく、上記の映画で『天国から来たチャンピオン』と『チャンプ』は、奇しくもグルーシンが音楽を手がけた作品だ。しかも両作ともに、アカデミー作曲賞にノミネートされた。それが所以かどうかは定かでないが、ウォーデンはぼくにとって忘れられないアクターとなった。
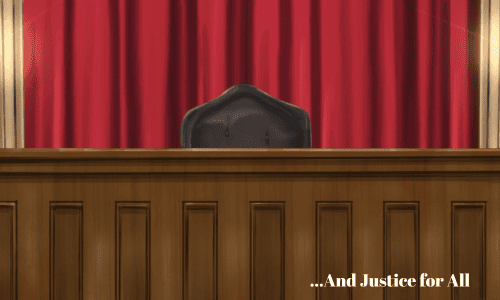
いっぽう主役のパチーノが出演した映画で、この『ジャスティス』以外にグルーシンが音楽を手がけた作品というと、シドニー・ポラック監督の『ボビー・デアフィールド』(1977年)と、アーサー・ヒラー監督の『喝采の陰で』(1982年)がある。どちらも作品の出来はまずまずといったところだが、音楽のほうは両作ともにグルーシンらしく気の利いたスコアとなっている。特に『ボビー・デアフィールド』の音楽は、日本でも公開に合わせてサントラ盤が発売されたこともあり、ぼくにとっては長い間慣れ親しんだものとなっている。しかもこのサウンドトラック・アルバムは、グルーシンとラリー・ローゼンとによって立ち上げられた音盤制作会社、グルーシン/ローゼン・プロダクションの作品なのである。
レコーディング・エンジニアのローゼンはもともとドラマーだったが、グルーシンとはかつてアンディ・ウィリアムスのバンドでおなじ釜の飯を食った仲。のちにふたりがコンテンポラリー・ジャズの最大級のレコード会社、GRPレコードを設立したことはあまりにも有名だ。そんなふたりの共同プロデュース作品だけに『ボビー・デアフィールド』のスコアでは、リー・リトナー、オスカー・カストロ・ネヴィスのギター、ハーヴィー・メイソン、ラリー・バンカーのドラムス、チャック・フィンドレーのフリューゲルホーンなどがフィーチュアされた。またそれと同時に、ザ・ニューヨーク・ジェイルハウス・アンサンブルによるインストゥルメンタル、ヴィクトリア・マイケルズのヴォーカル・ナンバーなど、アルバム用のオリジナル・レコーディングも行われた。
この『ボビー・デアフィールド』でメガホンをとったシドニー・ポラックは、アメリカの映画人ではぼくがもっとも敬愛する監督なのだけれど、正直云ってこの映画は凡作に感じられる。ポラックの演出はいつもながら実に綿密なのだが、ストーリー展開は緩慢だしムードもやや重たい。パチーノと相手役のマルト・ケラーとの好演が光るだけに、ちょっと残念だ。ただヌーヴェルヴァーグ作品を支えたフランスの撮影監督、アンリ・ドカエによるきめ細やかなカメラワークと、物語の舞台が意識されたグルーシンのヨーロピアン・テイストが香るスコアは、ことのほか美しい。ジャズ・アコーディオンの第一人者、フランク・マロッコが奏でる愁いをひそめたメロディック・ラインは、いつまでもこころに残る。
かたや『喝采の陰で』は、パチーノの主演作にしては珍しくコメディ・タッチのドメスティック・ドラマ。個人的には、彼の演技力の高さをあらためて実感した作品だった。しかしながらそれに反して、作品に盛り込まれたアイディアは凡庸に終わっているように思われた。おそらく監督の演出がよくなかったのだろう。大ヒットした『ある愛の詩』(1970年)もそうなのだけれど、アーサー・ヒラーの監督作品はいつもどこか締まらないというか、いまひとつ決め手に欠けると、ぼくには思えてしまうのだ。グルーシンのスコアは、彼の代表作のひとつ『トッツィー』(1982年)のそれを彷彿させる、ソフィスティケーテッドかつハートウォーミングなコンテンポラリー・ジャズ。とはいえ、こころもちコンパクトにまとめられた感じがするのは否めない。
実際ヒットに恵まれなかった『喝采の陰で』だが、当然のごとく公開当時はサントラ盤も発売されなかった。パチーノが主演を務めた作品にもかかわらず、日本では本国公開の4年後にセゾングループ傘下の映画館においてつつましやかに上映された。ただこの映画には、公開まえから興味深いエピソードがある。実はこの映画の音楽は、当初ジョニー・マンデルが担当していた。ヴィンセント・ミネリが監督した映画『いそしぎ』(1965年)の音楽を担当し、その主題歌として作曲した「シャドウ・オブ・ユア・スマイル」で第38回アカデミー賞歌曲賞を獲得した、あのマンデルだ。それでもプロデューサーがよりコンテンポラリーなスコアを要求したことから、急遽マンデルは降板させられグルーシンが起用されたのである。
セッション・シンガー、ザッカリー・サンダースが歌った主題歌
ところが、これが土壇場での交代劇だったため、映画ではグルーシンではなくマンデルが作曲者としてクレジットされていた。さらに面白いことに、採用されたグルーシンのスコアも、もともと『喝采の陰で』のあとに公開を控えていた『トッツィー』のために彼が書いた、初期のスケッチに手が加えられたものだったのだ。ぼくはさきに『喝采の陰で』のスコアが『トッツィー』のそれを彷彿させると述べたけれど、つまるところ両作の音楽からおなじようなイメージが喚起されるのは、至極当然のことだったわけである。これらの逸話は、2007年にサントラ盤の復刻で広く知られるヴァレーズ・サラバンド・レコードによって『喝采の陰で』のスコアの音源がCD化された際に、明らかになった。
おまけにこのヴァレーズ・サラバンド盤には、グルーシンによるスコアが網羅されるいっぽうで、本編では使用されることのなかったマンデルが作曲した6曲も収録されている。このマンデルのスコアが、お蔵入りにするにはあまりにも惜しい素晴らしい出来。ピアノとストリングス、それにギターなどによるハートウォーミングなテーマといい、オーケストラによるリリカルでエレガントなアンサンブルといい、マンデルらしいたおやかさが際立った素晴らしいスコアである。なお過去にシングル盤のみで発売された、グルーシンが作曲、アラン・バーグマン、マリリン・バーグマン夫妻が作詞を手がけ、マイケル・フランクスが歌った主題歌「カミン・ホーム・トゥ・ユー」は、このCDには収録されていないのでご注意あれ。
このEP盤「カミン・ホーム・トゥ・ユー」もまたグルーシン/ローゼン・プロダクションの作品だが、1982年にワーナー・ブラザース・レコードからリリースされた。マイケル・フランクスは、そのジェントル・ヴォイスとジャズやボサノヴァが採り入れられた洗練されたサウンドで、日本でも人気を博していたAOR系シンガーソングライター。ちょうどこのレコードが発売された年、フランクスは「サントリービール・サウンドマーケット ’82 デイヴ・グルーシン&ドリーム・オーケストラ」と題されたグルーシンの日本公演にも同行し、名曲「アントニオの歌(虹を綴って)」を含む4曲を歌った。当初「カミン・ホーム・トゥ・ユー」はアルバム未収録のレアな1曲だったが、のちに5枚組CD『ザ・ドリーム 1973 – 2011』(2012年)に収録された。

だいぶ脇道にそれてしまったが、このへんでハナシを『ジャスティス』に戻すとしよう。これまで述べてきた『ボビー・デアフィールド』『喝采の陰で』が決してわるいというわけではないのだけれど、パチーノの主演映画としてもグルーシンの音楽作品としても、やはり『ジャスティス』が出色の出来であると、ぼくは思う。ここで詳細を語ることはできないが、この映画の終盤の法廷シーンには痛快などんでん返しがある。この場面で、いままさに進行している裁判がとんだ茶番であると、法廷を侮辱するような暴言を吐きまくる正義感溢れる弁護士は、いかにもパチーノらしいキャラクターと感じられる。そういった社会派ドラマでありながら、積極的にコミカルでオーヴァーな演出が施されているところが、この映画のミソとさえ思われる。
この映画の原題『…And Justice for All』は、しばしばアメリカ合衆国の公式行事で暗誦される「忠誠の誓い」と称される成文からとられたものであることは明らか。すなわちそれは、万民に自由と正義を保障する民主国家に忠誠を誓う──といった一節を引用したものだ。パチーノ演じる弁護士は、正義を守るためなら法廷で判事に手を上げることも辞さない熱血漢。そのため彼は物語の冒頭から、拘置所に収容されていたりする。ところが彼は、やり過ぎの嫌いはあるものの妥協を許さぬ法律家として、多くのひとびとから信頼を集めている。映画の大詰めで司法制度の矛盾と裁判の不条理を訴えながらひと悶着起こすパチーノに、思わず拍手喝采するのはぼくだけではあるまい。その点『ジャスティス』は「正義とはなにか」を問う映画だったとも云える。
大暴れして法廷から追い出されたパチーノが裁判所正面の広い石段に座り込んでいると、下からかつて罪悪感から精神の平衡を欠いた親友の弁護士が足取りも軽やかにやってきて、能天気な調子で挨拶してくる。彼のこころの病は治ったのか悪化したのかよくわからないけれど、こころにくい演出である。なによりもこの映画、観賞後にスッキリとした気分にさせられるのがいい。そんなエスプリの効いたラストシーンでは、おもむろにパーカッションとドラムスとによる軽快なリズムとフェンダー・ローズによる水面に波紋が広がるようなフィルインが聴こえてくる。この映画の主題歌「サムシング・ファニー・ゴーイン・オン」だが、ザ・ニューヨーク・ジェイルハウス・アンサンブルをバックに、ザッカリー・サンダースが歌っている。
作曲はもちろんグルーシンが、作詞は毎度おなじみのアラン・バーグマン、マリリン・バーグマン夫妻が担当。ほどよくファンキー・テイストが香るヴォーカルを聴かせるサンダースは、イリノイ州シカゴの出身でニューヨークに活動の拠点を置く、業界では有名なセッション・シンガーだった(1992年没)。早い時期から彼をバッキング・ヴォーカリストに起用していたのは、フュージョン・シーンの雄、ボブ・ジェームス。ジェームスのリーダー作はもちろんのこと、彼がプロデュースやアレンジを手がけた音楽作品では、幾度となくサンダースのクレジットが見受けられた。ほかにもプロデューサー、アレンジャーでは、クインシー・ジョーンズやウィリアム・イートンなどが、レコーディングの際に度々サンダースを召喚していた。
よく知られている音楽作品では、クインシー・ジョーンズのサウンドトラック・アルバム『ウィズ』(1978年)、ビリー・ジョエルの『ニューヨーク52番街』(1978年)、ドナルド・フェイゲンの『ナイトフライ』(1982年)などでも、サンダースによるバックグラウンド・ヴォーカルを聴くことができる。普段は簀の子の下の舞として活躍するサンダースではあるが、この「サムシング・ファニー・ゴーイン・オン」では堂々と主役を張っている。そういう意味では、非常に貴重なレコーディングと云えるのだけれど、なぜかオフィシャルな音盤化はいまもって実現していない。そもそも『ジャスティス』が公開された当時、そのサウンドトラック・アルバムはおろかテーマ曲のシングル・レコードさえ発売されなかったのである。
計30曲が収録されたヴァレーズ・サラバンド盤
ぼくはグルーシンの手がけた映画音楽では、コンテンポラリー・ジャズが本格的に採り入れられたシドニー・ポラック監督、ロバート・レッドフォード主演によるポリティカル・サスペンス『コンドル』(1975年)がもっとも好きなのだけれど、次点を選ぶとなるといささか思案に余る。しかしながら、終始緊迫感が漂う『コンドル』とはずいぶん雰囲気が違うけれど、ジャズのイディオム、ファンキーでリズミカルなグルーヴ、リズム・アンド・ブルースのテイストなどが、渾然一体となってひとつの音世界を構築しているという点、平たく云えばグルーシンならではの上質のフュージョン・サウンドが繰り広げられているというところでは、この『ジャスティス』も同系列に属するものと云えるのではなかろうか。
思えばぼくが好きなグルーシンのフィルム・スコアといえば、むろん『コンドル』は別格の扱いになるのだけれど、それ以外では図らずも1970年代の最後の3年間の作品に集中している。具体的には、映画の公開順に挙げると『ボビー・デアフィールド』(1977年)『グッバイガール』(1977年)『天国から来たチャンピオン』(1978年)『チャンプ』(1979年)『ジャスティス』(1979年)『出逢い』(1979年)といった作品だ。もともとジャズ・ピアニストだったグルーシンは、フィルム・ミュージックのクリエイターとしては、ハリウッドの伝統を汲みながら、ちょっとそこから逸脱するような多様性と革新性をもった作曲家と云える。上記のスコアは、そんなディスティンクティヴな音楽性がもっとも存在感を放ち、自ずと魅力的に映るものと、ぼくは思うのである。
なかでもこの『ジャスティス』の音楽には、ユニークという点では他の追随を許さない、グルーシン・サウンドの素晴らしさを、あらためて感じさせられた。映画を観たときからグルーシンのペンによるスコアに強く惹かれていたぼくは、それがいつまでたっても音盤化されないことに、ずいぶん長い間もどかしい思いをさせられたものである。その点では、いまだ日の目を見ない『グッバイガール』のスコアにもおなじことが云える。幸いなことに『ジャスティス』のサウンドトラックは、2008年ついに前述のヴァレーズ・サラバンド・レコードによってCD化された。フィルム用に編集されたモノラル音源14曲、そのフルレングス・ヴァージョンのステレオ・ミックス音源11曲、本編未使用の5曲といった、計30曲が収録された豪華盤だ。

ただ残念なことにこのCDに、ザッカリー・サンダースの歌唱による「サムシング・ファニー・ゴーイン・オン」のヴォーカル・ヴァージョンは収録されていない。このことは、おそらくマスターテープの破損や紛失などが原因ではなく、歌詞の著作権者であるバーグマン夫妻の許可が得られなかったことに起因するのだろう。まあ、およそ20年もまえの音源がそれ以外すべて掘り起こされたわけだから、ひとまず素直に喜ぶとしよう。また、このCDのバックインレイには、ザ・ハリウッド・スタジオ・シンフォニーによる演奏と明記されているが、これは便宜上あとから銘打たれたバンド名だ。なおレコーディングは、カリフォルニア州バーバンクにあるワーナー・ブラザース・レコーディング・スタジオ(通称バーバンク・スタジオ)で行われた。
レコーディングには多くのミュージシャンが参加しているが、さきにデイヴ・グルーシン自身のキーボードを中心としたリズム・セクションによるパフォーマンスが録音され、そのトラックにあとからホーン・セクションとストリング・セクションとによるアンサンブルがオーヴァーダブされた。クレジットを観ると、ギターにトム・ロテラ、ベースにチャック・バーグホファー、ドラムスにハーヴィー・メイソン、ジョー・ポーカロ、スティーヴ・シェーファー、パーカッションにシーラ E.ことシーラ・エスコヴェード、シンセサイザーにイアン・アンダーウッド、トランペットにチャック・フィンドレー、トロンボーンにビル・ワトラス、フルートにジェローム・リチャードソン、サックスにトム・スコット、ラリー・ウィリアムズと、錚々たる顔ぶれである。
曲目のほうは、鑑賞用音楽として成立するフルレングス・ヴァージョンについて触れておく。イントロにおけるパーカッション類の律動とローズの分散和音が印象的な「サムシング・ファニー・ゴーイン・オン(メイン・タイトル)」は、ファンキーなディスコ・ファンク。テナーの熱いブローイングが聴きものだが、ソウルフルなホーンズ&ストリングスのアレンジにも注目したい。バウンシーな「ライフ・アット・コート」は、ミュート・トランペットをトップに置いたホーンズのアンサンブルがいかにもグルーシンらしい。ローズとソプラノもファンキーに跳ねる。ヨーロッパの香りが漂うゆったりした「ゴー・シー・グランパ」は、シンセによるメロディとストリングスのオブリガートが美しい。終盤のホンキートンク・ピアノの音色も印象的だ。
ジャジーなラヴ・テーマ「バラード・フォー・ゴッド」は、リラックスした4ビートと転調が心地いいこれぞという名曲。ブラシとアップライト・ベースとによる小気味いいリズムと、ギターの軽やかなストロークに乗って、グルーシンのピアノ・プレイが素早い指遣いでスウィングする。ペダルポイントが活かされたローズとアルトによるブリッジ「ジェイズ・アウト」をはさんで、躍動感に溢れたスラップ・ベースがはじき出すグルーヴに胸がすく「クライアント・ヴィジット」では、フルートのジャジーなソロと後半のオーケストラによるダイナミックな展開が聴きどころ。重苦しい空気が漂うなかファンキーなリズムが繰り出される「サンクス・ギヴィング」と「プレート・フィニッシュ/フラストレーション」は、グルーシンによる典型的な緊迫感溢れるスコア。
さらにスコアは、ホーンズとスラップ・ベースが緊張感を高める「ホステージ・ヴィジット」ふたたびペダルポイントが効果的なローズとアルトがフィーチュアされた「クライング・ジャグ」そして現代音楽風の弦楽器が不穏なムードを醸し出す「ディフェンド・オア・ゲット・アウト」とつづく。本編未使用曲のなかには、ジャズ・ファンクやサンバのセッション、さらにはカクテル・ミュージック風の「サンクスギヴィング・サンク」の別ヴァージョンなど、聴き応えのあるトラックもある。これだけ充実した音源が揃っているのにもかかわらず、なぜ当時音盤化されなかったのか不思議でならない。いずれにしても、ここにある音楽がグルーシンの傑出したフィルム・スコアであるということは、紛れもない事実である。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。








コメント