常に前進し続けるミュージシャン、ボブ・ジェームスの最新作『ジャズ・ハンズ』を聴く
 Album : Bob James / Jazz Hands (2023)
Album : Bob James / Jazz Hands (2023)
Today’s Tune : Beerbohm
ボブ・ジェームスの音楽に触れると、自然とピュアな気持ちになる
ボブ・ジェームスは、常に前進し続けるミュージシャンだ。先日、彼の最新作『ジャズ・ハンズ』(2023年)が、ようやくぼくの手許に届いた。思わず「ようやく」と云ってしまったが、べつにアルバムがリリースされるまで、想定以上に時間がかかったというわけではない。この「ようやく」は、ぼくの「早く聴きたい」という気持ちがストレートに現れたもの。敢えてファーストネームで呼ばせてもらうが、ボブの新作がリリースされるという情報がもたらされるたびに、ぼくはまるで子どものようにその到来をこころから待ち望んでしまうのだ。それこそ子どもの頃から、もう何十年もそういう思いを繰り返してきた。そしていつも、ぼくのなかに純粋無垢なこころが蘇る。それは、いまも変わらない。
いまさら説明の必要もないと思うが、ボブはジャズ/フュージョンの世界では1960年代から活躍するビッグネーム。コンポーザー、アレンジャー、キーボーディスト、そしてプロデューサーとして、数えきれないほどの音楽作品を幅広く手がけてきた。しかも彼は、コマーシャルな仕事でもただビジネスライクに処理するのではなく、常にその作品をアートオリエンテッドな音楽に仕上げてしまうのだ。そんなマジックの起源は、いまになってみると20代のボブが得たアヴァンギャルドな着想と、あながち無関係とは云いきれないように思われる。その昔、彼は前衛芸術の作曲家、ロバート・アシュリーとゴードン・ムンマの協力を得て、ジャズに電子音楽の手法を取り入れたことがあった。そういうフレキシビリティは、いかにもボブらしい。
そんなボブの作品に触れると、ぼくは音楽に対して自然とピュアな気持ちになる。なぜなら彼が、どんなシテュエーションにおいても音楽と向き合うとき、寛容で、柔軟思考で、開放的で、そして偏見をもたないからだ。そして、彼の音楽の本質を見極めようとする気持ちは、いまもまったく止まるところを知らない。今作でもまた、なにか新しいことにチャレンジしているのだろうと、ぼくの期待は高まるばかりだ。今回もトリオで吹き込まれた『エスプレッソ』(2018年)と同様に、ボブの自己レーベルであるタッパン・ジー・レコードからのリリースとなる。このレーベル名の専用実施権は現在、エヴォリューション・ミュージック・グループがもっているのだが、同じトリオによる『フィール・ライク・メイキング・ライヴ!』(2021年)では、なぜか使用されていなかった。

エヴォリューションは、香港の九龍(カウルーン)に拠点を構えるレコード会社だが、上記のライヴ・アルバムのレーベルはエヴォリューション・メディアと記載されていた。ささいなことかもしれないが、長年ボブの音楽に親しんできたぼくにとって、タッパン・ジーは特別の思い入れがあるレーベルなのだ。このレーベル名の由来は、ニューヨーク州を流れるハドソン川にかかる橋の名前。ロックランド郡とウェストチェスター郡を結ぶ交通の要衝である。やわらかな青地に黄色のつり橋のシルエットが三つ並んだセンターラベルが懐かしい。同レーベルは1977年に当時のCBSレコード傘下で発足され、その制作活動は1985年まで継続された。
これも往年のファンのかたには釈迦に説法になってしまうのだが、敢えて云わせていただく。タッパン・ジーといえば「タッパン・ジー」という曲、ウェストチェスターといえば「ウェストチェスター・レディ」という曲が即座に思い出される。それぞれ、ボブのリーダー作『BJ4』(1977年)と『スリー』(1976年)に収録されている、彼の自作曲である。どちらもシンプルなメロディック・ラインとユニークなグルーヴをもった人気曲だ。クラブ世代からはサンプリング・ソースとして重宝されている。特に後者は、ヒップホップ・ミュージックにおいて、そのイントロのベースのリフとドラムスのパターンがオマージュされることが多く、それが意識されたのか現在もボブのライヴ・パフォーマンスにおける重要なレパートリーとなっている。
往年のタッパン・ジー・レコードと、この10年のボブ・ジェームス
もしモダン・ジャズのようにクロスオーヴァー/フュージョンにもスタンダーズというものがあるとするならば「ウェストチェスター・レディ」はまさにその呼称に違わぬものと云えるだろう。ちなみに、ロンドンに拠点を構えるチェリー・レッド・レコードから『ヴェリー・ベスト・オブ・タッパン・ジー・レコード』(2018年)という2枚組のコンピレーション・アルバムがリリースされているが、おもしろいことにこのCDでは「タッパン・ジー」がDisc-1「ウェストチェスター・レディ」がDisc-2と、それぞれの冒頭を飾っている。やはりこの2曲は、重要なナンバーと認識されているのだろう。なおこのCDには、ジョアン・ブラッキーン(p)やアレン・ハリス・バンドの未CD化アルバムからの貴重なトラックも収録されているので、機会があればぜひ手にとっていただきたい。
ところで、タッパン・ジー・レコードがスタートした1977年以降、ぼくはボブのアルバムをすべてリアルタイムで体験してきた。だからぼくは、このレーベルにとても愛着を感じるのだ。1975年に彼は、まだCTIレコードにアーティストとして在籍していたが、CBSのA&Rディレクターに就任した。メイナード・ファーガソン(tp)、エリック・ゲイル(g)、ケニー・ロギンス(vo)などのアルバムをプロデュースしていくなかで、1977年にCTIレコードとの契約が切れるとすぐに自己のレーベルを立ち上げた。それが、タッパン・ジーだ。レーベル第1弾は、ギタリストのスティーヴ・カーンの初リーダー作『タイトロープ』(1977年)で、ボブ自身も間もなく『ヘッズ』(1977年)を発表した。
この『ヘッズ』とCTIにおける最終作『BJ4』が、ぼくのボブ・ジェームス初体験だ。それからというもの、ぼくは半世紀近く彼の音楽を追いかけてきたことになるが、改めてそれを思うと感慨深いものがある。しかも、いまだに彼の新作を待ち焦がれるような自分がいるわけで、成長しないぼくもぼくだが傘寿祝いを迎えてもなお相変わらず前進し続けるボブもボブだ。ということで、すっかり長くなってしまったが新作『ジャズ・ハンズ』を観ていこう。発売元のエヴォリューション・ミュージック・グループでは、現在グローバルな事業展開がなされているが、おなじアジア地域ということもあるのか、日本へ輸出されるCDには親切なことに日本語帯とライナーノーツが付属されている。

ところが、ぼくはその帯を見てちょっと疑問をもったのである。というのも、セールスコピーに「10年ぶりのソロアルバム」と記載されていたからだ。ボブを知らないひとが見たら、彼の音楽活動が長らく停滞期にあったと勘違いしそうだ。もちろん、そんなことはない。冒頭でも断言したが、彼は常に前進し続けるミュージシャンなのだから──。そこで念のために、ぼくは自室のCD棚にある、彼がこの10年にリリースした作品を確認してみた。すると、2013年に日本のジャズ/フュージョン作品を数多く手がけた伊藤八十八(故人)とボブが共同でプロデュースした唯一のソロ・ピアノ作『アローン』が、まず目にとまる。サブタイトルに「Kaleidoscope by Solo Piano」とあるように、万華鏡のごとき千変万化するピアノ演奏のパターンを堪能することができる傑作だ。
蓋しこのアルバムの発表から10年という意味なのだろうか?とにもかくにも、手許のCDを見とどけて見よう。デヴィッド・サンボーン(as,ss,sopranino)との共作『クァルテット・ヒューマン』(2013年)、韓国の女流作編曲家でオカリナも吹くレイチェル・クァグとのコラボ作『ポイエーマ』(2014年)、ミシガン州トラヴァース・シティの講堂における実況録音『ライヴ・アット・ザ・ミリケン・オーディトリアム』(2015年)、フォープレイの盟友ネイザン・イースト(b,vo)との共作『ザ・ニュー・クール』(2015年)、女性フルーティスト、ナンシー・スタニッタとのデュオ『イン・ザ・チャペル・イン・ザ・ムーンライト』(2017年)、トリオによる『エスプレッソ』(2018年)、ドイツのトランペッター、ティル・ブレナーとの共作『オン・ヴァケーション』(2020年)、トリオによるライヴ盤『フィール・ライク・メイキング・ライヴ!』(2021年)と、実に変化に富んだ仕事ぶりだ。
そして、前作にあたる『2080』(2022年)は、ボブと自分の孫くらい若い、DJでエレクトロニック・アーティストのサム・フランツとによるコラボレーション作品。「東京JAZZ」の元プロデューサー、八島敦子が設立したエイト・アイランズ・レコードからリリースされた。このアルバムなどは、これまでのボブのどの作品とも違う音風景を呈していた。それは、エキサイティングでありながらロマンティックで、ときにはアヴァンギャルドな一面すらのぞかせる。ジャズ/フュージョンという言語に依存することなく、自由自在にイノヴェイティヴな音楽を創造してしまうところが、いかにもボブらしい。やはり、彼は前進し続けている。「10年ぶり」という言いまわしは、まったく似合わないのである。
ジャンルやスタイルを異にするアーティストたちが集結したアルバム
さすれば本作には「10年ぶりのソロアルバム」というよりも、この10年間のボブのキャリアの集積による、ひとつの到達点のような風情さえ感じられてくる。オープナーの「マンバリシャス」は、ボブのツアー・メンバー、ジェームス・アドキンスが打ち出すドラムスのリズム・パターンが精力的かつ痛快無比。とにかく、これにやられた。クワイア音源のシンセサイザーをバックに、ボブのピアノが流麗なフレーズをインプロヴァイズする。レニー・カストロのパーカッションのラテン・フレイヴァーも気持ちがいい。ボブとアドキンスの共作だが、タイトルはあのドイツ生まれのフルーツ・キャンディのこと?つづく「ジ・アザーサイド」は1960年代のポップ・チューンを彷彿させるゆったりしたジャズ・ロック。ブルージーでノスタルジックなリッキー・ピーターソンのハモンドは、ボブの楽曲では逆に新鮮に響く。
アルバム・タイトルになっている「ジャズ・ハンズ」は、フォープレイのヴォーカル・ナンバーがクリアにイメージされる。こういうセンシュアルでダンサブルなR&Bテイストの曲は、コンテンポラリー・ジャズのアルバムにおいてアクセントにもなるし、次曲に備えるための箸休めの役割も果たす。しかしボブの作曲とは、ちょっと意外だった。ヒップホップ・シンガー、シーロー・グリーンによるゴスペル・タッチのヴォーカルから、絶妙な心情表現が発露する。ドラム・ループも彼のプログラミングによるものだ。次のホアキン・ロドリーゴ風の「カム・イントゥ・マイ・ドリーム」では、スパニッシュなテーマから洗練された感じのシンコペーションへの移行が意表を突く。ビロードのように滑らかな音色で哀愁を醸し出しているのは、デイヴ・コーズのアルト。
前半を締める「ビアボーム」は、シンコペーテッドなサンバ風のリズム、クラシカルなテーマ、そして気持ちよくスケールアウトするピアノのインプロヴィゼーションと、これぞボブ・ジェームスといった一曲。こういう爽快感が、やみつきになるのだ。曲名はボブの愛称。彼を見出したクインシー・ジョーンズがそう呼んだ。1960年代にブロードウェイの仕事をしていたボブが、しきりに英国のエッセイスト、マックス・ビアボームの戯曲を採り上げようとしていたことに由来する。つづく「ジ・アルケミスト」はマイケル・パラッツォーロのオリジナルで、彼のセンシティヴなベースがフィーチュアされた瞑想的なナンバー。クラシカルなハーモニーのなかにジャズのニュアンスが加味されているが、それがまるで光と影のように豊かな色彩を織りなしている。
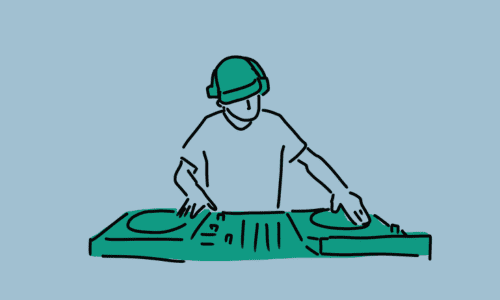
ベースもドラムスもプログラミングの「モップヘッド」では、ヒップホップのビートをベースに古典的な和声が絡み、ボブのエレピがブルージーなソロをとる。ゆったりしたテンポのなかで、シンセによるパンフルートとクワイア・サンプルも効果的に響く。この曲から次曲へのつなぎがいい。アルバム中もっとも踊れるナンバー「ザット・バップ」は、トランス・フォーマー・スクラッチを生み出したことで知られるターンテーブリスト、DJ・ジャジー・ジェフが大胆にフィーチュアされた曲。弾力感に富んだシンセ・ベースはカイディ・テイタムによる。このコンビが星野源の「喜劇」をリミックスしたことは、記憶に新しい。ボブは彼らが作り出すループとサウンドにフェンダー・ローズで応戦。気持ちよさげに、ファンキーなフレーズを繰り出している。
もしかすると、ダンスフロアを席巻するようなグルーヴ感に満ちたこの曲あたりが、本作の目玉なのかもしれない。ちなみに、ジェフはウィル・スミスとのデュオ、ジャジー・ジェフ&フレッシュ・プリンスにおいて、1987年の「ア・タッチ・オブ・ジャズ」と1988年の「ヒア・ウィ・ゴー・アゲイン」という曲で、ボブの「ウェストチェスター・レディ」をサンプリングしている。ところで、クールなヒップホップ・ジャムで盛り上がったあと、本作のムードはがらっと変わる。ボブとレイチェル・クァグとの共作「ザ・シークレット・ドロワー」は、ウェザー・リポートを彷彿させる異国情緒が漂う曲。やはりボブのツアー・メンバーのウクライナ出身のアンドリュー・チュマットがアルトで参加。しかしながら、ここではボブによるソリッドでスパークリーなキーボードが随一。
ラストの「シー・ゴッデス」は、カリブ海のクルーズ船のなかで実況録音されたトラック。ピアノによるリリカルなルバートといい、インテンポ以降のドラマティックな展開といい、1980年代のボブの楽曲を思い起こさせる。それこそタッパン・ジー・サウンドと云いたくなるような、聴き応えのある曲だ。ボブのピアノ、トム・ブラクストンのテナー、そしてドゥワイト・シルズのギターと、それぞれの熱いアドリブ・ソロが繋がれていき曲は大いに盛り上がる。その爽快感が、アルバムのクロージングに相応しい。いかがだろう、確かにこれまでのボブの作品にも、数多くのプレイヤーがフィーチュアされるものはあった。でも、コラボの時間枠は様々とはいえ、ここまでジャンルやスタイルを異にするアーティストたちが集結したアルバムは過去になかったと思う。果たせるかなボブ・ジェームスは、常に前進し続けるミュージシャンなのである。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。








コメント