現在も前進しつづけるボブ・ジェームスのまさに大胆なデビュー作

Album : The Bob James Trio / Bold Conceptions (1963)
Today’s Tune : My Love (from Candide)
決してひとところに止まらず、常に前進しつづける
ボブ・ジェームスは、デイヴ・グルーシンと並んで、ぼくがもっとも影響を受けたアーティストだ。一般的にも、コンテンポラリー・ジャズの大御所という意味合いで、ふたりはよく比較される。確かに、そのキャリアにおいて共通する点はたくさんあるのだけれど、その音楽性には微妙な違いがあるように、ぼくには感じられる。
デイヴの音楽(特に作曲やアレンジ)には、ある種ハリウッドの伝統を汲んだところがある。それに対してボブは、もう少しアートオリエンテッドな音楽を目指しているように、漠然とではあるが、それでも紛ごうことなく感じられる。チャレンジ精神が旺盛というか、決してひとところに止まらず、常に前進しつづける──そんなところがあるんだな。
たとえば、彼の最新アルバム『2080』(2022年)は、自分の孫くらい若い、DJでエレクトロニック・アーティストのサム・フランツとのコラボレーション作品になるが、これまでのボブのどの作品とも違う景色を呈している。それは、エキサイティングでありながらロマンティックで、ときにはアヴァンギャルドな一面すらのぞかせる──そんな音世界。

さらに云えば、そこで繰り広げられている音楽を、あるひとつの側面からジャズやフュージョンに分類してしまうのは、あまりにも不自然なことと思われる。確かにボブは、1970年代以降、クロスオーヴァー/フュージョンの代名詞的存在と観られてきた。しかしながら、当の本人はそんなことに囚われることはまったくなくて、特定の言語に依存しない音楽を自由自在に創造してきたのだ。その点は、いまも変わっていない。
ところで、この新作を制作したEIGHT ISLANDS RECORDSのプロデューサー、八島敦子さんにとって、ボブ・ジェームスの音楽とのはじめての出会いは、レコード店でジャケットに魅せられてたまたま手にとった、ボブのデビュー作『ボールド・コンセプションズ』だったという。そして──このアルバムから受けた衝撃こそが、今回、八島さんを動かす一因となったようだ。
大胆な着想が斬新な音世界として具現化
1962年、まだ大学生だったボブ・ジェームスは自己のピアノ・トリオで、ノートルダム・ジャズ・フェスティヴァルに出演──優勝を果たす。そのことが、あのクインシー・ジョーンズの目にとまり、マーキュリー・レコードにおいて、ロン・ブルックス(b)、ボブ・ポーザー(ds)とともにレコーディングを行うことに……。その音源をまとめたものこそが『ボールド・コンセプションズ』だ。ちなみに本作では、クインシーが音楽監督を務めている。
本作は、初リリースから六十年近くも経った2022年において、国内では初のCD化──とのこと。ああそうなんだ──と、ちょっと意外だった。レコードの時代には国内盤も発売されていたし、米国ではいまから二十年以上も前にCD化されていたからね──それなりによく知られた、人気盤と勝手に思い込んでいた。そうはいっても、この作品を正当に評価するひとは、どれだけ居るのだろう?──なんて、ぼくはついつい疑問に思ってしまう。
前述のように、その昔、ボブ・ジェームスはクロスオーヴァー/フュージョンの代名詞的存在──といった先入観が、多くのリスナーにあったから、本作は、生粋のジャズ・ファンのかたたちからは当然のごとく見向きもされなかった(あの頃はフュージョンを軟弱な音楽と馬鹿にする傾向があった)。それでも、一部のマニアのかたからは、レニー・トリスターノやデニー・ザイトリンに連なる白人ジャズ・ピアニストの珍盤と、変な感じで重宝されることもあった。

しかも、実際に聴いていただければ(奇食扱いされる理由を)おわかりいただけると思うが、本作ではアルバム・タイトルのとおり、アヴァンギャルドと云っても過言ではないほどの、大胆な着想が斬新な音世界として具現化されている。それをひとことで云えば、現代音楽のジャンルのひとつである、ミュージック・コンクレート──ということになる。たとえば、ボブ自身は通常のアコースティック・ピアノも弾いているけれど、ときとしてプリペアード・ピアノの手法を即興演奏に取り入れたりしている。
さらに、ここで使われているパーカッション類がスゴイ!たとえば、テンプルブロック、ヒョウタン、ガラスや竹で出来たウィンドチャイム、磁気テープなどの特徴的な音色が聴こえてくる。ときには、(主にポーザーが)ドラム缶をマレット、ワイヤー・ブラシ、おはじき 、ゴルフボールなどで叩いたり、鉄パイプをハンマーで打ったりしている。さらには、スライドホイッスルやトーネットも吹く……。
ちなみに、やはりトリオで吹き込んだ次作『エクスプロージョンズ』(1965年)において、ボブは、前衛芸術の作曲家、ロバート・アシュリー&ゴードン・ムンマのコンビの協力を得て、電子音楽の手法を取り入れている。そのぶんパーカッション類は鳴りを潜めて、全体のサウンドからも、どちらかといえば、より現代音楽に接近したような印象を受ける。そういう意味では『ボールド・コンセプションズ』のほうがよりジャズらしい作品──と、云えるのかもしれない。
変わらないのは、意外性というか、フレッシュな独創性
曲目もなかなか興味深い。全8曲中、ボブのオリジナルは2曲──「トリロジー」と「クエスト」は、どちらも(いかにも彼らしい)シンプルなテーマのあとに、フリー・フォームの即興演奏が大胆に展開されて、ふたたびテーマに戻る──という構成。この2曲が、前述した独創的な実験的技法が、もっとも全面に出された楽曲だ。
それに対して、ちゃんとモダン・ジャズの名曲が採り上げられているのも、おもしろい。ジョン・コルトレーンの「モーメンツ・ノーティス」でボブは、たたみかけるような高速プレイで、名ジャズ・ピアニストぶりを発揮──その点では同様に、一部ミュージック・コンクレートとプリペアード・ピアノの手法が採用された、マイルス・デイヴィスの「ナーディス」やディジー・ガレスピーの「バークス・ワークス」も、どちらかといえば正攻法的な演奏と云える。
むしろミュージック・コンクレートなしの曲──シンガー・ソングライターのマット・デニスのバラード「ザ・ナイト・ウィ・コールド・イット・ア・デイ」が、速いテンポで演奏されて原曲とはまったく違う印象を与えていたり、レナード・バーンスタインのミュージカル『キャンディード』(1956年)からの「マイ・ラヴ」では、心地いいポリメトリックなグルーヴ感が生み出されていたり、ボサノヴァ風にアレンジされてヒットした「フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン」がしっとりとしたバラードで演奏されていたりする──それらのほうに、ぼくは意外性を感じた。
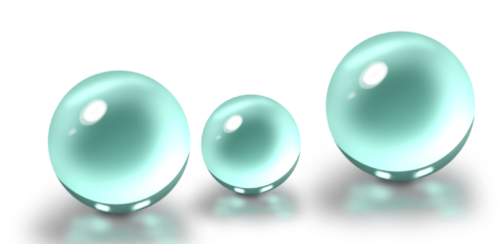
いやいや、それは意外性というか、フレッシュな独創性と云うべきかもしれない。この点には、のちのコンテンポラリー・ジャズ・シーンを牽引するサウンド・クリエイターとして大活躍することになる、ボブ・ジェームスの音楽性が、強く感じられる。そういったことから逆算してみても、本作は、現在も止まることを知らない音楽家の、貴重な出発点の記録であって、もっと高く評価すべきものではないだろうか。
なおCDには、もともと『マーキュリー 40th アニヴァーサリー V.S.O.P. アルバム』(1984年)という4枚組LPに収録されていた「朝日のようにさわやかに」と「ゴースト・ライダーズ・イン・ザ・スカイ」の2曲が追加されている。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。









コメント