かつてビバップ全盛期の優れたピアニストだったアル・ヘイグがニュー・メインストリームの熟練ピアニストとして吹き込んだ上質のアルバム『インヴィテーション』
 Album : Al Haig Trio / Invitation (1974)
Album : Al Haig Trio / Invitation (1974)
Today’s Tune : Holyland
初期のビバッパー時代──初リーダー作を吹き込むまで
アル・ヘイグというと、ヨーロッパ系アメリカ人のバップ・ピアニストとしては、草分け的存在だ。1922年7月22日ニュージャージー州ニューアーク生まれの彼は、1940年代の初頭からプロのジャズ・ピアニストとして活躍していた。9歳からピアノのレッスンを受けはじめたヘイグは、ニュージャージーの公立高校ナトリー・ハイスクールに進学し、当時からナット・キング・コールやテディ・ウィルソンの影響を受けて、ジャズ・ピアノを弾くようになった。高校卒業後は沿岸警備隊の務めに従事しながら、マサチューセッツ州のボストン周辺でフリーのミュージシャンとして活動した。その後奨学金を受けて、オハイオ州のリベラル・アーツ・カレッジ、オーバリン大学へと進み音楽理論を学ぶも、敢えなく中退。1944年、いよいよニューヨークへ進出する。
ヘイグは、かつてバードランドをはじめとするジャズ・クラブが数多く集まっていた、いわばジャズの中心地、ニューヨークのマンハッタン52丁目に活動の拠点を構えた。彼は早々にトランペッターのディジー・ガレスピーのグループに加わり、1946年まで演奏しつづけた。いまもモダン・ジャズ初期の歴史的演奏と高い評価を得る、“ミュージクラフト・セッション”と称される1945年から1946年にかけての吹き込みにおいて、ガレスピーのクインテットやセクステットでピアノを弾いているのは、だれあろうヘイグである。さらに彼は1948年からは、アルト奏者のチャーリー・パーカーのグループに加入。その後ヘイグは、マイルス・デイヴィスの若き日の名作『クールの誕生』(1957年)のレコーディングにも参加している。
このクール・ジャズの礎を築いたとも云われる歴史的名盤の収録曲のうち、1949年1月21日の吹き込みにヘイグが参加しているのだ。ホーン・セクションにアルト、バリトン、トランペット、トロンボーンのほか、ジャズでは稀なケースだがフレンチホルンとチューバが加えられており、どちらかというと各々のソロ・プレイよりもアンサンブルを味わうべきアルバムと云える。この日のセッションでは、どうしてもジョン・ルイスとジェリー・マリガンとがアレンジを手がけた重奏に、注意を惹きつけられてしまうのだが、ジョー・シュルマンのベースとマックス・ローチのドラムスとともにリズムを支えているのは、確かにヘイグのピアノなのである。うっかり忘れてしまうのだけれど──。
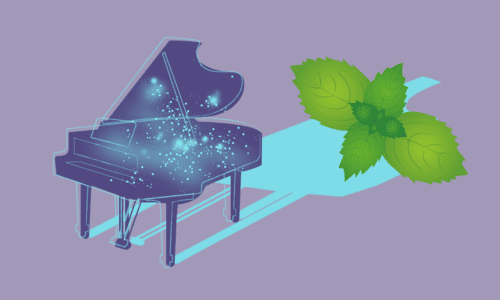
正直に告白すると、ぼくはこの『クールの誕生』を一度として真剣に聴いたことのないきわめて不届きなヤツである。そもそもこのレコード、高校生だったぼくは、ジャズ・レコード史上、最重要作品という世評に乗せられて、手にしたまで。一般的には、クロード・ソーンヒル楽団のアレンジャーだったギル・エヴァンスのオーケストレーションがイノヴェイティヴだとか、西海岸のジャズ・シーンに多大な影響を与えたとか、いろいろなことが云われているけれど、ぼくにとってはリラックスしたライトなサウンドのBGMとして楽しむことに止まる1枚。ジャズの帝王もまだ22歳、そのフレッシュな演奏には好感がもてる。ただヘイグのピアノ・プレイは、あまり聴こえない。たまに耳に入るコンピングにしても、いいのかどうかわからない。
ただ、こんなこぼれバナシがある。このころミッドタウン・マンハッタンのシアター・ディストリクト、ブロードウェイ1580番地にあったジャズ・クラブ、ロイヤル・ルーストのオーナー、モンティ・ケイがマイルス・デイヴィスに「好きなメンバーを集めて、好きなように音楽をやってみないか」ともちかけたことは、よく知られている。ところで、そのコトバがそのまま『クールの誕生』のコンセプトに繋がったのだとすれば、当時のヘイグはデイヴィスから有能なミュージシャンとして一目置かれる存在だったことになる。このとき彼はまだ26歳だったが、すでにイッパシのジャズ・プレイヤーだったのだ。まあ、ぼくがそんなふうに見識を深めるのはずっとあとのことで、当初はヘイグの名前すら気に留めなかったのである。
ヘイグの初リーダー作は、名門プレスティッジ・レコードからリリースされた。プレスティッジは、もともと音楽プロデューサーのボブ・ウェインストックが1949年に立ち上げたニュー・ジャズというレコード会社だったが、ちょうどこのころ社名が変更されたばかりだった。1950年2月27日に行われたヘイグの吹き込みは『アル・ヘイグ・トリオ』(1950年)という、無策無為のタイトルが付された4曲入りEP盤。その名のとおり、ベースにトミー・ポッター、ドラムスにロイ・ヘインズを据えたトリオ編成によるレコーディングである。このときのセッションは、のちにスタン・ゲッツ・ウィズ・アル・ヘイグ名義のLP『プリザヴェーション』(1967年)に収録されたので、広く知られているだろう。
この演奏を聴くと、曲は短めだがヘイグがすでに優れたビバッパーだったことがわかる。アップテンポでの小気味いいシングル・トーン、スロー・バラードでの素早い指遣いによるフィルインなどは、なんとも美しく爽やかだ。しかもヘイグの技巧的なピアノ・プレイはビバップ・スタイルといえども、バド・パウエルの演奏のように鬼気迫るエクスプレッションを見せることはなく、飽くまで端正で軽やかなのである。いささか語弊があるかもしれないが、そんなとっつきやすいところがヘイグの魅力のひとつと、ぼくはかねてから思っている。ちなみにゲッツとの初共演は1949年のことだが、ヘイグは1952年にロサンゼルス移り、再度彼のグループに参加している。その後ふたたびニューヨークに戻るのは、1954年のことだった。
ニューヨークに戻ったヘイグは1954年3月13日、フランスのジャズ・ピアニスト、アンリ・ルノーのプロデュースでレコーディングを行うことになる。ベースにビル・クロウ、ドラムスにリー・エイブラムスを迎えた、ピアノ・トリオによる吹き込みは全8曲。すぐにフランスのスウィング・レーベルやアメリカのピリオド・レコードによって、10インチ盤として商品化された。アルバムのタイトルは、前述のプレスティッジ盤とおなじく『アル・ヘイグ・トリオ』(1954年)という。ところで面白いことに、さきの吹き込みと同日のことになるが、ルノーが帰ったあとときを移さず、今度はエソテリック・レコードのオーナー兼エンジニアのジェリー・ニューマンが、このトリオのレコーディングを行ったのである。
はじめて聴いたヘイグのアルバムはイングランドでの吹き込み
結局、その際吹き込まれた13曲のうち8曲が収録された10インチ盤が、エソテリックから発売された。ところが、このエソテリック盤のタイトルがまたまた『アル・ヘイグ・トリオ』(1954年)という。なんとも、ややこしい。ただ幸いなことにその3年後、エソテリックは社名をカウンターポイントに変更するとともに、くだんの13曲すべてを収録した12インチ盤を発売した。このときアルバム・タイトルもジャケットも一新されたわけだが、これこそが、ヘイグのファンにとっていまやマストハヴなアルバムとなっている『ジャズ・ウィル・オー・ザ・ウィスプ』(1957年)だったのである。ぼくもまた、数あるヘイグの優れた作品のなかでも、このアルバムがベストワンであると思う。
ということで、1954年3月13日にアル・ヘイグ・トリオによって行われた、いわゆるマラソン・セッションは、こうしてピリオドの『アル・ヘイグ・トリオ』と、カウンターポイントの『ジャズ・ウィル・オー・ザ・ウィスプ』との2枚にめでたく落ち着いた。この2枚を聴く度ごとに、ヨーロッパ系アメリカ人のなかでは、ヘイグが圧倒的にビバップ期を代表するプレイヤーだったと、あらためて確信させられるのである。またここで告白してしまうけれど、同時期のバド・パウエルによるやたらと凄味ばかりが際立つお世辞にもコンディションがいいとは云えないプレイに我慢して耳を傾けるくらいなら、美意識を表現することに比重が置かれた実に調和のとれたヘイグの演奏を聴くべきと、ぼくは思っていたりする。
ここまでもっともらしく語ってきたぼくも、実はビバップ全盛期のヘイグについて知ったのは、彼の演奏にはじめて触れてからちょっとあとのことだった。そもそもぼくの場合、ヘイグのアルバムを聴きはじめたのはかなり遅いほう。ジャズには小学校高学年から親しんでいたし、前述のように『クールの誕生』も聴いていたけれど、ヘイグの名前を覚えたのは社会人になってからのことだった。当時の勤め先の上司がたまたまジャズ通だったのだが、ぼくがそれまでヘイグのアルバムを1枚も聴いたことがないと知ると、英国のスポットライト・レコードからリリースされた『インヴィテーション』(1974年)を貸してくれた。そして、イングランドのバーンズで吹き込まれた本作の冒頭を飾る「ホーリーランド」を聴いた瞬間、ぼくはやにわにヘイグのピアノ・プレイのとりこになったのである。
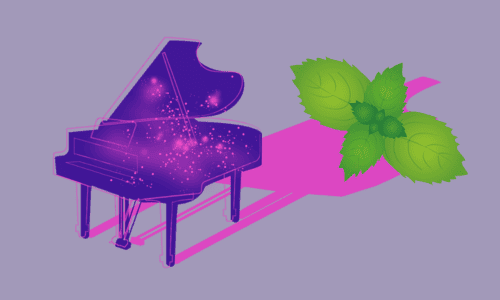
この『インヴィテーション』の詳細については後述するが、とにかくこのアルバムから、ぼくは遅ればせながらヘイグを追いかけるようになった。折よくこのアルバムが発表された1970年代の中ごろから、ヘイグはすでにわが国でも人気のピアニストだったのだろう、以降日本のレコード会社が度々彼のリーダー作を制作していた。ぼくはイースト・ウィンド盤『チェルシー・ブリッジ』(1975年)を手はじめに、インタープレイ盤『セレンディピティ』(1977年)『バド・パウエルの肖像』(1978年)プログレッシヴ盤『バースデイ・セッション』(1977年)バップランド盤『ブルー・マンハッタン』(1984年)といったトリオ作品を矢継ぎ早に入手し、とことん聴き込んだものである。
なおインタープレイ・レコードは、1977年にカリフォルニア州ロサンゼルスにおいて妙中俊哉とフレッド・ノースワーシーとが共同で立ち上げたジャズ専門のレーベル。輸入盤は簡単に入手できたし、一部の作品は国内仕様のレコードもリリースされていた。そういえばインタープレイは、ヘイグやパウエルから影響を受けたピアニスト、クロード・ウィリアムソンのアルバムも積極的に制作していたが、そのことも含めて個人的にはずいぶんお世話になったレーベルと云える。またバップランドは当時キングレコードが新しく立ち上げたジャズ・レーベル。妙中さんのプロデュースで1980年の1月に吹き込まれた『ブルー・マンハッタン』は、どういうわけかヘイグの没後にリリースされた(ヘイグは心不全で1982年11月16日に他界している)。
これらのアルバムは、どれも佳作で甲乙つけ難い。なによりもヘイグのスタイリッシュかつエレガントなスタイルのピアノ・プレイが際立っている。それは勢いに任せてスウィングするようなものではなく、メロディアスなフレーズを綴りながらその合間にあでやかな技法を軽やかに鏤めていくような様式だ。その演奏に耳をそばだてていると、彼がことのほか表現上の技巧に重きを置き、常に美を追求しているように思われてくるのだ。ことに玉を転がすようなシングル・トーン、その素早い駆け上がりと駆け下り、そして繊細かつ華美なトレモロなどは、音像に目の覚めるような色彩を与える。そんなヘイグの素晴らしい演奏技術を、当時のぼくは満喫していたのだけれど、彼が過去にビバップ時代のジャズを象徴するピアニストだったことは、まだ知らなかった。
そんなぼくも過去に遡って、すでに述べたビバップ時代のヘイグの演奏にこころを奪われることになるのだが、その契機は思いがけず早くやってきた。ときは1980年代の末葉だったが、ヘイグの出身地でもあるニュージャージー州ニューアークのマイナー・レーベル、デル・モラル・レコードからリリースされた彼のトリオ作『トゥデイ!』(1964年)が、フレッシュサウンドによって不意を衝くように復刻されたのである。このレコードは、センターラベルにミントの葉が描かれていることから、コレクターたちの間では“ミントのアル・ヘイグ”という呼び名で通っており、入手困難な幻の名盤と謳われていた。ディスクユニオンがディストリビューターとなりDIWレコードから国内盤も発売されたが、ぼくはジャケットの紙材が良質なこちらを購入した。
ぼくはいわゆるレコード・コレクターではないし、当時は(まあいまもそうだけれど)浅学非才のジャズ・ファンだったので、この『トゥデイ!』がブートレグまで出まわるほどの希少度の高い超人気盤であるとはつゆほども知らなかったし、過去にそういうレアなレコードをめぐる騒動の渦中に巻き込まれることもなかった。ときにくだんのDIW盤のライナーノーツを、ジャズ喫茶MEGのマスターであり、辛口の批評家として知られる寺島靖国が手がけている。氏をして「“ミントのアル・ヘイグ”を手に入れるのは吉永小百合のハートを射止めるよりむずかしく思われた」と云わしめるほどの『トゥデイ!』ではあるけれど、申し訳ないがぼくの場合、このアルバムに対してそれほどの愛着が湧くことはなかった。
ぼくにとって『トゥデイ!』は、血眼になって探し求めるような屈指の名盤ではなく、どちらかというと気軽に手にとるような飽きのこない実に楽しい作品。批判を浴びそうだけれど、喩えて云えば様々な具材が入った五目炒飯のようなものなのである。というのも、ミルト・ジャクソンの「バグス・グルーヴ」デューク・エリントンの「サテン・ドール」はたまたヘイグのオリジナル「スリオ」といった、思わずため息が出るような正統派バップ・スタイルの力強い演奏が展開されるいっぽうで、フランス出身のギタリストでシンガーソングライター、サッシャ・ディステルの「ザ・グッド・ライフ」ベルギー出身のハーモニシスト、トゥーツ・シールマンスの「ブルーゼット」など、ボサノヴァのリズムが活かされたポップなナンバーもプレイされているからだ。
復活後はニュー・メインストリームの熟練ピアニストとして活躍
このアルバムのラストを飾る「サウダージ」という曲などは、タイトルからもわかるように、ソフィスティケーテッドなテイストを帯びながらも、ストレートにサンバやショーロといったブラジルのトラディショナルな音楽を感じさせる。てっきりブラジルのミュージシャンの曲かと思いきや、このトリオでベーシストを務めているエディ・デ・ハースのオリジナルだった。彼はジャワ島西部の都市、バンドンの出身だけれど、少年時代にはウクレレを弾いていたとのことだから、ハワイアンにはもちろんのことブラジル音楽にも親しんでいたのかもしれない。それくらい晴れやかさと爽やかさが横溢する、チャーミングな曲だ。ヘイグは軽快なコンピングをキープしながら、鮮明なオクターヴ奏法でメロディを、歯切れのいいシングル・トーンでソロを繰り出している。
ところで、寺島さんはDIW盤のライナーノーツにおいて、氏のヘイグ愛が溢れんばかりに才筆を振るっているのだが、この「サウダージ」やまえに挙げた「ザ・グッド・ライフ」「ブルーゼット」などについて「平凡な流行歌」「硬質のヘイグに不釣合いなボサ風リズム」「これらの演奏が好きになれない──」というようなコメントを付けている。このときぼくは、そんな寺島さんの歯に衣着せぬ物言いから、すっかり氏のファンになってしまったのだけれど、上記の3曲に対して嫌気がさすようなことはまったくない。世代の違いもあるから見解が相違するところもあると思うが、それでも寺島さんの『ジャズ・ウィル・オー・ザ・ウィスプ』をしっかり聴いてほしいという熱いメッセージは、ぼくもしかと受け止めたのである。
ぼくは、なにを差し置いてもこれだけは聴くべきだろうと、すぐにカウンターポイント盤『ジャズ・ウィル・オー・ザ・ウィスプ』を購入した。そこには『トゥデイ!』のなかの「バグス・グルーヴ」「サテン・ドール」「スリオ」といったバップ・スタイルの力強いプレイ、そしてジーン・デ・ポールが作曲したラヴ・バラード「あなたは恋を知らない」における、ひたすら美に価値を置くようなあでやかな陰影を湛えた演奏へと繋がるものがあった。そういったヘイグのユニークかつアトラクティヴ なピアニズムが遺憾なく発揮されていること、選曲の妙が際立っていることを慮ると、やはり『ジャズ・ウィル・オー・ザ・ウィスプ』を彼の最高傑作と云わざるを得ない。しかも私感では、噛めば噛むほど味が出る、まるでスルメイカのような作品と思われる。
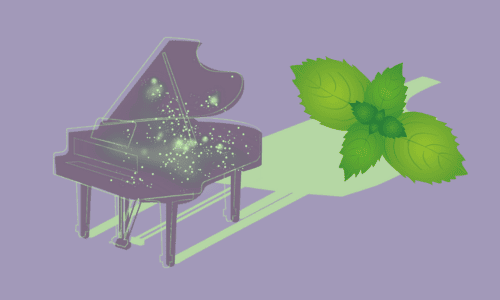
それを機にいつの間にかビバップ期のヘイグに心酔するようになったぼくにとって、もちろんベストワンは『ジャズ・ウィル・オー・ザ・ウィスプ』だが、同日録音の躍動感溢れるトリオ・プレイが冴えるピリオド盤『アル・ヘイグ・トリオ』や、おなじくピリオド・レコードからリリースされたギタリストを加えたクァルテットが軽妙洒脱なセッションを展開する『アル・ヘイグ・クァルテット』(1954年)もまた首位に迫る勢いだ。とはいってもぼくは、さきに挙げたイースト・ウィンド、インタープレイ、プログレッシヴなどのアルバムも含めて、1970年代中盤以降のヘイグ作品も相変わらず愛聴しつづけてきた。ヘイグがフェンダー・ローズも弾いている、ギタリストのジミー・レイニーとのコラボ作『スペシャル・ブリュー』(1976年)でさえ好きだ。
スポットライト・レコードからリリースされた『スペシャル・ブリュー』でのヘイグは、ビバップのスタイルを残しながらもジャズ・ロックないしエレクトリック・ジャズにもアプローチしている。それ故往年のファンには見向きもされないだろうけれど、ぼくはわりと好き。また、妙中さんがプロデュースを手がけ、インタープレイ・レコードの前身であるシーブリーズ・レコードからリリースされたソロ・ピアノ『ピアノ・インタープリテーション』(1976年)などは、ヘイグの耽美的とも云える陰影に富んだピアニズムが全開した素晴らしい作品だ。実は1968年以降、ヘイグはプライヴェートのゴタゴタ(3番目の奥さまに関するある事件)でいっとき引退状態にあったのだが、彼の斬新な試みは、不遇の時期を強いられたことに対する反動のようにも思われる。
結局のところ、バップ・ピアニストのヘイグも時代の趨勢とともに、音楽のスタイルを変えざるを得なかったわけだが、これはしごく当然のこと。しかしながらヘイグの場合、たとえジャズにおけるいくつかのサブジャンルを彷徨ったといえども、そのピアニズム自体を変えることはなかったと、ぼくは思うのだ。そして前述の『トゥデイ!』は、その移り変わりにおける過渡期の作品だった。その後ヘイグは、しばらくジャズ・シーンの第一線から退くが、不死鳥のごとき復活を遂げ、ニュー・メインストリームの熟練ピアニストとして上質のアルバムを何枚も吹き込んでいく。そのまさに嚆矢となったのが、ぼくが最初に聴いたヘイグのレコード『インヴィテーション』だった。疑う余地もなく、彼の後期の代表作である。
このアルバムは、サイドにフランス生まれのベーシスト、ジルベール・ロヴェルと、ビバップ時代から活躍する名ドラマー、ケニー・クラークが迎えられたこともあり、その安定感のあるサウンドのなかに洗練されたムードが醸し出され、モダンな味わいをもった作品に仕上がっている。冒頭の「ホーリーランド」は、ピアニストのシダー・ウォルトンの曲。彼のナチュラルで華麗な演奏もいいけれど、ぼくは高貴なまでに優雅なヘイグのプレイのほうが断然好きだ。ルバートで12小節、インテンポで12小節、それが交互に演奏されるという珍しい形式のマイナー・ブルース。とにかくヘイグの全身全霊を傾けたピアニズムが美しく、一度聴いたらなかなか脳裏から離れない名演だ。
ブロニスラウ・ケイパーの「インヴィテーション」では、シンコペーテッドな軽快なリズムに乗って、ヘイグが敏捷な指遣いで次々に艶かしいフレーズを繰り出していく。ほどよく張り詰めた空気感も素晴らしい。J. J. ジョンソンの「エニグマ」では、ほかの吹き込みを選ぶ余地がまったくなくなるような、ビューティフルなバラード演奏が展開される。これを聴いて、ぼくは完全にヘイグに夢中になった。ヘイグのオリジナル「ソウボ・シティ・ブルース」は、オーソドックスなマイナー・ブルースだが、歯切れのいいピアノとしなやかなベースとの絡みが、現代的な印象を与える。B面最初のタッド・ダメロン作「イフ・ユー・クッド・シー・ミー・ナウ」では、ゆったりしたテンポのなかでピアノによる絢爛な楽句が溢れかえる。そこはかとなくブルージーなのもいい。
ヘイグのオリジナル「サンバルハザ」は、愁いを帯びたバウンシーなジャズボサ。ヘイグのピアノがときに小気味よくときに力強く跳ねる。ベース・ソロもいい。ビリー・ストレイホーン「デイドリーム」では、ヘイグのリリカルでインプレッショニスティックなピアニズムが顕著に現れる。その高貴なバラード・プレイに、身を任せるばかりである。ラストを飾るヘイグのオリジナル「リニア・モーション」は、新時代の彼を象徴するような1曲。モーダル・ジャズのなかにクラシックのイディオムが見え隠れするのがユニーク。ヘイグは従来以上にアクティヴなプレイを展開。ベース・ソロ、ドラムスとの4バースも出来する、ダイナミックかつエレガントな、解釈次第ではヘイグらしいナンバー。ただこういうモダンなセンスは、ビバップ期の演奏では目立たなかった。そういう意味でも、本作は貴重な1枚と云える。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。








コメント