ピーター・ワシントン(b)、ケニー・ワシントン(ds)との最初の吹き込みであり、絶妙な選曲と漲溢する歌ごころが全開するビル・チャーラップ(p)の『オール・スルー・ザ・ナイト』
 Album : Bill Charlap Trio / All Through The Night (1998)
Album : Bill Charlap Trio / All Through The Night (1998)
Today’s Tune : Pure Imagination
ジャズに新しいも古いもない──「もう古いよ」とはどういうこと?
ジャズに新しいも古いもない。もちろん時間的な古さあるいは新しさは、ジャズ延いてはあらゆる音楽にもあると思う。たとえば、一般的にイノヴェーションというコトバで云い表される、テクノロジーやインヴェンションにおいては吐故納新がはかられることもあるのだろうけれど、このコトバがさらに意味するところのユニークなアイディアやポジティヴなインフルエンスは、実はあまり時間的な影響を受けることはないように思われるのである。問題はいいかわるいか、あるいは好きか嫌いかということに尽きるのではないだろうか。ヨハン・ゼバスティアン・バッハの楽曲は、バロック音楽と呼ばれる300年もまえに書かれたものだけれど、いまになってもなおフレッシュに響く。
ジャズもまた然りである。そのルーツがアメリカのルイジアナ州ニューオーリンズで生まれた音楽であることは、一般的にもよく知られている。ジャズのご先祖さまであるブルースやラグタイムは、およそ130年まえの音楽。百花繚乱のミュージシャンによって熱演が繰り広げられたハード・バップにいたっては、登場からせいぜい70年くらいしか経っていない。しかしながら、バロック音楽の息の長さには到底及ばないものの、ジャズもまた歴史と文化が香る音楽になりつつある。というか、すでになっているのかな──。いずれにしても、ぼくはハード・バップというスタイルに、古さを感じるようなことはない。一般的にもマイルス・デイヴィスやジョン・コルトレーンの音楽は、いまだに愛されつづけている。
そういえば昔、こんなことがあった。ぼくは高校生のころからジャズ・ピアノを独学していたのだけれど、大学に進学して間もなく、ジャズ・クラブにもよく足を運ぶようになった。そんなある日、ぼくがピアノを弾くことを知った某クラブのオーナーが、深い意味はないのだろうけれど「好きなピアニストは?」と訊いてきた。ところがぼくは、つい虚勢を張ってこころにもなく、マッコイ・タイナーと答えてしまったのだ。まったく赤面の至りで、いまでもそのことを思い出すと、体内をめぐる血液がぜんぶ上昇してくるような気分になる。しかも、ぼくの答えを聞いたオーナーは、ニヤニヤしながら「もう古いよ」と仰った。ホント、穴があったら入りたいとは、このことである。

いまだったら素直にビル・エヴァンスと答えたのだろうけれど、あのころのぼくは、公然とエヴァンスがいちばん好きと云ったら、エヴァンスしか知らないひとと思われかねないと、勝手に思い込んでいたのだ。いやいや当時は、確かにそういう気運があったように思う。ジャズはもともとブラックルーツの音楽だから、アフリカ系アメリカ人以外のプレイヤーが演奏するジャズは、本来のジャズとは異質のものと観る向きもけっこうあった。エヴァンスのピアニズムには、ヨーロッパの印象主義音楽からの影響が顕著に窺えるから、彼がクリエイトする音楽は、インプロヴィゼーションやスウィング・フィールを抱えながらも、エクセプショナルなジャズと捉えられたのだろう。いまでは、そんな偏見もなくなったと思うけれど──。
さらに云えば、現代においてエヴァンスの音楽が初心者に優しく具眼の士からも愛聴されるのは、単純にビート感やグルーヴ感が強調されたものではなく、リズムやハーモニーさらにはインプロヴィゼーションに至るまで独特の意匠が凝らされたものだから。さらにそのエレガントでリリカルなピアノのタッチが、リスナーを得も云われぬ美の世界に誘い、ただただ音の連なりに陶酔させるのだろう。そんなエヴァンスをぼくは、いまも昔もピアニストとして至高の存在と思っている。にもかかわらず、若き日のぼくは、ただの浅はかな見栄坊だった。ジャズの先達をまえにして、ダイナミックでバウンシーなプレイが際立つタイナーのピアニズムにも通じていると、とっさにひけらかしてしまったのである。
確かにタイナーは、当時のぼくにとって憧れのピアニストだった。ジャズ・ピアノを独学していたころのぼくにとって、あたかもリスナーを眩惑するようなアドリブ・プレイは、演奏法の模範として有意義なものだったと云える。彼のインプロヴィゼーションに観られるブルースのなかのモーダルな解釈、ダイナミックなスケールアウト、そして美麗なコードのヴォイシングなどは、青二才のぼくには人智を超越したもののようにさえ感じられたし、単純にクールに響いたもの。タイナーとの出会いは、それまでレコードを聴いてピアニストが繰り出すフレーズをコピーするばかりだったぼくに、表面的に模倣するばかりでなくしっかり音楽理論も掘り下げなければと一念発起させるほど、衝撃的なものだったのである。
と、調子のいいことを云っているけれど、実はそれからしばらくしてタイナーの演奏に対するぼくの関心は、だんだん薄れていった。たぶんぼくは、彼のピアノのテクニックばかりに耳をそばだてていて、それを必死で追い求めることのみに意識を傾けていたのだろう。純粋にジャズを楽しむことを、すっかり忘れていたのだ。それ故ぼくはタイナーのレコードに、次第に魅力を感じなくなっていった。ブルーノート・レコードのBNLAシリーズあたりから違和感を覚えはじめ、マイルストーン・レコードからリリースされた数々のアルバムともなると、ピアノ・プレイに対しては相変わらずスゴいと感じながらも、音楽作品としては一向に満足がいかなかった。結局、ぼくの好きなタイナーのリーダー作は、インパルス! レコードの6枚のみに止まったのである。
ところで「好きなピアニストは?」と訊かれたぼくは、なんと答えればよかったのだろう。フランス出身のミシェル・ペトルチアーニか、ドミニカ共和国出身のミシェル・カミロか、はたまたキューバ出身のゴンサロ・ルバルカバか。当時(1980年代後半)注目を集めていたピアニストというと、彼らの名前が自然とアタマをよぎる。みな高い独自性と巧緻性とを兼ね備えた、優れたテクニックをもつジャズ・ピアニストだ。でも残念ながら、彼らの演っている音楽に、ぼくの感性はそれほど刺激されることはなかった。件のジャズ・クラブのオーナーを心服させるには、どんなピアニストの名前を挙げればよかったのか、いまとなっては知る由もないけれど、ずっとあとになってあることに気づいたのである。
オーソドックスはオーソドックスでも高踏的なオーソドクシー
それは、クラブのオーナーがタイナーのことを「もう古いよ」と言い表したのは、なにもその演奏スタイルを時代遅れのものと観ていたからではない──ということだ。なぜならタイナーがベーシストのジミー・ギャリソン、ドラマーのエルヴィン・ジョーンズとともにジョン・コルトレーンを支えていたのは、1960年代前半のことだけれど、よく知られている『マイ・フェイヴァリット・シングス』(1961年)『バラード』(1963年)『至上の愛』(1965年)といったアルバムにおける彼のピアノ・プレイは、いま聴いても古色蒼然としたところなど微塵もないからだ。前述したインパルス! レコードからリリースされたタイナー自身の6枚のリーダー作においても、また然りである。いや、むしろ瑞々しく感じられるくらいだ。
これはぼくの想像だけれど、おそらくクラブのオーナーもそんなことは百も承知二百も合点だったのだろう。もしかするとその当時、1960年代にスタイルを確立したタイナーが時代の趨勢とともに迷走するのを、憂えていたのかもしれない。その往年の輝きを愛でればこそ、逆にタイナーの現況に、旬を過ぎたピアニストと云わんばかりに見切りをつけたのではなかろうか。それで「もう古いよ」という云いかたになったのであれば、なんの不思議もない。まさにぼくも、そう思っていたのだから──。ハナシが長くなってしまったけれど、冒頭で述べたようにユニークなアイディアやポジティヴなインフルエンスは、時間的な影響を受けることはない。繰り返すけれど、ジャズに新しいも古いもない。いいかわるいかなのである。
ときにぼくがジャズ・ピアノを独学していたときにお気に入りだったピアニストといえば、ソニー・クラーク、ウィントン・ケリー、トミー・フラナガンということになる。レッド・ガーランドにハマったのは、成人してからのこと。前述のようにマッコイ・タイナーも大好きだったけれど、手本とするにはちょっとハードルが高かった。そういう意味合いでは、レイ・ブライアントやリチャード・ティーもまた然り。もっとも強く影響を受けたのは、云うまでもなくビル・エヴァンスなのだけれど、彼はぼくにとって神さまのような存在なのだ。そういうわけで、当時のぼくはハード・バップの代表的なピアニストのレコードから、多くを学んだ。特にアドリブのしかた、コンピングのしかた、スウィングのしかたなど、ジャズ・ピアノの基本的なところを──。
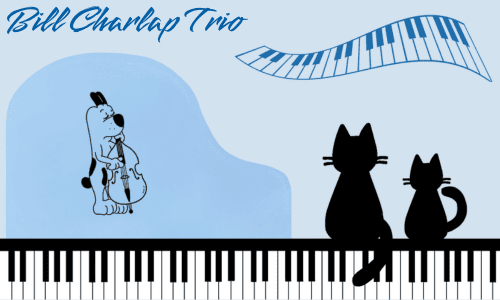
ぼくはいまでも、時間的な古さあるいは新しさとは関係なく、ハード・バップをジャズのスタイルのひとつと捉えたうえで、その豊富に存在する音盤を楽しみつづけている。テーマがメロディアスに歌われ、アドリブがホットなドライヴ感を与えながら展開され、さらにそのバックグラウンドでは心地いいビートが打ち出されているというハード・バップは、ぼくにとってはもっとも気軽に興じることができる音楽であり、同時にことのほか深く味わうことができるジャズでもある。もちろんぼくの場合、よくターンテーブルにのせるレコードといえば、1950年代から1960年代までのハード・バップ全盛期のアルバムになるのだけれど、それよりずっとあとの世代のピアニストの作品のなかにも、それほど多くはないけれど愛聴しているものがある。
なかでもビル・チャーラップのアルバムには、強い愛着がある。優れた演奏技術や表現力をもったジャズ・ピアニストが矢継ぎ早に登場してくるなかで、長きにわたりピアノ・トリオの最前線で活躍しつづける現役のプレイヤーといえば、ぼくは真っ先にチャーラップ(実際は“シャーラップ”と発音する)のことを思い浮かべる。彼がレギュラー・トリオによるニュー・アルバム『アンド・ゼン・アゲイン』(2024年)をブルーノート・レコードからリリースしたことは、まだ記憶に新しい。その手に汗握るスウィンギーなアドリブ・プレイと、ため息の出るようなバラードのインタープリテーションには、衰える様子はまるでない。というか、むしろ一段と磨きがかかったという印象を受けた。
このビル・チャーラップ・トリオの新作は、ニューヨーク市マンハッタン区グリニッジ・ヴィレッジに所在するジャズ・クラブ、ヴィレッジ・ヴァンガードにおいて、実況録音されたもの。云うまでもなくこの名門クラブは、過去にソニー・ロリンズをはじめ、ビル・エヴァンス、ジョン・コルトレーンなどの名盤が生み出されたことで知られる。そしていまもなお、優れたプレイヤーたちの名演を発信しつづけている、モダン・ジャズの拠点。2023年9月9日のビル・チャーラップ・トリオによるライヴの模様が収められたこのアルバムもまた、数々の先人の名高きライヴ盤に連なる、46分あまりと短い時間ではあるけれど至福のひとときを過ごすことができる、素晴らしい1枚である。
このアルバムは、ビル・チャーラップ・トリオの進化の軌跡を捉えたものとも云えるが、なにがしかの新機軸が打ち出されているというわけでもない。ではどういうことかというと、トリオ各々の演奏技術と表現力が、さらに三位一体のサウンドとグルーヴが、飛躍的に進歩しているというか、よりいっそう成熟度を高めているのである。そもそもチャーラップは、イノヴェーションというコトバとはあまり縁のないピアニストだ。彼には、それこそハード・バップのマナーを丁寧になぞりながら、そのスタイルを一途にブラッシュアップしていくような風格がある。しかもチャーラップの場合、わりと早い時期からそういう貫禄を漂わせていた。そういう意味では、逆に稀有なピアニストと云えるかもしれない。
チャーラップのピアノ・プレイには、まったくケレン味がない。モダン・ジャズの王道を行くような演奏だ。ひとことで云えば、オーソドックスということになる。しかしながらそれは、ジャズの本質を見抜く鋭い聴力をもつリスナーをして「もう古いよ」と云わしめるような類いのものではないと、ぼくは信じるのである。だからまことに僭越ながら、ちょっと生意気なことを云わせていただく。もしあなたがチャーラップのプレイを聴いて、なんだハード・バップのスタイルに則った月並みな演奏ではないかと思われたら、できればもう少しだけ彼の紡ぎ出す楽句に神経を集中していただけると嬉しい。必ずや、それがオーソドックスはオーソドックスでも、高踏的なオーソドクシーであると気づかれるであろう。
知られざる曲を精彩を放つものにする繊細な音の織成
さきに挙げたミシェル・ペトルチアーニ、ミシェル・カミロ、ゴンサロ・ルバルカバといった、1980年代の後半にジャズ・シーンを席巻していた新奇性に富んだ凄腕のピアニストたちに夢中になれなかったぼくが待望していたのは、まさにチャーラップのようなピアニストだったのだ。ぼくは1990年代の前半から、ほぼリアルタイムで彼のことを追いかけてきた。チャーラップとの出会いは、幸いなことに彼の初リーダー・アルバム『アロング・ウィズ・ミー』(1993年)においてだった。ぼくがこのCDをショップの店頭で手にとったのは、些細な理由から。アルバムの冒頭にポーランド出身の作曲家、ブロニスラウ・ケイパーの「オン・グリーン・ドルフィン・ストリート」が収録されていたからである。
この曲はぼくにとって、ファイヴァリット・チューンであるとともに、ジャズ・ピアニストのセンスやテクニックを評価するときの指標となっている。この名曲において、チャーラップはついとメロディから弾きはじめる。テーマをそつなくメロディアスにうたわせたあと、まるで鼻歌を口ずさむようにアドリブを展開。しかもそこで繰り出されるフレーズは、実に粒立ちのいい音でまとまっている。この時点で、チャーラップが確たるピアノのテクニックを有していることは明白だ。しかし彼は、超絶技巧を振りかざしたりはしない。 チャーラップは、ひたすら曲を歌わせることに集中するばかり。そんないぶし銀の演奏技術を披露する彼は、当時まだ24歳だった。その点では、さすがに100年とまではいかないけれど、数十年にひとりの逸材と云いたい。
繰り返しになるけれど、チャーラップがプレイするジャズは、ごくごくオーソドックスなモダン・ジャズ。彼のピアニズムに、驚天動地の斬新な趣向などはまったくないけれど、そういったことがつまらなく思えるくらい、その至高の歌ごころは驚異的だ。ぼくのこころを鷲掴みにしたものは、まさにそれである。チャーラップの演奏は常に歌っている。くわえて彼は採り上げる楽曲を、とても大切に扱う。このキアロスキューロ・レコードというあまり目立たないレーベルからリリースされたチャーラップの初リーダー・アルバムは、選曲のほうもどちらかというと地味目。ところが、たとえ世間一般であまり知られていない曲でも、彼の手にかかると、名曲の誉れ高きジャズ・スタンダーズと比較しても遜色のない輝きを放つのである。

たとえばアルバム・タイトルにもなっている「アロング・ウィズ・ミー」にしたって、ハロルド・ロームが音楽を手がけた1946年初演のブロードウェイ作品『コール・ミー・ミスター』のなかの1曲だけれど、だれが知っていようか。この曲をチャーラップ以外のプレイヤーが演奏しているのをいまだに耳にしたことがないけれど、ぼくは本作ではじめてこの曲を聴いたとき「へえ、こんないい曲があるのか」と、目からウロコが落ちる思いだった。実はこれはほんの一例に過ぎなくて、チャーラップのアルバムでは毎度のごとく、彼の選曲に対する卓越した才能が発揮されているのだ。音楽の本質を見極める能力と、それを実際に全身全霊で音にする表現力──この2点がビル・チャーラップというピアニストの最大の魅力と、ぼくは思うのである。
そんなチャーラップにぼくがすっかりゾッコンになったのは、オランダのレーベルであるクリス・クロス・ジャズから『スーヴェニア』(1995年)『ディスタント・スター』(1997年)につづいてリリースされた『オール・スルー・ザ・ナイト』(1998年)において。チャーラップにとっては、コラボ作やコンセプト・アルバムなどを除くと、通算4枚目のリーダー作にあたる。クリス・クロスにおけるまえの2枚も優れた作品ではあるけれど、そこに収められたいくつかのトラックでは、チャーラップが珍しくいささか先鋭的な演奏に傾いている。能ある鷹は爪を隠すでもないが、彼もまた普段は表面に出さないだけで、実は進取の気性に富んだ一面をあわせもつのである。とはいえチャーラップについては、知られざる曲を精彩を放つものにする、その繊細な音の織成を高く評価したい。
その点で『オール・スルー・ザ・ナイト』は、傑出した作品である。選曲において、リスナーにおもねるようなところがまったくないのが、いまも新鮮に映る。そして本作は、現在まで長きにわたりビル・チャーラップ・トリオのサイドメンを務めることになる、ピーター・ワシントン(b)、ケニー・ワシントン(ds)との最初の吹き込みでもあり、非常に重要な一枚と云える。オープナーは、コール・ポーターが1934年のミュージカル『エニシング・ゴーズ』のために書いた「オール・スルー・ザ・ナイト」だが、ドラマティックなルバート、そして流れるようなアドリブと、ピアノの華麗な動きが際立つ。ベースとブラシも、バッキング、ソロ、8バースとヴィヴィッドな美技を披露する。
オグデン・ナッシュ作詞、ヴァーノン・デューク作曲による「ラウンドアバウト」は、リリカルなバラード。トリオの繊細な表現が、楽曲に深い味わいをもたせている。リー・アダムス作詞、チャールズ・ストラウス作曲による「プット・オン・ア・ハッピー・フェイス」は、アルバム中もっとも軽やかで洗練されたハード・バップ。1960年のミュージカル『バイ・バイ・バーディー』からの1曲だが、ここでは明るいトーンでドライヴするピアノが第一等。半音下がる(E♭→D)転調も気が利いている。アレック・ワイルダー作詞作曲による「イッツ・ソー・ピースフル・イン・ザ・カントリー」は、ミッドテンポの寛いだナンバー。ベースのメロディアスなソロもいい感じだ。
アーヴィング・バーリン作詞作曲による「ザ・ベスト・シング・フォー・ユー・ウッド・ビー・ミー」では、突き抜けるような青空のように爽やかなスウィング感が最高。ディライトフルなピアノ、グルーヴィーなランニング・ベース、ライトハーテッドなブラシの8バースと、うま味のあるプレイがつづく。アンソニー・ニューリー作詞、レスリー・ブリッカス作曲による「ピュア・イマジネーション」は、個人的には大好きな曲。1971年のミュージカル映画『夢のチョコレート工場』の主題歌だが、ここでは唯一ソロ・ピアノでしっとり歌い上げられている。ロレンツ・ハート作詞、リチャード・ロジャース作曲による「ノーバディズ・ハート」は、歩くようなテンポと軽いブルース・フィールがお洒落。ドラムスのソロも小粋だ。
ベティ・コムデン、アドルフ・グリーン作詞、ジュール・スタイン作曲による「ダンス・オンリー・ウィズ・ミー」と、コール・ポーター作詞作曲による「ドリーム・ダンシング」とのメドレーは、リリシズムに富んだソロ・ピアノにはじまり、インテンポ後はトリオによる静かで激しいインタープレイが展開される。ラストを飾るのは、ふたたびリー・アダムスとチャールズ・ストラウスとのコンビよる「アイヴ・ジャスト・シーン・ハー」である。1962年のミュージカル『オール・アメリカン』からの1曲。トリオは落ち着いたムードで、まさにモダン・ジャズの王道を行くようなプレイを展開。ブロック・コードを織り交ぜたよくスウィングするピアノといい、しなやかなベース・ソロといい、お約束のキレのあるドラム・ソロといい、とにかくイノヴェーションというコトバからはほど遠いスタイルだけれど、決して古く響くことはない。ぼくにはそれが、とてもかけがえのないものに思えるのである。
(引きつづきビル・チャーラップ・トリオの『アンド・ゼン・アゲイン』について、下の記事をお読みいただければ幸いです)

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。









コメント