スムース・ジャズ・シーンを牽引するキーボーディスト、ブライアン・シンプソンのスタビリティとインテリジェンスに富んだデビュー作『クローサー・スティル』
 Album : Brian Simpson / Closer Still (1995)
Album : Brian Simpson / Closer Still (1995)
Today’s Tune : Because Of Love
フュージョン・ブームの終焉とスムース・ジャズの登場
スムース・ジャズというコトバが使われはじめたのは、1980年代の後半のこと。とはいってもこの呼称、最初はアメリカのラジオ・ステーションがなんとなくそう云っていただけで、音楽ジャンルとして一般的に定着したのは1990年代に入ってからだろう。スムース・ジャズは、クロスオーヴァー、フュージョンの流れを汲む音楽であることは間違いないが、いまも日本では評価されたり人気となることはあまりない。確かに1970年代後半から1980年代後半にかけて、日本でもフュージョン・ブームはあった。海外のミュージシャンも然ることながら、邦人アーティストでもアルト奏者の渡辺貞夫をはじめ、ギタリストの高中正義、渡辺香津美、キーボーディストの深町純などは、早い時期から人気を博していた。
やがて1980年代に入ると、イギリスのシャカタクやレヴェル42、アイスランドのメゾフォルテ、オランダのフルーツケーキといったUSA以外のフュージョン系グループも、日本のリスナーに大いに歓迎された。日本のアーティストも、少なからずその影響を受けた。フュージョンはもともとジャズから派生した音楽で、使用楽器やビート感覚の違いはあるものの、当初はインプロヴィゼーションに主眼が置かれていた。ところが日本産のフュージョンも上記のグループに触発されたのだろう、たちまちジャズ色がすっかり薄くなったポップ・インストゥルメンタルといった趣きを呈する作品が多くなった。国内の人気グループ、カシオペアやザ・スクェア(のちのT-SQUARE)などのアルバムには、その傾向が顕著に窺えた。
ぼくはこれでも、どんな音楽でも色眼鏡で見るようなことはないと自負している。そうはいってもぼくにだって、当然のことながら趣味趣向はある。正直に告白するけれど、猫も杓子もフュージョンを聴いていたような当時のヒット作品は、ぼくの耳には却って無味乾燥なものに響いた。確かにぼくには音楽の嗜好においてマイノリティな部分があるけれど、俗受けするような音楽を量産する傾向にあった当時の制作サイドにも問題があったと思う。内容や出来映えに納得のいく当時のフュージョン作品といえば、大御所のチック・コリアやハービー・ハンコック、個人的に推しのボブ・ジェームスやデイヴ・グルーシンのように、もともとカテゴリーにとらわれないアーティストのものくらいだった。

いまから考えると、あのころの日本でのフュージョン・ブームは、あたかもバブル景気と並行していたようにも思われて、ちょっと興味深くもある。しかし当時のフュージョンに閉塞感を感じていたぼくは、GRPレコードの諸作のように良心的であり高品質でもあるフュージョン作品は継続的に聴いていたけれど、実はモダン・ジャズに回帰しはじめていた。ぼくがいにしえのジャズ作品をアナログ・レコードで買い漁っていたのは、ちょうどこのころ。だから幸いなことに、まるで好景気を象徴するような能天気な音楽に流されることはなかった。そういえばGRPレコードに所属するフュージョン系のアーティストによって、GRPオールスター・ビッグ・バンドが結成されたのは1992年のこと。もしかするとGRPはフュージョン・シーンの閉塞感を打破するものとして、ハード・バップに活路を見出したのかもしれない。
とはいっても、GRPのジャズ路線は往年のハード・バップとはかなりテイストが異なる。ぼくの感覚では、4ビートのコンテンポラリー・ジャズといったイメージで捉えている。それはともかく、当時のぼくは1950年代から1960年代までのモダン・ジャズを味わうだけで、決して満足していたわけではない。そもそも10代の前半からぼくは、クロスオーヴァーやフュージョンに親しんでいた。もちろんプレイヤーの巧妙な即興演奏にも惹かれたけれど、それ以上にぼくがフュージョンという音楽に魅力を感じたのは、モダン・ジャズとはごくわずかでありながら相当に違う感じを与えるハーモニーと、思いのままに変化するリズムを有するところ。ひとことで云えば、ぼくはフュージョンのトーンとグルーヴが好きなのだ。
バブル崩壊とともに日本のフュージョン・ブームもまるで泡沫のように消えていったが、大衆にすり寄るばかりで先行きの見えない状態にあった音楽の求心力が一気に低下したことに、実のところぼくはちょっとホッとしていた。それでいて、これまで自分が欣慕してきたようなフュージョン・スタイルの音楽を、強く欲してもいたのだけれど──。そんなときに登場してきたのが、スムース・ジャズだった。最初にも云ったけれどスムース・ジャズは、アメリカのラジオ・ステーションが好んでプレイしていた音楽の影響から生まれた。セレクトされていたのは、数あるフュージョン作品のなかでも特に聴き心地のいいもの。多くのフュージョン系のアーティストたちは、局でオンエアされる楽曲の人気にあやかるように自己の演奏や作曲のフォーマットを調整しはじめた。
アメリカにはスムーズ・ジャズ専門のステーションがいくつもあるけれど、日本にはそれがない。ただ1980年代の後半に開局したJ-WAVEあたりは、J-POPやビッグ・ネームの洋楽などに交えて、コマーシャリズムとは縁遠い音楽を流していた。そこでは身近ではあまり聴かないワールド・ミュージックや知られざるアダルト・オリエンテッド・ロックなども含めて、とにかく心地いい良心的な音楽であれば、アーティストの有名無名を問わず採り上げられていた。たとえばブラジリアン・ジャズ・スタイルの女性シンガー、ケヴィン・レトーのデビュー作『ユア・スマイル』(1991年)などは、国内発売される以前にいち早くプレイされていた。なお彼女の音楽は当時、ニュー・アダルト・コンテンポラリーと云い表された。
スムース・ジャズの申し子のようなキーボーディスト
このニュー・アダルト・コンテンポラリーが、次第にスムース・ジャズという名称に変わり定着した。スムース・ジャズはもともとラジオ・フォーマットの音楽だから、楽曲は自ずと尺が短くなる。アドリブ・パートも1970年代のフュージョンに比べると、かなりコンパクトになっている。それでも実力のあるフュージョン系のプレイヤーが演奏しているから各楽器のソロはジャジーだし、レパートリーのハーモニーにもほどよい緊張感がある。グルーヴ感については、ジャズ、ロック、ラテン、リズム・アンド・ブルース、さらにはヒップホップまで、フュージョン時代と同様に許容範囲が広い。しかも聴き心地のよさが主眼とされる音楽だから、メロディはシンプルでトータル・サウンドはそフィスティケーテッドだ。
ただ日本では、なかなか広まらない。国土の広いアメリカではラジオ・ステーションは膨大な数に上るし、そこに住むひとたちにとってラジオはテレビやスマートフォン以上に親しまれているメディア。日本人とは違いアメリカ人の大多数には、カーステレオで音楽を聴く習慣がある。そんななかスムース・ジャズは1980年代の後半から、カントリー・ミュージック、コンテンポラリー・ヒット・ラジオ、アダルト・コンテンポラリーなどに次ぐ、人気ラジオ・フォーマットとなっている。スムース・ジャズが台頭してきたころの日本では、フュージョン・ブームはすでに終わっており、ラジオに関してももともとステーションが少なく、若者たちからの支持もとうに失われていた。スムース・ジャズが流行らないのも無理はない。
それでもぼくのようにフュージョン・ミュージックの本質的な部分に魅力を感じているものは、たとえムードづくりのためのBGMと揶揄されようとも、スムース・ジャズにも関心をもたざるを得ない。だがスムース・ジャズのCDといえば、クロスオーヴァー/フュージョン時代に活躍したビッグネームの作品以外は、ほとんど国内盤がリリースされることはなかった。1990年代の初頭といえば日本の一般家庭ではインターネットが普及していなかったから、結局スムース・ジャズを聴くには輸入盤を扱うCDショップをいくつもハシゴするしかなかった。あのころからぼくは、日本の音楽シーンから徐々に離れていくようになったし、なんだか自分がだんだん浮世離れしたひとになっていくような気がしたもの。
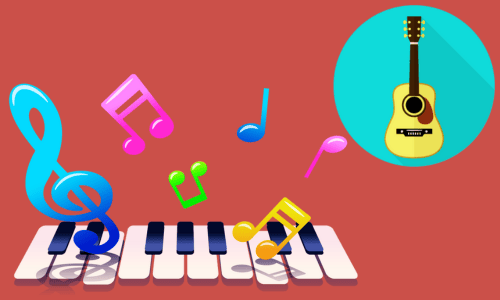
そうはいっても、ひとの騒いでいる枠のなかから抜け出して自分の好きな音楽を楽しむということは、それはそれで贅沢なひとときと云える。ということで当時ぼくが密かに愛聴していたスムース・ジャズというと、けっこういろいろ聴いていたのだけれど、ここではキーボーディストのみを挙げておく。新譜がショップの店頭に並ぶと必ず購入していたのは、グレッグ・カルーキスとアレックス・ブニョン。ふたりの作品はまさに良質なスムース・ジャズと云えるけれど、1980年代の後半からのアルバム・リリースということを考慮すると、スムース・ジャズの先駆者と云えるかもしれない。1990年代に入ってからは、近年すっかりファンク色の強くなったブライアン・カルバートソンがデビューしているが、彼もまた当時はスムース・ジャズの逸材だった。
2000年代以降に登場したキーボーディストでは、ロンドン出身のオリ・シルクもお気に入りのひと。このひとはもともとベーシストのダニー・シュガーとともにシュガー&シルクというユニットで、ブリット・ファンクの系譜に連なるようなダンサブルなリズムとポップなフックに富んだ音楽を演っていた。それでもシルクはアメリカのコンテンポラリー・ジャズ系ないしフュージョン系のアーティストをリスペクトしていて、ソロになってからはよりラジオ・フォーマットにアプローチするようになった。ぼくは彼を、現代スムース・ジャズ・シーンの雄と観ている。そしてもうひとり、いまのシーンを牽引するキーボーディストといえば、ブライアン・シンプソンのことを忘れるわけにはいかない。
ブライアン・シンプソンは、まさにスムース・ジャズの申し子のようなキーボーディスト。このスムース・ジャズにカテゴライズされるアーティストのピアノ・プレイやソングライティングを俯瞰したとき、彼のテクニックとセンシティヴィティは群を抜いていると云える。現在63歳のシンプソンのリーダー作は、昨年リリースされた『ソウル・コネクション』(2023年)で11枚を数える。アルバム制作のペースは速いとは云い難いが、どのアルバムも細部まで丁寧に作り込まれている。彼の場合、ラジオ・フォーマットだからといって粗製濫造に走るようなことは、これまでに一度もなかった。結果シンプソンのアルバムはいつも、スムース・ジャズとしての機能をしっかり果たす完成度の高さを誇る。軽く聴き流しても、じっくり聴いてもいい。
シンプソンは比較的日本でも人気のサクソフォニスト、デイヴ・コーズのバンド・メンバーだったことがある。2006年にはおなじくサックス奏者のカーク・ウェイラムらとともに、コーズ率いるランデヴー・オール・スターズの一員として来日した。そのときシンプソンはキーボーディストとしてはもちろんのこと、バンドのミュージカル・ディレクターとしても活躍した。実は当時のシンプソンは、ランデヴー・エンターテインメントというレーベルの専属アーティストだった。このレーベルはプレイヤーであるコーズ、スムース・ジャズ専門ステーションのパイオニアとして知られるフランク・コディ、そしてA&R、プロデューサーとして有名なハイマン・カッツによって、共同で創設されたもの。
このランデヴー・エンターテインメントの作品は、ディストリビューターのいまはなき日本のレコード・レーベル、ビデオアーツ・ミュージックによって、一部ボーナス・トラックが追加された国内仕様のCDとして発売された。シンプソンのアルバムも2nd作の『イッツ・オール・グッド』(2005年)と3rd作の『アバーヴ・ザ・クラウズ』(2007年)は日本で発売されたので、2006年の日本公演とあわせて彼のことを記憶にとどめたひと、あるいは彼のファンになったかたも案外多いかもしれない。興味深いのは『イッツ・オール・グッド』の国内盤の帯に「スムース・ジャズ=快適&スムースな日々の生活を創造します」という説明書きがあること。日本において、スムース・ジャズというジャンルが定着していないことがわかる。
デビュー作にしてじっくり味わえるオトナの音楽を展開
シンプソンはその後、シャナキー・エンターテインメントに移籍し、前述の最新アルバム『ソウル・コネクション』まで順調にリーダー作を吹き込んでいく。シャナキーはもともとアイルランドの伝統音楽であるフィドル・ミュージックに特化したレーベルだったが、1990年代の半ばあたりからスムース・ジャズに力を入れるようになり、現在もこのジャンルの人気アーティストを多く抱える。ケルトをはじめ、ジャズ、ブルース、フォーク、レゲエ、ゴスペルなどなど、世界の広範囲にわたるジャンルの音楽を手がけてきたこのインデペンデント・レーベルは、もはやスムース・ジャズのメッカといった風格さえ感じさせる。シンプソンは、大ベテランのジェフ・ローバー、10代の若き鬼才ジャスティン・リー・シュルツと並んで、このレーベルの看板キーボーディストだ。
そんなシンプソン、近年はヒゲにしてもメガネやファッションにしてもやたらお洒落で、まるでちょいワルオヤジのような風態だけれど、1stアルバム『クローサー・スティル』(1995年)を発表したときは、まだ30代半ばで爽やかなインテリ青年という印象を与えていた。このシンプソンのデビュー作は、ワシントン州ケント市に拠点を構えるノートワーシー・レコードという超マイナー・レーベルからリリースされた。カタログのアイテム数は少ないが、マイケル・パウロ(as)、マイケル・ホワイト(ds)、ポーリン・ウィルソン(vo)などの上質のスムース・ジャズ作品を制作した。残念なことにこのレーベル、詳細は不明だが2000年代の前半に閉鎖されたようだ。当然のごとく作品はすべて廃盤、入手も現在は困難を極める。
ノートワーシーの作品では、ハワイ出身のフュージョン・バンド、シーウィンドの1981年の未発表音源5曲を追加したコンピレーション・アルバム『リメンバー』(1995年)が、ファンの間では大きな話題となった。かくいうぼくも、当時は小躍りしたもの。実はぼくはこのアルバムと同時に、シンプソンの『クローサー・スティル』を購入した。シンプソンは1980年代の中盤あたりから、ジャンルを問わず数多くの音楽作品のレコーディングに参加しているけれど、そのころのぼくはノーマン・ブラウン(g)のモー・ジャズ作品で彼のことを知ったばかりだった。そんなとき『クローサー・スティル』を一聴して、少しまえにデビューしたブライアン・カルバートソンと同様に、シンプソンはたちまちぼくにとって重要なキーボーディストとなった。

シンプソンは1961年5月11日、イリノイ州ガーニー村に生まれた。ガーニーは風光明媚な観光スポットとして知られる。ジャズ好きの父親に感化されて、10歳からピアノを弾きはじめた。当時もっとも影響を受けたピアニストは、オスカー・ピーターソンだという。ノーザン・イリノイ大学音楽学部においてピアノの学士号を取得すると、ロサンゼルスへ移りプロ・ミュージシャンとして活動を開始。前述のノーマン・ブラウンをはじめ、ボニー・ジェームス(ts, ss)、エヴァレット・ハープ(ts, as)といったスムース・ジャズ系のミュージシャンと共演する。また、1980年代から1990年代にかけて活躍したニュージャージー出身のスウィートなソウル・グループ、サーフィスの1990年のスマッシュ・ヒット「ファースト・タイム」の作曲を手がけたりもしている。
おもしろいことに、当時松任谷正隆の秘蔵っ子シンガーソングライターとして注目を集めていた、障子久美の4thアルバム『ビコーズ・イッツ・ラヴ』(1992年)に、ロサンゼルスの名うてのミュージシャンに交じって、シンプソンがアレンジャー兼キーボーディストとして参加している。当時の日本で彼のことを知っているひとは、ほとんどいなかっただろう。もっとも注目されるのは、女性シンガーソングライター、ジャネット・ジャクソンのライヴ・ツアーに参加したこと。シンプソンは1994年12月、ミネソタ州ミネアポリス市で行われたライヴでキーボードを担当しているが、その模様はヨーロッパで堂々とリリースされたブートレグ『ジャネット/アブソリュート・ライヴ』(1995年)で聴くことができる。そして、この件は『クローサー・スティル』につながる。
ぼくはシンプソンのリーダー作のなかでは、この『クローサー・スティル』を断然推す。マイナー・レーベルの作品だけに、制作費は低予算だったと想像される。ただその点、1曲を除いてすべてシンプソンのオリジナルだが、彼のソングライティングとアレンジの妙技によってカヴァーされている。またサウンドに彩りを添えるのに、PCM音源が搭載されたワークステーション・タイプのシンセサイザー、KORG M1が上手く使われている。レコーディングではシンプソンのピアノが主軸に据えられ、バックをオリヴァー・ウェンデル(synth)、レイ・フラー(g)、ラリー・キンペル(b)、マイケル・ホワイト(ds)、ブライアン・キルゴア(perc)といった西海岸の名手たちが固めている。
冒頭の「ビコーズ・オブ・ラヴ」は、云うまでもなくジャネット・ジャクソンの5thアルバム『ジャネット』(1993年)のなかの1曲。オリジナルのクールなグルーヴはそのままだが、見事にピアノを軸としたインストゥルメンタルに料理されている。このトラックにはレックス・サラス(synth)、サム・シムズ(b)、ステイシー・キャンベル(vo)といった、前述のジャクソンのツアー・メンバーが参加している。つづく「クローサー・スティル」では、しなやかなビート感と明るいメロディック・ラインが爽やか。スローな「エイプリル」では、アレン・ハインズの生ギターがセンチメンタルな世界を演出。ファンキーな「ヒドゥン・プレジャーズ」では、ベースのスラッピングとピアノのブルージーな歌いまわしが気持ちいい。透明感のあるエスノ風「ミッドナイト・クレイジー」では、キーボードとパーカッションの高速デュオを満喫。
ゆったりしたボサノヴァ「ブラジリア」では、ジョナサン・バトラーのギターとスキャットを堪能。バウンシーな「サムワン・ジャスト・ライク・ユー」では、ピアノのスウィング感が心地いい。シンセによるインタールード「ユア・スマイル」をはさんで、アーバン・グルーヴ「イン・モーション」へ突入。シンプソンのブルース・フィーリングが全開する。ハートウォーミングな「モーニング・グローリーズ」では、シンプソンのリリカルな一面が窺える。シンコペーションがいい塩梅の「レイク・ショア・ドライヴ」では、エヴァレット・ハープの熱いテナー・ソロもフィーチュアされる。小曲「アルマーニ B」は、ファンキーなピアノ演奏によるクロージング。ということで本作は、スタビリティとインテリジェンスに富んだ、シンプソンの初期の傑作。バブル時代のフュージョンの諸作とは違い、じっくり味わえるオトナの音楽である。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。







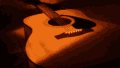

コメント