アーマッド・ジャマルの最大のヒット作『バット・ノット・フォー・ミー』と有名曲「ポインシアナ」
 Album : Ahmad Jamal Trio / But Not For Me (1958)
Album : Ahmad Jamal Trio / But Not For Me (1958)
Today’s Tune : Poinciana
あの有名な「ポインシアナ」とは、どんな曲?
みなさんは「ポインシアナ」といえば、誰の演奏を思い浮かべるだろう?この曲は、ナット・サイモンというひとが作曲した。ニューヨーク生まれの彼は、1930年代から1950年代にかけて活躍した、ピアニストであり、バンドリーダーでもある。彼は映画やミュージカルにたくさんの楽曲を提供しているが、この曲はそういった劇中歌とか主題曲ではなくて、1936年に純粋なポップスとして書かれたものだ。そもそも、よほどの音楽愛好家をのぞいて、サイモンの名前を知っているひとは、なかなかいないのではないだろうか?しかしながら、この「ポインシアナ」という曲は、あまりにも有名。タイトルは知らなくても、メロディには聴き覚えがある。あるいは、実際に聴いたことはないけれど、題名は知っている──そんな曲だ。
この曲、サブタイトルが「The Song Of Tree」というが、ポインシアナというのは、まさに花木の名前。マダガスカル原産の常緑高木で、枝の先に赤、オレンジ、黄色などの花をつける。和名をホウオウボク(鳳凰木)というが、葉の形が中国の伝説の鳥、鳳凰の翼を彷彿させるところから、その名がついた。日本では、夏になると沖縄県の宮古島などで観られる。那覇では、市のシンボルにもなっているそうだ──と、これは豆知識。たしかに「ポインシアナ」は、たとえば熱帯の空気や貿易風をイメージさせられる、明るい曲調が魅力的。キューバの音楽、カンシオン・ボレロの形式にのっとった、ゆったりしたリズムが心地いい。
ところで、この曲には面白いエピソードがある。作曲者のサイモンは、ある日マンハッタンのブロードウェイにある、著名なイタリアン・レストラン、マンマ・レオーネズで食事をしていた。そのとき突然「ポインシアナ」のメロディが、彼のアタマにひらめく。彼はとっさにテーブル・クロスにそのテーマのラフを書きとめる。そして店の好意でクロスを自宅に持ち帰った彼は、まもなく、メモした旋律をもとにピアノを使って曲を仕上げたという。さらに、この曲の作詞を担当したバディ・バーニエは、フロリダから届いたばかりのポインシアナの絵葉書からインスピレーションを受け、およそ30分で歌詞を仕上げたとのこと。いい曲は、神の啓示に導かれるように、瞬間的に創造されるのだ。
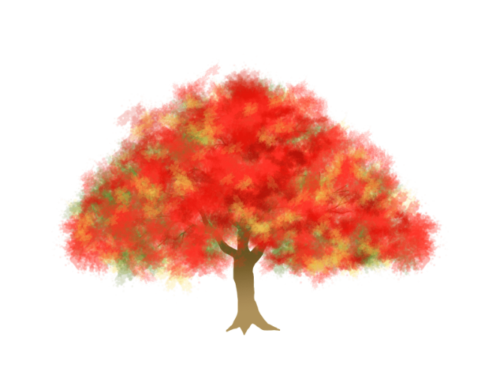
ところが完成した「ポインシアナ」は、当時のポピュラー・ソングとしてはいささか長めで、数年もの間ほとんど誰からも興味をもたれなかった。そんななか、早い時期からこの曲の稀有な愛好家だったのが、クラリネット奏者でオーケストラのリーダーでもあったジェリー・ウォルド。彼は、ビル・エヴァンスの初レコーディング『リッスン・トゥ・ザ・ミュージック・オブ・ジェリー・ウォルド』(1956年)で、エヴァンスのファンにとってはおなじみのひと。1943年のホテル・ニューヨーカーでのライヴにおいて、ウォルドが「ポインシアナ」を披露したところ、曲の知名度は一気に高まったのである。その後は、グレン・ミラーのアーミー・エアフォース・バンド、ベニー・カーター楽団、デヴィッド・ローズ楽団などによって、ぞくぞくとこの曲は採り上げられた。
ヒット後の「ポインシアナ」は、熱帯の風が吹いてくるような熱っぽいメロディ・ラインと恋人が現れることを願う歌詞が相まって、どちらかといえば情熱的なラヴ・ソングというイメージが強いせいか、多くのヴォーカリストによって採り上げられるようになる。ビング・クロスビー、フランク・シナトラ、フォー・フレッシュメン、マンハッタ・トランスファーなどが、すぐに思い浮かぶ。それに対してインストゥルメンタルはというと、快演はそれなりに存在するのだろうが、すぐさま列挙するのはなかなか難儀なことだったりする。ソニー・ロリンズの復帰作『ネクスト・アルバム』(1972年)と、ボビー・ライル・トリオの『ナイト・ブリーズ』(1985年)──ぼくが、いま自室の棚から見つけたのは、たったそれだけ(なんとも知識が浅い!)。
アルバムの大ヒット──「ポインシアナ」は大人気曲に
たしかに、ぼくは浅学菲才の身ではあるが、あえて言い訳をさせていただく。この「ポインシアナ」については、ある強烈なインパクトを与える演奏が残されている。ほかに数多の演奏が存在するとしても、それが一応満足すべき程度の出来具合だったら、くだんの演奏の前ではすっかり霞んで見えてしまう。だから、ぼくは「ポインシアナ」といえば、すぐにその演奏を思い浮かべるのだが、それがアタマから離れないものだから、咄嗟にそのほかの快演を思い出すことができないのだ。そして、鮮烈な印象を与えるプレイで「ポインシアナ」を有名曲に押し上げた立役者といえば、誰あろうピアニストのアーマッド・ジャマルである。彼は、2023年4月16日に92歳でこの世を去ったが、彼の演奏をオーディオでプレイしているいま、改めてしみじみと感じ入るものがある。
ところで、ジャマルの「ポインシアナ」は『バット・ノット・フォー・ミー』(1958年)というアルバムに収録されている。ぼくのようなピアノ・トリオの愛好家なら、一度は聴いたことがあるであろう有名盤だ。本作は、ポーランド系アメリカ人であるレナード&フィルのチェス兄弟が、1956年にシカゴで立ち上げたジャズ・レーベル、アーゴ・レコードからリリースされた。これもまた豆知識だが、アーゴは、英国に同名のレーベルが存在していたことから、1965年にカデットと改名された。こちらのレーベル名も、ジャズ・ファンにはおなじみだろう。ジャマルは、3枚目のリーダー作『カウント・エム 88』(1956年)から、しばらくの間アーゴ、カデットの専属アーティストだった。ちなみに、それ以前の2作では、ピアノ+ギター+ベースという旧ピアノ・トリオのスタイルをとっていた。
ジャケットの表記を見ればわかるように、本作の正式なタイトルは『ahmad jamal trio At The PERSHING / BUT NOT FOR ME』である。つまり本作の音源は、シカゴのサウス・サイドにあったパーシング・ホテルのラウンジにおいて実況録音されたもの。1920年代から閉館する1964年まで、そのラウンジで数多のジャズ・プレーヤーたちによるライヴ・パフォーマンスが披露された。ジャマルのグループは、1957年からそこのハウス・トリオだった。本作の吹き込みは1958年1月16日だが、翌日の17日の演奏も『アット・ザ・パーシング VOL.2』(1960年)としてリリースされた。CD時代にはヨーロッパのギャンビット・レコードが、この2枚のLPをまとめた『コンプリート・ライヴ・アット・ザ・パーシング・ラウンジ 1958』(2007年)を発売している。

このCDには、1958年に45回転のシングル盤としてリリースされた、およそ8分のオリジナルを3分に短縮した「ポインシアナ」のエディット・ヴァージョンも収録されているので、興味のあるかたはご賞味あれ。いずれにしても、アルバム『バット・ノット・フォー・ミー』は、当時のジャズのレコードとしては未曾有の大ヒットを記録し、同時に「ポインシアナ」は大人気曲となった(アルバム・チャートで2年間10位以内にとどまった)。面白いのは、これを機に大金を手に入れたジャマルは、シカゴにアルハンブラというダイニングバーをオープンさせた(営業期間は1959年〜1961年)。ちゃっかり『アーマッド・ジャマルズ・アルハンブラ』(1961年)というライヴ盤を吹き込んでいたりもする。
ジャマルのトリオは、パーシング・ラウンジ時代から、サイドはイスラエル・クロスビー(b)とヴァーネル・フルニエ(ds)で固定されていたが、アルハンブラの閉店を機に解散。彼は活動の拠点を、シカゴからニューヨークへ移した。実は、ぼくはシカゴ時代のジャマルが好きなのだが、それはその後の彼が自己の演奏形態を大きく変えたからだ。特に1968年にインパルス!に移籍してからの彼は、まるでレーベル・カラーに染まったかのごとく求道的な音楽を展開するようになる。まあ、それだけ時代の流れに敏感なひとだったのだろう。かつての名演「ポインシアナ」の再考&再演を『ポインシアナ・リヴィジテッド』(1969年)という作品で試みているけれど、ひとことで云うとやり過ぎだ。
アーマッド・ジャマルはスゴいピアニスト
そこには、当時全盛だったモード・ジャズに影響されたジャマルがいる。当然のごとく即興演奏においては、飛躍的に束縛から解き放たれている。スケールアウトもするし、逆に自由度が増したせいか、あの流麗なメロディがぜんぜん出てこなかったりする。サビに入ってようやく、ああ「ポインシアナ」だったのかと、ハッキリわかるような仕様だ。もちろん、モード・ジャスがわるいわけではないし、インパルス!に罪があるわけでもない。ただ、シカゴ時代のジャマルに親しんでいたものからすると、モーダルなセンスを発揮し多弁にアドリブしまくる彼の姿に、驚きと戸惑いを覚えざるを得なかったのである。次作の『ジ・アウェイクニング』(1979年)のように、まるで鬼火のように静かで激しい情熱を燃やすような演奏も、クールでいいのだけれど──。
ほんとうは、もっと広いこころをもってしてジャマルの音楽を楽しむべきなのかもしれないが、シカゴのホテルやレストランのラウンジでプレイしていたころの彼の輝きを、ぼくはどうしても忘れることができない。そして、それを象徴するのが「ポインシアナ」なのだ。ピアノのブロック・コードで奏でられるエキゾティズムあふれるメロディ・ラインとハーモニー、ドラムスとベースによる4拍目にアクセントをつけた軽快なリズム、ラテン・ミュージックの熱いムードのなかで、ニューオーリンズの伝統的なセカンド・ライン・ビートがひたすらつづいていく──そんな心地いいグルーヴに乗って、ジャマルは意識的に音数を少なくしていき、絶妙な“間”をつくることで、得もいわれぬ心地よさを生み出す。
このシングル・トーンで音符を少なめに弾くスタイルが、あのマイルス・デイヴィスに影響を与えたことは、あまりにも有名だ。ついでに云うとマイルスは、ジャマルのスペースをとる弾きかたに加え、軽妙なタッチ、小気味いいリズム感、出しゃばることのないさり気ない表現などが、たいそうお気に召していたよう。たしかにマイルスも決して吹きまくるタイプではないが、彼の音楽の美しさに関する独特な考えかたは渋くもあり鋭くもありで、さすがと云うしかない。彼が自己のグループの当時のピアニスト、レッド・ガーランドにジャマルのように弾け!と云っていたのはご愛嬌だけれど、たとえば同グループの「飾りのついた四輪馬車」などは、明らかに『バット・ノット・フォー・ミー』に収録されているジャマルのヴァージョンからヒントを得ている。

このアルバムのいちばんの聴きどころは「ポインシアナ」だが、そのほかの曲といえば──リラックスしたムードが横溢するラテン調の「バット・ノット・フォー・ミー」ちょっと物憂いムードだが途中リリカルなワルツになる「ヴァーモントの月」シングル・トーンとブロック・コードが上手く使い分けられた軽快な4ビート「ミュージック、ミュージック、ミュージック」左手のコンピングがガーランドを彷彿させるものの、右手の単音による軽妙洒脱がアドリブがいかにもジャマルらしい「ノー・グレイター・ラヴ」メロディ・ラインに大胆に手が加えられ、寡言な即興演奏とシンプルなリフで盛り上げられる「ウディン・ユー」かなり丁寧に弾きこまれていて、ジャマルのバラード演奏へのコダワリが感じられる「ホワッツ・ニュー」など、名演揃い。
繰り返しになるが、ここでのジャマルの演奏は、スペースを置くことに注力されたスタイル。結果的に、クロスビーのベースも、フルニエのドラムスも、とにかくよく聴こえてくる。こういうサウンドは、耳の遣りどころをその都度かえることができるので、何度聴いても飽きが来ない。もしジャマルがそこまで計算していたのなら、彼は相当なしたたか者だ。いや、本作をよく聴いてみるとわかるのだが、彼はときおりやたら弾きまくっている。楽曲もけっこういじっている。その点、案外お茶目なひとなのかもしれない。確実なのは、彼が侮ることのできないスゴいピアノのテクニックの持ち主であるということ。晩年はまるで宇宙人のように難解なプレイもしていたけれど、わかりやすい「ポインシアナ」は、安心して聴ける。そういう盤は、自然とことあるごとにターンテーブルにのせられるのである。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。








コメント