レジェンダリーなジャズ・ファンクのパイオニア、ロイ・エアーズ逝く──ファンキーなサウンドのなかにもクールネスとメロウネスとが交錯する代表作『エヴリバディ・ラヴズ・ザ・サンシャイン』
 Album : Roy Ayers Ubiquity / Everybody Loves The Sunshine (1976)
Album : Roy Ayers Ubiquity / Everybody Loves The Sunshine (1976)
Today’s Tune : The Golden Rod
なみなみならぬ手腕をもつ歴としたジャズ・ヴィブラフォニスト
ロイ・エアーズがこの世を去った。長い闘病生活の末、2025年3月4日にニューヨーク市で亡くなった。現地時間5日(日本時間では6日)に、オフィシャル・フェイスブック・ページにて明らかにされた。84歳だった。昨年(2024年11月3日)ロサンゼルス市の自宅でクインシー・ジョーンズが亡くなったばかりだが、彼がそうであったようにエアーズもまた、プロデュース気質で新たなフィールドに足を踏み入れることを臆することなく常に流行の最先端を行く音楽家だった。彼は一般的にはレジェンダリーなジャズ・ファンクのパイオニアとして観られているが、むろんひとつの分野に収まりきらない広い視野と柔軟な思考を兼ね備えた音楽性をもつミュージシャン。ミュージック・シーンにおいて、たいへん稀有な存在だった。
エアーズは、コンポーザー、アレンジャー、プロデューサー、そしてヴィブラフォニストとして数多くのレコーディングに携わり、長いあいだ音楽ファンを楽しませてくれた。ぼくも中学生のころから彼のアルバムを聴きはじめたのだけれど、いつの間にか自室のレコード棚にはその作品がズラリと並んでいた。エアーズの奏でるサウンドは、平たく云うと、どう聴いてもカッコよくて、いつでもキマッテいる。すこぶるお洒落で洗練された響きと心地いい躍動感をもった彼の音楽は、たいへん親しみやすいものだから、多くのリスナーから支持されつづけている。エアーズはクラブ・シーンにおいてもっとも再評価された音楽家のひとりだが、これほど世代を超えて愛されるミュージシャンは、ほかにいないかもしれない。ここにあらためて、ご冥福をお祈りする。
ところでロイ・エアーズは、歴としたジャズ・ヴィブラフォニストである。しかも、なみなみならぬ手腕の持ち主だ。最初にも云ったとおり、彼は概してジャズ・ファンクの先駆的存在と名状される。あまつさえ1980年代にイギリスのクラブ・シーンで生まれたアシッド・ジャズのムーヴメントにおいては、最大級のインフルエンサーと崇め奉られ、さらに1990年代の終わりごろには、“ネオ・ソウルのゴッドファーザー”という異名をとった。確かにエアーズはフュージョンが隆盛を極めた1970年代の半ばから、すでにアレンジャー、プロデューサーとしての手腕を発揮していたし、その後も時代の趨勢とともに自己のサウンドにディスコやブラック・コンテンポラリーの要素を積極的に採り入れた。でもそんな彼ももともとは、ポスト・バップ・ジャズ・アーティストだったのである。

もっとも古いエアーズの吹き込みといえば、テナー奏者のカーティス・エイミーがパシフィック・ジャズ・レコードに残した2枚のアルバム『ウェイ・ダウン』(1962年)『ティッピン・オン・スルー』(1962年)あたりだろう。エアーズのハード・バッパー然としたプレイに、ちょっと驚かれる向きもあるかもしれない。また、当時としては珍しいソウルフルな女性アルト奏者兼ヴォーカリスト、ヴァイ・レッドの初リーダー・アルバム『バード・コール』(1962年)においても、エアーズは鮮やかなマレット捌きを披露している。おなじみのチャーリー・パーカーのナンバーを、軽やかに演奏する彼もまた思い切りキマッテいる。さらにピアニストのジャック・ウィルソンのボサノヴァ・アルバム『ジャック・ウィルソン・クァルテット』(1963年)や『ランブリン』(1966年)は、もはやエアーズ抜きでは語れない作品と云える。
そんななかエアーズは、しっかりアルバム・デビューを果たしている。それはユナイテッド・アーティスツ・レコードからリリースされた『ウェスト・コースト・ヴァイブス』(1963年)という作品だが、1963年6月14日、18日にロサンゼルスで吹き込まれた正真正銘、彼の初リーダー・アルバムである。プロデュースをイギリス出身のジャズ評論家、レナード・フェザーが手がけている。レコーディング・メンバーは、ロイ・エアーズ(vib)、ジャック・ウィルソン(p)、ビル・プラマー(b)、ヴィクター・ガスキン(b)、トニー・バズレー(ds)、ケニー・デニス(ds)、そしてカーティス・エイミー(ss, ts)となっている。気ごころの知れた西海岸の精鋭たちによる演奏は、瑞々しさが際立つのと同時に非の打ちどころがない。
本作は全10曲中5曲がヴァイブ+ピアノ・トリオのクァルテットで、残りの5曲がさらにエイミーのサックスが加わったクインテットで吹き込まれた。アルバム・タイトルからクール・ジャズの特徴とも云えるリラクゼーションに富んだライトなサウンドを思い浮かべる向きも多いかと思われるが、確かにここでのアンサンブルにはそういう側面も窺える。しかしながらこのコンボ演奏は、どちらかというとハード・バップをより洗練されたスタイルに発展させたものと受け取られる。ときにモーダル、ときにソウルフルなサウンドが、アーバンなムードを醸し出している。たとえばボサノヴァ調にアレンジされたヘンリー・マンシーニの「酒とバラの日々」などは、レア・グルーヴの観点から捉えても魅力的に響くだろう。
またエアーズは本作ですでに、高品質のオリジナル・ナンバーを2曲披露している。アルバム冒頭の「サウンド・アンド・センス」は、16小節からなるモダンな感覚が研ぎ澄まされたブルース。かたや「リカーズ・ディレンマ」は、都会の香りを放つソウルフルなジャズ・ワルツ。どちらもエアーズのセンスのよさを感じさせる佳曲だ。さらに本作では、彼のヴィブラフォニストとしての華麗な技巧や表現力をたんと味わうことができる。特にチャーリー・パーカーの「ドナ・リー」やセロニアス・モンクの「ウェル・ユー・ニードント」といった曲では、高速のテンポにおける彼の鮮烈な演奏テクニックを堪能。手垢のついたバップの名曲に新たな息吹をもたらすところは、いまにしてみればいかにもエアーズらしいと思われる。
ぼくがエアーズのアルバムを聴きはじめたのは1970年代の後半だったけれど、ようやく日本でも彼のアルバムがコンスタントに発売されるようになったころのことだ。それまでのエアーズの国内盤といえば、アトランティック・レコード時代の一部のアルバムと、1971年のモントルー・ジャズ・フェスティヴァルにおける実況録音盤『ロイ・エアーズ・ユビキティ・アット・モントルー』(1972年)くらいのものだった。ちなみにこのライヴ盤は日本限定発売で、オリジナルのLPレコードには4曲が収録されていた。1996年にヴァーヴ・レコードがCD化した際に、新たに5曲が追加された。ときに『ウェスト・コースト・ヴァイブス』も、当時は輸入盤で入手するしかなかったのだけれど、すでに国内でもCD化されているようなので、ぜひ聴いていただきたい。
ハービー・マンのグループのメンバーとなり、知名度が一気に上がる
この『ウェスト・コースト・ヴァイブス』は長らくぼくの愛聴盤となっているのだが、いまあらためて聴いてみてもまったく古さを感じさせない。というかぼくは、このエアーズが21歳という若さでものしたデビュー作を聴き直して、ある感慨を催した。どういうことかというと、彼はこの作品以降新味を求めて音楽のスタイルにおいて変化を重ねていくが、その音楽性の本質的なところはまったく変わっていないように思われるのである。時代は移ろえども、エアーズはいちアーティストとして不易流行なのである。その点では、さきに引き合いに出したクインシー・ジョーンズとも共通する。ハード・バップを演ろうとジャズ・ファンクを演ろうと、そのソフィスティケーテッドな独自性は変わらないのだ。
そんなエアーズの音楽家になるまでのプロセスについて、簡単に触れておく。エアーズは本名をロイ・エドワード・エアーズ・ジュニアというが、1940年9月10日カリフォルニア州ロサンゼルス市に生まれた。彼の実家があったロサンゼルスのダウンタウン、サウス・パークは、南カリフォルニアのブラック・ミュージック・シーンの中心地でもある。それに加えてエアーズが育ったのは、父親がトロンボーンを吹き母親がピアノを弾くという、いわゆる音楽一家の家庭だった。そして5歳のとき、あのライオネル・ハンプトンからヴィブラフォンのマレットをプレゼントされたことは、広く知られている。そんなエアーズを取り巻くまわりの状況からすれば、彼が音楽の道を志すようになるのはごく自然なことのように思われる。
その後エアーズはロサンゼルスのトーマス・ジェファーソン高校に進学する。この学校は、多くの才能あるミュージシャンを輩出したことで知られる。アルト奏者のフランク・モーガン、テナー奏者のデクスター・ゴードン、トランペッターのアート・ファーマーも同校の出身者だ。ちなみに前述のヴァイ・レッドも、エアーズの先輩に当たる。そういう意味でこの学校は、結果的にセントラル・アヴェニューのジャズ・シーンの発展に大きく寄与したことになる。高校時代のエアーズはヴィブラフォンの演奏以外にも、教会の聖歌隊で歌ったり、ラテン・リリックスというバンドのリーダーを務め、スティール・ギターやピアノを弾いたりもした。さらにエアーズはロサンゼルス市立大学に進んだあとヴィブラフォンに集中し、1962年からスタジオの仕事を開始する。
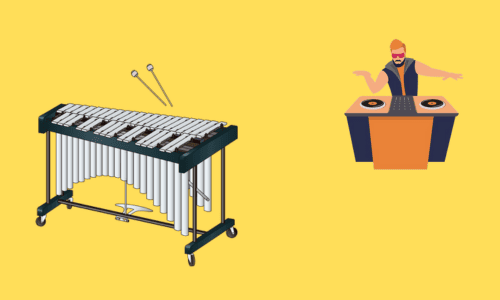
前述のようにエアーズは、カーティス・エイミー、ヴァイ・レッド、ジャック・ウィルソンらのサイドメンを務めたあと、早々に初リーダー作『ウェスト・コースト・ヴァイブス』をリリース。さらにリロイ・ヴィネガー・クインテットやジェラルド・ウィルソン・オーケストラなどのレコーディングに参加したあと、ついに大学を中退し1966年からフルーティスト、ハービー・マンのグループの正式メンバーとなる。これを機にミュージック・シーンにおいてエアーズの知名度は、一気に上がったのである。マンは1960年代以降のジャズ・フルーティストとしてはもっとも卓越したテクニックのもち主のひとりだが、プロデューサーとしても腕を振るったひとで多くの若手ミュージシャンを発掘した。
たとえば、マンは『スタンディング・オヴェイション・アット・ニューポート』(1965年)というライヴ・アルバムで、アルバム・デビューするまえのチック・コリアをフィーチュアしている。当時コリアはまだ24歳だったが、すでに嶄然として頭角を現している。その点、コリアよりひとつ年上のエアーズもまた、マンのお眼鏡に適った若き俊英のひとりと云える。実はぼくがエアーズの演奏にはじめて触れたのは、ほかでもないマンのレコードでのことだった。故人であるぼくの父は、基本的にはクラシックのレコード・コレクターでありながら、マンの音楽に強い愛着を示していた。だからぼくはものごころがつくまえから、マンが奏でるちょっとエキゾティックでオプティミスティックなサウンドに慣れ親しんでいたのである。
特に1961年11月17日、ニューヨーク市マンハッタン区グリニッジ・ヴィレッジに所在した有名なジャズ・クラブ、ヴィレッジ・ゲイトで実況録音された『ヴィレッジ・ゲイトのハービー・マン』(1962年)というレコードは、いやというほど聴かされた。いま思えば、ぼくがフルートとヴィブラフォンとの楽器としての相性のよさに気づいたのは、このレコードにおいてだった。ちなみにここでマレットを揮っているのは、エアーズではない。のちにカナディアン・ソフト・ロック系グループ、ハーグッド・ハーディ&ザ・モンタージュのリーダーとして名を馳せる、ハーグッド・ハーディである。エアーズが登場する最初のマンのレコードといえば『中東の印象』(1967年)。彼のプレイは、このアルバムの3曲で聴くことができる。
この3曲は1966年11月9日にニューヨークでレコーディングされたものだが、ドラムスやパーカッションに加えて中東の撥弦楽器ウードがフィーチュアされた異色のセッションである。これがエアーズにとってマンとのはじめての吹き込みと思われるのだが、もしかするとそれよりまえの録音が存在するのかもしれない。というのもマンのアルバムには、たとえば『ビート・ゴーズ・オン』(1967年)のように、1964年から1967年にかけて行われた7つのセパレートなセッションをまとめたものもあるからだ。また、マンのアルバムのなかに日本人の血を引くウェストバージニア州カイル生まれのシンガー、タミコ・ジョーンズとのコラボ作『男と女』(1967年)というのがあるが、こちらもやはり3つのセッションで構成されている。
この『男と女』は、ジョーンズのソウルフルなヴォーカルも然ることながら、全体に心地いいサウンドとリラックスしたムードが溢れる、ラウンジ・ミュージックとして有用なボサノヴァ・アルバムである。ところで本作のセレクションのうち、1966年11月23日ニューヨークで吹き込まれた3曲のヴィブラフォンが実はエアーズによるものだったと、ぼくが知ったのは2010年代に入ってからのこと。なにせアナログ・レコードのジャケットには、クレジットの記載がまったくなかったのだから、それもやむなしというものだ。そして、ぼくの知る限りでは『メンフィス・トゥー・ステップ』(1971年)のなかの表題曲(1970年11月ニューヨークにて録音)をもって、エアーズはマン作品への参加に終止符を打っている。
ユビキティが結成され音楽スタイルも大きな飛躍を遂げる
とにもかくにも、前述の『中東の印象』から『メンフィス・トゥー・ステップ』までのマンのリーダー作で、もしヴィブラフォンが奏でられていたら、それをプレイしているのはおおかたエアーズだろう。そのなかでぼくが最初に聴いたアルバムはどれかといえば、実のところハッキリと思い出せない。なにぶんそれは自分の幼少期のことで、当時のぼくはといえば、ただ父がかけていたマンのレコードを聴くともなしに聴いていただけなのである。たぶんウードとバグパイプが入ったエキゾティックな『ウェイリング・ダルヴィーシュズ』(1968年)か、ポップ路線の『ウィンドウズ・オープンド』(1968年)、あるいは唯一CTIレコードからリリースされた『グローリー・オブ・ラヴ』あたりだろう。
いずれにしてもエアーズの名前を覚えたのは、あの『メンフィス・アンダーグラウンド』(1969年)であることは間違いない。ビルボード誌のジャズ・アルバム・チャートで、堂々の1位を獲得、R&Bのアルバム・チャートでも2位を記録した大ヒット・アルバムだ。ぼくは小学校に入学するまえからこのレコードを無意識に聴いていたのだけれど、ジャズやフュージョンを本格的に聴くようになった中学生のころ、それこそ耳の穴をかっぽじって聴き直したもの。このアルバム、曲目を観るとリズム・アンド・ブルースのカヴァー集という印象を与えるが、ファンキーな躍動感とエキゾティックな雰囲気が横溢するロック・オリエンテッドなサウンドはいかにもマンらしく、聴いているといつの間にか身体を揺り動かしていたりする。
なおこの作品において、エアーズはもちろんのこと、ラリー・コリエル(g)、ソニー・シャーロック(g)、そしてミロスラフ・ヴィトウス(b)の名前が、ぼくのアタマにインプットされた。同じころエアーズは、マンの肝煎りでアトランティック・レコードに『ヴァーゴ・ヴァイブズ』(1967年)『ストーンド・ソウル・ピクニック』(1968年)『ダディ・バグ』(1969年)といったリーダー作を吹き込んでいる。彼はこれらのアルバムで、ハービー・ハンコック(p)、ロン・カーター(b)、ジョー・ヘンダーソン(tp)、チャールズ・トリヴァー(tp)などを従え、個性的なニュー・メインストリーム・ジャズを展開しているが、ジャズの評論家のなかにはそこにあるプレイこそジャズ・ヴァイブの神髄を究めたものと高く評価する向きもある。
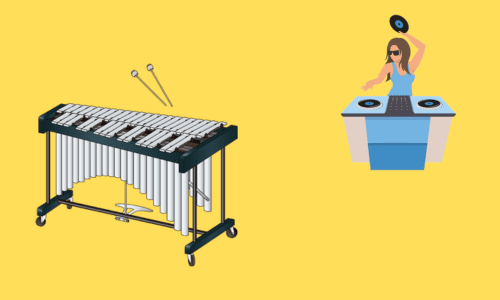
またそのかたわら日本コロムビアの企画によりエアーズは、シャーロック、ヴィトウス、そしてドラマーのブルーノ・カーを率いてロイ・エアーズ・クァルテット名義の『カミン・ホーム・ベイビー』(1969年)『オール・ブルース』(1969年)『アンチェイン・マイ・ハート』(1970年)も録音。そのうち最初の2枚はダイレクト・カッティングでの吹き込みだが、彼は卓越したパフォーマンス能力を発揮している。だがそれにもまして注目すべきは、ポリドール・レコード移籍第1作『ユビキティ』(1970年)のリリースだろう。このときエアーズをリーダーとするバンド、ユビキティが誕生。彼自身の音楽スタイルも、大きな飛躍を遂げる。そしてファンク、ソウルのテイストは着実に増しブギーやディスコにも積極的にアプローチされ、エアーズ・サウンドは1970年代から1990年代までの音楽シーンを一気に駆け抜ける。
ついでに云っておくと、ロイ・エアーズ・ユビキティの“Ubiquity”という馴染みのないコトバは、哲学や神学で使われる“遍在性”のこと。それすなわち、いたるところに存在する──ということ。はじめてこのバンド名を目にしたぼくはすぐに辞書で調べて、単純にカッコイイな──と思ったもの。このバンド名義のオリジナル・アルバムは、エアーズ抜きの『スターブーティ』(1978年)も含めると、ぜんぶで13枚となる。まあ、そのあとソロ名義になっても基本的な音楽性は変わらないのだけれど──。佳作揃いなのでベストワンを選ぶのは難しいのだが、とりあえず中学生のぼくがはじめて輸入盤で手にした『エヴリバディ・ラヴズ・ザ・サンシャイン』(1976年)をおすすめしておく。DJ/クラブ世代からも、長らく重宝される1枚だ。
チャノ・オフェラルによる軽快なコンガに乗ってハンドクラップとおなじみの「ヘーイ!ウー!〜」というコーラスではじまる「ヘイ・ウー・ホワット・ユー・セイ・カム・オン」は、グルーヴィーなイントロダクション。アップテンポの「ザ・ゴールデン・ロッド」は、エアーズのヴィブラフォンとフィリップ・ウーのローズがはじけるブギー・フュージョン。ミッドテンポの「キープ・オン・ウォーキング」は、カナダのシンガーソングライター、ジノ・ヴァネリの曲をカヴァーしたもの。チルアウトなアーバン・ムードは絶品だ。バウンスする心地いいリズムの「ユー・アンド・ミー・マイ・ラヴ」は、アルバム中もっとも濃厚なソウル・ナンバー。メロウネスが全開する「ザ・サード・アイ」では、ウーのローズが大きくフィーチュアされる。
ラテンとファンクとが交錯する「イット・エイント・ユア・サイン・イッツ・ユア・マインド」では、ウーによるアープ・オデッセイとロナルド・ヘッド・ドレイトンによるギターがワイルドなムードを演出。ジョン・ショーン・ソロモンによる反復するベース・ラインが刺激的な「ピープル・アンド・ザ・ワールド」では、チカスことデビー・ダービーのヴォーカルがソウル・フィーリングを炸裂させる。スペーシーな浮遊感をもつ「エヴリバディ・ラヴズ・ザ・サンシャイン」では、本作で多用されているソリーナ・ストリング・アンサンブルが効果的に使用されている。ストレートなジャズ・ファンク「タン・パワー」では、ダグ・ローズによるドラムスが打ち出す歯切れのいいビートが痛快。ヒップホップ・ミュージックのネタとしても人気を博した「ロンサム・カウボーイ」では、クセのあるファンク・ビートに乗ってラップが登場する。
このアルバムでエアーズは、本業のヴィブラフォンはそっちのけで、フェンダー・ローズ・エレクトリック・ピアノ、アープ・オデッセイ、ソリーナ・ストリング・アンサンブル、パーカッション、それにリード・ヴォーカルなどを受けもっている。もちろんカヴァー・ナンバー1曲を除くすべての楽曲のコンポジション、アルバムのプロデュースも彼が手がけた。エアーズはのちにオハイオ州シンシナティ出身のソウル・グループ、ランプ、5人組のコーラス・グループ、エイティーズ・レディーズ、女性ソウル・シンガー、シルヴィア・ストリプリン、サクソフォニストのフスト・アルマリオらの作品で、卓越したプロデュース能力を発揮する。そういう自分をまえに出さずトータル・サウンドをクリエイトすることに専念するようなところは、本作においてもまた然りである。彼は本来ヴィブラフォンの達人だから、ちょっともったいない気もするのだが──。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。









コメント