ジョー・ザヴィヌルがウェザー・リポート結成以前に残したピアノ・トリオ・アルバム『トゥ・ユー・ウィズ・ラヴ』
 Album : Joe Zawinul Trio / To You With Love (1961)
Album : Joe Zawinul Trio / To You With Love (1961)
Today’s Tune : I Should Care
フュージョン系がデビュー時に残した立派なモダン・ジャズ作品
ジョー・ザヴィヌル(1932年7月7日 – 2007年9月11日)といえば、エレクトリック・ジャズ・バンド、ウェザー・リポートのキーボーディスト。あるいはその少しまえでは、マイルス・デイヴィスの『イン・ア・サイレント・ウェイ』(1969年)でオルガンを弾き、おなじくマイルスの『ビッチェズ・ブリュー』(1970年)でエレピを弾いたひと。さらにそのまえでは、アルト奏者のキャノンボール・アダレイのバンド・メンバーとして、アルバム『マーシー・マーシー・マーシー』(1966年)でエレピを弾き、大ヒットした表題曲を作曲したひと。一般的には、そんなイメージではないだろうか?ぼくはザヴィヌルのキーボード・ワークやソングライティングから直接影響は受けていないけれど、ウェザー・リポートの音楽は好きだったのでアルバムはひと通り所持する。
とはいっても今回ご紹介するのは、ウェザー・リポートの作品ではない。おそらくザヴィヌルの最初期の吹き込みと思われる『トゥ・ユー・ウィズ・ラヴ』(1961年)という、まったく彼らしからぬタイトルのアルバム。ついでに云うとジャケットにあしらわれたバラのイラストも、上述したようなザヴィヌルの一般的なイメージにはまったくそぐわない。ちなみにこれはロナルド・レヴィンというひとのペインティングだが、まさか彼はベーシストのロン・カーター(本名はロナルド・レヴィン・カーター)ではないだろう。カヴァーアートを担当したレヴィン氏のことはまったく知らないけれど、ザヴィヌルのアルバム以外にもストランド・レコードの作品を何枚か手がけているようだ。
ストランドは、1959年から1965までデッカ・レコード傘下で運営されていた、ニューヨーク(のちにフィラデルフィアに移る)のマイナー・レーベル。ザヴィヌルのアルバムも、おそらくそれほどプレスされなかっただろう。それにもかかわらずこのレコード、なぜか中古レコード店でよく見かけたもの。しかもレアなはずなのに、値段がつり上がるようなこともなかった。ザヴィヌルはジャズにいち早くシンセサイザーをもち込んだりファンク・グルーヴを導入するなどして、エレクトリック系サウンドを主軸としたジャズの発展に貢献したひと。つまりジャズの歴史において彼は、重要な人物のひとりのはず。そのわりにジャズ・ピアニストとしての彼は、一部の熱心な愛好家を除く多くのジャズ・ファンに、端からスルーされていたりする。
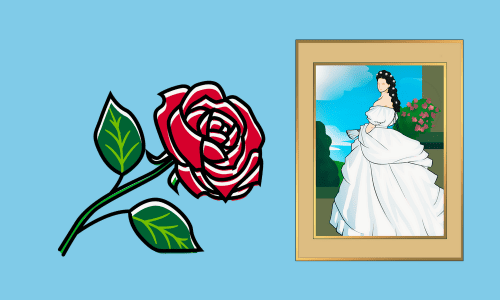
現にぼくがこのレコードを購入する際、あるひとからこんなことを云われた。ご当人は単におちゃらかしただけなのだろうが、彼の「そんなの買うの?」というコトバは、モダン・ジャズにおいてザヴィヌルは門外漢であるという見解をほのめかすものと、ぼくには受けとられた。それは1990年のことで、ぼくはすでに社会人になっていた。偶然にも勤め先の上司が筋金入りのジャズ・マニアだったのだが、御茶ノ水のとあるレコードショップでザヴィヌルの『トゥ・ユー・ウィズ・ラヴ』を「そんなの」と云ったのはこのひと。まあ彼はぼくにとってジャズの師匠みたいな存在だから、ぼくはそういうものかと素直に受けとめたもの。しかしながらぼくは、自らの飽くなき好奇心に抗うことはできなかった。
あのウェザー・リポートのザヴィヌルはその昔、どんなジャズ・ピアニストだったのか?ぼくは興味津々だった。師匠の「それよりヘイグやガーランドを聴け!」という託宣のごときコトバを右から左に、ぼくは『トゥ・ユー・ウィズ・ラヴ』を購入した。そもそもぼくのなかには、ある揣摩臆測があった。それはエレクトリック・ジャズやフュージョンで名を馳せたキーボーディストは、デビュー時に立派なモダン・ジャズ作品を残していることがままある──というもの。むろんこれは絶対的な法則性を有するものではないけれど、知識や見識は浅はかであるにしてもある程度はぼくの経験値によるもの。もし具体的に例示しろと云わたら、思いのほかいともたやすく挙げることができたりするのである。
これは云わずもがなだが、ハービー・ハンコックのデビュー・アルバム『ウォーターメロン・マン(Takin’ Off)』(1962年)は、ハード・バップの可能性を押し広げた名作だ。対するチック・コリアも負けじと初リーダー作『トーンズ・フォー・ジョーンズ・ボーンズ』(1966年)において、より先進的なハード・バップをアグレッシヴリーに展開している。まあこのふたりの場合、フュージョンやロックも演るけれどジャズ・シーンにおいても大御所と云えるから、はじめてのスタジオ・アルバムがモダン・ジャズ作品であってもなんの不思議もない。ではボブ・ジェームスの場合はどうだろう。彼はフュージョン・シーンのエグゼクティヴ的存在。ところがそのデビュー作は『ボールド・コンセプションズ』(1963年)という、前衛的なピアノ・トリオ・アルバムだった。
東のボブ・ジェームスとくれば、西のデイヴ・グルーシンである。グルーシンはフュージョンばかりでなく、アダルト・コンテンポラリーやフィルム・ミュージックなど、広範囲にわたり活躍するキーボーディストだが、音楽家としてのキャリアはジャズ・ピアニストからスタートしている。ファースト・アルバムはピアノ・トリオで吹き込んだ、ブロードウェイ・ミュージカルのジャズ・ヴァージョン『サブウェイズ・アー・フォー・スリーピング』(1962年)だった。これらのジェームス、グルーシンの両アルバムは、モダン・ジャズの作品として評価するとき企画性においても演奏技術においても高品質と云えるし、ジャズの愛好家の間でもけっこう人気が高い。つまり彼らはジャズ・ピアニストとしてホンモノなのである。
ウェザー・リポート結成以前のザヴィヌルによるいくつかの渾身作
さらに挙げると、あのクルセイダーズのキーボーディスト、ジョー・サンプルにも『トライ・アス』(1969年)というリリカルでトランスペアレントなピアノ・トリオ作品がある。またファンク・マスターとして高く評価され、いっときはディスコ・サウンドにまで傾倒したジョージ・デュークも、初リーダー作『ザ・ジョージ・デューク・クァルテット』(1966年)において、ハード・バップ、モーダル・ジャズといった、ごくごくオーソドックスなジャズを演っている。さらにデュークを継承するようなキーボーディストで、リズム・アンド・ブルースからポスト・ディスコまでこなすパトリース・ラッシェンでさえ、デビュー・アルバム『プレリュージョン』(1974年)では、スリリングにドライヴするジャズ・ピアノを披露している。
ということで、それらの名盤に実際に触れることによって培われた、勘や感覚みたいなものから体得された知識によって、ザヴィヌルの『トゥ・ユー・ウィズ・ラヴ』にもきっとなにかしら得るものがあると、ぼくは信じてやまなかったのである。実際このアルバムは、モダン・ジャズの好盤としてしっかり機能するものでもあり、ザヴィヌルの長いキャリアにおいて非常に貴重な作品でもあった。ぼくは本作を彼の最初期の吹き込みと云ったけれど、実はそれよりまえにジョー・ザヴィヌル・トリオ名義の『ザ・ビート』(1957年)という、7インチのシングル・レコードがリリースされている。これは1957年3月12日オーストリアのウィーンにおいてレコーディングされたもので、同国のコンティネント・レコードから発売された。
この吹き込みでザヴィヌルは、サイドにジョニー・フィッシャー(b)、ヴィクトール・プラシル(ds)といったオーストリアのジャズメンを従えているが、考えてみれば彼はウィーンの生まれで、ボストンへ渡るのはその2年後のことだった。ぼくはこのレコードを所持していないけれど、幸いなことに音楽配信で聴くことができる。ひとことで云えば、スウィンギーでクールなモダン・ジャズ作品だ。若き日のザヴィヌルは、そのピアノ・プレイに推進力があって音の粒だちもよく、いっぱしのジャズ・ピアニスト然としている。そのほかのオーストリア時代のザヴィヌルのレコーディングといえば、1955年から1958年までのジ・オーストリアン・オールスターズ名義の作品がある。一部配信でも聴くことができるので、興味のあるかたはどうぞ──。

ところで、ぼくがエレクトリック・ジャズのアドヴァンスに寄与した音楽家の原点を探求しようとする、ある意味で根源的な精神から手にした『トゥ・ユー・ウィズ・ラヴ』は、オーストリア時代の『ザ・ビート』のスタイルが引き継がれた、純然たるモダン・ジャズ・ワーク。しかも結果的には、ぼくが事前に予想していたものよりもはるかに優れていて、しかも美しい作品だった。ザヴィヌルのソロ名義のアルバムというとそれほど多くはないのだけれど、どれも渾身の作品ばかりだ。ぼくは特に彼がウェザー・リポートのキーボーディストとして活動する以前に、アトランティック・レコードに吹き込んだ3枚が好きだ。正確には2枚目だけ、なぜかアトランティックのジャズ・サブシディアリーであるヴォルテックス・レコードから発売された。
それはともかく、このアトランティックの3枚のアルバムを聴くことによって、ザヴィヌルの音楽的エヴォリューションの軌跡を辿ることができる。ウィーン音楽院でたんとクラシック音楽を学んだ経験もあるザヴィヌルだけに、リーダー作を重ねるごとにジャズを新たな高みに導くような風格が感じられる。一般的には3枚目の『ザヴィヌル』(1971年)が、もっとも高い評価を得た。さきに挙げたマイルスのアルバムでエレクトリック・ジャズの洗礼を受けたのちの、いわばウェザー・リポートのオーパス・ゼロ的作品だ。このアルバムを聴くと、ウェザー・リポートの独特のサウンドの背後にある、クリエイティヴィティの原動力となっているのが、ほかでもないザヴィヌルであることがよくわかる。
その前作にあたる『サード・ストリームの興亡』(1968年)においても、ザヴィヌルはすでにアートオリエンテッドなジャズを展開している。ここで彼は、テナー奏者で作編曲家のウィリアム・フィッシャーの協力を得て、アルバム・タイトルにあるようにジャズとクラシックを融合させた第3の音楽を創出しているのだ。リズム・セクション、テナーとトランペットの2管、さらにヴィオラ3本にチェロ1本といったユニークなストリング・アンサンブルが加えられた、斬新な編成によるレコーディング。内容的にもモード、フリーといったジャズ、ゴスペル、インドの伝統音楽、そしてクラシックと、様々な音楽が採用されている。個人的にはオーストリアのピアニスト、フリードリヒ・グルダの曲「ウィーンより愛をこめて」の美しさにシビレた。
ザヴィヌルとグルダは、フリードリヒ・グルダ・ウント・ザイン・ユーロジャズ・オーケストラの『ユーロスウィート/2台のピアノとバンドのための変奏曲』(1967年)で共演済み。これはオーストリアのプライザー・レコードからリリースされたアルバム。1966年の夏にライヴ・レコーディングされたビッグバンド作品だ。J. J. ジョンソンのトロンボーンとザヴィヌルのピアノとが各々フィーチュアされた2曲を収録。意外にもどちらも聴きやすいジャズ・ピースである。本作は長い期間、グルダ・ファン泣かせの幻の名盤と云われてきたが、いまではCD化もされており気軽に楽しむことができる。ザヴィヌルの吹き込みとしては、アトランティック盤の1枚目と2枚目とのはざまに位置することから、ぼくにとっても愛聴盤となっている。
どんな演奏形態であってもいつも美しいザヴィヌル・サウンド
ところが、そのアトランティック・レコードの1作目『マネー・イン・ザ・ポケット』(1966年)において、ザヴィヌルはまだ芸術志向でもなく革新的なジャズのスタイルを追求しようともしていない。前述の『サード・ストリームの興亡』から彼の作風はかなり変わるけれど、この作品には2年後の演奏形態のシフトをまったく示唆するところがない。ちょうどハービー・ハンコックがブルーノート・レコードの新主流派として人気を集めていたせいか、ここでのザヴィヌルはセクステットでの演奏を中心にハード・バップやソウル・ジャズをグルーヴィーに展開している。個人的には「ミッドナイト・ムード」が大好きだ。ザヴィヌルのペンによるリリカルなジャズ・ワルツだが、この隠れた名曲をもっとも愛してやまなかったのは、あのビル・エヴァンスだった。
この『マネー・イン・ザ・ポケット』を聴いていても感じられることなのだが、ザヴィヌルという音楽家はいい意味で堅物なひとなのではないだろうか。決して柔軟性がないわけではないが、そうかといって彼が融通無碍に振る舞う場面はまったく観られない。ザヴィヌルの場合、間違ってもビジネスライクな演奏をしたりコマーシャリズムに走るなど、絶対にあり得ないこと。彼は常にマイルールに忠実に、自己の音楽をまえに押し進めていくのである。だからザヴィヌルが創造する音楽は、どんな演奏形態であってもいつも美しい。いかにすれば音楽を美しく響かせることができるか、彼はそれを的確に見極める能力をもっている。それゆえ、どうあってもブレない。その生真面目さが、作品の品格を高めてさえいる。
ぼくは、ザヴィヌルの音楽に真摯に向き合うところ、そして音楽に対する人智を越えた審美眼が、作曲や演奏においてそのまま彼の個性になっているように感じる。ぼくがザヴィヌルの音楽に、親愛の情を抱きながらもちょっと近寄りがたいと感じるほど、畏敬の念を抱くのはそんなところからだ。たとえば『マネー・イン・ザ・ポケット』のなかで、ロバート・メリンとガイ・ウッドによる名曲「ただひとつの恋」が、ソロ・ピアノで演奏されている。この比類なき美しいメロディック・ラインをもったラヴ・バラードには、ジョン・コルトレーン&ジョニー・ハートマンをはじめとする名演が数多存在する。しかしながら、ザヴィヌルの繊細な感受性が生み出す格調高雅とも云うべきパフォーマンスは、ごく稀少なものである。

そんなザヴィヌルの誠実で上品なピアノ演奏、そして楽曲における緻密なコンポジションとアトモスフィアの構築を、襟を正さずとも堪能できるのが、ジョー・ザヴィヌル・トリオの唯一のフルアルバム『トゥ・ユー・ウィズ・ラヴ』だ。ただ本作は表向きはトリオ名義になっているけれど、実際は10曲中7曲の編成がトリオ+コンガとなっている。ただそこはザヴィヌルのこと、全編を通してアフロキューバン・ジャズを全開させ、ノリノリになるようなことはない。ただこれもまた彼の計算のうちかもしれないが、ピアノの流麗さにリズムの軽快さが加味されることによって、本作は全体的に優雅かつ爽快な印象を与える。ヨーロッパ起源の音楽の正統な教育を受けたザヴィヌルだけに、音楽家としての育ちのよさみたいなものが滲み出ていて、実に面白い。
レコーディング・メンバーは、ジョー・ザヴィヌル(p)、ジョージ・タッカー(b)、フランキー・ダンロップ(ds)、レイ・バレット(cga)と、ジャズ・ファンならだれもが知るような名プレイヤーばかり。タッカーはどちらかといえば飾り気はないけれど、躍動感に溢れた力強いボトムをキープするいわば堅実なベーシスト。ダンロップはセロニアス・モンクのサポーターとして知られるが、わりと簡素なフレーズを歌わせるタイプ。それでも緩急自在のドラミングは、いぶし銀の芸と云える。ふたりとも確たる音楽教育を受けているせいか、どこか品格が漂う。いっぽうバレットはブーガルーとアーリー・サルサのトップランナーでありジャムセッションの達人でもあるが、とにかくジャズ・プレイヤーとの相性がいい。なお吹き込みは1959年9月、ニューヨーク市で行われた。
曲目はすべて、よく知られたジャズ・スタンダーズとトラディショナル。アルバムは気鋭のアレンジャー、アクセル・ストルダールとムード・ミュージックの父ことポール・ウェストンとの共作「アイ・シュッド・ケア」によって幕を開ける。もともと映画の主題歌だが、多くのジャズ・ピアニストによって採り上げられている。ここではラテンと4ビートを上手く組み合わせたリズミカルなアレンジにこころが弾む。ピアノのシングル・トーンとブロック・コードとの緩急のついたプレイが気もちいい。つづくラルフ・レインガーの映画音楽「イージー・リヴィング」では、トリオ演奏の寛いだムードから、コンガが入ってきて一気にテンポが明快になる。ピアノによるドラマティックなイントロとエンディングも印象的だ。
パーシー・メイフィールドの「プリーズ・センド・ミー・サムワン・トゥ・ラヴ」は、原曲どおりのリズム・アンド・ブルース。ピアノがトリガーとなりバンド全体がコーラスごとに盛り上がっていくところが痛快。ベース・ソロのぶっとい音と渋い語り口もいい感じだ。リチャード・ロジャースの「春の如く」は、トリオのみの演奏。ピアノのブルース・バラード風の解釈が異彩を放っている。コール・ポーターの「ラヴ・フォー・セール」では、唯一アフロキューバン・ジャズが全開する。クールなピアノのソロのあとは、コンガのひとり舞台となる。B面のトップ、ファッツ・ウォーラーの「スクイーズ・ミー」では、ピアノのブルースからアウトする感じがスタイリッシュ。短尺ながら4バースにおけるドラム・ソロも鮮やかだ。
イングランド民謡の「グリーンスリーヴス」は、詩的な美しさをもったソロ・ピアノ。つづく「ただひとつの恋」は前述の『マネー・イン・ザ・ポケット』ではソロ・ピアノだったが、ここではトリオに途中からコンガも加わり、ピアノはブルージーなフレーズを紡ぎ出す。アリー・リューベルの「マスカレード・イズ・オーヴァー」では、アップテンポの2ビートから4ビートへと華麗に進行し、シンプルではあるが弾けるようなグルーヴ感をもったドラムスのソロが高く舞い上がる。ガス・アーンハイム、ハリー・トビアス、ジュールス・ルメアの共作「スウィート・アンド・ラヴリー」では、トリオがスローテンポでダルなムードを醸し出している。スモーキーなブラシ・ワーク、ブルージーなベース・ソロ、ゴスペル・タッチのピアノ・プレイが余韻を残す。のちのザヴィヌル・サウンド同様、風格をまといながら──。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。








コメント