CTIレコードがその衰退期に制作した、オールスター集結のスーパー・フュージョン・バンド、フューズ・ワンの第1作『フューズ・ワン』
 Album : Fuse One / Fuse One (1980)
Album : Fuse One / Fuse One (1980)
Today’s Tune : Grand Prix
フューズ・ワンは当初バンド名を“フューズ”と勘違いされていた
フューズ・ワンというフュージョン・バンドがあった。音楽ジャンルの名称として、それまでのクロスオーヴァーに取って代わって、フュージョンがすっかり定着した1980年にシーンに登場した。だが1984年に3枚目のアルバムを発表すると、まるでひと夏の甘い思い出のように消えていった。まあ実際にはそんなロマンティックでセンティメンタルな印象は、まったくなかったのだけれど──。ただこのバンド、最初のアルバムがリリースされる際、日本の大手電子部品メーカーTDKとタイアップしていた。それは当時TDKが製造していた、いまではすっかり過去の遺物となってしまったカセットテープのCMキャンペーンでのこと。バンドの「ダブル・スティール」という曲が、TDKのCMソングとして使用された。バンドのアルバム、シングルは、ともに大ヒットを記録した。
ここでいささか気になることがあるので、ついでながら記しておく。まずこの「ダブル・スティール」という曲だが、フュージョン・バンドのオリジナル・ナンバーということで、当然のごとくインストゥルメンタルである。それまでのTDKのCMソングといえば、ビー・ジーズやスティーヴィー・ワンダーといった大御所の歌ものが採用されていた。ところが、このフューズ・ワンは一般的にはどこの馬の骨とも牛の骨とも分からないバンド。しかも親しみやすいヴォーカルはなし。この異色の起用はCMプランナーにとって冒険だったと思うのだけれど、結果的にそのコンセプトは見事に成功し、当時の若者たちに強いインパクトを与えた。爽快な疾走感をもつインスト「ダブル・スティール」が、彼らの感性にフレッシュに響いたのだろう。
いまひとつ触れておきたい点といえば、フューズ・ワンというバンド名である。むろん「ひとつに融合する」という意味なのだろうが、少なからず新たな音楽ジャンルであるフュージョンが意識されての命名だろう。ところでこのバンド、登場した当初は多くのひとから、その名を“フューズ”と勘違いされていた。しかもとんでもないことに、国内盤を発売したキングレコードもそう思い込んでいた。LPレコードのタスキに微妙ではあるが、“フューズ”をバンド名として示すような表記がある。さらに「ダブル・スティール」に「フレンドシップ」をカップリング曲としたシングル盤のほうでは、ジャケットやライナーノーツにおいてこのバンドのことがはっきり“フューズ”と呼称されている。もはや云い逃れはできない。まあ、かく云うぼくも最初はそう思っていたのだけれど──。
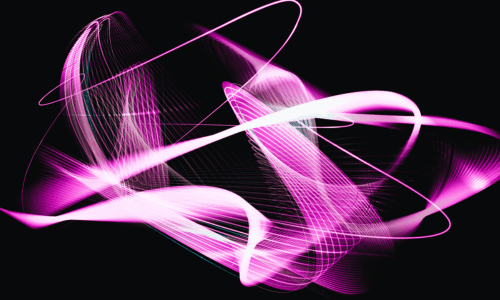
くだんのフューズ・ワンのファースト・アルバムは云うまでもなく『フューズ・ワン』(1980年)だが、もしかしたら日本ではこのバンド、初お目見えからセカンド・アルバム『シルク』(1981年)がリリースされる翌年までの間、ずっと“フューズ”の名称で通っていたのかもしれない。キングレコードが発売した『シルク』の国内盤のタスキに記されたバンド名も、今度はちゃんとフューズ・ワンとなっている。さきに挙げたシングル盤のジャケットが、それ以降修正されたかどうかは定かではないが──。まあこういう誤解が発生する原因は、本国の原盤制作会社からの情報不足あるいは伝達ミスにあると容易に想像されるのだが、そのいっぽうで、このアルバムがCTIレコードにおいて制作されたものであるということが、多くの業界関係者、そして音楽ファンにある先入観を与えていたようにも思われるのである。
CTIレコードは、1967年に音楽プロデューサーのクリード・テイラーによって創設されたジャズ系レーベル。ちなみにこのレーベル、A&Mレコード傘下でスタートした当初は“CTI”という名称は“Creed Taylor Issue”を省略したものだったが、1970年に独立した際にあらためて“Creed Taylor Incorporated”の略称とされた。テイラーは、それまでABCパラマウント・レコード、インパルス! レコード、ヴァーヴ・レコードといったレーベルで多くのジャズ作品を手がけていたが、ヴァーヴ時代からジャズのポピュラリゼーションに意欲的だった。たとえば、アントニオ・カルロス・ジョビンやジョアン・ジルベルトをはじめとするブラジル出身のミュージシャンを積極的に起用し、率先してジャズ作品にボサノヴァを採り入れたのは、テイラーそのひとである。
テイラーはCTIレーベルを立ち上げてからアルバム制作において、クラウス・オガーマンをはじめ、ドン・セベスキー、ボブ・ジェームス、デヴィッド・マシューズといったハウス・アレンジャー、GRPレーベルを立ち上げるまえのデイヴ・グルーシン、ブラジル出身のエウミール・デオダート、アルゼンチ出身のラロ・シフリンといった錚々たる顔ぶれを、オーケストレーターとして起用。リード・ミュージシャンが繰り出す熱いプレイに、スウィートな響きを加えるようになった。その作品数は120にも及ぶと云われているが、そのコンテンツの中心はまさにクロスオーヴァーと呼ばれる音楽。特にクラシック、ワールド・ミュージック、あるいは同時代のソウル・ミュージックが題材として採り入れられ、ジャズにアレンジされた楽曲はレーベルの呼びものとなった。
CTIサウンドは一部、1940年代後半から1960年代前半にかけて確立されたモダン・ジャズの愛好者からは批判を受けたが、ジャズにこだわらない聴衆からは大いに歓迎された。その点でテイラーのジャズをポピュラライズするという当初の目論見は、見事に成就したと云ってもいいだろう。世代的なこともあるのだろうけれど、かく云うぼくもまたCTI作品をよく聴いていたし、以降フュージョンの世界に自分が深く足を踏み入れるようになったのは、同レーベルの作品群の恩恵に預かったからと自認する。ところでCTI作品のなかに、現在もジャズ/フュージョン・シーンをリードする、ボブ・ジェームスの『はげ山の一夜』(1974年)という名盤がある。いまもクラブ・シーンにおいて、ジャズ・ファンクの名曲と崇められている「ノーチラス」を収録したアルバムだ。
ジェームスにとってCTI第1作に当たるこの『はげ山の一夜』の原題、実は『Bob James One』という。実際のところそれのみならず、彼のCTI時代のアルバム・タイトルにはすべて、リリース順に振られた通し番号が付されているのだ。また、クラシック作品をエレクトリック・ジャズにアレンジしたナンバー「ツァラトゥストラはかく語りき」という、異例のヒット曲を飛ばしたエウミール・デオダートのCTI作品のなかに『ラプソディー・イン・ブルー』(1973年)というアルバムがある。本作の原題は『Deodato 2』だが、云うまでもなく彼にとってCTI第2作に当たるが故の命名である。すでにお気づきのことと思うが、くだんのフューズ・ワンのバンド名が“フューズ”というふうに間違えられたのは、アルバム『フューズ・ワン』のタイトルにある“One”が作品の通し番号と誤解されたからだろう。
クロスオーヴァー・ブームに先鞭をつけたレーベルCTIの衰退期
とはいってもこの『フューズ・ワン』というアルバム、クリード・テイラーがプロデューサーとしてクレジットされた、正真正銘CTIレコードのカタログに掲載される作品だが、実質的にはキングレコードが主導となって制作されたものなのだ。そのわりにバンド名を間違えるというのは、一体全体どのような事情なのか。まあそれはともかくこのアルバムは、すでに衰退期にあったCTIレコードの久々のヒット作品であり、外観的にはCTIのブランドイメージが強調されていながら、サウンド的にはあまりCTIっぽくないという異色作でもある。どういうことかというと、CTIはクロスオーヴァー・ブームに先鞭をつけたレーベルだけれど、フューズ・ワンがプレイする音楽は、もはやクロスオーヴァーではなくフュージョンなのである。
クロスオーヴァーからフュージョンへの変遷は、1970年代から1980年代にかけてのミュージック・シーンにおいて、重要な進化の過程とも云える。サウンド的には、クロスオーヴァーが実験的な側面をもっていたことから、いささか混沌とした状態にあったのに対し、フュージョンはよりソフィスティケーテッドでアーバンでポップという、ひとつのスタイルが確立されたものだった。この進化を促した要因としては、高度な演奏技術を身につけたミュージシャンが登場したこと、楽曲がメロディアスで聴きやすくなったこと、録音技術の向上によってクリアでタイトなサウンドが主流になったことなどが挙げられる。CTIレコードの黄金期といえば、やはり1970年代の前半と云えるのではないだろうか。それすなわち、まさしくクロスオーヴァーが人気を博していた時代なのである。
CTIの黄金期を象徴するものといえば、繰り返しになるけれど、ジャズを基調としながら、クラシック、ブラジリアン・ミュージック、リズム・アンド・ブルースなどのエッセンスを融合したサウンド。ハウス・アレンジャーのなかでは、ドン・セベスキーによるゴージャスなオーケストレーションがもっとも典型的と云える。また外観では、レコード・ジャケットの独特のアートワークが象徴的だった。CTI作品では、フォトグラファーのピート・ターナーによる鮮やかな色彩のジャケット写真が、LPサイズで最大の魅力を放ちブランドイメージを確立した。だがそんなCTIの優れた意匠と芸術的センスも、その時代特有のもの。かつてミュージック・シーンにおいてフレッシュな存在だったCTIも、時間の経過とともに過去のものとなったのである。
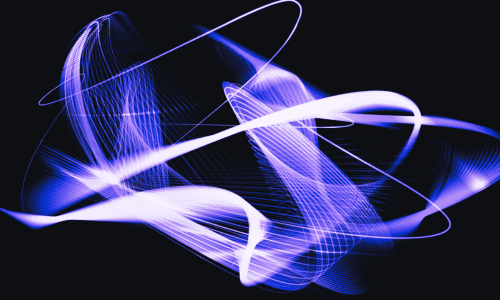
そんなCTIの名盤とといえば、ギタリストのウェス・モンゴメリーがオーケストラをバックにザ・ビートルズをはじめとするポップ・ナンバーをプレイした『ア・デイ・イン・ザ・ライフ』(1967年)、ハード・バップのトランペッター、フレディ・ハバードがジャズ・ファンクに挑んだ『レッド・クレイ』(1970年)、ギタリストのジョージ・ベンソンがラテンのリズムとファンキーなグルーヴに乗ってハードなプレイを展開する『ホワイト・ラビット』(1972年)、そして前述のキーボーディスト、エウミール・デオダートがクラシックの名曲をファンキーなエレクトリック・ジャズにアレンジして大ヒットさせた、ある意味でクロスオーヴァーの象徴とも云える『ツァラトゥストラはかく語りき』(1973年)などがすぐに思い浮かぶ。
さらに忘れてはならないのは、モダン・ジャズ・クァルテット(MJQ)のヴィブラフォニストであるミルト・ジャクソンが壮大なストリングスをバックにブルージーなプレイを展開する『サンフラワー』(1973年)、ギタリストのジム・ホールが見事にジャズ化されたホアキン・ロドリーゴの名曲を、静謐を湛えた品格のある演奏で聴かせる『アランフェス協奏曲』(1975年)。特に後者は、CTIレーベル晩年の最高傑作のひとつとも云われている。以上のアルバムは、CTI作品を体験したことがないというかたにはぜひとも手にとっていただきたいのだが、どれも1980年代のフュージョン・サウンドとは、まったく異なる印象を与えるものばかりである。ただ急速なトレンドやテクノロジーの進化から、フュージョンがすっかり定着した時代においては、オワコン扱いの憂き目を見た。
いささか余談になるが、ボブ・ジェームスがCTIレーベルに『BJ4』(1977年)を吹き込んだあと、自己のレーベル、タッパン・ジーに移籍し、ときを移さず新作『ヘッズ』(1977年)のレコーディングに取り掛かっている。ところで、興味深いのは『BJ4』と『ヘッズ』とが、まったく趣きの異なる作風に仕上がっているということ。サウンドの質感ひとつとってみても、レコーディング・エンジニアがジャズの分野を中心に活躍したルディー・ヴァン・ゲルダーからフィル・ラモーンの薫陶を受けたジョー・ジョーゲンセンへバトンタッチされたことから、まるで違う印象を与える。まあ、ぼくはどちらも好きなのだけれど、実はこの2枚の違いにクロスオーヴァーからフュージョンへの進化を感じていたりする。なお前者はビルボード誌のジャズ・アルバム・チャートで3位にランクイン、後者は堂々の第1位を獲得した。
CTIレコードは、きわめて独自性の高いレーベルだった。だがこのレーベルが創出する作品の独自色が、逆に経営面において、その先行きを不透明にしていたとも云える。1970年代後半における音楽市場、特にジャズ/フュージョン・シーンの時流、そして経済状況の変化が影響したのだろう、結局1978年に破産宣告を受ける。かねてから経営難に陥っていたCTIは、CBSレコード(現在のソニー・ミュージックエンタテインメント)と配給契約を結び、結果的にCBSに対する多額の負債を清算することとなったのである。この破産時に本国アメリカではソニー・ミュージックが原盤権とマスターテープを保有。そして日本での原盤権は、キングレコードが買い取った。キングレコードは現在も、CTI作品のうち120タイトルを「CTI ALLTIME COLLECTION」と銘打って、CDでリリースしつづけている。
なおこの破産時に、ボブ・ジェームスとサクソフォニストのグローヴァー・ワシントン・ジュニアとは、自身のリーダー作の原盤権を買い取っている。ジェームの4枚のリーダー作品は、タッパン・ジー・レコードの扱いとなった。いっぽうソウル・ジャズに特化したCTIの某系レーベル、KUDU(クードゥー)からリリースされていたワシントン・ジュニアの8枚のリーダー・アルバムは、当時彼が所属していたモータウン・レコードによっていまも販売されている。いずれにしても、1980年代のフュージョン・シーンにおいて時代に取り残された感じが否めないCTI作品ではあるが、1990年代の中ごろから後半にかけて、レア・グルーヴやクラブ・ジャズのブームにおいて再評価の機運が高まり、いまでも多くのファンに支持されている。流行とはそういうものなのだろう。
ということで、長々とCTIレコードについてお伝えしてきたが、ここからはフューズ・ワンのハナシに集中する。レコードのセンターラベルにCTI作品ではもっとも一般的な(ぼくには黄色に見えるのだけれど)オレンジラベルと呼ばれるものが使用され、プロデューサーをこれまでどおりクリード・テイラーが務めたアルバム『フューズ・ワン』といえば、さきにも触れたとおり、もともとプロジェクトをリードしたのはキングレコード。レコーディングとミキシングに至っては、CTIサウンドの立役者である名匠ルディ・ヴァン・ゲルダーがエンジニアを務めたのは、全7曲中2曲のみである。この配慮にもこころなしか、ミュージック・シーンにおけるクロスオーヴァーからフュージョンへの変遷に対する、制作サイドの留意が感じられる。
アルバム・コンテンツの調和がとれたフュージョン全盛期を代表する1枚
上記のファースト・アルバムがヒットしたことから、翌年にセカンド・アルバム『シルク』がリリースされる。やはりテイラーがプロデュースを手がけ、今度はヴァン・ゲルダーが全曲においてレコーディング・エンジニアを務めた。1作目のジャケット写真はなぜかテイラー自身が撮影したものだったが、2作目のアートワークではCTIのお抱えフォトグラファー、ピート・ターナーが復帰している。また本作では、レコードの両面ともに2曲ずつの収録という、各ミュージシャンの即興演奏をクローズアップするロング・パフォーマンスが採用されている。これらの特徴は、CTIの黄金期の作品を彷彿させる。その点、同時代のフュージョン作品として遜色のない洗練されたサウンドを纏いながらも、テイラーのジャズへの強いこだわりが感じられる。まあ、それが彼の弱点でもあるのだけれど──。
また、フューズ・ワンにとってサード・アルバムにしてラスト・アルバムとなった『アイス』(1984年)は、実はCTI作品ではない。キングレコードが1978年に立ち上げた日本を代表するフュージョン・レーベル、エレクトリック・バードからリリースされた。プロデュースもテイラーではなく、同レーベルの創設者である川島重行が手がけている。サウンド・プロデュースとアレンジは、もとCTIのハウス・アレンジャーでエレクトリック・バードから何枚かアルバムを発表しているデヴィッド・マシューズが担当。ニューヨークのファーストコール・ミュージシャンたちによるエキサイティングなセッションが繰り広げられる本作、内容的にはわるくないのだが、ハッキリ云ってフューズ・ワンのアルバムというよりはマシューズの作品といった印象を与える。
この『アイス』では、一部『フューズ・ワン』『シルク』に参加したミュージシャンも参加しているが、どちらかというとマシューズ所縁のプレイヤーのほうが存在感を放っている。全曲マシューズのオリジナル(1曲のみスティーヴ・ガッドとの共作)であること、そしてなによリもテイラーの不在ということから、このサード・アルバムではCTIレーベルのブランドイメージは雲散霧消している。ちょっと意地悪な云いかたになるが、はたしてバンドにフューズ・ワンの名前を掲げる必然性があったのか、はなはだ疑問である。まあ、もともとフューズ・ワンはパーマネント・バンドではなかったし、確かな演奏技術をもつミュージシャンたちが制約を受けることなく存分に能力を発揮することができる場として、テイラーが構想したプロジェクトだったのだけれど──。
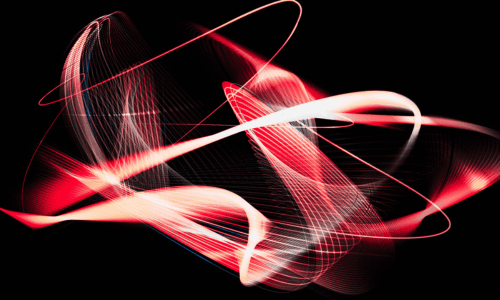
ということで、テイラーの音楽全般に対する知識とセンス、そしてクリエイティヴィティとビジネスとの両面を担うマルチタスク能力が、上手い具合に作用した1980年代型フュージョン作品といえば、やはりファースト・アルバム『フューズ・ワン』ということになる。このアルバムがヒットしたことによりふたたび制作資金を得たテイラーは、CTIレーベルに固執しつづけ往年のブランディングに立脚するようになる。ただぼくはそんな彼にもまた、プロデューサーとしての限界を感じてしまうのだった。フューズ・ワンが3枚のアルバムを残して消え去った背景には、そんなことが原因として存在するようにも思われるのである。しかるに夢幻泡影を嘆きながらも、一時の輝きを放つCTIフュージョンの名作『フューズ・ワン』を、じっくり味わおうではないか。
バンドの核となるのは、ロニー・フォスター(key)、スタンリー・クラーク(b)、レオン・ンドゥグ・チャンクラー(ds)。この3人は『シルク』にもひきつづき参加しているし、チャンクラーに至っては同作においてアレンジャーも務めている。フィーチュアリング・アーティストとしては、ジョー・ファレル(fl, ss, ts)、ジョン・マクラフリン(g)、ラリー・コリエル(g)、トニー・ウィリアムス(ds)が挙げられる。さらにサポート・ミュージシャンが数多く参加しているが、ホルへ・ダルト(key)、ヴィクター・フェルドマン(key)、ドン・グルーシン(key)、ヒュー・マクラッケン(hca)、ウィル・リー(b)、レニー・ホワイト(ds)、パウリーニョ・ダ・コスタ(perc)、ロジャー・スキテロ(perc)と、錚々たる顔ぶれである。
また本作では、アレンジャー兼キーボーディストとして、人気フュージョン・バンド、スパイロ・ジャイラのもとメンバー、ジェレミー・ウォールが参加している。ウォールはテイラーにその手腕を買われ、マルチ・リード奏者、ユセフ・ラティーフの『テンプル・ガーデン』(1979年)や、女性ヴォーカリスト、パティ・オースティンの『ボディ・ランゲージ』(1980年)といったCTI作品で、すでにコンポーザー、アレンジャー、キーボーディストとして活躍していた。フューズ・ワンのサウンドにおいて、ジャズに根ざした高い音楽性が維持されるいっぽうでポップ性も重視されているのは、彼の存在によるところが大きい。そういえば、どちらかというと即興性よりも曲調に主眼が置かれた楽曲が目立つという点で、フューズ・ワンとスパイロ・ジャイラとは共通する。
アルバムのトップを飾るフォスターの「グランプリ」は、メロディアスなフュージョン・ブギー。クラークのパワフルかつヴィルトゥオーシックなテナー・ベース、ファレルの情感を溢れさせながらも鋭さを感じさせるテナー、そしてフォスターの小気味よくソウルフルなフレーズを綴るフェンダー・ローズと淀みなくソロが展開される。ベドルジフ・スメタナの交響詩『わが祖国』の第2曲「ヴルタヴァ」(ドイツ語では「モルダウ」)のパラフレーズ・ナンバー「ウォーターサイド」は、軽やかなサンバ。雄大なストリングスをバックにウォールのエレクトリック・グランドがリズミカルにメロディを奏でる。コリエルのエレクトリックとアコースティックのもち替えによるソロも効果絶大。黄金期に比べるとかなりポップだけれど、CTIブランドが意識された1曲と云えるだろう。
クラークの「サンシャイン・レディ」は、美しいメロディック・ラインとハートウォーミングな雰囲気が心地いい、いかにも1980年代のフュージョンらしい洗練されたタッチの曲。ファレルのソプラノとマクラフリンのアコースティック・ギターもメロウな世界を演出する。マクラフリンの「トゥ・フーム・オール・シングス・コンサーン」は、プログレッシヴ・ロックとジャズ・ファンクが交錯するハードコア・フュージョン。シャッフル・ビートに乗ってマクラフリンのギター、ファレルのテナーが熱いソロを展開する。ウォールの「ダブル・スティール」は、ダンサブルな8ビートとファンキーなメロディック・ラインがキャッチーなナンバー。ファレルのブルージーなテナーを中心に、ウォールのエレガントなピアノ、フォスターのファンキーなミニモーグが彩りを添える。
マクラフリンの「フレンドシップ」は、ミスティカルなムードのゆったりしたテンポから高速サンバに移行するドラマティックな曲。ファレルのフルートとマクラフリンのアコースティック・ギターがトランスライクかつアップビートなプレイを繰り広げる。アルバムのラストを飾るクラークの「タクシー・ブルース」は、シャッフル・ビートが炸裂するブルース・ナンバー。クラークのドライヴするスラップ・ベース、コリエルのブルージーかつロッキッシュなギターがすこぶるクール。マクラッケンのブルース・ハープもいい味を出している。アルバムの締めくくりに相応しい、エナジェティックなパフォーマンスだ。圧倒的なテクニックや音楽的深みをもつ、凄腕ミュージシャンたちを上手くまとめているのはウォールだろう。それはアルバム・コンテンツの調和にもつながるもので、その点でも本作はフュージョン全盛期を代表する1枚と云えるのではないだろうか。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。








コメント