進化を遂げたビル・チャーラップ・トリオのヴァイタリティ溢れる自由闊達なプレイが際立つヴィレッジ・ヴァンガードにおける実況録音盤『アンド・ゼン・アゲイン』
 Album : Bill Charlap Trio / And Then Again (2024)
Album : Bill Charlap Trio / And Then Again (2024)
Today’s Tune : And Then Again
キャリアのはじまりはジェリー・マリガンのバンド・メンバー
前回はビル・チャーラップの4枚目のリーダー・アルバム『オール・スルー・ザ・ナイト』(1998年)についてお伝えした。このアルバムは、その後いまに至るまでサイドメンを務めることになる、ピーター・ワシントン(b)、ケニー・ワシントン(ds)との最初の吹き込みであり、絶妙な選曲と漲溢する歌ごころが全開するビル・チャーラップ・トリオの代表作である。ここでのチャーラップのピアノ・プレイに観られる高踏的なオーソドクシーと、知られざる曲を精彩を放つものにする繊細な音の織成は絶品と云える。ところが、そんなふうに賛辞を贈りながらも前回のぼくといったら、毎度のことながら余談が過ぎて、肝心のチャーラップについて語るべきことを山のように残してしまった。自省するとともに、今回は彼のことに集中したいと思う。
(ビル・チャーラップ・トリオの『オール・スルー・ザ・ナイト』については、下の記事をお読みいただければ幸いです)
チャーラップ(実際は“シャーラップ”と発音する)のジャズ・ピアニストとしての最大の魅力といえば、音楽の本質を見極める能力と、それを実際に全身全霊で音にする表現力との2点である。彼はレコーディングの際の選曲において、卓越した才能を発揮する。チャーラップは世間一般であまり知られていない曲をセレクトすることがままあるのだけれど、そういう曲でも彼の手にかかると、名曲の誉れ高きジャズ・スタンダーズと比較しても遜色のない輝きを放つのである。それは彼が決して超絶技巧を振りかざしたりはせずに、どこまでも曲を歌わせることに集中するからだ。そういういぶし銀の演奏技術は、その初リーダー・アルバム『アロング・ウィズ・ミー』(1993年)において、すでに披露されていた。吹き込み当時のチャーラップは、まだ24歳だった。
またチャーラップには、1950年代から1960年代まで隆盛を極めたハード・バップのマナーを丁寧になぞりながら、そのスタイルを一途にブラッシュアップしていくような風格がある。しかも彼の場合、わりと早い時期からそういう貫禄を漂わせていた。新奇性に富んだ凄腕のピアニストたちがジャズ・シーンを席巻するなかで、チャーラップはケレン味のないモダン・ジャズの王道を行くようなプレイをもってして、長きにわたりピアノ・トリオの最前線で活躍しつづけてきた。彼のピアニズムに驚天動地の斬新な趣向などは少しもないけれど、そういったことがつまらなく思えるくらい、その至高の歌ごころは驚異的。そういう意味では、逆に稀有なピアニストと云えるのかもしれない。
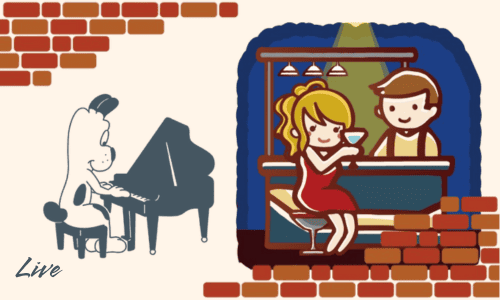
ぼくは1990年代の前半から、ほぼリアルタイムでチャーラップのことを追いかけてきた。ひょんなことから手にとった『アロング・ウィズ・ミー』を聴いて、すぐに彼のファンになった。このアルバムは、フォトグラファーとしても知られる音楽プロデューサー、ハンク・オニールが、1970年に設立したキアロスキューロ・レコードというレーベルからリリースされた。ペンシルヴェニア州ウィルクスバリ市、およびニューヨーク市に拠点を構えるこのレーベルの名称は、もとは“キアロスクーロ”と発音されるイタリア語で、“明暗”という意味。ルネサンス期の素描の技法に由来するワードだ。そんなアーティスティックな風情にも惹かれ、ぼくはこのレーベルの作品を何枚も購入した。
もちろん、キアロスキューロ・レコードのカタログにおいて、ぼくの最大のお目当てはチャーラップである。このレーベルの作品では、チャーラップとはおなじハイスクールに通った仲でもあるアルト奏者のジョン・ゴードンをはじめ、ギタリストのジーン・バートンシーニ、ベーシストのショーン・スミス、おなじくベーシストのジェイ・レオンハートなどのリーダー・アルバムにおいて、彼のピアノ・プレイを聴くことができるのだ。また、チャーラップは同レーベルにおいて、テッド・ローゼンタール(p)、ディーン・ジョンソン(b)、ロン・ヴィンセント(ds)といった、バリトン・サックスの第一人者、ジェリー・マリガンの元サイドメンたちとともに『ザ・ジェリー・マリガン・ソング・ブック』(1997年)というトリビュート作も吹き込んでいる。
マリガンはぼくにとって、ペッパー・アダムスと並んで好きなバリトン奏者。ぼくがもっとも敬愛する音楽家、デイヴ・グルーシンとも親密な間柄だった。ふたりはノワール派として知られるアラン・コルノー監督のフレンチ・アクション・サスペンス映画『メナース』(1977年)のサウンドトラックを手がけたこともあるし、コラボレーション・アルバム『リトル・ビッグ・ホーン』(1983年)を吹き込んでもいる。なおこのアルバムでは、前述のハンク・オニールがプロデューサーとして関わっているのも興味深い。また、マリガンの最後のリーダー作『ドラゴンフライ』(1995年)にも、さきに挙げたローゼンタール、ジョンソン、ヴィンセントといったレギュラー・メンバーとともに、グルーシンがピアニストとして参加している。
ではチャーラップは、どこでマリガンと関わっているのか?実はグルーシンがエグゼクティヴ・プロデューサー、そしてピアニストとして参加した、GRPレコードのオムニバス盤『ハッピー・アニヴァーサリー・チャーリー・ブラウン&スヌーピー!』(1989年)に、マリガンのクァルテットによる「レイン・レイン・ゴー・アウェイ」という曲が収録されている。このセッションでピアノを弾いていたのが、誰あろうチャーラップだった。迂闊にも、はじめてこの曲を聴いたときのぼくといえば、マリガンの演奏ばかりに気を取られて、ピアニストのことなどまったく気に留めなかったのだ。慌てて調べてみると、すでに所持していたマリガンのアルバム『ロンサム・ブールヴァード』(1990年)のピアニストも、チャーラップだった。まったく、いい加減なものである。
そんな醜態をさらしているうちに、オランダのレーベルであるクリス・クロス・ジャズから、チャーラップのリーダー作がリリースされた。セカンド・アルバム『スーヴェニア』(1995年)では、フリー・ジャズのパイオニア的アルト奏者、オーネット・コールマンのオリジナル曲「ターンアラウンド」が採り上げられていて、意表を突かれたもの。まあこれはコールマンの初期の曲だから、どちらかというと標準的なブルース・ナンバーと云える。むしろチャーラップのソフィスティケーテッドな解釈によるプレイのほうが、新しさを感じさせる。ピアニストのジャック・レイリーがリー・コニッツに捧げた曲「ハーフ・ステップ」などは知るひとぞ知る曲だけれど、原曲のクールなフィーリングがより研ぎ澄まされたものとなっている。
日本での人気を決定的なものにしたのはプロデューサーの原哲夫
ベニー・カーターのスモーキーでムード満点のバラード「スーヴェニア」に至っては、よりセンシティヴィティに富んだアーバンなスロー・ナンバーに様変わりしている。ということで、このアルバムの最初の3曲を聴いただけで、チャーラップの選曲と楽曲解釈に対するシャープな美的センスを痛切に感じさせられる。チャーラップは引きつづきサード・アルバム『ディスタント・スター』(1997年)においても、楽曲がもつ既存のイメージに新しい息吹をもたらすような路線を果敢に押し進める。むろん以上の2枚は優れた作品ではあるのだけれど、そこに収められたいくつかのトラックにおいて、チャーラップが珍しくいささか先鋭的な演奏に傾いているという点で、若干好みから外れる。
ただこれらのアルバムから、能ある鷹は爪を隠すでもないが、チャーラップもまた普段は表面に出さないだけで、実は進取の気性に富んだ一面をあわせもつジャズ・ピアニストであることがわかる。このキャラクターは、後述するアルバムにおける彼のプレイにもつながるものだ。とはいえぼくとしては、チャーラップについては、数々の華やかなジャズ・スタンダーズのあいだで霞むような楽曲に光を当てる審美眼や、そしてそれを高みへいざなうように歌わせる演奏能力を、高く評価したいのである。そういう思いから観ると、前回ご紹介したクリス・クロス・ジャズにおける最終作『オール・スルー・ザ・ナイト』は、やはり数あるチャーラップのリーダー作のなかでも傑出したアルバムであると云わざるを得ない。
確かこの『オール・スルー・ザ・ナイト』がリリースされたころには、日本のジャズの愛好家のあいだでも「スゴいピアニストがいる」と、チャーラップのことが取り沙汰される機会が多くなっていたと記憶する。その少しあと、わが国で彼の人気を決定的なものにしたのは、ヴィーナスレコードのプロデューサー、原哲夫だ。1995年からチャーラップはフィル・ウッズ・クインテットに参加していたのだけれど、コンコード・ジャズからリリースされたウッズのリーダー作の何枚かで、当時の彼のピアノ・プレイを聴くことができる。そのころすでにヴィーナスレコードにも2枚ほど吹き込んでいたウッズは、プロデューサーである原さんにチャーラップのことを強く推したという。結局、チャーラップが参加する、ウッズのヴィーナスレコード第3弾『チェイシン・ザ・バード』(1998年)が制作された。
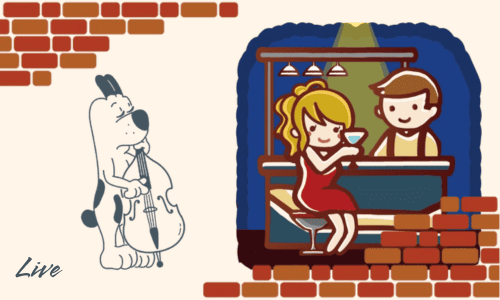
チャーラップに惚れ込んだ原さんは自ら、彼の5枚目のリーダー作『ス・ワンダフル』(1999年)を世に送り出す。やはりピーター・ワシントン(b)、ケニー・ワシントン(ds)がサイドメンを務めるトリオ作だが、これもまた忘れがたい逸品だ。ところが、トリオはほどなくしてブルーノート・レコードに移籍。第1弾の『星の降る夜』(2000年)は、日本でもリリースされ人気を博した。そんなわけで、原さんは自分のレーベルでこのトリオの作品を制作することができなくなった。そのため、ジェイ・レオンハート(b)、ビル・スチュワート(ds)というチャーラップと過去に共演歴のあるふたりがサイドに据えられた、よりスウィンギーなニューヨーク・トリオが編成された。ファンは期せずして、同時に2タイプのトリオを楽しむことができるという幸運に恵まれたわけである。
さてここで、さすがに100年とまではいかないけれど、数十年にひとりの逸材と云いたくなるようなチャーラップの横顔に触れておくとしよう。彼は本名をウィリアム・モリソン・チャーラップといい、1966年10月15日ニューヨーク市に生まれた。母親は1960年代に活躍したポップ・シンガー、サンディ・スチュワート。1963年に発表した「虹色の日記」が、スマッシュヒットとなった。父親はブロードウェイの作曲家、ムース・チャーラップ。ミュージカル『ピーター・パン』(1954年)が、その出世作である。ところが彼はチャーラップが7歳のときに他界している。チャーラップは自己のアルバムにおいて、知られざるミュージカル・ナンバーを採り上げることがままあるけれど、そういうところは父親からの影響によるものかもしれない。
その後、母親のスチュワートは、トランペッターのジョージ・トリフォンと再婚(実際は再々婚)している。トリフォンは、ビル・ワトラス&ザ・マンハッタン・ワイルドライフ・レフュージのメンバーとして知られる。なおムース・チャーラップにはすでに前妻のエリザベスとのあいだにふたりの子どもがいたのだが、ひとりはベーシストのトム・チャーラップだ。なんだか、ややこしくなってきたな──。ちなみにこの音楽一家、サンディ・スチュワート(vo)、ビル・チャーラップ(p, arr)、トム・チャーラップ(b)、ジョージ・トリフォン(tp, flh)、それに前述のロン・ヴィンセント(ds)といったメンバーで『サンディ・スチュワート&ファミリー』(1994年)というアルバムを吹き込んでいたりする。なんとも、仲がよろしいことで──。
チャーラップは2007年に、カナダのサスカチュワン州レジャイナ市出身の凄腕ピアニスト、リニー・ロスネスと結婚している(子もち同士の再婚)。4つ年上の姉さん女房、しかもスゴい美人。ただただ、羨ましいかぎりである。さらにつけ加えると、1940年代から現代まで長きにわたり活動し、ストライド・ピアノからフリー・ジャズまで幅広くプレイするピアニスト兼コンポーザーのディック・ハイマンは、チャーラップの遠縁にあたる。生まれたときからジャズが溢れた日常を過ごし、3歳からピアノをはじめ、しっかりクラシックのメソッドも学んだチャーラップ。幼少期から恵まれた環境でそれにともなう充実した音楽教育を受けたのだから、彼が並外れた歌ごころを身につけているというのも、大いに得心がいく。
そんなチャーラップのプレイも、この15年くらいのあいだに微妙な変化を見せているように、ぼくには感じられるのだけれど、みなさんはいかが思われるだろうか。これは飽くまで個人的な感想だけれど、それまでの彼といえば、まるで厳格なまでに楽曲を歌わせるよう身を持する──そんな印象を与えてきた。しかしながら、チャーラップはあるときから、さながらクビキから解き放たれたかのように、ときおり縦横無尽なプレイを展開するようになった。まえに述べたように、彼は普段ケレン味のないモダン・ジャズの王道を行くようなプレイをしているけれど、実は進取の気性に富んだ一面をあわせもつジャズ・ピアニストなのである。そんなウラのキャラクターが表面に現れるシーンに出くわす機会が、徐々に増えているように、ぼくは思うのである。
オープンマインドな姿勢でその卓越した技巧をさらけ出す
これもまたぼくの勝手な想像だけれど、なんだかんだいってもリニー・ロスネスと人生を共有するようになったことが、チャーラップの音楽性や演奏の作法をよりのびやかなものにしたのではないだろうか。いずれにせよ、この才媛の誉れ高き姉さん女房が彼に与えた影響は、すこぶる大きいと思われる。なぜなら、チャーラップとロスネスとが結婚後にブルーノート・レコードに吹き込んだデュオ・ピアノ・アルバム『ダブル・ポートレイト』(2010年)が、並外れていい出来だからだ。そのうえ、プロデュースはチャーラップ、ロスネス、そしてエンジニアでもあるジョエル・モスによる共同作業となっているけれど、音を聴くかぎりではイニシアティヴを取っているのは明らかにロスネスなのである。
このアルバムでは、ブルース・フィールについてはあっさりとした淡い味つけにとどめられていて、ブラジリアン・ミュージックや現代音楽の要素が感覚的に採り入れられている。これはロスネスの得意とするマナーなのだけれど、それが作品を、明るく澄んだ鮮やかな色合いのサウンドと軽やかで爽やかなピアニズムが際立つものにしているのは、一目瞭然ならぬ一聴瞭然である。こういう味わいは、従来のチャーラップのアルバムにはないもの。彼のプレイも平生とは違って、より柔軟で鷹揚なものに映る。ストイックなまでにもっとも純粋で濃縮されたモダン・ジャズの本質を究めてきたチャーラップが、オープンマインドな姿勢でその卓越した技巧をさらけ出すようになったのは、このころからではないだろうか。
思えばチャーラップは、長らくブルーノート・レコードに所属しレギュラー・トリオによる活動を継続させながら、そのいっぽうでわが国が誇るヴィーナスレコードのプライヴェート・ブランドであるニューヨーク・トリオにおいても、高品質な作品も逐次制作してきた。ニューヨーク・トリオのアルバムは『夜のブルース』(2001年)から、テナー・サックス&クラリネットの名手であるケン・ペプロウスキーをゲストに迎えた『スターダスト』(2009年)まで8枚を数える。いかにも日本人の嗜好に合うような中庸を得たスタイルのピアノ・トリオによる味わい深い演奏は、レーベル独自の録音技術による力強く存在感のある音質と相まって、ぼくにもあらためてモダン・ジャズの素晴らしさを教えてくれた。
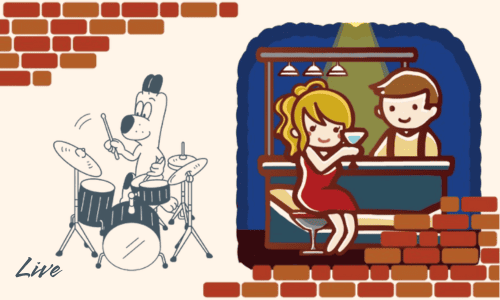
その後、チャーラップはおなじ志向をもつギタリスト、ピーター・バーンスタインを迎えたドラムレスのトリオ編成で『アイム・オールド・ファッションド』(2010年)を吹き込むと、10年以上も同好の士としてともにレコーディングに臨んだヴィーナスレコードの原さんと袂を分かつ。このこともまたチャーラップにとっては、転機のひとつだったのではないだろうか。レコーディングは共同リーダー作やイレギュラーな作品が目立つようになるけれど、当時の彼には、自己の音楽性を意のままに拡大させていくような風格があった。また、チャーラップは2015年から、ニュージャージー州立ウィリアム・パターソン大学のジャズ科において、ディレクターとして後進の指導にあたるようになる。
それと同時に、満を持してひとまわり大きくなったビル・チャーラップ・トリオの快進撃がはじまるのである。インパルス! レコードからリリースされた2枚『ノーツ・フロム・ニューヨーク』(2016年)『アップタウン・ダウンタウン』(2017年)、そしてふたたびブルーノート・レコードに戻って吹き込まれた『ストリート・オブ・ドリームス』(2021年)では、レギュラー・トリオによるディテールに至るまで精巧に描かれるサウンドスケープ、そして芸術的なまでに臨場感や疾走感が横溢するダイナミズムが眩いばかりだ。しかもトリオの動きは、これまで以上にスムースで無駄のないものとなっている。それがサウンドに都会的なイメージを与えているのだけれど、このトリオが大きな進化を遂げたことがまざまざと実感される。
その最大の見せ場となったのが、2023年9月9日のライヴの模様が収められた『アンド・ゼン・アゲイン』(2024年)である。ニューヨーク市マンハッタン区グリニッジ・ヴィレッジに所在する、名門ジャズ・クラブ、ヴィレッジ・ヴァンガードにおいて実況録音されたもの。パーソネルは、敬意を表して再記するが、ビル・チャーラップ(p)、ピーター・ワシントン(b)、ケニー・ワシントン(ds)の3人。ブルーノート・レコードからのリリースだ。面白いことにチャーラップは、ちょうど20年まえの2003年9月にも同クラブでライヴを行っていて、その音源はやはりブルーノートから『ライヴ・アット・ザ・ヴィレッジ・ヴァンガード』(2007年)としてリリースされた。
グラミー賞においてベスト・ジャズ・インストゥルメンタル・アルバムにノミネートされたこのアルバムでは、そこに収められたトリオのパフォーマンスが、スタジオ・レコーディングのそれとは明らかに異なり実に大胆な様相を呈しているのが、最大の魅力となっている。だがしかし、それは『アンド・ゼン・アゲイン』における、進化を遂げたトリオのヴァイタリティ溢れる自由闊達なプレイには到底及ばない。むろん、その手に汗握るスウィンギーなアドリブ・プレイと、ため息の出るようなバラードのインタープリテーションには、衰える様子はまるでない。というか、むしろ一段と磨きがかかったという印象を受ける。なによりも驚かされたのは、チャーラップが誰もが知るジャズ・スタンダーズに、婉曲的なエクスプレッションを与えているという点である。
オープニングを飾るケニー・バロンの「アンド・ゼン・アゲイン」がスゴい。アップテンポに乗って、ブルースに対するモーダルな解釈、ダイナミックなスケールアウトと、チャーラップのアドリブがスピーディに天翔ける。興奮した女性客が、思わず奇声をあげる。ランニング・ベースとドラム・ソロも痛快だ。ジェローム・カーンの「オール・ザ・シングス・ユー・アー」では、リズムが途中ルンバになるところが心地いい。ミッドテンポでもチャーラップは、力強く色彩豊かなピアニズムを発揮する。セロニアス・モンクの「ラウンド・ミッドナイト」でもまた、リズムが途中ワルツになったりルンバになったりする。チャーラップの即興演奏に対する度量の大きさが窺える、悠然としたプレイが堪能できる。
デイヴ・ブルーベックの「イン・ユア・オウン・スウィート・ウェイ」では、アフロ・キューバンからクラシックまで飛び出すアブストラクトなプレイが、都会的なムードを高める。なかでも変幻自在のドラミングが素晴らしい。ジミー・ヴァン・ヒューゼンの「ダーン・ザット・ドリーム」では、チャーラップのバラードに対する洗練された解釈が際立つ。ヴィンセント・ユーマンスの「サムタイムズ・アイム・ハッピー」は、選曲といい寛いだスウィング感といい、いかにもチャーラップらしいトラックだ。ジョージ・ガーシュウィンの「私の彼氏」では、意外にもアップテンポでトリオはバップ・スピリッツを全開。チャーラップの抑揚の効いたプレイは流石のひとこと。ヴィクター・ヤングの「ほのかな望みもなく」では、チャーラップがスローテンポで曲を歌わせることに集中。見事な締め括りだ。46分と短い時間ではあるが、この至福のひとときを味わわない手はない。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。









コメント