ジャズをフィルムに収めつづけた名カメラマン、ウィリアム・クラクストンの半生が綴られた映画『JAZZ SEEN カメラが聴いたジャズ』のサウンドトラック・アルバム
 Album : Till Brönner / Original Music From The Film Jazz Seen (2001)
Album : Till Brönner / Original Music From The Film Jazz Seen (2001)
Today’s Tune : Clax’s Theme
レコード・ジャケットをアートにした名カメラマン
おそらくジャズの愛好家くらいしか知らないと思われるが、2001年にドイツで製作された『JAZZ SEEN カメラが聴いたジャズ』という映画がある。どちらかというと地味な、上映時間が80分ほどの短いドキュメンタリー・フィルムだけれど、ちゃんとギャガ・コミュニケーションズによって配給され、本国公開の翌年にわが国でも公開された。とはいっても当時、渋谷区道玄坂2丁目のフォンティスビルの4階にあったミニシアター、シネ・アミューズ(2009年に閉館)でのレイトロードショーだったのだけれど──。どうやら現在は動画配信サービスでは鑑賞することができないようなので、興味のあるかたにはいまとなっては入手しにくいかもしれないが、国内仕様のDVDが発売されているのでそちらを探されることをお勧めする。
ときにこの『JAZZ SEEN カメラが聴いたジャズ』とはいったいどんな映画かというと、サブタイトルに“The Life And Times Of William Claxton”とあるように、アメリカのフォトグラファー、ウィリアム・クラクストン(1927年10月12日 – 2008年10月11日)の半生が綴られた記録映像というかフィルム・エッセイ。クラクストンは、1950年代からジャズをはじめとする音楽を愛好しながら、数多くのミュージシャンたちをフィルムに収めつづけたことで広く知られる。なかには彼のことを、レコード・ジャケットをアートにした名カメラマンと云う向きもある。作品としては1960年代のジャズ・アーティストを被写体とし、その絶妙な瞬間を捉えた写真集『ジャズライフ』(1961年)が有名だ。
カリフォルニア州パサデナ出身のクラクストンは、西海岸を活動の拠点としていたが、ジャズ・ミュージシャンばかりでなくハリウッド・スター、セレブリティやモデルの撮影も行っていた。2000年に出版された、俳優のスティーヴ・マックイーンの写真集は特に有名だ。また、クラクストンの奥さまは、モデル兼女優として活躍したペギー・モフィット。1960年代のファッション・シーンにおいてアイコン的存在だった彼女は、濃いめのメイクにアシンメトリカルなヘアカットという特徴的なスタイルで注目を集めた。ハービー・ハンコックのサントラが人気の、ミケランジェロ・アントニオーニ監督の『欲望』(1967年)にも、チラッと出演していたりする。
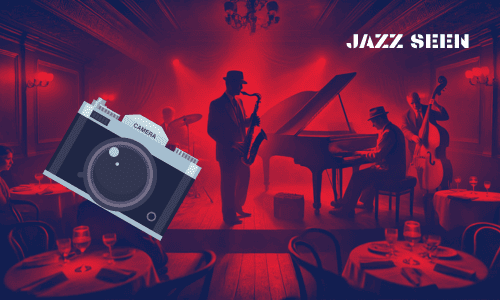
クラクストンが制作した史上初のファッション・フィルム『ブラック・ベーシック』(1967年)にも、モフィットは出演している。ロック・ミュージシャンのデヴィッド・ルーカスによるモーグ・シンセサイザーを使用した音楽も含めて、創意溢れた作品だ。このフィルムはデザインの歴史に影響を与えた優れた作品ということで、ニューヨーク近代美術館に収蔵されている。なおモフィットは2024年8月10日、86年の生涯を閉じた。云うまでもなく彼女は、クラクストンとともに映画『JAZZ SEEN カメラが聴いたジャズ』にも出演している。この映画は、モフィットの写真を含めたクラクストンが撮影した数々の作品、クラクストン本人の貴重な写真や映像、そして彼が関わった各界の著名人へのインタビューなどで構成されている。
この映画では、クラクストンの偉大な足跡をたどる上で、数多くのビッグネームのコメントが織り込まれている。その出演者といえば、俳優のデニス・ホッパー、コメディアンで俳優のリチャード・ルイス、映画監督のジョン・フランケンハイマー、ドイツ出身の写真家、ヘルムート・ニュートン、イギリス出身のヘアドレッサー、ヴィダル・サスーン(シャンプーのブランド名ではないよ)、作曲家のバート・バカラック、ピアニストでシンガーのダイアナ・クラール、シンガーソングライターのカサンドラ・ウィルソン、ピアニストのラス・フリーマン、ドラマーのチコ・ハミルトン、アルト奏者でありクラリネット奏者でありトランペット奏者でもあるベニー・カーターなど、そうそうたる顔ぶれである。
クラクストンがフォトグラファーになるキッカケは、少年時代に大判カメラをプレゼントされたこと。具体的にそれは、4×5インチ(102×127mm)のシートフィルムを使用するカメラだった。彼はこの当時高級品だったであろう光学的な機械を手にすることによって、あらゆる外界の像をフィルム上に描くという魅力的な作業にとりつかれたのである。そのいっぽうで、そんな多感な少年時代にジャズ・ジャイアンツのレコードを夢中で聴いていたクラクストンは、青年期から次第にレコード・ジャケットの写真を手がけるようになる。やがてウェストコースト・ジャズの名門レーベルで写真とデザインとを同時に任されるようになった彼の名声は、1950年代の西海岸ならではのリラックスしたクールなサウンドの流行とともに、一躍世界的なものとなった。
たとえば、クラクストンがジャケット撮影を務めたジャズ作品ですぐに思い出されるのは、ユニセックスなハスキー・ヴォイスがレイジーなムードを醸成するユニークなヴォーカル・アルバム、チェット・ベイカーの『チェット・ベイカー・シングス』(1956年)。ちなみにこのアルバムのジャケット写真では、マイクに向かって歌うベイカーの画像が3色に着色されたカラフルなものがもっとも有名だけれど、オリジナルである10インチ盤のラス・フリーマンとのツーショットや、リイシュー盤のギターを抱えてほくそ笑むベイカーのフォトも、すべてクラクストンが撮影したものだ。彼はベイカーのアルバムはもとより、ロサンゼルスの名門レーベル、パシフィック・ジャズの多くの作品を手がけた。
それ以外で、好むと好まざるとにかかわらず、目の覚めるようなジャケットという点でぼくが高く評価するのは、チコ・ハミルトン・クインテットのデビュー・アルバム『ブルー・サンズ』(1956年)。マルチ・インストゥルメンタリストのバディ・コレットがフィーチュアされた人気盤。ジャケットに写るウィットに富んだバンド・メンバーのポージングに惹かれ手にとったら、チェンバー・ジャズ・ユニットによるクラシカルな演奏が繰り広げられていて意表を突かれた。それに反して、バーニー・ケッセル(g)、レイ・ブラウン(b)、シェリー・マン(ds)の3人が、高所ではしゃぐジャケット写真が印象的な『ザ・ポール・ウィナーズ』(1957年)は、内容のほうもそのままでハッピーでユーモラスなセンスのよさが光る。
ジャズ映画の監督というイメージが強いドイツの異才
そんなわけでジャズ・カメラマンの大家とも称される、ウィリアム・クラクストンの実像に迫ったドキュメンタリー・フィルム『JAZZ SEEN カメラが聴いたジャズ』は、終始ジャズの香りが立ち込める映画。チェット・ベイカーのクールな音楽ではじまり、ルイ・アームストロング、エラ・フィッツジェラルド、カーメン・マクレエ、サラ・ヴォーンといった20世紀において影響力の大きなジャズ・ヴォーカリストたちの素晴らしいパフォーマンスが、次々に音と映像で鏤められていく。たとえクラクストンのことを知らなくても、あるいはジャズをあまり聴くことがなくても、だれもがジャズの魅力というか洒落た雰囲気を気軽に楽しむことができる作品に仕上がっていると、ぼくは思う。
このスタイリッシュな映像作品『JAZZ SEEN カメラが聴いたジャズ』のメガホンをとったのは、ドイツ出身の映画監督、プロデューサー、そして俳優でもあるユリアン・ベネディクト。このひとがまた、かなりの変わり種なのだ。1963年9月28日ノイボイアーン生まれの彼は、フランクフルトでクラシック音楽の教育を受け、2年ほどローマで生活し、現地のロック・バンドでサックスを吹いていたという。はたまたパリに移り、ソルボンヌ大学で人文科学を学んでいたこともある。また、ドイツの映画監督、ルドルフ・トーメの恋愛映画『リーベ・アウフ・デン・エアステン・ブリック(ひとめぼれ)』(1991年)で主演俳優を務め、その後も何本かのフランス映画に出演している。なお上記の映画の音楽は、チコ・ハミルトンが手がけた。
そんなベネディクトがジャズに関心をもつようになったのは、たまたまミュンヘンで公演を行っていたチコ・ハミルトンの演奏に触れたとき。その後、ベネディクトはニューヨークに滞在しているとき、実際にハミルトンとテナー奏者のビル・サクストンからジャズ演奏の手ほどきを受けている。そんな不思議な巡り合わせから、ベネディクトは『チコ・ハミルトン ― ダンシング・トゥ・ア・ディファレント・ドラマー』(1994年)というドキュメンタリー・フィルムを撮り、ハミルトンに捧げた。また彼は1997年に、今度はジャズの名門レーベル、ブルーノート・レコードと、その創設者であるアルフレッド・ライオンとフランシス・ウルフの物語を描いた映画を製作することになる。

この『BLUE NOTE ハート・オブ・モダン・ジャズ』(1997年)というおよそ90分の映画は、グラミー賞にノミネートもされた。そしてなによりも、ドラマーのアート・ブレイキー、ベーシストのロン・カーター、ピアニストのハービー・ハンコック、テナー奏者のソニー・ロリンズ、トランペッターのフレディ・ハバードなど、かつてブルーノートに所属していたスター・プレイヤーたちが出演していることが、ジャズ・ファン垂涎の1本にしている。もちろん、日本ヘラルド映画(現在の角川ヘラルド・ピクチャーズ)の配給により、1999年にわが国でも堂々と公開された。しかも日本では同年に、東芝EMIからオリジナル・サウンドトラック・アルバムまでリリースされた。まあサントラ盤といっても旧譜からのコンピレーション・アルバムなのだけれど──。
そういえば昨年、音楽評論家のピーター・バラカンが主宰する「Peter Barakan’s Music Film Festival 2024」というイヴェントがシネマート新宿において開催されたが、そのなかで『BLUE NOTE ハート・オブ・モダン・ジャズ』が採り上げられていた。これはバラカンさんが選んだ音楽映画フェスティヴァルなのだけれど、氏はこの作品のほかにもベネディクトの映画をもう1本セレクトしている。それは『自分の道 欧州ジャズのゆくえ』(2006年)という90分弱のフィルム・エッセイ。タイトルどおりベネディクトがヨーロッパのジャズを探求した作品で、イタリア、ポーランド、そしてスカンディナヴィアのジャズ・シーンに焦点が当てられている。本作に登場するヨーロッパのジャズを確立したミュージシャンたちを挙げれば、枚挙にいとまがない。
ベネディクトはほかにも『JAZZ SEEN カメラが聴いたジャズ』にも出演しているフォトグラファー、ヘルムート・ニュートンの写真集にちなんだ『ヘルムート・ニュートンのSUMO ― 最も高額な本の制作過程』(1999年)というテレビ映画や、自動車産業で知られる都市の理想とはかけ離れた実態を明らかにした『ヴォルフスブルクの1日』(2003年)という短編ドキュメンタリー・フィルムなどの監督も務めている。まあこれらの作品は日本では観ることができないので、ユリアン・ベネディクトといえば、わが国ではジャズ映画の監督というイメージが強い。だが残念なことに『BLUE NOTE ハート・オブ・モダン・ジャズ』『自分の道 欧州ジャズのゆくえ』はともに、国内における映像ソフトの発売がない。今後に期待したい。
ということで、ハナシを『JAZZ SEEN カメラが聴いたジャズ』に戻すけれど、ぼくはベネディクトの作品では本作がもっとも好きだ。クラクストンの写真は実際に演奏されたジャズよりも、ジャズという音楽の本質を雄弁に語っているように感じられる。もっと云えば、彼は被写体となる人物の本質をパーフェクトなまでに捉え切っている。いったいどうしたら、あんな写真を撮ることができるのだろう。おそらくクラクストンは決定的瞬間を偶然に捉えるのではなく、さながらジャズ・プレイヤーが当意即妙なトーンやフレーズを繰り出すように、最善のタイミングを見計らってシャッターを切るのだろう。そんな芸術家としての、あるいは人間としてのクラクストンを、ベネディクトは本作においてベストなフォーマットで観せてくれたのである。
ところで『JAZZ SEEN カメラが聴いたジャズ』もまた、サウンドトラック・アルバムが存在する。ユニヴァーサル・ジャズ・ジャーマニーからのリリースだが、日本でも国内盤が発売された。これが思いのほか素晴らしいアルバムなので、ジャズのファンかどうかにかかわらず、ぜひ多くのかたに手にとっていただきたいもの。ベネディクトは、なぜクラクストンがカメラで捉えたひとびとはみな輝いているのか──このアルバムを聴けば、その秘密を垣間見ることができるかもしれないと述べている。本盤には19曲が収録されているが、そのうち8曲は既存の録音。センスの光る選曲がなされているのと同時に、ジャズ・シーンにおいて歴史的に貴重な吹き込みも含まれている。
具体的には、チェット・ベイカーのパリでの吹き込み『チェット・ベイカー・クァルテット Vol. 2』(1956年)から「四月の思い出」と「テンダリー」ルイ・アームストロング・ウィズ・サイ・オリヴァー&ヒズ・オーケストラの1950年にデッカ・レコードからシングル盤としてリリースされた「セ・シ・ボン」ダイアナ・クラールの『ラヴ・シ-ンズ』(1997年)から「ピール・ミー・ア・グレープ」ヴァーヴ・レコードからリリースされた『ベン・ウェブスター・ミーツ・オスカー・ピーターソン』(1959年)より「ザ・タッチ・オブ・ユア・リップス」エラ・フィッツジェラルド&デューク・エリントンの1965年にヴァーヴ・レコードからシングル盤としてリリースされた「イマジン・マイ・フラストレーション」──。
既存の録音+フィルム・スコアによる贅沢なジャズ・アルバム
さらにアート・テイタムの1955年のソロ・ピアノによるライヴ・レコーディング「ボディ・アンド・ソウル」──テイタムはこの曲を何度も弾いているけれど、ぼくはこのビバリーヒルズにある作曲家のレイ・ハインドーフの自宅で録音された演奏が特に好きだ。このトラックはエマーシー・レコードからリリースされた2枚組LP『20th センチュリー・ピアノ・ジーニアス』(1986年)に収録されている。このレコードは、のちに日本でも未発表12曲を加えたCD『ピアノ・ディスカヴァリーズ』(1996年)としてリイシューされたので、興味のあるかたはご賞味あれ。そして本盤にはあと1曲、ジェリー・マリガン&スタン・ゲッツの『ゲッツ・ミーツ・マリガン・イン・ハイファイ』(1957年)から「ア・バラード」が収録されている。
これらの既存曲は、監督であるベネディクトが自らコンパイルした。いっぽう残りの11曲は、映画のために書き下ろされた正真正銘のフィルム・スコア。つまり『JAZZ SEEN カメラが聴いたジャズ』のサウンドトラック・アルバムは、東芝EMIが『BLUE NOTE ハート・オブ・モダン・ジャズ』の日本公開に合わせて制作した単なるコンピレーション・アルバムとは異なり、映像の背景音楽として新たにレコーディングされたトラックが根幹を成す音盤なのである。11曲のうち、多くのジャズ・ミュージシャンが採り上げているスタンダード・ナンバー、ジョニー・グリーン作曲、エドワード・ヘイマン作詞による「アウト・オブ・ノーウェア」を除くすべての楽曲が、ティル・ブレナーのペンによるものである。
ティル・ブレナーは、1971年5月6日ドイツ、フィーアゼン生まれのトランペッターでありシンガーでもある。彼はこの『JAZZ SEEN カメラが聴いたジャズ』で音楽監督を務めており、楽曲のコンポジション、リズム・セクションとストリング・セクションのアレンジ、そしてプロデュースを一手に担っている。いまやブレナーはわが国でも人気のジャズ・プレイヤーとなっているけれど、広く知られるようになったのは5枚目のリーダー作『love』(1999年)がリリースされてから。この美しいバラード・アルバムは、いまはなきジャズの専門誌「スイングジャーナル」が主催するジャズ・ディスク大賞のニュー・スター賞に輝いた。そんな出来事に、当時のぼくは「やはりな」とひとりでニヤニヤしたもの。

というのも、ぼくがブレナーに興味をもったのはそれより数年まえのことで、そのキッカケはドイツ、アーヘン出身のピアニスト、フランク・カステニアーがブレナーのデビュー作『ジェネレーションズ・オブ・ジャズ』(1994年)に参加していたこと。カステニアーは1991年からずっとWDR ビッグ・バンドのキーボーディストを務めていたのだけれど、ぼくが彼に惹かれたのはソロ・ピアノで吹き込まれた初リーダー作『オータム』(1997年)を聴いたときのこと。スウェーデンの作曲家イングリッド・マテルネの作品集というまったく未知のコンテンツではありながら、曲にしても演奏にしてもどこかノスタルジックな気分にさせるところがあった。ぼくにとっては、長きにわたり愛聴盤となっている。
そんなわけで、カステニアー聴きたさにブレナーのアルバムを手にとったぼくだが、今度はレコーディング当時まだ22歳だったこの若きトランペット吹きにすっかり惚れ込んでしまった。1999年までベルリン・ドイツ交響楽団の首席トランペッターを務めただけあって、そのテクニックには卓越したものがある。ディテールの美しいフレージングも然ることながら、エアの音がはっきり聴こえるほど余計に口を開けて吹く独特の奏法に魅了された。ことにハーマン・ミュートを使用した、霞がかかったような深い陰影を湛えたサウンドは絶品だ。ところが、そのころ日本で入手することができたブレナーのアルバムといえば、4作目の『ミッドナイト』(1996年)のみ。しかも意外なことにポップなフュージョン作品で、どうにも腑に落ちなかった。
結局ぼくは好きが高じて、デビュー作同様ドイツのレーベル、マイナー・ミュージックからリリースされていた『マイ・シークレット・ラヴ』(1995年)『ジャーマン・ソングス』(1996年)といったブレナーのリーダー作、そして彼がゲスト・プレイヤーとしてフィーチュアされたスリー・オブ・ア・カインドの『ドリップ・サム・グリース』(1996年)を、一気に個人輸入してしまった。以来いまに至るまで、ぼくはブレナーの大ファンだ。実は『JAZZ SEEN カメラが聴いたジャズ』にぼくの関心が向いたのも、彼がスコアを手がけていたからなのである。そしてこのサウンドトラック・アルバムは、従来のブレナーのリーダー作と比較しても遜色ない。嬉しいことに、カステニアーも参加している。
パーソネルは以下のとおり──。ティル・ブレナー(tp, flh)、ペーター・ウェニガー(ts)、フランク・カステニアー(key)、ブルーノ・ミュラー(g)、フランツ・ヴァン・へースト(b)、ハンス・デッカー(ds)、ダニエル “トッポ” ジョイア(perc)と、ドイツの名うてのジャズ・プレイヤーで固められている。さらにトーステン・ショルツ(vln)がコンサートマスターを務める、ストリング・セクションが加わる。アルバムのオープニングを飾る「ジャズ・シーン」では、アンニュイな感じでスウィングするトリオ演奏にクラクストンのナレーションが重なる。全体のテーマである「クラクストンのテーマ」は、寛ぎ感と緊張感とが入り交じったバラード。ブレナーによるハーマン・ミュートの音色が美しい。デイヴ・グルーシンの「ランダム・ハーツ」という曲からの影響が強く感じられる。
12小節のブルース「シュート」は、グルーヴィーなハード・バップ。テナー、ハモンド・オルガン、ドラムスとソロが繋がれていく。テーマのヴァリエーション「フルーデッド」は、クァルテットからストリング・セクションへ移行する変奏がいかにも映画音楽然としたトラック。歩くようなテンポのスウィング感が心地いい「アウト・オブ・ノーウェア」では、ミュート・トランペット、ピアノのソロが上品で都会的な気分を演出する。テーマのヴァリエーション「リフレクションズ」は、ソロ・ピアノによる演奏。テンポ・ルバートでの叙情的な即興演奏は、やはりグルーシンを彷彿させる。スウィートなボサノヴァ「ヴェルニサージュ」では、なんといってもテナーのハードなブレスによるソフトなサウンドが第一等。ストリングスも入る一服の清涼剤だ。
ボサノヴァからインプレッショニズムな展開を見せる「ザ・フロッグマン」は、希有なオーケストレーションによるジャズの小品。3度目のテーマ・ヴァリエーション「スティーヴ・マックイーン」は、ジャズ・ワルツにアレンジされている。ピアノ・トリオによるドライな味わいのプレイは、きわめてクールだ。「ブルース・フォー・ペギー」は、ブギーのリズムが痛快なファンキー・ジャズ。強烈なシャッフル・ビートに乗って展開される、ギターとハモンドとによるソロ交換が楽しい。ラストの「ザ・モーメント」では、印象主義音楽のイディオマティックな表現が感じられるピアノ、スモーキーなトーンとエアの音が独特のフリューゲルホーン、それらを包み込むようなストリングスが鮮明な印象を与え爽やかな余韻を残す。既存の曲もあわせて、本作は実に贅沢なジャズ・アルバムである。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。








コメント